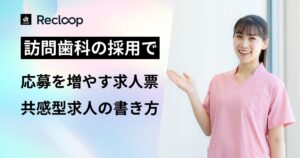歯科医院の院長からよく耳にするのが「以前は求人を出せば応募があったのに、最近は反応がない」という声です。多忙な業務の合間に、同じ求人広告を出し続けてしまうのは自然な流れかもしれません。しかし、同じ内容を繰り返し出すことには大きな落とし穴があります。求職者側の視点に立てば、何カ月も同じ求人が出続けている歯科医院に対して「人が定着しないのではないか」「ずっと人手不足なのではないか」という不安を抱くのは当然です。結果として求人の露出回数が増えても、応募につながらないという逆効果を招きかねません。
この背景には、労働市場そのものの変化があります。歯科業界に限らず、医療職や専門職の採用は「売り手市場」が続いています。インターネットやSNSの普及により、求職者は複数の職場を簡単に比較できるようになりました。さらに、働き方への価値観も多様化し、給与や条件だけでなく、雰囲気ややりがい、柔軟な働き方が判断材料として重視されるようになっています。つまり、求人広告は「出し続ければ応募が来る」時代から、「どう伝えるかを工夫しなければ選ばれない」時代に移り変わっているのです。
本記事では、同じ求人を出し続けるリスクと効果の限界を整理し、その背景にある時代の変化を解説します。その上で、歯科医院が採用活動においてどのように情報発信を見直すべきか、次の一歩を考えるヒントをお伝えします。
なぜ同じ求人を出し続けることが逆効果になるのか?

昔は同じ求人でも応募が集まった理由
歯科医院が同じ求人広告を何カ月、時には何年も繰り返し出していると、求職者の視点ではどう映るでしょうか。まず最も大きな印象は「人が集まらず、ずっと人手不足に困っているのではないか」という不安です。歯科業界は専門性が高く人材不足が慢性的に続いていることを多くの求職者も理解していますが、それでも「同じ医院がいつも求人を出している」という状況は、定着率の低さや労働環境の厳しさを連想させやすいのです。
さらに、現在の求職者は求人を一度見て即決することはほとんどありません。スマートフォンで複数の媒体を横断的に見比べ、何度も検索して「本当にここで働きたいか」を吟味します。その際、目に入る求人が常に同じ内容だと、「改善の努力をしていない」「魅力がアップデートされていない」「以前も見たな」と感じられ、応募意欲は下がります。広告が繰り返されるほど親しみが増す時代もありましたが、今では“新しさ”や“変化”がないと逆に敬遠されるのです。
特に、歯科衛生士や歯科助手といった職種は人材の流動性が高いため、応募者は「条件面」だけでなく「医院の雰囲気」や「医院の将来性」まで敏感にチェックしています。そのため、同じ求人を出し続ける行為は「情報更新のない医院=現場も停滞している」という誤解を生みやすく、医院の評価を下げるリスクを伴います。
求人情報の鮮度が失われる
求人広告は本質的に「鮮度が命」といっても過言ではありません。たとえ掲載日が更新されていたとしても、文章や写真が一言一句同じであれば、求職者には「古い情報」と認識されてしまいます。特に歯科医院は、診療スタイルや働き方、制度が少しずつ変わっていくのが一般的です。スタッフの入れ替わりや設備の導入、診療時間の調整など、小さな変化は日常的にあります。それらを反映せずに何年も同じ内容を出し続ければ、「情報をきちんと伝える意識がないのでは」と疑われても仕方がありません。
さらに、求人媒体の仕組み上も不利になります。多くの求人サイトや検索エンジンは“新着情報”を優先的に表示するアルゴリズムを採用しています。そのため、内容の更新がない求人は次第に後ろに押しやられ、露出機会そのものが減少します。つまり、医院が「出し続けているつもり」でも、実際には求職者の目に触れる頻度が下がっているのです。
鮮度を欠いた求人は、いわば冷めきった料理のようなものです。見た目は同じでも「食欲をそそられない」、つまり応募につながらない状態になります。医院側としては掲載コストや時間をかけても、効果は薄れ、むしろ逆効果になっていきます。
求人は「数」ではなく「質」の時代
少子高齢化が進み、働き手の数が限られる今は、求人広告を“数”で勝負する時代ではありません。以前は「とにかく求人を出せば誰かが応募してくれる」という状況がありましたが、いまは人材の母数自体が減少しており、特に歯科衛生士は有資格者の絶対数が不足しています。この中で同じ求人を出し続けても、求職者の関心を引くことは難しいのです。
求職者が重視するのは「どんな医院なのか、自分が入職した未来が伝わる具体性」です。給与や休日数などの条件はもちろん重要ですが、それ以上に「働いてみたら自分はどうなるか」という実感を持てるかが鍵になっています。例えば、スタッフの声を交えた紹介や医院の雰囲気が伝わるエピソード、キャリアを築けるイメージなどが、応募を後押しする大きな要素になります。
同じ求人を漫然と出し続けることは、この「質的な情報」を軽視していると受け取られやすくなります。結果的に「この医院は他と比べて魅力に欠ける」と見られ、数を重ねても応募は増えません。むしろ「工夫がない」「応募者に対する誠意が足りない」と判断され、ブランドイメージを損ねてしまうこともあります。
信頼性を損なうリスク
同じ求人を出し続ける行為が最も危険なのは、医院の信頼性を損なう点にあります。求人が長期間消えないと、求職者は「人が入ってもすぐ辞めるのではないか」「条件が実際と違うのではないか」と疑います。こうした疑念は一度抱かれると払拭が難しく、医院全体の評価にまで影響します。
また、近年は口コミサイトやSNSを通じて職場の評判を調べることが当たり前になっています。求人で伝えていることと、スタッフや退職者の声に乖離があると、「やはりあの医院は問題があるのでは」という不信感が広がります。とりわけ歯科医院は地域に根ざしているため、評判の広がりは早く、信頼を回復するには多大な労力がかかります。
さらに、求人媒体側の評価にも影響します。長期にわたり成果が出ない求人は「反応のない広告」として扱われ、プラットフォーム内での優先度が下がる場合があります。結果として、ますます応募が集まらないという悪循環に陥るのです。信頼を得るための採用活動が、かえって信頼を失う原因になりかねない。これが、同じ求人を出し続ける最大のリスクだといえるでしょう。
なぜ同じ方法が通用しなくなったのか?

少子化と人材供給の減少
歯科医院の採用が以前より難しくなっている大きな要因の一つは、少子化に伴う労働人口の減少です。日本の総人口はすでに減少局面に入り、特に20代から30代の若年層が減っています。歯科衛生士や歯科助手といった職種は資格やスキルを必要とするため、そもそも人材の母数が限られています。その中で若手層の絶対数が少なくなれば、当然ながら「求人を出せば応募が来る」という構図は成立しなくなります。
また、学校を卒業して新しく歯科衛生士資格を取得する人の数も頭打ちです。全国的に歯科衛生士養成校は存在しますが、入学者数は年々安定しているものの増加には至っておらず、需要の高まりに供給が追いついていません。特に都市部の歯科医院では、数多くの医院が限られた人材を取り合う形になり、条件の似た求人が乱立しています。この状況で同じ求人を繰り返し出しても、単純に分母が少ないため効果は出にくいのです。
つまり、人口動態という不可逆的な要因が背景にある以上、従来の「数を打てば当たる」という発想は通用しません。むしろ「数少ない応募者にどう魅力を伝えられるか」が問われる時代に入っているのです。
働き方に対する価値観の多様化
もう一つの背景は、働き方への価値観が大きく変化している点です。かつては給与や休日数などの条件面が最優先で、一定の基準を満たしていれば応募につながることが多くありました。しかし現在は「ライフスタイルとの両立」「自分に合った環境」「成長できるかどうか」といった多様な要素が判断基準になっています。
歯科医院で働くスタッフの多くは女性であり、子育てや家庭との両立が現実的な課題です。「急な休みに対応できるか」「時短勤務は可能か」といった柔軟性は、単なる条件以上に重要視されます。さらに、若い世代は「やりがい」や「チームの雰囲気」も大きな決め手にしています。SNSの普及によって職場の雰囲気や実際の働き方が可視化されるようになり、「条件が良くても雰囲気が合わなければ応募しない」という選択が当たり前になっています。
このように、求職者が求める基準が多様化している中で、同じ求人を出し続けても「条件の羅列」にしか見えず、心に響きにくくなります。単に給与や待遇を提示するだけではなく、「どんな人が働いていて、どんな日常があるのか」を伝えなければ選ばれない。背景にあるのは、働き手の価値観が変化し続けているという事実です。
情報取得の手段が変わった
インターネットとSNSの普及は、採用活動のあり方を根本から変えました。かつてはハローワークや紙媒体での求人が主流であり、求職者が得られる情報は限られていました。そのため、同じ求人を繰り返し出しても「目に入ること自体」に大きな意味がありました。しかし今では、求職者は求人サイト、SNS、口コミサイト、さらには医院の公式サイトまで自由に比較できます。情報が氾濫しているからこそ、同じものを繰り返しても埋もれてしまうのです。
特に若い世代はInstagramやTikTokといったSNSで職場の雰囲気を調べる傾向が強く、求人広告よりもリアルな情報を重視しています。実際に働くスタッフの声や日常の様子が伝わらなければ、「応募したい」とは思われません。同じ求人広告を繰り返すことは、こうした情報環境の変化を無視したやり方であり、現代の求職者の行動パターンとズレているのです。
また、Googleなどの検索エンジンは常に最新情報を優先表示する仕組みを採用しています。同じ内容の求人はアルゴリズム上も不利になり、露出機会が減少します。情報の取得方法が変化した今、更新のない広告は「存在していない」に等しくなっているのです。
競争環境の激化と医院ブランディングの必要性
さらに大きな変化として、歯科医院同士の競争が激化している点が挙げられます。都市部では医院の数が多く、求職者にとっては選択肢が豊富です。条件面で大きな差をつけにくい状況では、「どんな医院で働くか」というブランディングが採用成功の鍵を握ります。
一方で、同じ求人を出し続ける医院は「自院の魅力を言語化できていない」と見られやすくなります。求職者からすれば「他の医院は雰囲気や働き方を発信しているのに、この医院は条件だけで変化がない」という印象になります。結果として「ブランド力の弱い医院」という評価につながり、ますます応募が集まりにくくなるのです。
医院のブランドとは、単に「おしゃれな雰囲気」という意味ではありません。「ここで働けば自分にとってメリットがある」「安心して長く続けられる」と感じてもらえる信頼そのものです。時代背景として、医院の数が多い環境下で求職者は医院を“選ぶ立場”に立っているため、ブランディングを意識した情報発信が不可欠になっています。
同じ求人を繰り返すことは、この競争環境の中で「差別化できていない医院」として埋もれてしまう最大の要因になります。
歯科医院が求人発信で見直すべきポイント

求職者が知りたい「日常」を描く
求人票に記載される給与や勤務時間といった条件は当然必要ですが、それだけでは応募者の心は動きません。現在の求職者が知りたいのは「実際に働いたときにどんな日常が待っているのか」という点です。例えば、診療前の朝礼での雰囲気や、診療後にスタッフ同士でどのように声を掛け合っているのか。あるいは、子育て中のスタッフが急な休みにどう対応できているのか。そうした小さな日常の断片が、応募者にとっては自分を重ねるための判断材料になります。
この「日常」を描く工夫は、多くの医院が見落としがちなポイントです。求人広告に文章だけを羅列しても、読み手は感覚的にイメージできません。そこで効果的なのが具体的なエピソードの挿入です。「昼休みに子どもを迎えに行けた」「院長が新人に付き添って患者対応をサポートした」といった一言があるだけで、医院の空気感は一気に伝わります。応募者は条件よりも「自分が安心して働けそうか」を知りたいのです。同じ求人を出し続ける代わりに、日常を切り取った情報を更新していくことが大きな改善につながります。
スタッフの声を活かす
応募者が最も信頼を寄せる情報源は「実際に働いている人の声」です。歯科医院の求人改善で効果的なのは、スタッフ自身の体験談を積極的に発信することです。「子育てと両立できて助かった」「前職では残業が多かったが、今は定時に帰れる」といったリアルな言葉は、条件の羅列よりも強く響きます。
同じ求人を出し続けて効果が薄れるのは、言葉にリアリティがないからです。そこで、スタッフの声を定期的に更新する仕組みを作れば、常に新鮮な求人情報として受け止められます。文章にするだけでなく、写真や動画を交えるのも効果的です。例えば、インスタグラムで「1日の仕事の流れ」を紹介する投稿を連動させれば、応募者はより具体的に職場をイメージできます。
また、スタッフ紹介は応募者だけでなく、医院に在籍するメンバーにとっても「自分たちの医院を誇れる」機会になります。内部のモチベーションにも良い影響を与えるため、採用活動と職場づくりを両立できる取り組みとして大きな意味を持ちます。
条件より「働き方の柔軟性」を示す
やすいのは、「これからの歯科採用で重要なのは、条件面の強調ではなく「柔軟に働ける環境」を示すことです。たとえば、勤務日数や時間の調整ができる、子どもの行事に合わせてシフトを組める、スキルに応じて段階的に業務を任せてもらえる、といった具体的な柔軟性です。
同じ求人を繰り返し出すだけでは、こうした「変化に対応できる医院の姿勢」が伝わりません。結果として「融通が利かない職場」という誤解を招くことさえあります。逆に、求人票の中で柔軟性をしっかり伝えれば、応募者は「ここなら自分の生活と両立できそう」と安心できます。
具体例を挙げれば「週3日から勤務可能」「午前のみの勤務も相談可」といった表現が有効です。ただし、単なる制度の列挙ではなく「実際にどのように活用されているか」を伝えることが大切です。「子育て中のスタッフが週3日勤務で活躍している」「介護と両立しながら午前勤務を続けている」といった実例を添えれば、柔軟性が単なる言葉ではなく、現場で機能していることが伝わります。出しっぱなしの求人」からは事情が見えず、誤解だけが積み上がっていくからです。
更新を前提にした発信サイクルを作る
改善の最も基本的なポイントは「求人情報を出しっぱなしにしない」ということです。同じ求人を出し続けて効果が薄れるのは、内容が更新されないからです。逆にいえば、定期的に情報を更新し、発信サイクルを作れば「常に新鮮な求人」として応募者に届きます。
例えば、3カ月ごとにスタッフの声を入れ替える、半年ごとに医院の取り組みを紹介する、といったルールを設けるだけでも効果は大きく変わります。更新のたびに「医院は変化している」「現場のリアルを伝えている」というメッセージが応募者に届きます。これにより、「長期間同じ求人が出ている=人が定着しない」という誤解も防げます。
また、求人媒体だけに頼らず、自院のホームページやSNSを活用することも重要です。ホームページで最新の取り組みを紹介し、SNSで日常を発信すれば、求人票の情報が補完され、応募者は立体的に医院を理解できます。こうした複数チャネルを組み合わせた発信が、今後の採用では不可欠になるのです。
明日からできる具体的な取り組み

①求人文を「使い回さない」習慣をつける
最も手軽に始められる改善は、「同じ求人文を繰り返し出す」という習慣をやめることです。文章をゼロから作り直す必要はなく、ポイントごとに一部を差し替えるだけで十分です。例えば、冒頭のメッセージを「現在は歯科助手を募集中です」から「この春から新しい仲間を迎えたいと考えています」に変えるだけで、読み手に新鮮さを与えられます。
また、医院で最近起きた小さな変化を文章に盛り込むのも効果的です。「新しい滅菌器を導入しました」「スタッフの研修を強化しました」といった情報は、現場が進化している証拠になり、応募者に安心感を与えます。同じ文章を使い回すのではなく「更新前提で求人を作る」ことが、最初のアクションです。
この取り組みを始めるだけで、求人を出し続けることによる“停滞感”を払拭し、「動きのある医院」として見てもらうきっかけになります。
②スタッフのストーリーを積極的に取り入れる
求人広告に「働く人の声」を盛り込むことは、効果的でありながら意外と実行されていない取り組みです。明日からでもできることは、まず既存スタッフに短いインタビューを行い、簡単なコメントを集めることです。「入職して一番助かったこと」「職場で好きな時間」「続けて良かったと感じる瞬間」など、1~2文で答えられる質問を準備すれば、無理なく集められます。
その声を求人広告に差し込めば、文章は一気にリアルになります。例えば「子どもの行事に参加できるようになり、家庭との両立がしやすくなった」といった一文は、条件の羅列よりも応募者の心に響きます。また、医院のホームページやSNSでそのコメントを紹介すれば、より立体的に医院を伝えられます。
「スタッフが主役の発信」を取り入れることは、採用だけでなく在籍スタッフのモチベーション向上にもつながります。発信に協力することで「自分の医院を一緒に育てている」という意識が芽生えるからです。
③採用媒体に頼らない発信チャネルを増やす
求人サイトや紙媒体だけに依存するのではなく、自院の情報発信チャネルを持つことも、明日から始められる具体的な取り組みです。ホームページやSNSを活用し、求人広告では伝えきれない日常や雰囲気を発信していきましょう。
特にInstagramは、写真や短い動画で医院の雰囲気を直感的に伝えられるため、歯科医院の採用と相性が良い媒体です。「スタッフ紹介」「院内イベント」「研修風景」といった投稿を積み重ねることで、応募者は「ここで働く自分」を具体的にイメージできます。これにより、求人広告を出した際にも「すでに知っている医院」として親近感を持ってもらえ、応募のハードルが下がります。
また、LINEやメールを活用して「気軽に見学相談を受け付ける」といった導線を用意すれば、応募までの心理的な距離を縮められます。求人広告の枠を超えた発信を持つことが、同じ求人を繰り返すことから抜け出すための具体的な一歩になります。
④採用活動を「医院の成長戦略」として捉える
最後に重要なのは、採用活動を単なる人員補充ではなく「医院の成長戦略」として位置づけることです。明日から取り組める行動としては、求人を出す前に「この採用で医院をどう変えたいのか」を一度立ち止まって考えることです。
例えば「診療ユニットを増やすために衛生士を採用したい」「患者対応の質を上げるために助手を増やしたい」といった明確な目的を設定すれば、求人の打ち出し方も自然に変わります。目的を明確にすることで、求人文には「この医院がどこを目指しているか」が表れ、応募者にとっても共感しやすいメッセージになります。
採用は単なる作業ではなく、医院の未来像を描く行為です。求職者に「この医院で一緒に成長できる」と感じてもらえれば、求人の効果は格段に高まります。同じ求人を繰り返すのではなく「未来を示す求人」へと切り替える意識が、これからの歯科採用の肝になります。
歯科医院の採用で「同じ求人を出し続ける」ことは、もはや有効な方法ではありません。むしろ「人が定着しないのでは」という不信感を招き、応募数を減らす逆効果を生みます。その背景には、少子化による人材不足、働き方への価値観の多様化、情報収集手段の変化、そして医院同士の競争激化があります。これからの採用で重要なのは、条件の羅列ではなく「日常の具体性」や「スタッフの声」を伝え、変化を発信し続けることです。採用活動を医院の未来を描く戦略と捉え直し、常に新鮮で信頼性のある情報を届けることが、応募を集めるための第一歩となります。