訪問歯科衛生士の採用に取り組む中で、「求人を出しても応募が少ない」「採用できてもすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えているクリニックは少なくありません。一般の歯科衛生士と比べて訪問分野の仕事はイメージが湧きにくく、仕事内容や働き方が具体的に伝わらないことが多いからです。その結果、応募につながらない、あるいは応募があっても期待していた人材とミスマッチが起きるといった問題が発生します。
さらに、訪問歯科の現場は「一人で患者宅を訪問するのではないか」「医療対応に不安がある」といった誤解を持たれやすく、求人情報だけでは安心感を与えられないこともあります。加えて、求人媒体の選び方や発信方法によっては、求めている層に情報が届かないケースも少なくありません。
本記事では、訪問歯科衛生士の採用を成功させるために必要な視点を、原因分析から改善策、求人条件の工夫、面接の進め方、採用後の定着支援まで順を追って解説します。単なる求人票作成にとどまらず、SNSの活用や紹介制度の運用など実践的な工夫も紹介し、応募者を増やし、長く働いてもらえる環境づくりを目指すための具体的なヒントを提示していきます。
次の章では、まず「なぜ訪問歯科衛生士の求人に応募が集まりにくいのか」という3つの原因から掘り下げていきます。
訪問歯科衛生士の求人で応募者が集まらない3つの原因

訪問歯科のイメージが出来ない
訪問歯科の現場では、歯石除去やブラッシング指導といった一般的な業務に加え、摂食状況の観察、嚥下機能の確認、介護職や家族への指導など、多面的な対応が求められます。しかし、求人票ではこれらの幅広い役割が「口腔ケア」などの短い表現で済まされ、実態が伝わらないことが少なくありません。
その結果、「専門性が高すぎて難しそう」「自分には荷が重い」と誤解されることがあります。本来、訪問歯科衛生士は在宅医療チームの一員として患者の生活を支える重要な存在であり、やりがいのある仕事です。その意義を伝えるためには、単なる業務リストではなく「患者の食事が改善して笑顔が増えた」「介護職から感謝された」といった具体的なエピソードを求人に盛り込むことが効果的です。
また、業務のサポート体制を明記することも大切です。「訪問時は必ず歯科医師と同行」「ケースごとにチームで振り返りを実施」といった一文があるだけで、孤立感の不安は和らぎます。業務内容を正しく、かつ安心感を持って伝えることが応募を呼び込む鍵になります。
求人媒体選びの適切な選択方法
応募が集まらない理由の一つに、求人媒体の選び方があります。訪問歯科という分野はまだ一般的な認知度が高くなく、通常の転職サイトや紙媒体では求職者に届かないこともあります。特に若年層はInstagramやTikTokなどのSNSを利用して情報収集をしており、中堅層は歯科専門求人サイトや紹介会社を使う傾向が強いといえます。
そのため、ターゲット層に合わせた媒体選びが不可欠です。例えば「子育て世代のパート希望者」を狙うなら、地域密着型の求人媒体やSNS発信が効果的です。一方で「キャリアを積んだ中堅層」には、歯科業界専門の転職求人媒体を活用するなど、ペルソナに応じた採用戦略を立てる必要があります。
さらに、媒体ごとに役割を分けて活用することも重要です。SNSでは現場の雰囲気やスタッフ紹介を発信し、採用サイトでは詳細な条件や福利厚生を整理し、紹介会社では求める人材像を明確に伝える、といった使い分けが成果につながります。媒体は数を増やせばよいわけではなく、ターゲットに最も響く場所に集中することが応募増加の近道です。
訪問歯科衛生士採用を成功させる具体的な改善策

魅力的な求人票の作成テンプレート
求人票は応募者との最初の接点であり、情報の伝え方次第で応募数が大きく変わります。しかし多くの求人は条件や業務内容の羅列にとどまり、求職者が「自分に合うかどうか」を判断できる情報が不足しています。重要なのは、仕事内容や待遇を伝えるだけでなく「ここで働いたらどんな日常が待っているか」を描くことです。
例えば「午前は施設訪問、午後は在宅ケア、夕方は医院に戻り片付け」といった1日の流れを示すと、働き方のイメージが明確になります。また「子育て中スタッフは保育園の送迎に合わせて勤務調整可能」といった具体的な制度利用例を添えることで、制度が形だけでなく実際に使えると伝わります。さらに、現場スタッフの体験談を引用するのも効果的です。「最初は不安だったが同行研修で安心できた」などの声は、応募者の不安を和らげ、共感を生みます。
求人票作成の基本は「共感→理想の未来→スタッフの声→制度の安心→行動導線」という流れです。まずは求職者が抱えがちな悩みに触れ、その後に「この職場なら解決できる」と未来像を提示します。次にリアルなスタッフの声で信頼性を補強し、制度や研修の具体像を伝え、最後に「見学歓迎」「同行訪問OK」と心理的ハードルを下げる導線を設けます。条件の数字より、生活に直結するシーンを描くことが応募を後押しします。
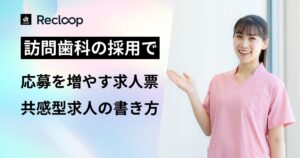
SNSを活用した採用ブランディング手法
従来の求人媒体だけでは訪問歯科の魅力が十分に届かないため、SNSを活用した採用ブランディングが重要です。InstagramやTikTokといったビジュアル中心の媒体では「働く人の表情」「現場の雰囲気」「スタッフ同士のやり取り」などを伝えることができます。これらは求人票だけでは表現できない要素であり、求職者が「ここで働く自分」を具体的に想像できるきっかけになります。
特に効果的なのは、スタッフの1日を短い動画や写真で紹介することです。訪問前の準備、患者宅での対応、直帰後の感想などをつなぐだけで、求職者は「どんな仕事か」「働きやすい環境か」を直感的に理解できます。また、「子育てと両立できている」「復職後でも安心して働ける」などライフスタイルに寄り添った投稿は共感を呼びます。
SNSは採用活動の「広告」ではなく「ブランディングの場」として位置づけることが大切です。医院の考え方やスタッフの価値観が自然に伝わる発信を継続すれば、応募前にすでに親近感や信頼感を持ってもらえます。さらに、ハッシュタグやリール機能を活用し、地域や職種で検索されやすい形にすることで露出が増えます。SNSを通じて「応募前にすでに好きになってもらう状態」を作ることが、採用成功への近道です。下記記事は訪問看護向けに記載した記事ですが、訪問歯科でも役立つ内容ですので一読ください。

リファラル採用の効果的な運用方法
リファラル採用は、既存スタッフからの推薦を通じて人材を集める手法であり、訪問歯科衛生士の採用においても有効です。信頼できる人からの紹介は応募者の不安を大きく和らげ、定着率も高くなる傾向があります。ただし「紹介してください」と呼びかけるだけでは機能しません。効果を出すには運用方法の工夫が欠かせません。
まず大切なのは、紹介された人が安心して応募できる仕組みを整えることです。例えば「見学だけでもOK」「まずはカジュアル面談から」といった導線を用意することで、紹介者も気軽に声をかけやすくなります。また、紹介したスタッフに対しても金銭的な報酬だけでなく「表彰」「感謝のメッセージ」といった非金銭的なフィードバックを組み合わせると、制度が形骸化せず継続的に利用されます。
さらに、紹介を依頼する際には「どんな人に来てほしいのか」を明確に伝えることが大切です。「子育て中でも柔軟に働きたい人」「訪問に興味はあるが未経験の人」など具体的な人物像を示すと、紹介者も声をかけやすくなります。紹介制度は単なる人材集めの手段ではなく「スタッフ全員で仲間を迎え入れる文化づくり」の一環として位置づけることが、長期的な採用成果につながります。
未経験者も応募したくなる求人条件の設定方法

研修制度・サポート体制の充実
未経験者が応募をためらう大きな理由は「自分にできるだろうか」という不安です。その不安を和らげるには、研修制度やサポート体制を明確に示すことが欠かせません。求人票に「研修あり」と一言添えるだけでは十分ではなく、「どのくらいの期間」「誰が担当」「どのような内容」を具体的に示す必要があります。
例えば「入職後3か月は先輩衛生士とペアで訪問」「最初の1か月は医師同行が中心」「困った時は即時チャットで相談可能」といった情報は、未経験者にとって安心材料になります。さらに、定期的な振り返り面談やケースカンファレンスの存在を伝えると「学びながら成長できる職場」というイメージを持ってもらえます。
また、研修内容はスキル面だけでなく「患者や家族とのコミュニケーション」「介護職との連携」など、訪問ならではの要素を含めると現場適応力を高められます。実際の先輩が研修を経て自信を持ったエピソードを紹介するのも効果的です。求職者は「制度がある」ことより「制度で成長できる」ことを求めています。こうした情報を盛り込むことで、未経験者でも一歩を踏み出しやすくなります。
柔軟な勤務時間・働き方の提案
訪問歯科に関心を持ちながら応募をためらう人の多くは、勤務時間や働き方に制約を抱えています。子育てや介護をしている人、フルタイム勤務に不安を感じる人にとって、柔軟な勤務体制が用意されているかどうかは大きな決め手となります。
「午前のみ勤務可能」「週3日から勤務OK」「直行直帰対応」といった具体的な条件を求人に記載することで、応募のハードルは一気に下がります。さらに「学校行事や家庭の事情による急な休みにも対応できる」といった事例を示せば、安心感が高まります。
訪問歯科は患者宅や施設への移動が伴うため、シフトの工夫や担当エリアの調整で柔軟性を出しやすい特徴があります。これを強みとして打ち出すことで「訪問歯科なら自分に合った働き方ができる」という認識を広めることが可能です。実際に柔軟な働き方をしているスタッフの声を載せることで、求職者は自分の生活と重ね合わせやすくなり、応募意欲が高まります。
キャリアアップ支援制度の整備
未経験者が長期的に働きたいと思うかどうかは、キャリアの展望を描けるかにかかっています。「訪問の仕事は補助的な役割にとどまるのでは」と誤解されやすいため、キャリアアップの道筋を明確に示すことが重要です。
例えば「訪問未経験からスタートして2年後にチームリーダーへ」「在宅医療の専門資格取得を支援」「学会参加や研修費用を会社が補助」といった情報は、成長意欲のある人に強い動機付けを与えます。また「管理者候補としてキャリアを積める」「教育担当者として新人育成に関われる」といった役割を提示すれば、単なる現場業務にとどまらない将来像を描けます。
キャリア支援を打ち出す際は「具体的にどんなサポートを受けられるのか」を示すことが大切です。資格取得の補助額や対象資格、キャリア相談の頻度など、数字や仕組みを伴った説明は説得力を持ちます。未経験者にとって「安心して始められる環境」と「成長できる未来像」が両立していると感じられる求人は、応募につながりやすくなります。
訪問歯科衛生士の採用面接で見るべきポイント

訪問歯科に適した人材の見極め方
訪問歯科衛生士の採用では、外来業務に比べて「人柄」や「柔軟さ」が重視されます。患者の生活の場に入る仕事であるため、技術力だけではなく、コミュニケーション力や環境適応力が不可欠です。面接時に確認したいのは、臨機応変に対応できるか、患者や家族の気持ちを尊重できるか、そしてチームワークを大切にできるかという点です。
例えば「患者宅で予定外の状況が起きたとき、どう対応しますか」といった質問で、冷静さや判断力を見極められます。また、これまでの職場での経験を掘り下げ「どのように人と関わり、信頼を築いてきたか」を聞くと、訪問に必要な姿勢が見えてきます。さらに、相手の話を最後まで聞けるかどうかも重要です。面接中の受け答えの仕方そのものが、患者対応の適性を示すサインになります。
訪問歯科では「正確に歯科処置をする能力」よりも「患者と長期的に関係を築ける力」が定着と満足度を左右します。そのため、採用の段階でスキルよりも人間性を重視し、教育で技術を補う方針を持つことが、成功につながります。

面接質問例と回答の評価基準
採用面接を成功させるには、事前に質問を用意し、評価基準を共有しておくことが重要です。感覚に頼った評価では、担当者ごとに基準が揺れ、採用の質が安定しません。訪問歯科に適した人材を見極めるには、実際の業務に近いシーンを想定した質問が有効です。
例えば「患者が拒否的な態度を示したとき、どう声をかけますか」「介護スタッフと意見が食い違ったら、どのように調整しますか」といった質問は、現場を意識した回答を引き出せます。ここで重要なのは「正解の有無」ではなく、相手の思考プロセスや姿勢を確認することです。柔軟に対応しようとするか、相手を尊重する姿勢があるかを評価します。
また、質問に対する回答内容だけでなく、話し方や表情、態度も評価対象に含めると適性を見極めやすくなります。評価基準を「傾聴力」「協調性」「柔軟な対応力」「学習意欲」といった軸に分け、複数の面接官でスコア化すれば、主観に偏らず公平な判断が可能です。面接は採用の分岐点であり、基準の明確化が質の高い採用を支える要素になります。
見学・同行による適性確認
訪問歯科衛生士の採用においては、面接だけでは見極めが難しい側面があります。そこで有効なのが「見学」や「同行」を取り入れた適性確認です。短時間でも実際の現場を体験してもらうことで、応募者自身が仕事内容を具体的に理解でき、クリニック側も応募者の適性を自然な形で確認できます。
例えば半日程度の見学で「患者宅への訪問の流れ」「準備や片付けの手順」「医師や助手との連携の様子」を見てもらうと、文章や説明だけでは伝わらない仕事の実態が分かります。同行では「患者や家族への声かけの仕方」「介護職とのやり取り」を観察でき、応募者のコミュニケーションの姿勢を把握する手がかりになります。
また、見学や同行の後には必ずフィードバックの時間を設け、「感じた不安」や「良いと思った点」を聞き出すことで、相互理解が深まります。このプロセスは応募者の不安を軽減し、納得感のある入職につながると同時に、早期離職を防ぐ効果もあります。実務試験のように応募者を緊張させる方法ではなく、自然な環境で適性を見極められる見学・同行は、訪問歯科に特化した採用方法として非常に有効です。
採用後の定着率を高める職場環境づくり

オンボーディングプログラムの構築
採用後の離職が多い理由のひとつは「入職後の不安が解消されないまま放置されること」です。訪問歯科衛生士は未経験からスタートするケースも多く、最初の数か月をどう過ごすかで定着率は大きく変わります。そのため、入職直後から段階的に慣れていけるオンボーディングプログラムを用意することが欠かせません。
例えば「入職1週目は院内研修と同行のみ」「2週目からは簡単なケアを担当」「1か月後から独り立ち」といった流れを明示すると、先の見通しが立ち安心できます。さらに、チェックリスト形式で習得項目を確認できるようにすると、本人も達成感を持ちながら成長を実感できます。
オンボーディングは単なる研修ではなく「職場文化や人間関係に溶け込むプロセス」です。仕事の内容だけでなく、チームのコミュニケーション方法や業務のルールを早期に共有することが重要です。入職初期にサポートが整っていると「ここなら長く働けそうだ」と思えるため、定着率を高める最初のカギとなります。
メンター制度の導入と運用
訪問歯科衛生士の仕事は、現場での判断や対応が多く、孤独感を覚えやすいという特徴があります。そのため、先輩スタッフが新入職員を一定期間サポートする「メンター制度」が効果を発揮します。メンターが日常的な相談相手となることで、不安や疑問を早期に解消でき、モチベーション低下や早期離職を防ぎやすくなります。
メンター制度を形だけにしないためには、役割を明確にすることが必要です。例えば「週1回の振り返り面談を行う」「訪問後に必ずフィードバックをする」といった具体的なルールを設けると、制度が機能します。また、メンター自身へのフォローも欠かせません。指導の負担が一方的にならないよう、管理者がサポートし、感謝の姿勢を見せることが継続性を支えます。
さらに、メンターとメンティーの相性も重要です。可能であれば性格や働き方を考慮して組み合わせると効果的です。信頼できる相談相手がいることで新入職員の安心感は増し、定着につながります。
定期的なフォローアップ面談の実施
採用直後のフォローが整っていても、時間が経つにつれ新たな不安や課題が生まれます。そのため、定期的なフォローアップ面談を実施し、状況を確認し続けることが定着率向上に直結します。特に「3か月」「6か月」「1年」の節目は離職リスクが高まりやすいため、このタイミングでの面談は欠かせません。
フォローアップ面談では「仕事の理解度」「職場環境への適応度」「今後のキャリア希望」を確認し、必要に応じてサポートを調整します。また、面談は上司だけでなく第三者的立場のスタッフや人事担当が行うと、本音を引き出しやすくなります。
面談の場で重要なのは「問題解決」よりも「安心して話せる場をつくること」です。スタッフが「自分の声を聞いてもらえている」と感じるだけでもモチベーションが保たれやすくなります。小さな不満や疑問を早期に拾い上げて改善する姿勢が、信頼感を築き、長期定着へつながります。
訪問歯科衛生士の採用は、応募を集めるだけでなく「安心して働き続けてもらうこと」が最大の課題です。応募が集まらない原因を把握し、魅力的な求人票やSNSでの発信を工夫し、未経験者でも挑戦できる条件を整えることが第一歩になります。さらに、面接では人柄や柔軟性を重視し、見学や同行を通じて適性を確認することでミスマッチを減らせます。そして採用後は、オンボーディングプログラム、メンター制度、定期面談を通じて不安を解消し続けることが定着率向上に不可欠です。採用から定着まで一連の流れを意識して整えることで、訪問歯科衛生士が安心して働ける環境が整い、結果的に安定した採用成功へとつながります。
株式会社HOAPでは訪問歯科の採用支援を行っております。特に近年はSNSの活用が採用成功を左右するとも言われています。採用に悩む院長は1度ご相談ください。
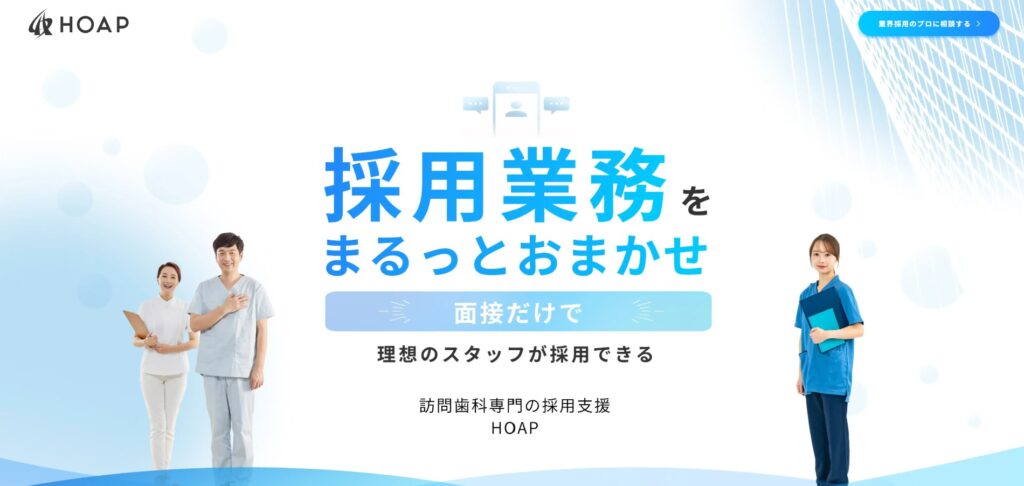
歯科医師や歯科衛生士・歯科助手などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。










