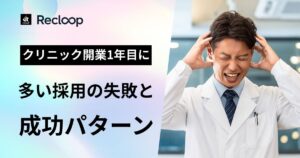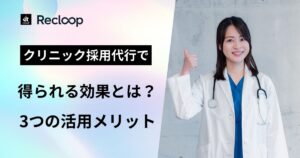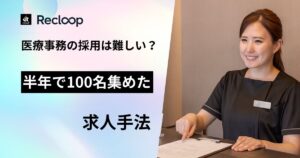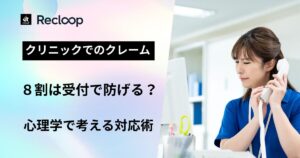小規模クリニックの採用において、「求人を出しても応募が来ない」「せっかく採用してもすぐに退職してしまう」といった声は少なくありません。特に看護師や医療事務といった職種は、慢性的な人材不足が続いているうえ、病院や大規模法人と比較されることが多く、知名度や条件面で不利に感じてしまうケースが多いのが現実です。
こうした状況に直面したとき、従来型の「求人を出して待つ」スタイルだけでは限界があります。求職者が能動的に動く市場ではなく、より多くの医療従事者が「条件や働き方を比べながら検討する」時代へと変化しているためです。そのため小規模クリニックこそ、待ちの姿勢ではなく、こちらから候補者に声をかけていく「スカウト採用」を導入する意義が高まっています。
スカウト採用は、従来の求人広告では出会えなかった人材に直接アプローチできる点が特徴です。看護師に対しては「夜勤がない」「家庭との両立がしやすい」といったメリットを伝え、医療事務に対しては「働きやすさ」や「人間関係の安心感」を前面に出すことで、応募につながりやすくなります。また、限られたリソースで運営される小規模クリニックだからこそ、一人の採用が持つ影響力は大きく、戦略的なスカウトの取り組みが必要不可欠になります。
本記事では、まず小規模クリニックにおける採用がなぜ難しいのかを掘り下げ、そのうえでスカウト採用の有効性を整理します。さらに、看護師と医療事務それぞれでのスカウト活用方法、そして最後に支援会社への代行活用という選択肢までを紹介し、実践的な視点から採用成功のヒントを提示していきます。次に、そもそも「なぜ小規模クリニックの採用は難しいのか」という根本的な課題について考えていきましょう。
なぜ小規模クリニックの採用は難しいのか

病院と比べられやすい
小規模クリニックの採用が難しい背景の一つは、求職者が転職活動をする際に「まず病院や大規模法人を検討する」という流れが一般的だからです。看護師にとって病院は教育体制やキャリアの広がりが明確にイメージでき、医療事務にとっても「安定感がある」「仲間が多い」という印象が強くあります。その結果、クリニックは「病院と比べて小さい場所」という印象に引きずられ、最初の検討リストに入りにくいのです。
また、求人票の見え方においても大きな差が生じます。病院は「教育研修が整っている」「福利厚生が手厚い」といった制度面を強調できるのに対し、小規模クリニックはそこまでの制度を整えることが難しい場合が多いです。結果的に、応募者から見て「条件が少なく見える」という誤解を招きやすくなります。
ただし実際には、小規模であることが必ずしも不利というわけではありません。顔の見える関係で働けることや、患者との距離の近さ、柔軟な働き方ができることは、病院勤務にはない魅力です。しかし「まず病院と比べられる」という比較を乗り越えるためには、求人の出し方や伝え方に一工夫が求められます。
求職者が応募をためらう心理的な壁
もう一つの難しさは、求職者が抱える「心理的な壁」です。特に病院での経験が長い看護師は、「もっと専門スキルを磨きたい」「幅広い看護技術を学びたい」と考えることがあります。その一方で、クリニックは急患や重症患者に対応する機会が少ないため、「ここでは自分のキャリアが思うように伸ばせないのでは」と受け止められてしまうことがあるのです。
医療事務でも似たような不安があります。受付や会計、カルテ入力に加え診療補助を担う場合もあるため、「業務が幅広すぎて未経験では難しいのでは」と思い込まれがちです。現場では段階的に学び、先輩スタッフのフォローを受けながら成長できる環境が多いのですが、求人票だけではその点が伝わらないことが多いのです。
つまり「業務そのものが過酷」というわけではなく、「実情がわからないために過度に不安を抱く」ことが応募を遠ざけています。求人や広報では、実際の一日の流れや新人がどのようにサポートを受けているかを明確に示すことが、心理的な壁を取り除くうえで欠かせません。
採用広報に使えるリソース不足
小規模クリニックでは採用担当者を専任で置けないケースが大半です。院長や事務長が診療や運営と兼務しながら採用活動を進めているため、どうしても後回しになりがちです。その結果、求人票の更新が遅れたり、応募者対応に時間がかかってしまったりすることも珍しくありません。応募者にとってはレスポンスの遅さが「この職場は採用に本気ではないのでは」という印象につながり、辞退を招くリスクとなります。
さらに情報発信の工夫も不足しがちです。大規模病院や法人では採用サイトやSNSを活用して職場の雰囲気を伝える取り組みが広がっていますが、クリニックではその余力がない場合が多いです。結果として「求人媒体に掲載して待つだけ」の採用になり、候補者との接点を広げられないまま終わってしまうケースが少なくありません。
採用活動に割けるリソースが限られていること自体は仕方のない現実ですが、それが応募数の減少や内定辞退の増加に直結している点は見逃せません。この課題を補うには、限られた時間でも効果的に候補者に届く方法を選ぶ必要があります。
地域性に左右されやすい採用市場
最後に、小規模クリニックが直面する特徴的な課題が「地域性の影響」です。都市部では医療機関が多数存在し、候補者はより条件の良い職場を比較検討できます。そのなかで小規模クリニックが選ばれるには、「病院にはない柔軟性」や「スタッフ間の距離の近さ」といった独自の魅力をはっきり示す必要があります。
一方で地方や郊外では、そもそも人材の母数が少なく「採用したい人が市場にいない」という状況が頻発します。特に看護師不足は全国的に深刻であり、その影響は小規模クリニックに直撃します。都市部のように求人を出せば一定数の応募が来るという環境ではなく、候補者が現れたときにいかにアプローチできるかが勝敗を分けます。
さらに地域では口コミや評判が採用に強く作用します。「あのクリニックは忙しそう」「人間関係が大変らしい」といった噂が広がると、それだけで応募が減ってしまいます。逆に「休みが取りやすい」「雰囲気が良い」といったポジティブな声が広がれば、応募につながることもあります。地域性を軽視すると採用活動は大きく停滞してしまうのです。
スカウト採用がクリニックに有効な理由

看護師・医療事務は「待つ採用」では人材が集まりにくい
小規模クリニックの採用活動において、求人広告を出して応募を待つ従来型の方法は限界に近づいています。特に看護師や医療事務は全国的に不足しており、そもそも「応募しよう」と動く候補者の数自体が少ないのです。そのなかで、病院や大規模法人のように知名度や条件で勝負するのは難しく、求人票だけで応募を集めるのは現実的ではありません。
さらに、求人広告に応募してくる層は「今すぐ転職を考えている人」に限られます。しかし実際の転職市場を見れば、看護師や医療事務の多くは「いずれ転職するかもしれない」「情報収集だけしておこう」という“潜在層”です。この層に届かない限り、母集団を広げることはできません。
スカウト採用は、この「待つ採用」の限界を補う手段です。こちらから候補者に直接アプローチすることで、まだ転職活動を本格的に始めていない層にも接点を持てます。応募を「待つ」のではなく、「声をかけて関心を高める」スタイルに変えることで、採用の可能性が広がるのです。
候補者にとってもメリットがあるスカウト採用
スカウト採用は、採用側だけでなく候補者にとっても利点があります。従来の求人広告経由では「自分から応募する」という一歩が必要ですが、スカウトを受け取ることで「自分を必要としてくれている」という安心感が生まれます。これにより、転職を迷っている人でも「話だけ聞いてみよう」と思いやすくなるのです。
特に看護師の場合、病院勤務からクリニック勤務に移る際には「給与が下がるのでは」「スキルが伸びにくいのでは」といった迷いが伴います。そこでスカウトの段階で「夜勤がないため家庭と両立しやすい」「患者さんとの距離が近く、じっくり看護できる」といったポジティブな情報を提示できれば、不安を和らげることができます。
医療事務にとっても同じです。「幅広い業務を任されるのでは」と心配している人に対して、「実際には段階的に学べる環境がある」「チームで協力しながら進めている」と具体的に伝えることで、応募を前向きに検討してもらいやすくなります。候補者にとって「自分に合う職場を知る機会」になるのがスカウト採用の強みです。
「自クリニックらしさ」を表現できる
クリニックは病院と比べると制度や待遇の充実度では劣る面がありますが、その一方で「小規模だからこそ伝えられる魅力」があります。患者との距離が近く、地域医療に深く関わるやりがいを実感できること、スタッフ同士の顔が見える関係でアットホームに働けること、柔軟にシフト調整ができることなどです。
しかし、求人票だけではこうした職場の雰囲気や特徴を十分に伝えきれません。スカウト採用では、一人ひとりに合わせたメッセージを作成できるため、「家庭と両立したい方には休暇の取りやすさ」「スキルを磨きたい方には診療科ごとの経験」を強調するなど、個別に響く情報を届けられます。
これは大規模病院には難しいアプローチです。大量採用を前提とする病院では個別対応はしづらいですが、小規模クリニックは人数が限られるからこそ、候補者ごとに丁寧なコミュニケーションをとることが可能です。その違いが、スカウト採用を通じて強みに変わります。
クリニック採用活動のスピード感を高められる
小規模クリニックにとって「一人の採用」の意味は非常に大きく、欠員が出たまま放置すれば診療体制に直結します。そのため、採用活動にはスピードが求められます。求人広告に応募が来るのを待っているだけでは、必要なタイミングで人材を確保できず、業務負担が増してしまうのです。
スカウト採用では、候補者に直接連絡を取り、面談や見学につなげるまでの時間を短縮できます。さらに、やり取りを通じて「すぐに転職を考えている人」か「まだ情報収集中か」を早い段階で見極められるため、優先順位をつけた対応が可能です。結果的に「必要なときに必要な人を採用する」というクリニックの現場ニーズに応えやすくなります。
加えて、スカウトメッセージは履歴として残るため、たとえすぐに応募につながらなくても、後から「やっぱりあのクリニックに興味がある」と候補者が戻ってくる可能性があります。単発で終わる求人広告とは違い、長期的な関係構築にも役立つのです。
このように、スカウト採用は「待つ採用の限界を補う」「候補者に安心感を与える」「小規模ならではの魅力を伝える」「スピード感を高める」という点で、クリニックにとって極めて有効な手法です。次のセクションでは、具体的に看護師採用においてスカウトをどう活用すれば効果を発揮できるのかを掘り下げていきます。
看護師採用でのスカウト活用法

病院勤務からの転職希望者に響くポイント
病院で働く看護師の多くは、夜勤や残業による負担、休暇の取りづらさに悩んでいます。特に30代以降になると、家庭や子育てとの両立を考える人が増え、「生活を見直したい」という動機で転職を検討するケースが目立ちます。こうした層に対してスカウトで効果的にアプローチするには、クリニックが持つ「夜勤がない」「シフトの柔軟性がある」「休日が確保しやすい」といった利点を強調することが重要です。
ただし注意すべきは、単に「うちは夜勤がありません」と伝えるだけでは差別化につながらないことです。病院以外の多くの職場でも夜勤がないからです。より響く表現にするには、「夜勤がないために子どもの送り迎えができる」「残業が少ないから趣味の時間を確保できる」といった、働き方が生活に与える具体的な影響を盛り込む必要があります。
スカウトは一人ひとりに直接届くメッセージだからこそ、候補者のプロフィールを見て、「家庭を持っている方には育児と両立できる点」「若手で学び直したい方には特定分野の経験が積める点」と、相手に合わせた訴求をすることが効果的です。病院からクリニックへの転職を考える看護師にとって、「自分に合った生活の形が手に入る」と実感できるメッセージが、応募につながります。
キャリア形成を重視する層へのアプローチ
一方で、看護師の中には「スキルアップや専門性を高めたい」という動機で転職を考える人も少なくありません。一般的にはクリニックは急性期対応が少なく、病院のように高度な処置に携わる機会は減ります。そのため「キャリアが停滞するのではないか」という懸念を抱かれがちです。
スカウトでこうした層にアプローチする際には、「診療科ごとに特定の知識や技術を深められる」という点を伝えることが有効です。例えば内視鏡クリニックなら内視鏡介助、小児科なら子どもの発達や予防接種の知識など、特化した分野での経験が積めることを具体的に示すと、キャリア志向の候補者にも魅力が伝わります。
また、教育体制が整っているクリニックであれば、その点を強調するのも効果的です。「新人には必ず一定期間の同行指導がある」「定期的に勉強会を実施している」などの実例をスカウトに盛り込むことで、「スキルが磨けないのでは」という不安を和らげられます。キャリア形成を意識する看護師にとって、学びの場があるかどうかは転職先選びの大きな決め手になります。
スカウト文面に盛り込むべき具体情報
スカウトメッセージは、単なる「応募してください」という呼びかけでは不十分です。候補者に「ここで働くイメージが持てる」情報を盛り込むことで、初めて応募につながります。特に看護師に向けたスカウトには、次のような具体要素を含めることが効果的です。
まずは一日の流れです。「午前は外来対応、午後は健診や処置」といった業務のイメージを伝えることで、候補者は「どんな働き方になるのか」を具体的に想像できます。次に、スタッフ同士の関係性やサポート体制を示すことも大切です。「常に医師が近くにいて指示を仰げる」「先輩がフォローに入る体制がある」といった情報は、安心感を与えます。
さらに、働きやすさを裏付けるエピソードも効果的です。「子どもの急な発熱で休んだ際に、スタッフ同士でカバーし合えた」「定時で帰れる日が多く、家庭と両立しやすい」などの事例は、求人票だけでは伝わりにくいリアルな魅力として候補者の心を動かします。スカウト文面には、制度名よりも「制度がどう役立ったか」のエピソードを盛り込むことが重要です。
スカウトを活かすための応募後対応
スカウトは入口にすぎません。実際に応募や問い合わせにつながった後の対応が、採用成功を大きく左右します。小規模クリニックでは院長が採用業務を兼務しているため、返答が遅れると候補者の関心が冷めてしまうリスクがあります。スカウト採用を成功させるには、応募後のスピード感と丁寧さが不可欠です。
具体的には、スカウトに反応があったら24時間以内に返答することを基本とし、見学や面談の日程を候補者の都合に合わせて柔軟に調整することが望まれます。また、面談の場では給与や休日数といった条件面だけでなく、働き方の柔軟性や人間関係の良さを伝えることで安心感を与えられます。
さらに、応募後のフォローも大切です。「見学後に疑問があれば気軽に相談できる窓口を用意する」「数日後に感想を伺う連絡をする」など、候補者が不安を残したまま辞退してしまわないように工夫することが求められます。スカウトで関心を持った候補者を、応募から採用までしっかり導くことができれば、クリニックにとって大きな成果につながります。以下の記事は歯科医院向けに書かれておりますが、クリニック採用にも役立ちますので、合わせてご確認ください。

このように、看護師採用におけるスカウト活用は「病院勤務からの転職希望者への訴求」「キャリア志向層への対応」「具体的なメッセージ設計」「応募後の迅速なフォロー」がポイントとなります。次のセクションでは、医療事務採用におけるスカウト活用方法について掘り下げていきます。
医療事務採用でのスカウト活用法

医療事務経験者と未経験者で異なるアプローチ
医療事務の採用においては、候補者のバックグラウンドによって響くポイントが大きく変わります。経験者の場合は「どんなシステムを使っているか」「業務の幅がどこまでか」といった実務面を重視する傾向が強いです。そのためスカウト文面では「電子カルテは◯◯システムを使用」「レセプト業務は専任スタッフが担当」といった具体的な情報を提示することで、業務量や負担をイメージしやすくし、安心感を与えられます。
一方、未経験者は「本当に自分でもできるのか」という不安が大きく、経験者向けと同じ情報を伝えても響きません。未経験者には「入職後に基礎から学べる環境がある」「研修やOJTでサポートがある」という安心感を前面に出すことが重要です。さらに、「受付業務から始め、徐々に会計やカルテ入力に進む」といった成長のステップを示せば、未経験でも挑戦しやすい印象を与えられます。
経験者と未経験者をひとまとめにして募集すると、どちらの心にも刺さらない曖昧なメッセージになりがちです。スカウトは個別に送るからこそ、候補者の経歴に合わせて訴求内容を切り替えることが成果につながります。
スカウト文面で信頼感を高める工夫
医療事務の採用では、スカウト文面における「信頼感」の表現が特に重要です。病院に比べてクリニックは人数が少ないため、「人間関係はどうか」「急な休みに対応してくれるか」といった不安を持つ候補者が少なくありません。そこで文面には、制度やサポート体制だけでなく、実際のエピソードを盛り込むことが効果的です。
たとえば「お子さんの体調不良で急に休むことがあっても、スタッフ同士でフォローし合える」「週に数日は定時退勤が可能」といった実体験を紹介するだけで、候補者にとっての安心材料になります。また、「院長や看護師とも距離が近く、相談しやすい環境である」といった人間関係の良さも具体的に伝えることで、働きやすさを感じてもらえます。
さらに、スカウトを送る際には「なぜその人に声をかけたのか」を明記することも大切です。「医療事務経験をお持ちで、当院の業務にすぐ活かしていただけると思い声をかけました」などの一文を添えることで、候補者は「自分を見てくれている」と感じ、信頼感を高めることができます。
クリニックでの働きやすさを伝える具体的な方法
医療事務の候補者は、給与や福利厚生以上に「安心して長く働けるか」を重視する傾向があります。したがって、スカウト文面には働きやすさを裏付ける情報を盛り込むことが不可欠です。
具体的には、「残業時間の実績」「有給取得率」「シフト調整の柔軟性」などの数字を伝えると説得力が増します。また、制度そのものを列挙するのではなく、「実際に制度がどう使われているか」を具体的に描写するのが効果的です。たとえば「子育て中のスタッフが時短勤務で働いている」「家庭の事情で急に休んだ際も、スタッフ全員で協力して対応した」といったエピソードは、働く姿をイメージさせやすくなります。
さらに、職場の雰囲気を伝える工夫も重要です。スタッフ紹介や1日の仕事の流れを簡単に盛り込むことで、「人間関係が良さそう」「ここなら安心できそう」と感じてもらえます。数字とエピソードの両面を組み合わせることで、候補者の不安を取り除き、応募への一歩を後押しできます。
応募後のフォローで医療事務の定着率を高める
スカウトで応募につながっても、入職までの過程や初期研修でフォローが不足すると早期離職につながりかねません。特に医療事務は未経験で入職する人も多いため、安心して続けられるかどうかが定着率に直結します。
応募後の面談では「業務内容」や「条件」だけでなく、「入職後の流れ」を丁寧に説明することが大切です。たとえば「最初の1か月は受付業務に集中」「3か月目からレセプトの補助」といったステップを示すと、候補者は自分の成長過程をイメージできます。また、見学や体験勤務の機会を設けることで、実際の職場環境を肌で感じてもらえるのも有効です。
さらに、入職後も「定期的に面談を行い、困っていることを聞く」「新人に必ずメンターをつける」といったフォロー体制を整えることで、安心して働き続けられる環境を示せます。スカウト採用は「出会うこと」がゴールではなく、「長く定着してもらうこと」が真の目的です。応募後・入職後まで一貫したフォローを意識することが、採用成功を定着率向上につなげます。

このように、医療事務採用におけるスカウト活用は「経験の有無に応じた訴求」「信頼感を高める文面」「働きやすさの具体的提示」「応募後のフォロー体制」が鍵となります。次のセクションでは、看護師・医療事務双方の採用を効率的に進めるために、スカウト運用を支援会社に代行する方法について解説します。
看護師・医療事務採用は支援会社に代行

スカウト採用が抱えるクリニックでの運用上の課題
スカウト採用は効果的な手法である一方、実際に運用するとなると多くのクリニックで課題が生じます。最大の問題は「工数の多さ」です。候補者リストを作成し、一人ひとりのプロフィールを確認して適切なメッセージを考える作業は膨大です。院長が日々の診療や運営業務と並行して取り組むのは現実的に難しいでしょう。
さらに、スカウト文面の質も成果を左右します。テンプレートのように画一的な文面を送るだけでは、候補者に「大量送信されている」と受け取られ、興味を持ってもらえません。一方で、個別にカスタマイズされたメッセージは効果的ですが、その分だけ時間と工夫が必要になります。
また、候補者から反応があった場合の対応スピードも重要です。返信が遅れると候補者の関心が薄れ、他の職場に流れてしまうリスクがあります。スカウトは「送ったら終わり」ではなく、その後の迅速なコミュニケーションが成功のカギです。これらの課題が積み重なり、せっかくスカウト採用を導入しても運用が続かず、成果を出せないケースも少なくありません。
採用支援会社を活用するメリット
こうした課題を解決する手段として有効なのが、採用支援会社にスカウト採用を代行してもらう方法です。専門の支援会社は、医療業界に特化した採用ノウハウを持ち、候補者へのアプローチから応募後のフォローまで一貫して対応できます。これにより、クリニック側は本来の診療や運営に集中しながら、採用活動の質を高められます。
支援会社を利用する最大のメリットは「効率化」です。候補者リストの作成やスカウト文面の作成、送信管理など、手間のかかる作業を代行してもらえるため、限られた人員でも採用活動を継続できます。さらに、専門家の知見を活用することで、候補者に刺さる表現や効果的なタイミングでのアプローチが実現できます。
また、支援会社は応募があった後のフォロー体制も支援できるケースが多く、候補者とのやり取りを円滑に進めるサポートをしてくれます。クリニックにとっては「採用活動の属人化を防ぐ」効果もあり、担当者が変わっても採用活動を止めずに進められるという安定感が生まれます。

実際の採用支援活用シーンと成果
採用支援会社にスカウト採用を代行した場合、どのような成果が得られるのでしょうか。実例としては、「これまで求人広告だけでは応募が月に1件程度だったクリニックが、スカウト採用を導入したことで毎月数名の候補者と面談できるようになった」というケースがあります。特に看護師は潜在層へのアプローチが鍵となるため、スカウトを通じて「今すぐではないが興味がある」という層とつながれるのは大きな効果です。
医療事務の採用でも同様です。採用支援会社を活用したことで、未経験者に対して安心感を与えるメッセージを送ることができ、結果として応募が増加したという事例もあります。求人広告では伝えきれなかった「働きやすさ」や「具体的な成長ステップ」をスカウトで伝えることで、候補者の心を動かせるのです。
さらに、採用支援会社が代行することで「採用活動が継続的に行える」というメリットもあります。自院での対応だと忙しさに応じて波ができやすいですが、代行を依頼すれば安定したアプローチが可能になり、採用のチャンスを逃しにくくなります。
採用支援を依頼する際の注意点
採用支援会社にスカウト採用を代行してもらう際には、依頼の仕方やパートナー選びが重要です。まず確認すべきは「医療業界に特化した実績があるか」です。もっといえばクリニックを支援したことがあるかです。一般的な人材サービス会社でもスカウト代行は可能ですが、医療業界、クリニック特有の働き方や候補者のニーズを理解していなければ、的外れなアプローチになりかねません。
また、依頼前に「どの業務まで代行してもらえるのか」を明確にしておくことも大切です。スカウトの送信だけを行うのか、候補者との一次対応まで含めるのか、あるいは面談設定まで支援してもらえるのかによって、成果の出方は大きく変わります。
さらに、クリニック側も「丸投げ」にしてはいけません。支援会社がスカウト文面を作成する際には、職場の雰囲気や実際のエピソードを提供することで、よりリアルで説得力のあるメッセージが作れます。採用を成功させるためには、支援会社とクリニックが二人三脚で進める姿勢が必要です。
このように、スカウト採用を支援会社に代行することは、クリニックが抱える「工数不足」「ノウハウ不足」「継続性の欠如」といった課題を解決する有効な手段です。最後に、本記事全体の内容を振り返り、小規模クリニックにおける採用成功のポイントをまとめます。
株式会社HOAPではクリニックに特化した採用支援を提供しております。採用に悩む院長先生はご相談いただければと思います。
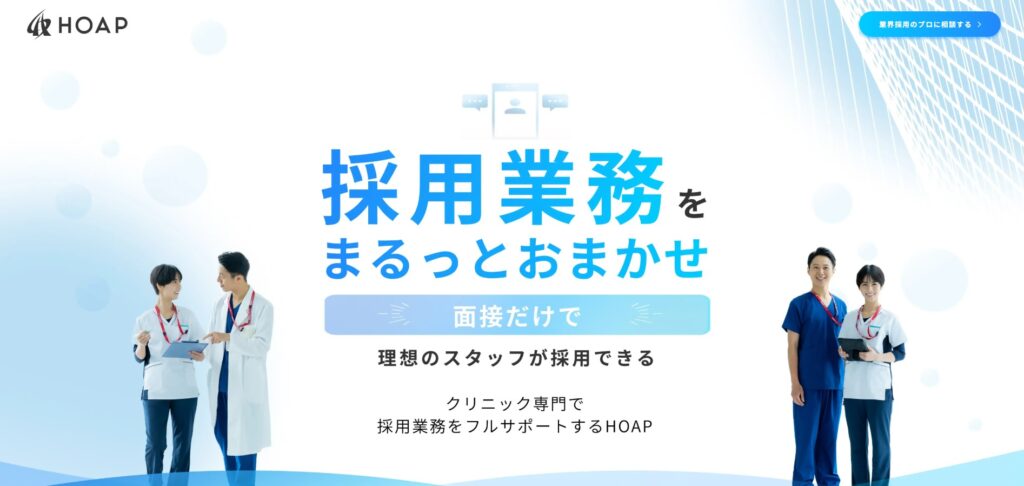
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。