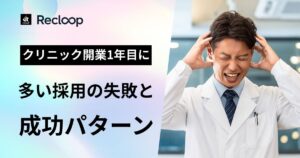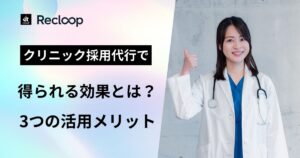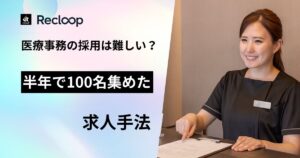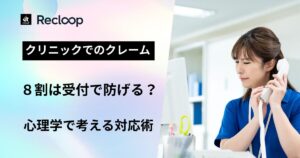クリニックでの医療事務採用は、多くの院長が頭を悩ませるテーマです。応募自体が少なく、ようやく採用できても短期間で離職してしまう。さらに、人材紹介会社に頼ると一時的には人材が確保できても、紹介料の負担が重くのしかかり、結果的に採用活動が継続的に回らない。こうした経験を持つクリニックは少なくありません。
そもそも医療事務は、診療報酬の算定やレセプト業務といった専門知識に加え、患者対応や電話応対といったコミュニケーション力も求められる職種です。そのため「誰でもできる仕事」とは言えず、採用市場においては慢性的な人材不足が続いています。さらにクリニックの場合は規模が小さいため、個人の力量が院内全体の雰囲気や業務効率に直結しやすいことも特徴です。
このような背景から、安易に人材紹介に依存するのではなく、クリニック自身が「どんな人材に来てほしいのか」「自院で働く魅力はどこにあるのか」を言語化し、求人の打ち出し方を工夫することが欠かせません。医療事務を長く続けたいと考える人材にとっては、職場環境やサポート体制、働き方のリアルなイメージが伝わる求人にこそ安心感を覚えるからです。
本記事では、クリニックの医療事務採用を「人材紹介に頼らず成功させる」ための考え方と具体的な戦略について解説します。まずはなぜ医療事務の採用が難しいのかを掘り下げ、次に人材紹介に依存するリスクを整理します。そのうえで、クリニックが自ら採用力を高めるための視点と、実践できる求人戦略を提示し、最後には明日から取り組める改善アクションを紹介します。段階を追って確認することで、自院に合った採用のヒントが得られるはずです。
なぜクリニックの医療事務採用は難しいのか?

医療事務の仕事内容と幅広い役割
クリニックにおける医療事務は、単に受付や会計を担当するだけではありません。診療報酬の算定やレセプト業務、患者対応、電話での問い合わせ対応、さらには院内での事務全般まで、多岐にわたる業務を担います。しかもそれぞれの業務には専門的な知識やスピード感が求められ、経験の浅い人材には大きな負担となることがあります。
医療事務は「事務職」でありながら、医療知識や制度への理解が必要とされる特殊な領域です。診療報酬は毎年改定されるため、業務に慣れた人でも常に新しい知識をアップデートし続けなければなりません。その一方で、患者にとってはクリニックの“顔”として接する機会が最も多い職種であり、対応の仕方ひとつでクリニック全体の印象が左右されることも少なくありません。
このように「幅広い業務範囲」と「専門性」、そして「接遇力」の三拍子を求められるため、医療事務を担える人材は限られています。結果として求人を出しても応募数が少なく、採用競争が激しくなるのです。さらに、採用後も業務の幅広さと責任の重さに戸惑い、短期間で離職してしまうケースも後を絶ちません。採用活動における難しさは、まさに職種そのものが抱える複雑さに起因しているといえます。
クリニック特有の採用市場の課題
医療事務を採用する際には、病院とクリニックでは事情が異なります。大規模病院では業務が細分化され、例えば「会計担当」「レセプト担当」といった形で分担されることが一般的です。しかしクリニックでは少人数体制であるため、一人の事務スタッフが受付から会計、レセプトまでを横断的にこなさなければなりません。つまり、同じ「医療事務」という名称でも、実際の仕事の幅や負担は大きく異なるのです。
この事情を理解している求職者は多くなく、「医療事務の経験あり」として応募してきても、実際には病院での部分的な経験しかなく、クリニック業務の全体像に対応できない場合があります。結果として採用後にミスマッチが発生し、現場に混乱を招くケースも少なくありません。
さらに、クリニックの求人は大手病院に比べると情報量が限られており、応募者が仕事内容を十分にイメージできないことも課題です。「どんな働き方ができるのか」「残業や休日はどうなのか」といった生活に直結する情報が不足していると、せっかく求人を目にしても応募に至らない可能性が高まります。
こうした採用市場の構造的な課題が、クリニックの医療事務採用を一層難しくしているのです。
医療事務の採用を人材紹介に頼らざるを得ない現実
採用が難しい状況の中、多くのクリニックが選択するのが人材紹介会社の利用です。人材紹介を利用すれば、求人広告を出しても応募が集まらない状況でも、短期間で候補者を紹介してもらえる可能性があります。特に医療事務経験者を求める場合、自力での募集だけでは出会いにくいため、紹介会社に頼ることは合理的な判断ともいえます。
しかし、この「頼らざるを得ない」という状況そのものが問題を複雑にしています。紹介料は年収の20〜30%に及ぶケースが多く、採用した人材が定着しなければ費用対効果が著しく下がります。しかもクリニック規模では採用人数が限られており、採用活動にかけられる予算も潤沢ではありません。そのため、1人あたりの採用コストが過度に膨らみ、経営にとって大きな負担になってしまうのです。
また、紹介会社に頼る体制が常態化すると、自院での採用ノウハウが蓄積されにくいという弊害もあります。つまり「また次も紹介会社に頼るしかない」という依存のサイクルが生まれ、採用活動を自走できなくなるリスクが高まります。クリニックの医療事務採用が難しい背景には、こうした依存構造が潜んでいるのです。
医療事務採用後の定着が難しい理由
仮に人材紹介を通じて採用ができたとしても、医療事務の定着率は必ずしも高くありません。理由の一つは、業務の幅広さや責任の重さに対するギャップです。入職前に「受付中心の業務」と想像していた人が、実際にはレセプトや保険請求など専門的で複雑な業務を任されると、想定外の負担感に直面します。
また、クリニックは少人数であるがゆえに、人間関係の影響が大きくなりやすい環境です。チームワークがうまくいかない場合、精神的な負担は病院よりも大きくなり、退職につながることがあります。さらに、育児や家庭の事情との両立が求められる年代のスタッフも多く、柔軟な勤務体制が整っていないと早期離職のリスクが高まります。
つまり、採用が難しいだけでなく「採用しても長く続けてもらえない」という二重の課題があるのです。これは単に人材紹介に頼るかどうかの問題ではなく、クリニックが「どのように働きやすさを伝え、支えていくのか」という採用・労務管理の根幹にかかわるテーマといえます。
ここまで見てきたように、クリニックの医療事務採用は、仕事内容の多様性、採用市場の構造的課題、人材紹介依存、そして定着の難しさが複雑に絡み合っています。次の章では、こうした背景を踏まえ、人材紹介に依存することの具体的なデメリットについて掘り下げていきます。
人材紹介に依存するデメリットとは?

高額な紹介料が経営を圧迫する
人材紹介を利用した採用の最大の問題は、そのコストの高さにあります。医療事務の年収は地域や経験によって異なりますが、概ね250万円から350万円の範囲に収まることが多いです。人材紹介会社に支払う手数料は年収の20〜30%が相場とされるため、1人を採用するだけで50万円から100万円近い費用が発生します。
クリニックの経営規模を考えると、これは決して小さな負担ではありません。例えば常勤医療事務を2名、人材紹介で採用した場合、数百万円単位の費用が一度に発生する可能性があります。しかも採用した人材が定着せず短期間で離職した場合、その費用は回収不能となり、再び新たな採用活動を始めなければなりません。
この「費用の先払いリスク」が、クリニックの採用活動を不安定にしています。本来であればスタッフの教育や職場環境整備に投資すべき資金を、紹介料に消耗してしまうのは中長期的に見て効率的とは言えません。経営資源の限られたクリニックにとって、高額な紹介料依存は経営全体の健全性を揺るがす要因となるのです。
採用の主体性を失い依存体質になる
人材紹介に頼り続けることで、クリニックが自ら採用活動を主体的に行う力が弱まってしまうことも大きな問題です。紹介会社に候補者を提示してもらう仕組みは一見効率的ですが、それは「自院の魅力をどう伝えるか」「どんな人材が合うのか」を考える機会を奪うことにもつながります。
採用活動は単なる人員補充ではなく、組織の将来を形作る重要なプロセスです。にもかかわらず、人材紹介に頼りすぎると「とりあえず紹介してもらった人を採る」という短期的な判断に偏りやすくなります。その結果、自院に合うかどうかの見極めが甘くなり、入職後のミスマッチを招きやすくなります。
さらに、紹介会社の利用が常態化すると「採用できない=紹介会社に頼るしかない」という固定観念が職場に根づいてしまいます。これでは自力で求人を出して応募者を集める工夫が育たず、ノウハウが蓄積されません。依存のサイクルから抜け出せない限り、採用コストは高止まりし続け、経営にとって慢性的な重荷となります。
ミスマッチ採用が増えるリスク
人材紹介を通じた採用は、必ずしも自院に合う人材を保証するものではありません。紹介会社はあくまで候補者をマッチングさせる役割を担いますが、その判断基準は「経験年数」や「資格の有無」といった表面的な条件に偏りがちです。
しかし、医療事務は知識やスキルだけでなく、患者対応やチームワーク、院長や看護師との連携といった人間関係スキルが大きな比重を占める職種です。紹介会社が提示する履歴書上の条件だけでは測れない部分こそ、クリニックにとって採用の成否を左右します。
そのため、紹介経由で採用した人材が「スキルは十分だが接遇が合わない」「経験はあるが柔軟性に欠ける」といった理由で短期間で辞めてしまうケースは珍しくありません。紹介会社にとっては「紹介した」という事実で契約は完了するため、定着やその後の職場での活躍までは保証されません。結果的に「採用はできたが、またすぐに採用活動に戻る」という悪循環が繰り返されるのです。
定着支援が欠けることで生じる長期的課題
人材紹介の仕組みには、採用後の定着を支援する機能がほとんどありません。多くの場合、紹介料を支払うのは入職時点であり、その後の教育やフォローはクリニック側の責任に委ねられます。
しかし実際には、医療事務の離職理由の多くは「仕事内容のギャップ」や「人間関係のストレス」といった採用後に顕在化する要因です。求人票や面接では分からなかった不安が、現場に入った途端に大きな障害となり、短期離職へとつながります。
定着率を高めるためには、採用活動そのものに「働きやすさ」や「サポート体制」を盛り込み、入職後の安心感を与える工夫が不可欠です。しかし、人材紹介に依存していると、どうしても「採用すること」自体がゴールになりがちで、その後のフォローに意識が向きにくくなります。
結果として、同じ失敗を繰り返し、紹介料ばかりが積み上がる状態に陥ってしまいます。長期的に見れば、これはクリニックの経営にとって持続可能性を損なう大きなリスクです。
ここまで、人材紹介に依存するデメリットを「コスト」「主体性の喪失」「ミスマッチ採用」「定着支援の欠如」という4つの視点から確認しました。次の章では、このような課題を踏まえ、「医療事務採用で実践すべき求人戦略」について、より具体的な方法を解説していきます。
条件を上げればいい?条件で選ぶ人は条件で辞める

クリニックの欲しい医療事務像を明確にする
採用を成功させる第一歩は、「どんな医療事務スタッフに来てほしいのか」を明確にすることです。多くの求人票では「医療事務経験者歓迎」「明るく対応できる方」といった抽象的な表現で終わってしまい、結果的に幅広い応募が集まるものの、自院に合う人材を絞り込めていないケースが目立ちます。
例えば、クリニックの患者層が高齢者中心であれば「落ち着いた対応ができる方」が望ましいかもしれません。一方で小児科であれば「柔軟に親子への声掛けができる方」が求められるでしょう。また、受付から会計・レセプトまで幅広い業務を担う環境なら「マルチタスクに抵抗がない方」が重要視されます。
このように「自院で活躍できる人物像」を明確にして言語化することで、求人票や面接の場でも一貫性のあるメッセージを発信できます。結果として、応募者も「ここでなら力を発揮できそう」と判断しやすくなり、採用のミスマッチを減らすことにつながります。欲しい人材像を定義することは、人材紹介に頼らず自力で採用力を高めるための土台となるのです。
人材紹介を使う前に成果報酬型求人媒体を活用
人材紹介を利用する前に、まず検討すべき選択肢として「医療系に強い成果報酬型求人媒体」があります。これは採用が決まるまで費用がかからず、実際に入職が成立した時点で初めて料金が発生する仕組みです。そのため「広告費を払ったのに応募がゼロ」というリスクがなく、限られた予算でも安心して始められます。
特に医療事務は人材不足が続く職種ですが、医療業界に特化した成果報酬型の媒体を利用すれば、ターゲットに合った応募者と出会いやすくなります。さらに、この仕組みは「自分たちの努力次第で結果を変えられる」点が大きな特徴です。求人票の書き方を工夫したり、クリニックの魅力を打ち出すポイントを整理したりすることで、応募の質と量を向上させることができます。
また、自院だけでうまく運用するのが難しい場合でも、医療分野に精通した採用支援会社に運用を任せることが可能です。そうした支援を利用すれば、成果報酬型媒体の特性を活かしながら効率的に採用活動を進められます。紹介料に依存せず、採用コストをコントロールできる方法として、成果報酬型求人媒体はクリニックにとって有力な選択肢となるのです。

ホームページの採用サイトを見直す
クリニックのホームページは患者向けに作られていることが多く、採用に特化した情報が不足している場合があります。しかし求職者の多くは、求人票を見たあとに必ずホームページを確認します。その際、採用に関する情報が不十分だと応募につながらない可能性が高まります。
採用サイトに必要なのは、単なる条件面の記載ではなく「働くイメージが湧く情報」です。例えば「1日の仕事の流れ」「スタッフインタビュー」「院長からのメッセージ」を掲載することで、応募者は職場の雰囲気をリアルに感じ取ることができます。また、「子育てと両立するスタッフの声」「長く勤めているスタッフの体験談」を掲載すれば、安心して応募できる材料になります。
さらに、求人媒体やSNSとリンクさせて情報を一元化することも大切です。求人票で興味を持った応募者がホームページを訪れたときに、同じメッセージが繰り返されていれば「信頼できるクリニックだ」と感じてもらえます。逆に情報が古いまま放置されていると「更新されていない=採用にも力を入れていないのでは」と誤解を招く可能性もあるため、定期的な更新は欠かせません。

SNSでクリニックのリアルを発信
近年、求職者は求人媒体だけでなくSNSから情報を収集しています。特に20〜30代の若年層は、InstagramやTikTokを通じて職場の雰囲気を確認する傾向が強まっています。クリニックにとっても、SNSは「人材紹介に頼らない採用チャネル」として活用すべき重要な手段です。
例えばInstagramで「受付スタッフの1日」「スタッフのオフショット」「院内イベントの様子」を投稿すれば、求人票だけでは伝えきれない“リアル”を届けられます。これにより応募者は「ここなら自分も働けそう」とイメージを持ちやすくなります。
また、SNSは応募前の軽い接点としても機能します。「気軽にDMで質問してください」と案内するだけで、求職者はハードルを下げて接点を持てます。人材紹介を通さずに求職者と直接つながれる点は、SNSならではの強みです。
重要なのは「見せたい姿」ではなく「実際の姿」を発信することです。完璧に整えられた宣伝よりも、普段のスタッフの自然な表情や院内の雰囲気を伝える方が、応募者にとっては安心材料になります。SNSは単なる広報ではなく、クリニックの採用力を高めるための「信頼構築ツール」として活用できるのです。

ここまで「医療事務採用で実践すべき求人戦略」を、欲しい人材像の明確化、成果報酬型媒体の活用、採用サイトの見直し、SNSでの発信という4つの観点から解説しました。次の章では、さらに踏み込み、これらを具体的にどう行動へ落とし込むか──明日から始められる改善アクションを紹介します。
明日から始められる医療事務採用の改善アクション

求人票を一文から見直す
最も手軽に始められる改善は、既存の求人票を一文から見直すことです。多くの求人票は「受付・会計・レセプト業務」など業務内容を簡潔に羅列していますが、これだけでは応募者にとって働くイメージが湧きません。そこで「患者さまに最初に声をかけられる受付や、診療報酬算定を担当するレセプト業務などを幅広く担当」と書き換えるだけで、具体性が高まり、仕事内容の全体像が伝わりやすくなります。
また「経験者歓迎」や「明るい対応ができる方」といった表現も見直しの余地があります。たとえば「小児科なので子ども好きな方歓迎」「地域の高齢患者さんが多いため落ち着いた対応ができる方」といった一文を加えるだけで、応募者は「この職場に自分が合うか」を判断しやすくなります。こうした小さな言葉の修正は即日実行でき、翌日から掲載される求人媒体に反映可能です。
さらに、求人媒体によりますが、求人票に「応募の前に見学可能」「LINEで質問だけでも歓迎」といった導線を付け加えることも有効です(NGな求人媒体もありますので事前に確認が必要です)。応募をためらう人に「まずは軽く接点を持つ」という選択肢を提示することで、応募者数が増えやすくなります。求人票の文言を丁寧に整えることは、明日から始められる最小かつ効果的な改善アクションです。

面接を「見極め」から「安心提供」の場に変える
面接は、クリニックにとって応募者を見極める場であると同時に、応募者にとって「ここで働きたい」と決意できるかを判断する場でもあります。多くのクリニックでは面接を形式的に進め、勤務条件の確認に終始してしまうケースがありますが、これでは応募者の不安を取り除けません。
改善の第一歩は、質問の仕方を変えることです。例えば「これまでの経験を教えてください」だけでなく「どんなときにやりがいを感じますか?」と尋ねることで、応募者が大切にしている価値観を把握できます。そして「当院では患者さんから直接感謝されることが多いので、やりがいを実感できる場面が豊富です」と伝えると、応募者は安心して働くイメージを持てます。
さらに「入職後は先輩スタッフがマンツーマンで業務を教えます」「子育てスタッフが多く急な休みにも理解があります」といった具体的なサポート体制を説明すれば、応募者の不安を払拭できます。面接を単なる審査ではなく「安心提供の場」に変えることは、即日実行できる大きな改善策です。
定着を見据えたフォロー体制を整える
採用はゴールではなく、スタートにすぎません。医療事務の離職理由の多くは「想像以上に業務が幅広かった」「職場の雰囲気に合わなかった」といった入職後のギャップにあります。そのため、採用時点から「どうやって定着につなげるか」を意識する必要があります。
改善アクションとして取り入れやすいのが「入職後3か月間のフォロー体制」を明文化することです。例えば「1か月目は先輩が同行して受付業務をサポート」「2か月目からはレセプト業務を段階的に習得」といった流れを事前に説明しておけば、応募者は安心感を持って入職できます。
また、定期的な面談を設けることも効果的です。「困っていることはありませんか?」と院長が直接確認するだけでも、スタッフは「気にかけてもらえている」と感じ、定着率が向上します。こうしたフォロー体制は特別な費用をかけなくても始められるため、明日から取り組める現実的な改善策です。
小さな発信を習慣化する
人材紹介に頼らず応募を増やすためには、日常的な発信の積み重ねが欠かせません。大きなキャンペーンや特別なイベントを企画しなくても、日々の業務の中で発信できる材料は数多くあります。
例えば「今日は○○スタッフの誕生日でした」「午後は患者さんからこんな嬉しい言葉をいただきました」といった一言をSNSで発信するだけでも、職場の雰囲気は伝わります。採用ページの更新も同様で、半年以上更新がない状態は「採用に消極的」と受け取られかねません。新しい写真やスタッフの声を1か月に1度追加するだけでも、応募者にとっての安心感は大きく変わります。
さらに、こうした発信は応募者だけでなく、既存スタッフのモチベーション向上にもつながります。自分たちの働く姿が外部に発信されることで誇りを持てるようになり、職場の雰囲気も明るくなります。小さな発信を習慣化することは、採用力と定着力の双方を高める「二重効果」を持つ改善アクションです。
ここまで「明日から始められる医療事務採用の改善アクション」を、求人票の見直し、面接での安心提供、フォロー体制の整備、小さな発信の習慣化の4つの観点から解説しました。これらはいずれも即日始められるものであり、積み重ねることで人材紹介に依存しない採用力の強化につながります。
クリニックにおける医療事務採用は、応募の少なさや定着率の低さから人材紹介に頼らざるを得ない状況が続いています。しかし紹介料の高さや依存体質化のリスクを考えると、自院で採用力を高める取り組みは避けて通れません。本記事では、求人票の工夫や欲しい人材像の明確化、成果報酬型求人媒体の活用、ホームページやSNSでの情報発信など、クリニックが自力でできる戦略を紹介しました。重要なのは「明日から実行できる小さな改善」を積み重ねることです。その努力の先に、人材紹介に依存しない持続可能な採用体制が築かれ、医療事務が安心して働き続けられる環境が整っていきます。
なお、株式会社HOAPでは、忙しい院長や採用担当者に代わり、採用活動を一括で支援するサービスを提供しています。在宅医療・クリニックといった医療業界に特化しているため、現場の実情に即した採用ノウハウをもとに、求人票作成から媒体運用、応募者対応までをサポート可能です。自力採用を基本としながらも「時間がなくて進まない」「求人を出しても応募が来ない」と悩むクリニックにとって、専門的な外部支援を組み合わせることは現実的な選択肢となります。
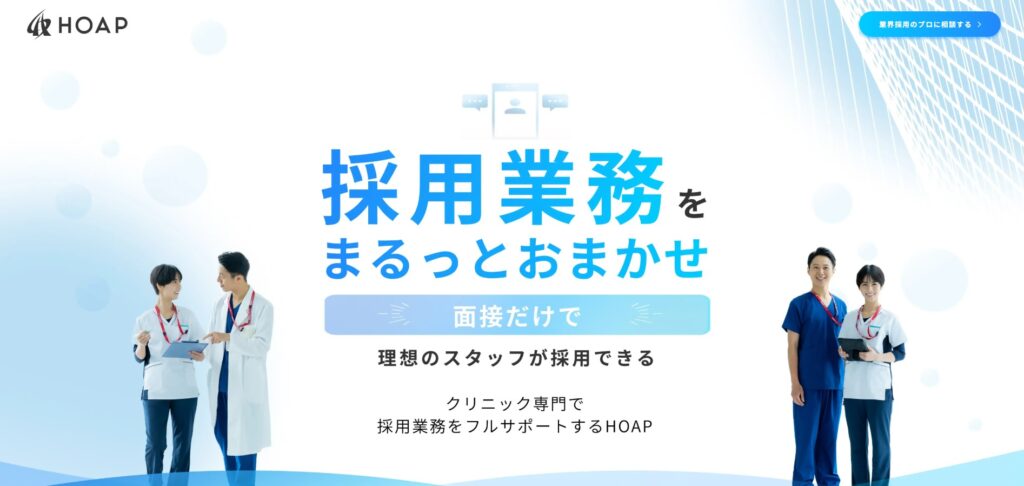
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。