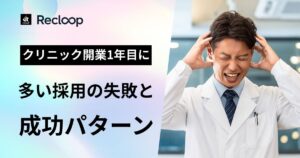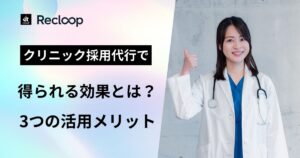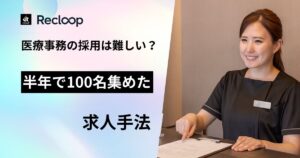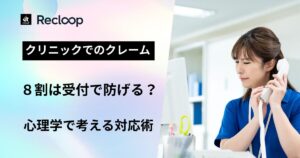クリニックの採用において「応募はあったのに、すぐ辞めてしまった」「実際に働いてもらうと想定していた人物像と違った」といった悩みは、多くの院長が経験しているものです。表面的には「人手不足だから採用しただけ」と片付けられがちですが、実際には採用プロセスのどこかに見落としや誤解が存在しているケースが少なくありません。特に医療現場は専門性が求められるため、採用のミスマッチは現場スタッフの負担増や患者対応の質低下にも直結し、経営にも影響を与えます。
なぜミスマッチが起こるのかを考えると、「求人情報での表現不足」「応募者の価値観や働き方のすり合わせ不足」「面接での確認ポイントの偏り」といった要因が見えてきます。例えば、勤務時間の柔軟さを求める人に対して「残業ほぼなし」と伝えていたものの、実際には患者の状況によりイレギュラー対応が多いとすれば、入職後に不満が生まれるのは当然です。また、スキル面だけで判断して採用しても、チームワークを重視する職場で協調性が欠けていれば、職場全体に摩擦が生じやすくなります。
こうした事態を避けるためには、単なる条件提示ではなく、クリニックの「働き方の実態」や「求める人物像」を具体的に言語化することが重要です。本記事では、クリニック採用における人材ミスマッチの背景を掘り下げながら、どのように採用活動を見直せばよいのかを順を追って解説していきます。まずは「なぜスタッフが定着しないのか」という根本的な問いから考えていきましょう。
クリニックではなぜスタッフが定着しないのか?

クリニックへの期待と現実のギャップが生む不満
クリニックに入職したスタッフが早期に辞めてしまう背景には、応募段階で抱いた期待と実際の業務との食い違いがあります。たとえば「残業が少ない」と伝えていたのに、患者対応や突発的な業務で時間外勤務が当たり前になっている場合、スタッフは「聞いていた話と違う」と受け止めやすくなります。これは単なる不満ではなく、採用時点での情報提供に課題がある典型例です。
さらに、クリニックは病院と違って組織が小さいため、一人ひとりの担当範囲が広くなる傾向があります。看護師であれば診療補助や処置に加え、受付フォローや物品管理を任されることもあります。「専門職の役割に集中したい」と考える人材にとっては、この幅広さが負担になりやすく、ギャップを感じやすいのです。仕事内容だけでなく、「人間関係」や「キャリアの見通し」にも同じ構図が当てはまります。入職前に描いていたイメージと違っていれば、早期離職は避けられません。
こうした齟齬を防ぐために、院長は採用段階で「理想的な一日」ではなく「実際の一日」を描写する姿勢が求められます。現場スタッフの声を交えながら伝えることで、応募者が自分の働く姿を具体的に想像できるようになります。
クリニックの職場文化と価値観の不一致
スタッフが定着しないもう一つの大きな要因は、クリニック特有の職場文化や価値観に合わない人材を採用してしまうことです。規模が小さい組織では、一人の行動や考え方がチーム全体に与える影響が大きくなります。協調性を重んじる現場に、個人プレーを優先する人材が加わると摩擦が生じやすくなり、結果として本人だけでなく周囲の離職を招くこともあります。
また、患者との接し方も価値観の分岐点になります。クリニックでは外来患者と長期的に関わることが多く、効率よりも「安心感のある対応」が求められる場面が少なくありません。しかし、病院出身者が「スピード重視の働き方」を持ち込むと、チーム全体との考え方にズレが生じます。価値観の不一致を放置すれば「この職場には合わない」と双方が感じ、早期離職につながるのです。
院長としては、面接でスキルや資格だけを見るのではなく、「どのような環境で力を発揮できるか」を深掘りすることが重要です。人物像のすり合わせを丁寧に行うことが、定着率を高める第一歩となります。
クリニックでのキャリアの見通し不足による不安
クリニックは病院と比べて組織が小さい分、「数年後にどう成長していけるのか」が見えにくい特徴があります。入職当初は新しい挑戦に意欲的でも、将来のキャリア像が描けなければ、スタッフは「このまま働き続けても成長できない」と感じて転職を検討しやすくなります。特に若手スタッフは「ここで長く働いた先に、自分はどうなれるのか」を敏感に意識します。
院長が「長く勤めてほしい」と願っても、それが評価制度や研修制度に反映されていなければ意味がありません。例えば「努力すれば昇給の機会がある」と言葉で伝えていても、明確な基準や実例がなければ信頼は得られません。その結果、「ここには未来がない」と感じてしまうのです。
解決の鍵は、小規模だからこそ描ける将来像を提示することにあります。「院長の右腕として責任ある仕事を任される」「地域に根ざした患者教育を担当できる」といった具体的な未来像を示すことで、スタッフは安心して働き続けられるようになります。
クリニック内でのコミュニケーション不足が引き起こす孤立
スタッフが定着しない理由として見落とされがちなのが、日常のコミュニケーション不足です。クリニックは少人数で業務を回すため、忙しさに追われると日々の声かけや振り返りが後回しにされがちです。その結果、スタッフは「自分の働きが認められていない」「困っても相談できない」と感じ、孤立していきます。
さらに、院長が診療や経営に集中するあまりスタッフとの距離をとりすぎると、「意見を言いにくい」「助けを求められない」という空気が強まります。孤立感は不安を増幅させ、離職を決断するきっかけとなります。
これを防ぐには、大掛かりな制度を設ける必要はありません。院長が意識して「1日数分の声かけ」「週1回の短い面談」など小さな時間を持つだけで、スタッフの安心感は大きく変わります。小さな積み重ねが、定着率を左右する重要な要素となるのです。このように、スタッフが定着しない背景には、
「期待と現実のギャップ」
「文化や価値観の不一致」
「キャリアの見通し不足」
「コミュニケーション不足」
といった複数の要素が絡み合っています。次の章では、これらを踏まえて【院長が採用で本当に見るべきポイント】について掘り下げていきます。
クリニックの採用で本当に見るべきポイントとは?

スキルよりも「価値観の相性」を優先する
院長が採用の場面で陥りがちなのは、経歴やスキルを重視しすぎてしまうことです。確かに、即戦力となる技術や資格は大切ですが、それ以上に重要なのはクリニックの文化や方針と一致する価値観を持っているかどうかです。どれほど経験豊富なスタッフであっても、「患者と丁寧に向き合う姿勢」や「チームで協力する意識」が欠けていれば、長期的には定着しません。
価値観の相性を見極めるためには、面接で「あなたが働くうえで大切にしていることは何ですか?」といった質問を投げかけることが有効です。単なる模範解答ではなく、具体的な体験談や行動に基づいた答えが出てくるかを確認すれば、その人が実際にどう考え、どう行動してきたのかが見えてきます。
院長としては「この人は即戦力かどうか」だけでなく「この人と一緒に日々の診療を支えていけるか」という観点で採用判断を行う必要があります。
求人票ではなく「クリニックのリアルな一日」を描く
応募者が入職後に感じるギャップを防ぐには、求人票に書かれた条件だけでなく、実際の働き方を具体的に伝えることが欠かせません。たとえば「残業ほぼなし」という表現は魅力的に映りますが、実際には患者の急変や予期せぬ対応で終了時間が延びることもあります。そうした実態を伏せたまま採用すると、入職後に不満が膨らみます。
ここで有効なのは、現場スタッフの「ある一日」を共有することです。診療開始前の準備、診療中の動き、昼休憩の雰囲気、診療終了後の後片づけなど、リアルな1日の流れを示せば、応募者は「自分がここで働いたらどうなるか」を想像できます。
院長が採用の場で「実際の声」を紹介することは、求人広告以上に信頼性を高めます。「求人票に書くこと」と「面接で話すこと」を分けず、一貫した情報提供を心がけることがミスマッチ防止につながります。
クリニックにおける面接では「質問力」が定着率を左右する
面接を単なる確認作業にしてしまうと、院長は応募者の本質を見抜けません。「どんな経験がありますか?」と経歴をなぞるだけでは、応募者の考え方や行動特性は見えてこないのです。むしろ大切なのは、応募者が自分自身を語れるような質問を投げかけることです。たとえば、
「前の職場でやりがいを感じた瞬間は?」
「働きにくいと感じたのはどんな場面?」
といった質問は、応募者の価値観を知るきっかけになります。また、「患者さんから感謝された経験を教えてください」と尋ねれば、仕事への向き合い方や対人姿勢が明らかになります。
院長にとって面接は「評価の場」ではなく「対話の場」です。応募者の言葉の中にある違和感や迷いを丁寧に拾うことで、入職後に起こり得る摩擦を事前に察知できます。質問力を磨くことが、定着率向上の最大の武器となります。
応募者のクリニックでの未来像を一緒に描く
採用の場面では「今のスキルが十分かどうか」だけでなく、「ここで働くことでどんな未来を描けるか」を共有することが必要です。スタッフが定着しない理由の一つは「先が見えない不安」です。これを解消するためには、院長が応募者と一緒に未来像を描く姿勢を見せることが効果的です。たとえば、
「3年後には患者教育を任せられる存在になってほしい」
「資格取得を支援するのでキャリアアップにつなげられる」
といった具体的なイメージを示すことで、応募者は安心感を持てます。小規模なクリニックだからこそ、スタッフの成長を間近で支えられる点を強調すると良いでしょう。
院長が「あなたをどう育てたいか」を言葉にして伝えることで、応募者は「ここで働き続けたい」と感じやすくなります。未来像の共有は、採用の瞬間から定着への第一歩を踏み出す行為でもあるのです。このように、採用で本当に見るべきポイントは、
「スキルより価値観」
「条件より実態」
「確認より対話」
「現在より未来像」
にあります。次の章では、こうした視点を踏まえ、【なぜミスマッチは起こるのか】をさらに背景から掘り下げていきます。
クリニックの採用でなぜミスマッチは起こるのか?

クリニックの求人情報が「理想像」に偏りすぎている
多くのクリニックで見られる採用の失敗は、求人情報が「魅力的に見せること」に偏りすぎている点にあります。応募を集めたい一心で、
・「残業ほぼなし」
・「家庭との両立が可能」
・「アットホームな職場」
といった表現を並べると、確かに応募数は増えます。しかし、その表現が実態から乖離していれば、入職後に「聞いていた話と違う」という不満を生み、早期離職の引き金になります。
とくにクリニックは、規模が小さく日々の診療状況によって働き方が変動しやすいため、誇張された表現はミスマッチを加速させます。たとえば「完全に定時退勤できる」と書かれていたが、実際は患者対応で15分~30分残業が常態化しているとすれば、それだけで応募者は裏切られたと感じます。
院長に求められるのは、「応募数を増やす」発想ではなく「本当に合う人に届く」発信です。過度に理想化するのではなく、リアルな姿を伝えることが、結果的にミスマッチを防ぎ、定着率を高めます。
クリニックでの面接が「スキル確認」に終始している
ミスマッチの大きな原因の一つが、面接での会話がスキルや経歴の確認にとどまっていることです。確かに資格や経験は欠かせない要素ですが、採用のゴールは「長く働き続けてもらうこと」です。にもかかわらず、「どこで何年働いたか」「どんな処置を経験したか」といった履歴中心の質問に偏ると、応募者の考え方や価値観を十分に知ることができません。
院長が面接で本当に確認すべきは、
・応募者がどんな職場を求めているのか
・どんな働き方に違和感を感じるのか
といった内面の部分です。「これまでの職場でやりがいを感じた瞬間は?」「逆に働きにくいと感じたのはどんなとき?」といった質問を通じて価値観を探れば、入職後に職場文化と合うかどうかを見極めやすくなります。
スキルだけを基準に採用すると、現場のチームワークを乱す人材や、患者対応に不向きな人物を抱え込むリスクが高まります。面接は「できるかどうか」ではなく「ここで一緒に働けるかどうか」を確かめる場に変える必要があります。
クリニックへ入職後のフォローが不足している
仮に採用段階でうまくマッチングできても、入職後のフォローが不足していれば、結果的にミスマッチと同じ状況を生み出します。とくにクリニックは少人数体制のため、新人が孤立しやすく、相談できる相手がいないまま不安を募らせてしまうケースが少なくありません。
「教えたはず」「慣れるまでの辛抱」と院長や先輩スタッフが考えていると、本人は「見捨てられた」と感じてしまいます。その温度差が退職につながります。院長に求められるのは、入職後3か月間のフォローを徹底することです。具体的には、週ごとの振り返り面談や「困っていることはないか」を確認する時間を設けるだけでも安心感が大きく変わります。
入職後の支援が整っていれば、小さな不満や疑問も早期に解消できます。逆に「放置されている」と感じさせると、本人の中で不信感が膨らみ、わずかな不一致でも大きな離職理由になってしまいます。
クリニックに「合わない人」を排除できていない
ミスマッチが起こるもう一つの背景は、「どんな人に来てほしいか」だけでなく「どんな人は合わないか」を明確にできていない点です。院長としては応募数を減らしたくないため、ついポジティブな要素ばかりを打ち出してしまいます。しかし、それでは本当に合わない人まで応募してしまい、入職後に不一致が顕在化します。たとえば、
「自分の判断で動くのが苦手な人」
「患者対応より事務作業を優先したい人」
「変化に対応するのが極端に難しい人」
など、クリニックで働くうえで厳しい特徴は必ず存在します。これを明言せず採用すると、本人にとっても不幸な結果になります。
むしろ、合わない人を明確にすることが「安心して応募できる人材」を引き寄せます。求人や面接で「こういう方は合わないかもしれません」と伝えることは、応募数を減らすどころか、むしろ本当に合う人材に響きやすくなります。このように、ミスマッチは
「求人情報の誇張」
「面接の浅さ」
「入職後の放置」
「合わない人を明示できないこと」
といった複数の要因が絡み合って発生します。次の章では、院長が取り組むべき【ミスマッチを防ぐ具体的な改善策】について解説していきます。
ミスマッチを防ぐためにクリニック院長ができる改善策

求人の段階で「クリニックのリアル」を伝える
ミスマッチを防ぐ第一歩は、求人情報の段階で現場の実態をしっかり伝えることです。魅力的な条件を並べることは応募数を増やす効果がありますが、誇張表現は必ず不信感につながります。大切なのは、応募数よりも「定着する人材に届くかどうか」です。
具体的には「残業ほぼなし」と書く代わりに、「患者の状況によって月に数回は残業が発生する」と正直に伝えるほうが信頼されます。また、「アットホームな職場」といった抽象的な表現ではなく、「週に一度スタッフ同士で症例を共有する勉強会を行っている」と具体的な習慣を紹介する方が応募者にとってイメージしやすいです。
院長自らが「このクリニックで働くと実際にどうなるか」を言葉にして届けることが、結果的にミスマッチを防ぐ最大の武器となります。
クリニックでの面接を「価値観のすり合わせの場」に変える
従来の面接はスキルや経験の確認が中心になりがちですが、ミスマッチを防ぐには、面接を「価値観のすり合わせの場」に変える必要があります。院長は応募者に、
「どんな職場を理想としていますか?」
「過去に働きにくいと感じた環境は?」
といった質問を投げかけることで、相手の価値観を引き出せます。
また、応募者に「このクリニックで大事にしていることは何だと思いますか?」と逆に問いかけることで、応募者がどれだけ事前に理解しているかを測れます。こうした対話を通じて、スキルよりも「文化的な相性」を見極めることができます。
院長にとって重要なのは「採用するかどうかを決める」よりも、「この人が本当に合う環境なのかを一緒に確認する」という姿勢です。
クリニックへの入職後3か月のフォロー体制を整える
採用がうまくいっても、入職直後に放置してしまえばミスマッチは必ず起こります。とくにクリニックは少人数で動いているため、新人が孤立しやすい傾向があります。そこで必要なのは、最初の3か月を「安心して学べる期間」と位置づけ、フォロー体制を整えることです。
具体的には、週1回の振り返り面談や、1日の終わりに5分間のチェックインを取り入れると、本人の不安や疑問を早期に解消できます。院長が「困っていないか?」と声をかけるだけでも、スタッフは安心感を得られます。逆に「慣れるまで見守ろう」と放置すると、本人は「頼れない職場だ」と判断し、離職を決断しやすくなります。
また、既存スタッフにも「新人への声かけ」をお願いすることで、組織全体でフォローする体制を築けます。フォローの習慣化が、結果的に定着率を高める最大の要因となります。
クリニックに「合わない人」をはっきり示す勇気を持つ
院長にとって心理的に難しいのは、「このクリニックには合わない人」を明確に伝えることです。しかし、これを曖昧にすると、誰でも応募できる求人となり、結果としてミスマッチが多発します。たとえば、
「自分で判断して動けない人」
「患者との対話より効率を優先する人」
「チームで協力するのが苦手な人」
といった特徴は、クリニックで働く上では不向きである場合があります。これを求人票や面接で正直に伝えることで、応募者自身が「自分には合わない」と判断できます。結果的に、定着する可能性の高い人材だけが応募してくるのです。
「合わない人」を示すことは、応募数を減らすどころか、むしろミスマッチを減らし、本当に必要な人材に出会う近道となります。このように、院長ができる改善策は
「求人でリアルを伝える」
「面接を価値観の対話に変える」
「入職後3か月のフォローを徹底する」
「合わない人を明確にする」
といった具体的な行動に集約されます。次の章では、これらを踏まえ、【明日からすぐに取り組める具体的な行動】について整理していきます。
クリニック院長が明日から取り組める具体的な行動

クリニックの求人情報を1か所だけ「具体化」してみる
求人票の表現は、多くの場合「働きやすい」「残業少なめ」「アットホーム」といった抽象的な言葉でまとめられがちです。しかし、明日からできる改善として有効なのは、この中から一つを具体化することです。
たとえば「残業少なめ」という表現を「患者対応で月に2〜3回、30分程度の残業が発生する」と変えるだけで、応募者の受け止め方は大きく変わります。「アットホームな職場」を「週1回、スタッフ全員で情報共有の時間を設けている」と書き換えるのも効果的です。抽象的な言葉を具体化するだけで、応募者は「この職場のリアル」を想像しやすくなり、結果的にミスマッチを減らせます。
院長が明日から取り組める小さな一歩は、「求人票の抽象表現をひとつ具体化する」ことです。
クリニックでの面接で必ず1つ「価値観を問う質問」を入れる
面接はスキル確認の場に偏りがちですが、価値観を確かめるための質問を一つ入れるだけでも採用の質は大きく変わります。たとえば「これまでの職場で働きやすいと感じた理由は何ですか?」や「患者さんから感謝された経験を教えてください」といった質問です。
これらの質問は、応募者の言葉の裏にある価値観を浮かび上がらせます。形式的な答えではなく、具体的なエピソードが出てくるかどうかで、その人がどのように仕事に向き合ってきたかが見えてきます。
院長が明日から取り組めるのは、「スキル確認の質問に加えて、価値観を掘り下げる質問を必ず一つ用意する」ことです。それだけで、定着する可能性の高い人材を見極めやすくなります。
クリニックへの入職初日の「5分面談」を習慣化する
スタッフの定着を左右するのは、入職してからのフォローです。とくに初日は不安が大きく、放置されると「ここでやっていけるだろうか」と疑念が膨らみます。そこで有効なのが、院長が入職初日に必ず「5分の面談」を行うことです。
「今日の仕事で困ったことはありましたか?」
「何か気になることはありましたか?」
といったシンプルな問いを投げるだけで、スタッフは安心感を得られます。形式的な挨拶よりも、短くても対話の時間を持つことが信頼関係の基盤となります。
さらに、この5分面談を週に1回続けるだけで、不安や不満を早期に解消できるようになります。明日からできる小さなアクションとして「初日からの短時間面談」を習慣化することは大きな効果を生みます。
クリニックに「合わない人」の特徴を紙に書き出す
ミスマッチを防ぐには、「求める人物像」を描くだけでなく「合わない人物像」を明確にすることが欠かせません。これは時間をかけずにすぐできる作業です。たとえば
「患者対応を避けて事務作業に偏る人」
「一人で判断するのを極端に苦手とする人」
「変化への適応が難しい人」
など、過去にうまくいかなかった事例を振り返りながら書き出してみると、クリニックにとって不向きなタイプが見えてきます。
この「合わない人」のリストは、求人情報や面接の中で自然に伝えることができます。「こういう方には合わないかもしれません」とあらかじめ伝えることで、応募者自身が判断でき、結果的にミスマッチを防ぐ効果が高まります。
院長が明日から取り組めるのは、「合わない人の特徴を3つ書き出す」ことです。このシンプルな行動が、採用の軸を強固にします。
ここまで述べたように、ミスマッチを防ぐために明日から取り組める行動は、小さな一歩で十分です。「求人票を一部具体化する」「面接で価値観を問う質問を加える」「入職初日に5分面談を行う」「合わない人の特徴を紙に書き出す」といった行動は、すぐに実践でき、長期的には定着率の向上につながります。
クリニックの採用で起こる人材ミスマッチは、求人情報の誇張や面接の浅さ、入職後のフォロー不足など、いくつもの要因が重なって発生します。しかし院長が視点を変え、「リアルな日常を伝える」「価値観をすり合わせる」「合わない人を明示する」といった具体的な工夫を加えることで、定着率は確実に高まります。大切なのは、応募数の多さではなく「長く一緒に働ける人材」と出会えることです。小さな改善の積み重ねが、患者に安心を届ける安定したクリニック運営へと直結します。