訪問看護ステーションの現場では、日々多くの課題に直面します。利用者やご家族の生活を支え、医療と介護のはざまで多職種と連携しながら動く中で、「一件一件に丁寧に向き合いたい」という思いと「時間や人員が足りない」という現実の間で葛藤することも少なくありません。そんな状況が続くと、スタッフ一人ひとりが「自分たちはなぜこの仕事をしているのか」「何を大切にしたいのか」を振り返る余裕を持てず、気づけば目の前の業務をこなすだけの日々になってしまうことがあります。
しかし、本来訪問看護は、利用者の生活そのものに寄り添い、その人らしい人生を最後まで支えるという大きな意義を持つ仕事です。だからこそ、日常の忙しさの中でも一度立ち止まり、「理念」や「価値観」を改めて問い直すことが重要になります。理念は抽象的なスローガンではなく、現場での判断やコミュニケーションを導く羅針盤であり、日々の意思決定を支える具体的な基準となるべきものです。
本記事では、訪問看護に携わる皆さんが自分たちの「なぜ」を掘り下げ、課題解決の先にある未来像を描き、組織としてのこだわりや譲れない価値観を明確にするための視点を整理します。それにより、スタッフ全員が同じ方向を向き、利用者や家族、地域に対してより確かな支援を届けられる土台を築くことを目指します。次章では、まず「なぜ」を問い直すことの意味から考えていきましょう。
「なぜ」を問い直すことから始めよう

理念を掘り下げるための「なぜの連鎖」
訪問看護の現場では、目の前の利用者や家族に対応することが中心になり、日々の業務を終えるだけで精一杯になることがあります。その中で理念を形だけの言葉として掲げていても、スタッフの行動や判断につながらなければ意味を持ちません。そこで有効なのが、「なぜ」を繰り返し問いかける方法です。表面的な理由にとどまらず、最低でも5回は掘り下げていくことで、本当に大切にしている動機や価値観が見えてきます。
例えば「なぜ訪問看護を選んだのか」と尋ねると、「在宅で暮らす患者さんを支えたいから」という答えが返ってくることが多いでしょう。しかし、さらに「なぜ支えたいのか」と問い直すと、「病院では叶わない生活の安心を守りたいから」といった深い思いが引き出されます。繰り返すうちに、「その人らしい人生を最期まで支えることが、自分の存在意義につながる」というように、スタッフ一人ひとりの核となる価値が言語化されます。
この作業は個人だけでなく、組織全体でも有効です。定例会議や勉強会で「なぜこの事業所を立ち上げたのか」「なぜ私たちはここで働いているのか」を共有することで、理念を共通言語として持てるようになります。理念の言語化は、一人の経営者や管理者のためだけでなく、チーム全体の方向性を揃えるための基盤になるのです。
理念を掲げることはゴールではなく、スタッフが日常の判断に迷ったときに「私たちが本当に大切にしているのは何か」と振り返るための土台です。だからこそ、「なぜ」を問い直し続ける習慣が、理念を机上の言葉ではなく「生きた指針」に変えていくのです。
個人の動機から組織の使命へつなげる
「なぜ」を掘り下げる作業で重要なのは、個人の想いを組織の使命とどう重ね合わせるかです。スタッフ一人ひとりには「自分がなぜ訪問看護を選んだのか」という動機があり、それぞれ異なる背景を持っています。子育てと両立しやすい働き方を求めた人もいれば、急性期病棟での経験を活かして在宅支援に挑戦したいと考えた人もいるでしょう。
これらの個人の動機を組織としての理念に接続できたとき、日々の業務は単なる仕事ではなく「使命」としての意味を帯びてきます。たとえば、「安心して自宅で過ごせる生活を支える」という理念がある場合、スタッフは「自分が訪問する一軒一軒が、その理念を具体化する場面なのだ」と理解できます。結果として、自分の仕事が組織全体の価値提供に直結していることを実感でき、モチベーションの維持につながります。
また、経営層にとってもスタッフの個別の「なぜ」を知ることは、組織運営において大きな意味を持ちます。理念はトップダウンで与えるものではなく、現場の声や個人の思いを反映しながら形づくられるものだからです。スタッフとの面談や研修で「あなたがこの仕事を選んだ理由は?」と問いかけること自体が、理念を共有する第一歩となります。
こうして個人と組織の動機が重なり合うとき、理念は単なるスローガンから「行動の源泉」へと変化します。さらに、この視点は後に触れる「こだわりの言語化」にもつながり、組織として何を大切にするかを示す力になります。
理念が課題解決の視点を変える
訪問看護の現場には、時間の制約や人材不足、家族との関係づくりなど多くの課題が存在します。これらの課題に対して表面的な対応を繰り返すだけでは、同じ問題が繰り返し発生する可能性が高いでしょう。ここで理念を基準にすると、課題解決の視点が変わります。
例えば「利用者の尊厳を守ること」を理念に掲げているステーションであれば、「訪問時間を短縮して効率化する」という課題設定だけでは不十分だと気づけます。尊厳を守るという視点から見れば、効率よりも「利用者が安心して会話できる時間を確保する」ことが優先される場合もあるのです。理念は意思決定の基準を与え、課題の本質を見極める手助けをします。
さらに、理念は組織外との関係づくりにも影響します。医師やケアマネジャー、地域包括支援センターとの連携において、理念を共有できていれば信頼関係が築きやすくなります。単に「訪問枠を埋める」「報酬を得る」ことだけが目的ではないと伝われば、相手も安心して連携できるでしょう。
つまり理念は、課題解決の際に「短期的な効率」ではなく「長期的な価値」を基準にするための羅針盤です。この視点をスタッフ全員で持つことで、判断への納得感が生まれ、利用者や家族に提供する支援の質も高まります。
理念を現場に根づかせるための共有の工夫
理念を掲げるだけでは意味がなく、日々の現場で生かされる状態をつくることが重要です。そのためには、理念を繰り返し確認し、実際の事例と結びつけて共有する工夫が求められます。
具体的には、定例ミーティングの冒頭で「私たちの理念に照らすと、今週の活動で印象的だったことは何か」を話し合う場を設けると効果的です。スタッフ一人ひとりが日常の中で理念を実感できるエピソードを出し合うことで、理念が単なるスローガンではなく「現場に生きている言葉」として共有されます。
また、新人研修の段階で理念を伝えるときも、単に暗記させるのではなく「あなた自身が大切にしたい価値観とどう重なりますか?」と問いかけることが重要です。理念を個人の体験や価値観と重ね合わせることで、スタッフ自身が自発的に行動に結びつけやすくなります。
さらに、利用者や家族に対しても理念を発信する工夫が有効です。パンフレットやホームページに理念を記載するだけでなく、訪問時の会話の中で「私たちはこの理念を大切にしているから、このように対応しています」と伝えることで、信頼感を高めることができます。
ここで紹介した共有の工夫は、後述する「キーワード活用」とも重なる部分があります。重要なのは、理念を『言葉として持ち続けるだけでなく日常の行動に結びつける」仕組みをつくることです。
訪問看護が解決したい課題とその先の未来

利用者が抱える孤独感と不安をどう減らすか
訪問看護の大きな役割のひとつは、利用者が抱える孤独感や不安を和らげることです。病院から在宅に移ると、急に「一人で生活を支えなければならない」という感覚に直面する方が多くいます。特に高齢者や慢性疾患を持つ方は、「体調が急に悪化したらどうしよう」「家族に迷惑をかけたくない」という不安を抱えがちです。これらは数値化しづらい心理的な課題ですが、生活の質を左右する大きな要素です。
訪問看護師が定期的に訪問し、体調のチェックだけでなく日常の会話や相談に応じることで、利用者は「自分を見守ってくれる人がいる」という安心感を得られます。これは薬や処置と同じくらい大切な支援です。孤独感や不安を軽減できれば、利用者の表情や生活意欲にも変化が生まれ、結果的に健康状態の安定につながります。
このような心理的な課題を解決することは、訪問看護が社会にもたらす価値のひとつです。未来像としては、「一人暮らしでも孤独を感じず、安心して在宅生活を続けられる社会」が描けます。その実現に向け、訪問看護は単なる医療サービスにとどまらず、生活を支える存在として位置づけられるべきでしょう。次に、家族の課題解決について考えてみます。
家族の介護負担をどう軽減するか
在宅療養を支えるのは利用者本人だけではなく、その家族も大きな役割を担っています。特に介護を担う家族は、身体的・精神的に大きな負担を抱えやすい状況にあります。
「夜間もずっと気が抜けない」
「仕事と介護の両立が難しい」
といった声は珍しくありません。こうした家族の疲弊が進むと、在宅療養そのものが継続できなくなるケースもあります。
訪問看護は、家族の介護負担を和らげる重要な存在です。具体的には、医療的処置を訪問看護師が担うことで家族の負担を軽減したり、体調や症状の変化について専門的に判断してくれることで、家族が不安を抱え込まずに済むようになります。また「この状況はよくあることです」と専門職から伝えられるだけでも、家族は安心し、心の余裕を持てるようになります。
未来像としては「家族が介護に追われるのではなく、笑顔で過ごす時間が増える社会」が挙げられます。訪問看護が介入することで、介護者自身の生活の質も向上し、利用者と家族の双方が幸せに暮らせる仕組みを築けるのです。次に、地域全体に広がる影響について掘り下げます。
地域に広がる支え合いの循環
訪問看護は利用者や家族にとどまらず、地域全体の仕組みに影響を与えます。高齢化が進む日本において、病院だけではすべてのニーズを支えきれません。在宅療養を支える訪問看護は、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担っています。
訪問看護師が地域に関わることで、医師やケアマネジャー、ヘルパーなど他職種との連携が活性化します。これにより「地域全体で一人を支える」という支援の輪が広がります。例えば、利用者の体調変化を訪問看護師が早期にキャッチし、医師に連絡することで入院を防げる場合があります。これは医療費の削減にもつながり、社会的にも大きな価値を生み出します。
未来像としては「地域が高齢者を安心して支えられるコミュニティとして機能する社会」が描けます。個人や家族が孤立するのではなく、地域全体で支える仕組みを整えることは、訪問看護が果たせる重要な役割です。最後に、こうした課題解決を可能にするために必要な視点について触れていきます。
課題解決の先に描く未来像の共有
訪問看護の本質は、単に現状の問題を解決することではなく、その先の未来を描くことにあります。孤独感や不安を軽減し、家族の介護負担を和らげ、地域全体に支え合いの仕組みを広げる。その先には、
・利用者が「自分らしく生きられる」社会
・家族が「安心して寄り添える」社会
・地域が「誰も取り残さない」社会
があります。
この未来像を組織全体で共有することが重要です。スタッフが日々の訪問の中で迷ったとき、「私たちはこの未来を目指している」という共通のイメージがあることで、判断の基準がぶれにくくなります。また、この未来像を利用者や家族に伝えることで、サービスに対する信頼感が深まり、「ここにお願いしてよかった」と思ってもらえるようになります。
未来像の共有は、単なる理想論ではなく、日々の小さな実践の積み重ねによって現実になっていきます。理念と同じように、未来像を繰り返し確認し、具体的なエピソードと結びつけながら語り合うことが欠かせません。その積み重ねこそが、訪問看護の価値をさらに高め、社会全体に希望を広げていくのです。
提供するサービスのこだわりを言語化する

オーダーメイドのケアをどう実現するか
訪問看護の現場では、同じ疾患を持つ利用者であっても、生活環境や家族構成、価値観は大きく異なります。そのため、一律のマニュアルだけでは本当に必要とされるケアは届けられません。そこで大切になるのが「オーダーメイドのケア」です。利用者一人ひとりの生活背景に合わせて柔軟に対応し、その人らしい暮らしを支えることこそ、訪問看護の真価だといえます。
例えば、同じ糖尿病の方でも「自分で血糖測定をしたい」と希望する人と「すべて任せたい」と感じる人では、支援の仕方が変わります。食事指導にしても、「家族と一緒に料理を工夫する楽しみを残したい」方と「できるだけ手間を減らして続けたい」方では提案内容が違って当然です。こうした違いを丁寧に受け止め、本人に寄り添った形に落とし込むことが、オーダーメイドのケアの実践です。
このこだわりを言語化することで、スタッフ全員が「私たちは利用者の生活に合わせた支援を重視する」という共通認識を持つことができます。さらに、利用者や家族に対しても「このステーションは自分たちの状況を理解してくれる」と安心感を与えられます。次に、多職種連携のこだわりを考えていきましょう。
医療と福祉の垣根を越えた連携
訪問看護の現場では、医師、ケアマネジャー、介護職、リハビリスタッフなど、多職種との関わりが欠かせません。そこで「医療と福祉の垣根を越えて連携する」ことをこだわりとして掲げることには大きな意味があります。なぜなら、在宅療養を支えるには医療的視点と生活支援の両方が必要だからです。
例えば、末期がんの利用者に対して「痛みを軽減する医療的支援」と「残された時間を家族とどう過ごすかという生活支援」の両方が求められます。看護師だけで対応するのではなく、医師が適切に処方を行い、介護職が日常生活をサポートし、リハビリスタッフが活動性を維持する。このように、それぞれの専門性をつなぎ合わせることで、初めて利用者の望む暮らしを実現できます。
また、多職種連携のこだわりを打ち出すことは、ステーションの信頼性を高める効果もあります。外部の関係者にとって「ここは情報共有が丁寧で、連携がスムーズ」と感じてもらえることは、紹介や協力の増加につながります。こだわりを言語化することで、ステーション内外に「私たちは一人で抱え込まず、チームで支える」という姿勢を示すことができるのです。次は、教育や研修への投資について掘り下げます。
スタッフ教育と研修への投資
質の高いサービスを維持するためには、スタッフ一人ひとりの成長が欠かせません。そのため「教育や研修に力を入れる」ことをこだわりとして明確にすることが重要です。訪問看護は病院と比べて一人で判断する場面が多く、新人や経験が浅いスタッフにとっては不安が大きい職場でもあります。その不安を解消し、安心して現場に出られるようにするためには、体系的な教育と研修が必要です。
例えば、新人スタッフには同行訪問を重ねて実践的に学ぶ機会を用意し、経験者には症例検討会や外部研修を通じてスキルアップの場を提供することが考えられます。教育のこだわりを「私たちは常に学びを重視し、成長できる環境を整える」と明言することで、スタッフの安心感が高まり、定着率の向上にもつながります。
さらに、このこだわりを利用者や家族に発信することも意味があります。「私たちは学び続けることで、より良いケアを提供します」と伝えることで、信頼感を強化できます。教育への投資はコストではなく、サービスの質を未来につなぐための重要な資源なのです。最後に、理念とつながる「こだわりの言語化」の意義をまとめます。
こだわりを理念と結びつける意義
ここまで述べてきたオーダーメイドのケア、多職種連携、教育研修といったこだわりは、単なる運営方針ではなく、理念と深く結びつけることで力を発揮します。「なぜそのこだわりを持つのか」を説明できると、外部からも内部からも納得感を得やすくなるのです。
例えば「利用者一人ひとりに合わせたケアを行う」というこだわりは、「その人らしい人生を支える」という理念と直結しています。「多職種連携を重視する」という姿勢は、「地域で支え合う社会をつくる」という未来像と結びつきます。「教育研修に投資する」という行動は、「スタッフが誇りを持って働ける職場を目指す」という価値観につながります。
こだわりを理念と結びつけることで、スタッフは日々の実践の意味を理解しやすくなります。また、利用者や家族に対しても「この事業所は何を大切にしているのか」が明確になり、信頼関係を築きやすくなります。こだわりを明文化し、理念とともに共有することが、訪問看護ステーションが持続的に成長していくための基盤となるのです。
「絶対にやりたくないこと」を共有する

理念を守るための「やらないことリスト」
理念や価値観を明確にするうえで、「私たちは何を大切にするか」と同じくらい大切なのが「私たちは何を絶対にやらないか」を言葉にすることです。現場では忙しさのあまり、「とりあえず効率優先で」「最低限だけで済ませよう」といった判断をしがちです。しかし、それを繰り返すと気づかないうちに理念から外れた行動が常態化してしまいます。だからこそ「やらないことリスト」を持ち、スタッフ全員で共有することが必要です。
例えば、
「患者さんや利用者さんを数字でしか見ない」
「スタッフの心身が疲弊しても放置する」
といった行為は、どんな状況でも避けるべきです。こうした「やらないこと」を明確に示すことで、判断に迷ったときの基準ができます。「何をするか」だけでなく「何をしないか」も明示することが、理念を実際の行動に落とし込む大きな支えとなるのです。次に、現場でよく起こりがちな「やりたくないこと」の具体例を見ていきましょう。
利用者や家族を「効率」で測らない
訪問看護の現場では時間管理が非常に重要です。訪問スケジュールが詰まっていると、一人あたりの訪問時間を削ろうとする誘惑が生まれます。しかし「効率だけで訪問時間を削る」ことは、理念に反する行為になりかねません。利用者にとっては短い訪問時間が「大切にされていない」と感じられることもあるからです。
もちろん効率を意識すること自体は必要ですが、それが利用者や家族との関係を犠牲にする形になってはいけません。「この利用者は処置が少ないから、早く終わってもいい」といった見方は、利用者の尊厳を損なう危険があります。私たちが「絶対にやらない」と決めるべきことのひとつは、「効率だけで人を測る」という考え方です。
訪問看護の理念が「その人らしい生活を支える」であるなら、利用者の声に耳を傾け、安心感を持ってもらえるような関わりを優先する必要があります。この視点を共有しておくことで、現場での迷いが減り、スタッフ同士が同じ方向を向いて行動できるようになります。次は、スタッフに関する「やりたくないこと」を考えます。
スタッフを犠牲にする職場環境は避ける
訪問看護ステーションを持続的に運営するためには、スタッフの健康や働きやすさを犠牲にしてはいけません。「人が足りないから残業は当然」「休みを取れなくても仕方ない」という空気が広がると、スタッフは疲弊し、離職につながります。これもまた「絶対にやりたくないこと」のひとつです。
理念や価値観を守るためには、まずスタッフ自身が安心して働けることが前提になります。利用者に寄り添う姿勢を大切にするなら、スタッフが自分の生活や健康を犠牲にしないようにすることも同じくらい大切です。
・「休暇を取ることを後ろめたく感じさせない」
・「業務を一人に抱え込ませない」
といった基本的な姿勢を共有することが、理念を現場に根づかせる土台になります。
この点を明確にしておくことで、経営層や管理者は「スタッフの犠牲による運営はしない」と意思表示できます。結果として、スタッフは安心して働き続けられ、利用者にとっても安定した支援につながります。最後に、「やらないこと」を共有することが組織全体に与える効果について考えましょう。
「やらないこと」を共有することの効果
「絶対にやりたくないこと」を組織で共有することには、大きく二つの効果があります。ひとつは、現場での迷いを減らす効果です。訪問看護では一人で判断する場面が多く、迷いがストレスになることも少なくありません。しかし「この行為は私たちの理念に反するからしない」と決まっていれば、迷う時間を減らせます。
もうひとつは、組織文化を強くする効果です。「やらないこと」がはっきりしている組織は、価値観に一貫性が生まれます。その一貫性がスタッフの安心感につながり、外部からも「この事業所は信頼できる」という印象を持たれやすくなります。
例えば、「数字だけで人を評価しない」「スタッフの疲弊を放置しない」といった姿勢を外部に発信すれば、利用者や家族だけでなく地域の関係者からも信頼される存在になります。理念や価値観を守り続けるためには、「やること」だけでなく「やらないこと」を徹底することが不可欠なのです。
組織を象徴するキーワードを決める
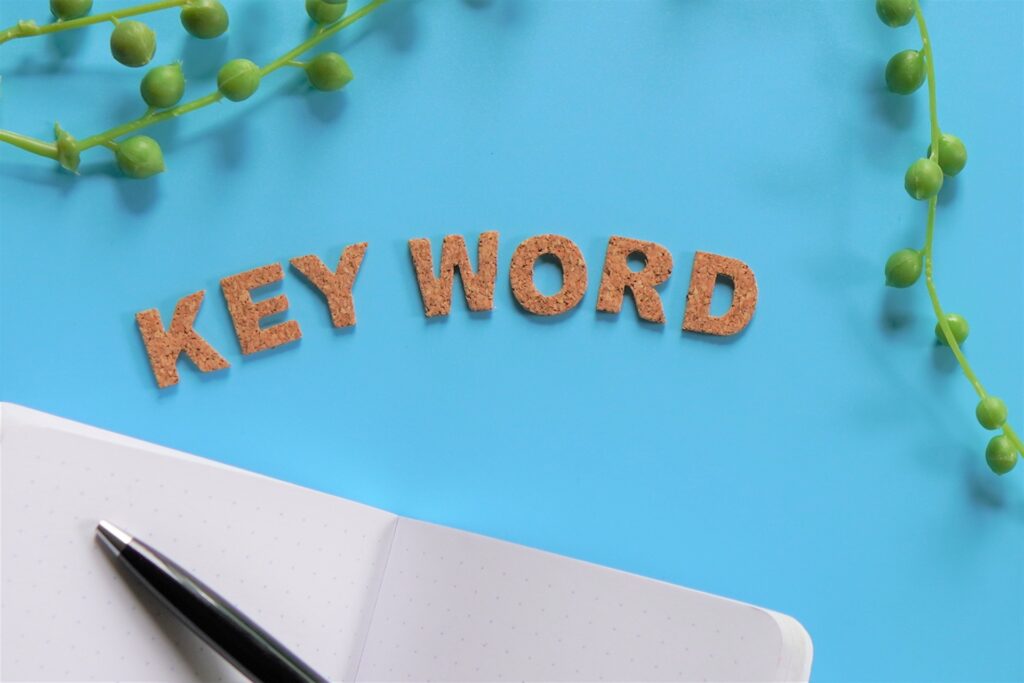
なぜキーワードが必要なのか
理念や価値観を共有しても、日常業務の中では「言葉が抽象的でイメージしづらい」と感じるスタッフも少なくありません。そこで有効なのが、組織を象徴するシンプルなキーワードを設定することです。短く、覚えやすい言葉は、理念を現場で実感できる「合言葉」のような役割を果たします。
例えば「信頼」「安心」「尊厳」といったキーワードを掲げれば、スタッフは訪問の中で迷ったときに「この行動は利用者の尊厳を守れているか?」と立ち返ることができます。理念を長文で読み返さなくても、キーワードがあれば瞬時に方向性を確認できるのです。
また、キーワードは外部に向けたメッセージとしても力を発揮します。利用者や家族、地域の関係者に「このステーションは〇〇を大切にしている」と伝えることで、信頼感を築きやすくなります。つまりキーワードは、理念を「日常に使える道具」に変えるために欠かせない要素なのです。次に、具体的にどのようなキーワードを選ぶべきか考えていきます。
訪問看護にふさわしいキーワードの例
訪問看護においてキーワードを設定する際には、医療の専門性だけでなく、生活を支える視点を含めることが重要です。たとえば「信頼」は基本的な土台です。利用者や家族が看護師に心を開き、不安を打ち明けられるのは、信頼関係があってこそです。
「安心」も訪問看護ならではのキーワードです。自宅というプライベートな空間にスタッフを迎え入れる利用者にとって、安心感は何より大切です。訪問の度に「今日も来てくれてほっとした」と感じてもらえることが理想です。
さらに「尊厳」という言葉は、人生の最期まで自分らしく過ごしたいという利用者の願いに応える姿勢を象徴します。他にも「成長」「挑戦」といったキーワードは、スタッフ自身のキャリア形成や組織の前進を後押しするものとして意味があります。
大切なのは、キーワードが表面的に聞こえる言葉ではなく、日々の業務やエピソードと結びつく具体性を持っていることです。次は、これらのキーワードを現場でどう浸透させるかを考えます。
キーワードを現場に根づかせる方法
キーワードを決めても、それが机上のスローガンにとどまれば意味がありません。現場で自然に使われるようにするためには、日常業務と結びつける工夫が必要です。
例えば、朝礼やミーティングで「今週は“安心”をテーマにした訪問を意識しましょう」と声をかける。訪問後の振り返りで「この利用者に安心を届けられたと感じた場面は?」と共有する。こうした小さな仕組みが、キーワードを生きた言葉に変えていきます。
また、新人教育でも「このステーションのキーワードは〇〇です。あなたの経験とどう重なりますか?」と問いかけることで、自分の価値観と組織の方向性を重ね合わせることができます。キーワードは暗記するものではなく、自分の行動に落とし込んで使うものだと理解してもらうことが大切です。
さらに、外部への発信にも活用できます。パンフレットや採用ページに「私たちのキーワード」として掲載するだけでなく、具体的なエピソードと一緒に紹介することで、共感や信頼を得やすくなります。次に、キーワードを決める過程そのものの意味を掘り下げます。
キーワード決定のプロセスが文化をつくる
実は、キーワードを何にするか以上に大切なのは「どう決めるか」というプロセスです。経営者や管理者が一方的に決めるのではなく、スタッフ全員が意見を出し合い、対話を重ねて選ぶことが理想です。その過程で
「私たちは何を大事にしたいのか」
「どんな姿勢を貫きたいのか」
を自然に共有できるからです。
たとえば「信頼」と「挑戦」のどちらを選ぶかを議論する中で、「信頼があってこそ挑戦できる」という意見が出るかもしれません。このやりとり自体が理念の確認作業となり、スタッフの納得感を高めます。最終的に選ばれたキーワードは、全員でつくった合言葉として強い力を持ちます。
また、定期的に見直すことも有効です。数年ごとに「今の私たちを象徴する言葉は何か」と問い直すことで、組織の成長や変化に応じたアップデートが可能になります。キーワード決定のプロセスそのものが、組織文化を育てる営みなのです。
訪問看護ステーションの運営において、理念や価値観を明確にすることは、日々の業務を支える羅針盤となります。「なぜ」を問い直すことで仕事の根幹にある思いを掘り下げ、解決したい課題と未来像を描くことで方向性を共有できます。さらに、提供するサービスのこだわりや「絶対にやりたくないこと」を言語化し、組織を象徴するキーワードを持つことで、理念は日常に生きた形で浸透します。理念は抽象的な言葉ではなく、具体的な行動を導く力を持つものです。スタッフ全員が共通の価値を意識しながら歩むことで、利用者や家族に寄り添う質の高いケアを実現し、地域社会に持続的な安心を届けることができるでしょう。

監修者:牟田 健登(Kento Muta)
株式会社クルージズ・テクノロジーズ代表取締役。2021年に創業し、在宅医療・介護業界に特化した人事コンサルティング・人事評価SaaSを展開。訪問看護ステーションや訪問介護ステーションを中心にサービスを展開中。











