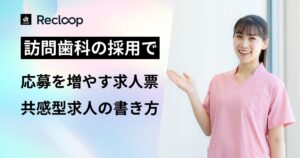歯科クリニックの院長の中には、「求人を出しても応募がほとんど来ない」「せっかく採用できても、すぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えている方が少なくありません。特に近年は歯科衛生士や歯科助手の人材不足が顕著になっており、求人を掲載するだけでは応募が集まらない状況が続いています。
その背景には、労働人口の減少や他業界との人材獲得競争の激化といった社会的な要因がありますが、同時にクリニック側の求人の打ち出し方や採用の進め方にも課題が潜んでいることが多いです。求人票に条件を並べるだけでは「どのクリニックも同じ」に見えてしまい、応募者に選ばれる理由が伝わりません。また、面接や入職後のフォローが不十分なままでは、採用しても定着に結びつかず、再び採用活動に追われることになります。
つまり、応募が集まらない・採用が定着しない背景には、社会全体の流れと、個別のクリニックが発信している情報や職場環境の両面が関係しているのです。本記事では、このような「採用がうまくいかない本当の理由」を順を追って掘り下げながら、歯科クリニックが明日から取り組める改善のヒントを提示していきます。次章ではまず、「なぜスタッフが集まらないのか」という現状認識から整理していきましょう。
なぜ歯科クリニックに応募が集まらないのか?
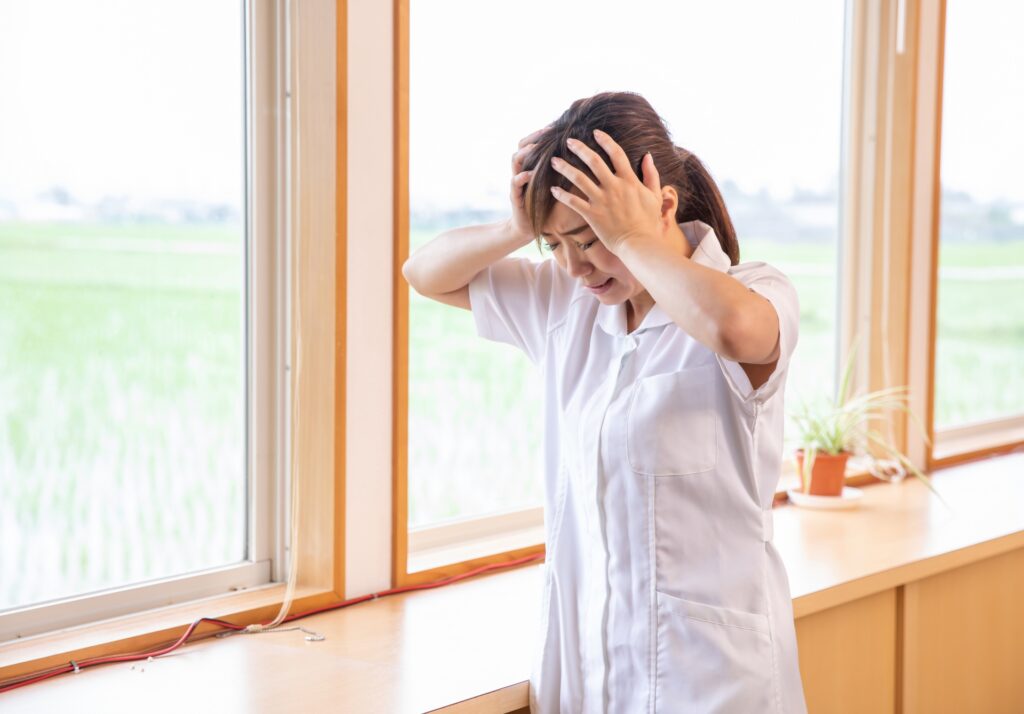
求職者が歯科クリニックを選びにくい理由
歯科クリニックの採用が難航する最大の要因の一つは、求職者が安心して応募できる情報が十分に提示されていないことです。歯科衛生士や歯科助手が転職を考えるとき、最も重視するのは給与額や休日の数ではなく、「働きやすさ」や「人間関係の良さ」といった要素です。求人票に数字として載る条件は一見比較しやすいものの、それだけでは「ここで働く自分の姿」がイメージしにくく、応募に踏み切れないのです。
たとえば子育て世代の歯科衛生士であれば、「急に子どもが熱を出したときに休めるか」「夕方に保育園へ迎えに行けるか」といった生活に直結する視点で職場を見ています。しかし、多くの求人にはそのような具体的なエピソードが書かれていません。結果として、「条件は悪くないけど、もし入職して合わなかったら困る」と慎重になり、応募を見送るケースが増えています。
また新卒者に目を向けると、「教育体制が整っているかどうか」が大きな関心事になります。実地研修の有無や、先輩スタッフがどの程度サポートしてくれるのかといった情報がなければ、安心して応募できません。こうした心理的なハードルを取り払う情報が求人票から抜け落ちていることが、応募の少なさにつながっているのです。
さらに最近では、求人票だけでなく口コミサイトやSNSを調べて判断する動きが当たり前になっています。求人票とネット上の評判が一致していれば安心感につながりますが、「求人ではアットホームと書かれているのに、口コミでは人間関係の厳しさが目立つ」といったギャップがあると、応募者は即座に候補から外してしまいます。つまり、応募が集まらない理由の多くは「情報がないこと」や「情報に一貫性がないこと」にあるのです。
他業界との歯科人材獲得競争
歯科衛生士の資格を持つ人材は年々減少しているわけではありません。それでも採用が難しくなっているのは、働き先の選択肢が広がり、歯科クリニック一本に絞る必要がなくなっているからです。
近年は、美容クリニックでホワイトニングや審美治療をサポートする仕事や、企業の健康経営を支える予防歯科部門、訪問歯科など多様な現場で衛生士が活躍しています。給与水準が歯科医院より高めに設定されているところもあり、若手ほど「せっかくならキャリアの幅を広げたい」と考える傾向が強いのです。
歯科助手も同様です。かつては歯科クリニックでの勤務が一般的でしたが、現在では美容業界や介護業界との競合が起きています。例えば美容クリニックでは受付兼助手として月給20万円後半スタートという求人もあり、残業が少ない場合は人気が集まりやすいのです。歯科助手の給与相場が地域によっては月給18万円台にとどまることを考えると、他業界に流れてしまうのは自然な流れともいえます。
つまり応募が集まらないのは「歯科業界そのものの人材不足」ではなく、「他業界との比較で選ばれにくくなっている」という構造的な問題でもあります。クリニック側がこの現実を把握せずに「人がいない」と嘆くだけでは、状況は改善しません。
歯科クリニック側の発信不足
応募を増やすためには、条件面以上に「このクリニックで働くとどんな日常になるか」を伝える必要があります。しかし、多くの求人票やホームページでは基本的な情報しか載っておらず、働く人の声や日常の雰囲気が発信されていません。
実際に応募につながりやすいのは、スタッフのリアルな声や院内の様子です。例えば「子どもの急な発熱でお休みをいただいたとき、同僚が『大丈夫?』と声をかけてくれた」というエピソードや、「月1回の勉強会で最新の治療知識を学べる」といった日常の積み重ねが、求職者に安心感を与えます。こうした情報がなければ、応募者は「条件は悪くないけど、雰囲気がわからない」と感じ、結局応募を控えてしまうのです。
SNSを活用して院内の取り組みやスタッフの日常を発信しているクリニックでは、応募数が明らかに多い傾向があります。特にInstagramで「スタッフ紹介」や「1日の仕事の流れ」を写真とともに発信することで、応募前に「ここなら働けそう」と思ってもらえるケースが増えています。逆に発信が一切ないクリニックは、求人票だけでは埋もれてしまい、応募に結びつきにくい状況です。
応募から採用までの導線の不備
もう一つ見落とされがちなのが、応募から採用に至るまでの流れです。せっかく興味を持ってもらっても、応募フォームが複雑だったり、問い合わせに対する返答が遅かったりすると、求職者の意欲は一気に下がってしまいます。
例えば、応募者がエントリーしてから3日以上返信がないと、その間に他のクリニックで内定が出てしまうことがあります。現在の転職市場では「24時間以内に返信する」のが望ましいとされており、対応スピードが直接採用の成否を分けるのです。
また、面接で求人票と異なる条件を提示された場合も応募者は不信感を抱き、辞退につながります。「残業ほぼなし」と書かれていたのに実際は週数時間発生している、といった食い違いはよくある事例です。このような小さな齟齬が積み重なり、応募が集まらない・採用につながらない状況を生んでいます。
さらに、見学やカジュアル面談といった「応募前に軽く関われる仕組み」がない場合も、応募者はハードルを感じます。「まずは話を聞いてみたい」という層を取り込めないまま、応募に直結する人材だけを待っていると、母集団が極端に小さくなってしまうのです。
このように、応募が集まらない理由は単なる人材不足ではなく、
①求職者の心理的な不安
②他業界との競争
③情報発信の不足
④採用プロセスの不備
といった複数の要因が重なった結果といえます。ここを理解しなければ、求人を出し続けても同じ壁にぶつかり続けることになります。次は、こうした背景を踏まえ、歯科クリニックの採用で「何を優先的に考えるべきか」という視点に移っていきます。
歯科クリニック採用で考えるべき優先順位とは?

条件面だけに偏らない見せ方
歯科クリニックの採用活動において、多くの経営者が最初に考えるのは給与や休日といった条件の改善です。もちろん条件が極端に劣っていれば応募が集まらないのは事実です。しかし「給与を上げたのに応募が来ない」という声があるように、条件面の調整だけでは問題を解決できません。
求職者にとって条件は「応募の最低基準」にはなりますが、「応募したい」と思う決め手にはなりにくいのです。実際、給与が平均より少し高い程度では決断につながらず、「このクリニックで働く自分がイメージできるか」「安心して続けられるか」がより重視されています。したがって優先順位をつける際には、条件の見直しだけでなく「情報の出し方」「働きやすさの証拠」を整えることを前提に考える必要があります。
条件改善を入り口にしつつ、応募者が安心できる情報をどのように提示するか。それが優先順位の第一歩といえるでしょう。
応募者に「選ばれる理由」を示す
次に優先すべきは、他のクリニックと差別化できる要素を明確に打ち出すことです。求職者は複数の求人を比較検討しており、その中で「ここに応募したい」と思える理由がなければ選ばれません。例えば、
「小児歯科に力を入れている」
「訪問歯科に積極的」
「スタッフの平均勤続年数が長い」
といった具体的な特徴は、応募者にとって大きな判断材料になります。単に「アットホームです」「働きやすい環境です」といった抽象的な表現では差別化にならず、むしろ不信感を抱かれる可能性があります。
さらに、求職者が知りたいのは「制度」そのものよりも「制度がどう役立っているか」です。「育休制度あり」よりも「育休後に復帰し、時短勤務で活躍しているスタッフがいる」と伝えた方が、リアリティがあり信頼感を生みます。こうした「選ばれる理由」を示すことが、採用改善における最優先課題の一つです。
応募後の体験を重視する
優先順位を考えるうえで忘れてはならないのが、応募後の体験です。求人票を見て「いいかも」と思っても、問い合わせへの対応が遅かったり、面接での対応が形式的だったりすると、求職者の意欲は一気に下がります。
例えば応募から24時間以内に返信があれば「しっかりした職場だ」と安心されますが、数日放置されると「人手不足で忙しすぎるのでは?」と不安が広がります。面接でも院長や採用担当者が応募者の経歴だけを一方的に確認するのではなく、「どんな働き方を希望していますか」「将来どんなキャリアを描きたいですか」といった対話を重視することで、応募者の満足度は大きく変わります。
優先順位をつける際には「応募者が問い合わせてから入職を決めるまでの体験」をイメージすることが欠かせません。ここが整っていなければ、せっかく応募数が増えても内定辞退や早期離職につながってしまいます。
定着につながる仕組みを最優先に
採用改善を考える際、最終的に最も優先すべきは「定着」です。採用にコストと時間をかけても、短期間で離職してしまえば再び同じ課題に直面します。定着を前提に考えることが、採用活動全体の効率を高める唯一の道といえます。
具体的には、入職後の教育体制やフォローの仕組みが整っているかを最優先で確認すべきです。
「入社初日にいきなり現場に放り込まれる」
「質問しづらい雰囲気がある」
といった状況では、早期退職につながります。逆に「最初の1か月は先輩が隣で指導する」「週1回の振り返り面談がある」といった仕組みがあれば、安心して定着できます。
また、働き方に柔軟性を持たせることも重要です。シフトの調整や時短勤務の選択肢があることで、家庭の事情を抱えるスタッフも長く働ける環境になります。採用の優先順位は、求人票に書く条件ではなく「どうすれば長く働いてもらえるか」を軸に考えるべきなのです。
このように、歯科クリニックが採用を進める際に考えるべき優先順位は、
①条件の見直しを入口にする
②応募者に選ばれる理由を示す
③応募後の体験を整える
④定着の仕組みを最優先に置く
という流れに整理できます。次は、これらの背景を踏まえ「なぜこうした優先順位が必要なのか」、その理由を深く掘り下げていきます。
なぜ採用がうまくいかない状況が続くのか?

採用活動が場当たり的になっている
歯科クリニックの多くでは、採用活動が「人が辞めたから急いで求人を出す」という流れで進んでいます。必要に迫られて動くため、短期的な視点に偏りやすく、根本的な改善につながりにくいのです。
たとえば「スタッフが辞めたから求人媒体に広告を出す」「応募が来ないから給与を少し上げる」といった動きは、目の前の穴埋めにはなりますが、同じことを繰り返すだけになりがちです。結果として、採用にかかるコストが膨らみ、定着率も改善されず、「求人を出しては苦戦する」サイクルが続いてしまいます。
本来であれば、採用は経営戦略の一部として計画的に取り組むべきものです。求める人材像を明確にし、どのような情報を発信すれば届くのか、入職後にどう育成して定着させるのかといった流れを持たなければ、いつまでも「場当たり的な採用」にとどまってしまいます。
求職者視点が欠けている
採用がうまくいかない大きな理由の一つは、求人情報や面接対応に「経営側の視点」が強すぎて、求職者の立場から考えられていないことです。
求人票には「週休2日」「賞与あり」といった条件が整然と並んでいますが、求職者が知りたいのはそれだけではありません。実際には、
「どんなスタッフが働いているか」
「教育やサポートはあるか」
「院長はどんな人か」
といった、働く日常に直結する情報が知りたいのです。ところが、多くの求人は経営側が伝えたい条件だけを並べて終わっており、求職者の疑問に答えきれていません。
面接においても同じです。経歴や資格の確認に終始してしまい、応募者の希望や不安を聞き出す場になっていないケースが目立ちます。求職者にとって「自分の話を聞いてもらえた」「ここなら安心して働けそう」と感じることが、応募後の意欲を高める最大の要素であるにもかかわらず、それが実現できていないのです。
発信と現実のギャップ
採用が長期的にうまくいかない理由として、求人やホームページで発信している内容と、実際の職場環境に差があることも挙げられます。
「残業ほぼなし」と記載していても、実際には1日30分〜1時間程度の残業が常態化していたり、「アットホームな職場」と打ち出しているのに人間関係に摩擦が多かったりすると、入職者は「聞いていた話と違う」と感じ、早期離職につながります。この不一致が続けば、口コミサイトにネガティブな投稿が増え、結果として次の応募も集まらなくなってしまいます。
逆に、多少厳しい部分も含めて正直に発信しているクリニックは、応募数こそ少なくても「自分に合いそう」と納得して入職する人が多く、結果的に定着率が高まります。採用がうまくいかない背景には、この「発信と現実の乖離」が存在することを見逃してはいけません。
定着を意識した仕組みが弱い
採用がうまくいかない状況が続く最大の原因は、採用した人が定着しないことにあります。離職が発生すれば、再び採用に追われ、またコストと時間がかかるという悪循環に陥ります。
定着につながらない理由はさまざまですが、典型的なのは教育体制やフォローの不足です。入職してすぐに一人で患者対応を任されてしまったり、相談できる相手がいない環境では、不安から短期間で辞めてしまう可能性が高まります。
また、ワークライフバランスを重視する人材が増えている中で、シフトの柔軟性がない、急な休みに対応できないといった環境も、離職を招きやすい要因です。結局、採用が続けて失敗するのは「採用の数を増やす」ことばかりに意識が向き、「入職後にどう働き続けてもらうか」という仕組みづくりが後回しになっているからなのです。
このように、採用がうまくいかない状況が続く理由は、
①場当たり的な採用
②求職者視点の欠如
③発信と現実のギャップ
④定着を意識した仕組みの不足
といった複数の課題が重なっているためです。次は、これらの課題を踏まえて「改善のために何をすべきか」という具体的な取り組みについて考えていきます。
歯科クリニック採用を改善する具体的な方法

求人票を「生活のイメージ」が伝わる内容に変える
改善の第一歩は、求人票を条件の羅列ではなく「ここで働くとどういう生活ができるか」を描けるものに変えることです。給与や休日といった数値的な条件はもちろん必要ですが、それ以上に求職者は「日々の働き方」を重視します。
たとえば「残業ほぼなし」だけでなく、「保育園のお迎えに間に合うスタッフが多い」と書けば、子育て世代にとっては具体的な安心材料となります。「有給消化率80%以上」だけでなく、「家族旅行や子どもの行事で休みを取ったスタッフの声」を載せれば、リアリティが伝わります。
数字とエピソードを組み合わせることで、応募者は「自分の生活に重ね合わせて考える」ことができます。求人票は条件を示すだけの書類ではなく、応募者が未来をイメージするための入口だと捉えることが重要です。
スタッフの声や日常を積極的に発信する
応募者が安心できる情報を得る場は、求人票だけではありません。SNSやホームページでの日常的な発信が、応募意欲を大きく左右します。
たとえばInstagramで「スタッフ紹介」を行うと、応募者は人柄や雰囲気を直感的に感じ取れます。「育休から復帰して時短勤務をしているスタッフ」「資格取得を目指して勉強しているスタッフ」などを紹介すれば、働き方の多様性が伝わります。さらに「1日の流れ」や「診療後の勉強会の様子」を写真や動画で発信すれば、働く姿をリアルに想像できるようになります。
また、クリニックの方針や院長の考え方をメッセージとして発信するのも効果的です。「患者さんとの関係を大切にしている」「スタッフの成長を支援する」などの理念は、共感を生み、応募者に「ここで働きたい」と思わせる要素になります。
応募から面接までをスピーディにする
どれだけ求人票や発信を工夫しても、応募後の対応が遅ければ採用は成功しません。求職者は複数の職場を同時に検討しているため、返信が遅れればその間に他のクリニックで内定が決まってしまうことも珍しくありません。
理想は、応募から24時間以内に連絡を取ることです。「応募ありがとうございます。まずは見学も可能です」といった簡単な返信でもよく、素早い対応が信頼感を生みます。さらに、面接の日程調整は候補日を複数提示するなど、応募者が動きやすい仕組みにすることが重要です。
面接時も形式的な質疑応答だけでなく、応募者の希望を聞き出す時間を設けると安心感が高まります。質問の一例としては「どんな働き方を希望していますか」「どんなサポートがあれば安心ですか」といった、応募者が将来を描ける内容が効果的です。
入職後のフォロー体制を整える
採用を改善する最終的なゴールは「定着」です。せっかく採用できても短期間で離職してしまえば、また採用活動に追われてしまいます。そのため、入職後のフォロー体制を整えることが最も重要な改善策となります。
具体的には、入職直後の研修やOJT(実地研修)を計画的に行い、一定期間は先輩スタッフが伴走する仕組みをつくることが有効です。また、1か月ごとに振り返り面談を設けることで、不安や疑問を早めに解消できます。
さらに、ライフステージの変化に対応できる柔軟な制度も欠かせません。時短勤務やシフト調整の仕組みを用意すれば、子育てや介護を担うスタッフも長く働き続けられます。こうした体制があることで、「ここなら長く働ける」と感じてもらえるようになります。
このように、求人票の見直し、日常的な発信、応募後のスピード感、入職後のフォロー体制といった具体的な取り組みを積み重ねることで、採用は改善に向かいます。次は、これらを踏まえたうえで「明日からすぐに始められる行動」を整理していきます。
明日からできる歯科クリニック採用改善のアクション

求人票の小さな書き換えから始める
大掛かりな取り組みを始める前に、まずは求人票の表現を一部書き換えるだけでも効果があります。条件の羅列だけでなく「そこで働く自分の姿」が想像できる文章に変えるのです。
例えば「週休2日制」と記載するだけでなく、「土曜日午後と日曜が休みなので、家族と過ごす時間を確保しやすい」と具体的に書き加えます。また「残業ほぼなし」とだけ記すのではなく、「保育園のお迎えに間に合うスタッフが多い」と伝えれば、子育て世代の応募意欲を高められます。
こうした小さな修正は即日対応でき、求人媒体やホームページの更新でその日のうちに反映可能です。まずは「数字+エピソード」で求人票を補強することが、明日からできる最も手軽なアクションになります。
SNSやホームページで日常を切り取る
応募者は求人票以外の情報を必ず探しています。そこで効果的なのが、SNSやホームページでの情報発信です。大がかりな運用を始める必要はなく、まずは「週に1回の投稿」からでも十分です。
例えばスタッフの誕生日をお祝いした写真や、診療後に勉強会をしている様子、院長がスタッフに声をかけている場面などを切り取って投稿するだけで、雰囲気が伝わります。応募者は条件だけでなく「人」を見て応募を決めるため、こうした日常の発信は強い後押しになります。
また、応募前に「ここなら安心して働けそう」と思ってもらうことが目的なので、完璧なコンテンツを作る必要はありません。「リアルな日常を伝える」という意識があれば、SNSは強力な採用ツールになります。
応募者対応のスピードを変える
改善の即効性が最も高いのは、応募が来たときの対応スピードを変えることです。返信を「できるだけ早く」ではなく「24時間以内に必ず」とルール化するだけで、応募者の離脱は大幅に減ります。
例えば、診療で忙しくても「応募ありがとうございます。詳細は明日ご連絡します」といった簡単な自動返信を設定しておくだけでも効果的です。返信の有無は求職者にとって「安心感」そのものです。
さらに、面接日程の提示は候補日を3つ以上まとめて送るとスムーズです。応募者が予定を合わせやすくなるだけでなく、「対応が早く、段取りが良いクリニック」という印象を与えられます。
入職後のフォローを一つ加える
定着率を上げるためには、入職直後の不安を解消するフォローを一つ加えるだけでも大きな効果があります。例えば「入職後1週間で必ず面談を行う」と決めることです。
新人は最初の数日で不安を抱えがちですが、面談があれば「困ったことを相談できる」と感じ、早期離職を防げます。さらに「1か月後・3か月後」のタイミングでの面談を組み込めば、長期定着につながります。
フォロー体制を完璧に整える必要はありません。まずは「入職1週間の面談」を習慣化することから始めると、安心して働ける環境づくりが一歩進みます。
このように、求人票の表現を少し変える、SNSで日常を発信する、応募対応を早める、入職後に短い面談を追加する、といったアクションは明日からすぐに取り組めます。採用改善は大きな投資が必要なわけではなく、小さな工夫の積み重ねで成果を出すことが可能です。
歯科クリニックの採用がうまくいかない背景には、人材不足だけでなく「求職者が安心できる情報不足」「他業界との競争」「採用プロセスの不備」「定着を意識した仕組みの欠如」があります。これらを踏まえ、求人票を生活のイメージが伝わる形に変える、SNSで日常を発信する、応募対応を迅速に行う、入職後にフォロー面談を設けるといった具体的な改善が求められます。採用は単なる人数確保ではなく、信頼関係を築き、長く働きたいと思ってもらえる環境を示す営みです。小さな一歩を積み重ねることで、応募が集まり、定着へとつながる採用の流れを実現できるでしょう。