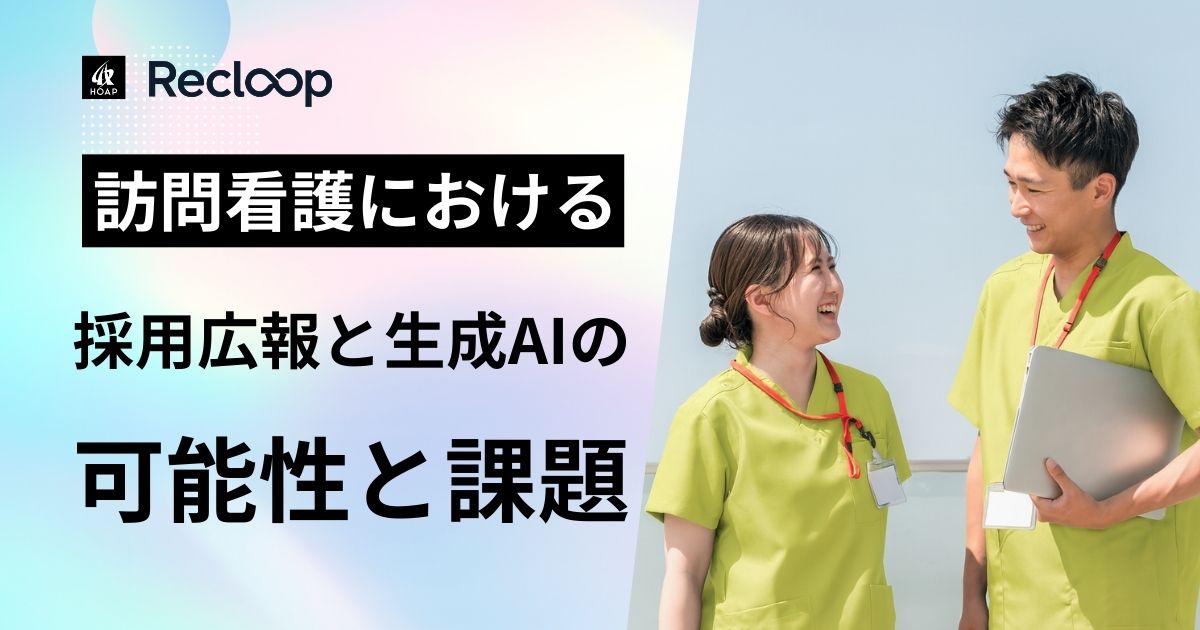訪問看護の採用活動において、多くの事業所が共通して抱えている悩みがあります。求人を出しても応募が集まらない、せっかく面接に進んでも定着につながらない、あるいは「仕事内容や魅力をどう伝えればよいのかわからない」という声です。訪問看護は病院勤務と比べて仕事内容のイメージが湧きにくく、働き方ややりがいも伝えづらい領域です。そのため、情報発信の工夫次第で求職者の印象が大きく変わってしまいます。
従来の採用広報は、求人票や説明会資料など、限られたフォーマットの中で表現することが中心でした。しかし、それだけでは「訪問看護ならではのやりがい」や「日々の働き方のリアル」を伝えきれません。結果として、求職者が不安を拭えず応募をためらったり、働く姿をイメージできないまま他の選択肢に流れてしまうこともあります。
そこで近年注目されているのが、生成AIの活用です。生成AIは、文章や企画を短時間で形にできるだけでなく、現場の声をもとにストーリー性のあるコンテンツを作ることにも向いています。採用広報の分野においても、AIを活用することで「訪問看護のリアルな魅力を、よりわかりやすく、より多くの人に伝える」ことが可能になります。
もちろん、AIの利用には課題もあります。精度や表現の適切さ、個人情報の扱いなど、人間の確認を欠かせない部分は残ります。しかし、人の手で補いながらAIを活用することで、これまで発信が難しかった情報を新しい形で伝えられる可能性が広がります。
本記事では、訪問看護における採用広報の現状を踏まえつつ、生成AIがどのように役立つのか、そしてその可能性と課題について解説します。次の章ではまず、「なぜ訪問看護で採用広報が難しいのか」を改めて考えていきます。
なぜ訪問看護で採用広報が難しいのか?

訪問看護という働き方の特殊性
訪問看護は、病院や施設での看護と比べて働き方のスタイルが大きく異なります。病棟であれば複数人のスタッフが一つの空間に常駐し、患者の状況をチームで共有しながら看護を進めることができます。しかし訪問看護では、看護師が一人で利用者の自宅を訪問し、その場で判断しながら対応を行います。相談できる同僚がすぐ隣にいない状況は、未経験者にとって強い不安につながります。
こうした働き方の特殊性は、求人票の数行の説明では十分に伝わりません。「一人で訪問する」と書くだけでは孤独感ばかりが強調され、サポート体制や訪問後の報告・相談の仕組みまでは伝わらないため、実際の働き方の全体像が見えにくいのです。求職者にとって「想像が難しい仕事」であること自体が、採用広報を難しくする一因となっています。
また、訪問看護は利用者の生活環境や家族の事情に合わせた個別性の高い看護が求められます。その柔軟性ややりがいは魅力的である一方、「標準化された病棟勤務」との違いをイメージできない人には伝わりにくいという課題も存在します。
情報発信の手段が限られている現状
採用広報の場面でよく用いられるのは、求人票やパンフレット、説明会でのスライドなどです。しかし、これらの媒体には情報量や表現方法に限界があります。例えば求人票では、給与や勤務時間、福利厚生などの条件面は明確に記載できますが、「働く雰囲気」や「チームの人間関係」といった要素は言葉だけでは伝えにくいのが実情です。
さらに、訪問看護は病棟のように「目に見える職場環境」がありません。求職者が見学に来ても、たまたまその日に訪問がなければ現場の様子を実感できない場合もあります。そのため、他職種と比べても「伝わりにくさ」が際立つ領域といえるでしょう。
SNSや採用サイトでの発信に取り組む事業所も増えていますが、忙しい日常業務の中で継続的にコンテンツを制作するのは負担が大きく、結果として情報更新が滞ってしまうケースも少なくありません。情報発信の手段が限られていることが、採用広報を難しくしている大きな理由です。
求職者が抱く不安と誤解
訪問看護の求人に接する求職者が抱きやすいのは、「自分に務まるだろうか」という不安です。病棟での経験しかない看護師は、在宅医療の知識や緊急時対応に自信を持てず、「一人で訪問するのは怖い」と感じがちです。求人票で「未経験歓迎」と書かれていても、どの程度サポートがあるのかが見えなければ安心できません。
また、訪問看護に対する誤解も根強くあります。「高齢者ばかりを診る仕事」「急変時に一人で責任を負わされる」といったイメージが独り歩きし、実際には医師や他職種との連携があるにもかかわらず、不安ばかりが強調されてしまうのです。こうした誤解を解消できないままでは、せっかく興味を持った人も応募をためらってしまいます。
求職者の不安や誤解を解消するには、現場のリアルな声や、実際のサポート体制をわかりやすく発信する必要があります。しかし、その「伝え方」を工夫できていないと、採用広報の効果は限定的になってしまいます。
定着までを見据えた採用広報の必要性
採用広報の目的は単に応募を集めることではありません。採用後に長く定着してもらうことこそが最終的なゴールです。そのためには、働くイメージを正しく伝え、「思っていた仕事と違った」というミスマッチを防ぐ必要があります。
訪問看護は、日々の利用者対応に加えて記録や報告業務も多く、慣れるまでに時間がかかります。もし採用段階で現場の大変さを伝えきれずに入職してしまうと、数か月で離職してしまうリスクが高まります。だからこそ、採用広報の段階で「やりがい」と「難しさ」の両面を伝え、求職者が納得感を持って選択できるようにすることが欠かせません。
しかし、求人票や面接だけではこのバランスを取るのは難しく、現場スタッフの声や具体的なエピソードを取り入れた広報が必要になります。ところが、そのための文章化や情報発信は簡単ではなく、ここにも広報の難しさがあります。
訪問看護の採用広報が難しい理由は、働き方の特殊性や情報発信の制約、求職者の不安や誤解、そして定着を見据えた情報提供の必要性にあります。これらの要素が重なり合うことで、「伝えたいことが伝わらない」というジレンマを生んでいるのです。
次の章では、このような課題に対して「生成AIがどのような可能性を持っているのか」を掘り下げていきます。
生成AIがもたらす新しい可能性

生成AIが情報発信のスピードと量を高める
訪問看護の採用広報において最大の課題のひとつは、情報発信の継続性です。現場は日々の訪問業務で忙しく、広報担当が専門で配置されている事業所は限られます。その結果、せっかく採用サイトやSNSを立ち上げても、更新が途絶えてしまうことが少なくありません。
生成AIは、この「発信が続かない」という課題に対して大きな力を発揮します。生成AIにテーマやキーワードを入力すれば、数分で下書きレベルの記事や投稿文を生成できます。これにより、ゼロから文章を考える負担を大幅に減らし、定期的な情報更新を可能にします。
たとえば「訪問看護師の1日の流れ」や「子育てと両立するスタッフの声」といったテーマは、現場には多くの素材が眠っています。AIがその素材を整理し、読みやすい文章に変換することで、これまで発信が難しかったコンテンツを短時間で公開できるようになります。スピードと量の両面で情報発信を支援する点は、生成AIがもたらす大きなメリットです。
採用広報のコンテンツに多様性を生み出す
もうひとつの可能性は、コンテンツのバリエーションを増やせることです。従来の採用広報は、求人票や数少ないインタビュー記事に偏りがちで、求職者から見ると「同じ情報が繰り返されている」印象を与えやすい傾向がありました。
生成AIを活用すると、同じテーマでも複数の切り口を提示できます。例えば「訪問看護のやりがい」を伝える際に、一方では「利用者との長期的な関わり」を強調し、別の角度では「一人で判断する力が身につく」ことを描く、といった具合です。AIは大量の言語パターンを生成できるため、伝え方にバリエーションを持たせやすく、読み手の共感ポイントを広げられます。
また、SNS用に短いフレーズをつくる、採用パンフレット用に丁寧な文章を準備する、といった媒体ごとの最適化も容易です。これにより「同じ素材を使いながら、異なる場面に合わせた発信」を効率的に行えるようになります。結果として、訪問看護の採用広報に新鮮さと多様性を加えることができます。
求職者目線の採用広報コンテンツを強化できる
訪問看護の採用で鍵となるのは、求職者が「自分ごと」として働く姿をイメージできるかどうかです。しかし現場にいるスタッフにとって、日常は当たり前すぎて魅力的に感じにくく、「どんな情報を発信すればよいのか分からない」という声もよく聞かれます。
生成AIは、求職者の立場をシミュレーションしながら文章を生成できる点に特徴があります。「子育てと両立できるか不安」「一人で訪問できるか心配」といった想定質問をAIに投げかけると、それに答える形の説明文を生成してくれるのです。これにより、読み手が知りたい情報に合わせたコンテンツを効率的に作ることが可能になります。
さらに、AIは文章のトーンを調整することも得意です。フランクで親しみやすい表現から、専門性を強調した信頼感のある書き方まで、用途に応じて出し分けることができます。こうした柔軟性は、従来の広報ではなかなか難しかった「求職者目線の強化」に直結します。
人とAIの協働で広報コンテンツの精度を高める
生成AIがつくる文章は便利ですが、そのまま使えば十分というわけではありません。事実関係の正確さや、現場特有のニュアンスは、人間によるチェックが不可欠です。しかし逆にいえば、人間が最終確認を担うことで、AIと人の協働は非常に大きな効果を発揮します。
例えばスタッフインタビューの文字起こしをAIに要約させ、その後に人間が「この言葉はスタッフらしさが出ているから残したい」と修正する。あるいは、AIが作った複数パターンの文章から、広報担当者が最も現場らしいものを選ぶ。このような協働プロセスは、スピードと質の両方を高めます。
訪問看護の採用広報においては、「利用者や家族への思い」「スタッフ同士の支え合い」といった温度感が特に大切です。AIだけでは拾いきれない温かさを人間が補完することで、リアルで信頼感のある発信につなげることができます。AIと人の役割をうまく分担することが、可能性を最大限に活かす鍵となるでしょう。
生成AIは、訪問看護の採用広報において「スピード」「多様性」「求職者目線」「人とAIの協働」という4つの側面で新しい可能性をもたらします。従来の発信では難しかった情報提供を効率的かつ魅力的に行えるようになり、応募のハードルを下げる効果が期待できます。
次の章では、より具体的に「訪問看護における生成AI活用の事例イメージ」を見ていきます。
訪問看護における生成AI活用の事例イメージ

生成AIで採用サイトの記事作成を支援する
訪問看護の採用広報でまず考えられるのは、採用サイトに掲載する記事やスタッフ紹介の作成です。従来は担当者が時間をかけて文章をまとめていましたが、現場業務との兼務では継続が難しいケースが多く見られます。そこで生成AIを活用すると、スタッフへのインタビュー内容を入力するだけで、読みやすい記事形式に整えることが可能になります。
例えば「子育てと両立する訪問看護師の一日」というテーマで取材した場合、インタビューのメモをAIに渡すと、文章を整理し、見出しや小見出しを付けて記事化してくれます。さらに、「求職者目線で魅力を強調してほしい」と指示すれば、単なる業務の羅列ではなく、働き方の安心感ややりがいが伝わる構成に変換できます。
こうしてAIが下書きを担い、人間が最終確認や細部の表現調整を行うことで、これまで数週間かかっていた記事制作が数日で完成するようになります。スピード感を持ちながら、現場のリアルを反映した情報発信が可能になるのです。
生成AIでSNSコンテンツのアイデア出しと文章化
InstagramやX(旧Twitter)といったSNSは、訪問看護の採用広報で注目される媒体ですが、日々の発信を継続するのは大きな負担です。そこで役立つのが生成AIによるアイデア出しと文章化の支援です。
例えば「訪問看護師に向いている人の特徴」というテーマをAIに依頼すると、「一人で判断する力」「柔軟に動ける姿勢」「利用者に寄り添う気持ち」といった要素を複数パターンで提案してくれます。それを短いキャッチコピーに変換すれば、SNS投稿用のフレーズとして活用できます。
また、写真や動画に添える説明文(キャプション)をAIに生成させれば、限られた文字数の中でも共感を呼ぶ表現が可能です。例えばスタッフの笑顔写真に「“ありがとう”の言葉が力になる。それが訪問看護の仕事です」と添えるだけで、閲覧者に職場の雰囲気を感じてもらえるでしょう。AIはこうした文章を短時間で複数案提示できるため、SNS運用の継続性を高める効果があります。
生成AIで求職者の疑問に応えるQ&Aコンテンツ作成
訪問看護を志望する人の多くは、仕事内容やサポート体制に関して具体的な疑問を抱えています。しかし、事業所側がそのすべてに対応するFAQを準備するのは容易ではありません。ここでも生成AIが活躍します。
例えば「訪問看護未経験ですが大丈夫ですか?」という質問に対して、AIに「新人研修」「同行訪問」「チームでの振り返り」といった情報を入力しておけば、分かりやすく整えた回答文を作成してくれます。さらにトーンを調整すれば、「安心感を与える優しい文章」や「専門性を強調する説明的な文章」といった形に変換することも可能です。
これを採用サイトやパンフレットに掲載することで、求職者の不安を事前に解消し、応募へのハードルを下げる効果が期待できます。AIを活用すれば、スタッフの手間を最小限にしながら、充実したQ&Aコンテンツを準備することができます。
生成AIを動画や音声コンテンツの補助として活用する
近年、採用広報では動画や音声による発信も増えています。訪問看護の現場風景を短い動画で伝えることは、求職者に強い印象を与える手段です。ただし、動画制作にはシナリオ作成やナレーション台本の準備といった工程が必要であり、ここでも時間的負担が課題となります。
生成AIは、動画や音声の台本作成を支援することができます。例えば「新人看護師が初めて利用者宅を訪問する流れを紹介する3分動画」と指示すれば、AIがナレーション文やシーン構成案を作成してくれます。これに基づいて撮影を行えば、従来よりも効率的にコンテンツを制作できます。
また、完成した動画に字幕を付ける際も、AIが自動的に音声を文字起こしして整えてくれるため、編集の手間が大幅に減ります。こうした支援によって、訪問看護の現場をリアルに伝える動画や音声コンテンツの制作が容易になり、採用広報の幅をさらに広げられるのです。
生成AIは、採用サイトの記事作成、SNS投稿、Q&Aコンテンツ、動画や音声の補助といった多様な場面で活用できます。これにより、訪問看護のリアルな魅力を効率的に発信できるようになり、求職者が安心して応募を検討できる環境を整えられます。
次の章では、こうした活用が進む中で浮かび上がる「生成AI利用の課題と注意点」について掘り下げます。
生成AI活用における課題と注意点
生成AIの情報の正確性と専門性を担保する必要性
生成AIの大きな強みは、文章を短時間で生み出せることです。しかし、その内容が常に正確とは限りません。AIは与えられた情報や学習データをもとに文章を作成するため、専門的な医療知識に関して誤解を招く表現をしてしまう場合があります。訪問看護における採用広報では、医療用語や制度、処置の説明が含まれることもあり、誤った情報が掲載されれば信頼性を損なうリスクが高まります。
たとえば「訪問看護でよく行う処置」というテーマでAIに文章を生成させると、実際には行わない医療行為を含めてしまうことがあります。こうした誤情報は求職者に誤ったイメージを与えるだけでなく、法的な観点からも問題になる可能性があります。そのため、AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、必ず専門知識を持つ人間が確認・修正することが必要です。
つまり、AIの出力はあくまで「素案」として扱い、最終的な文章の正確性と専門性を担保する役割は人間が担う。この前提を欠かさないことが、訪問看護におけるAI活用の第一の注意点といえるでしょう。
生成AI使用時の個人情報やプライバシーへの配慮
訪問看護の採用広報では、スタッフや利用者の実体験を紹介することがしばしばあります。生成AIにその内容を入力する際には、個人情報やプライバシーに十分配慮しなければなりません。氏名や住所はもちろん、病状や家族構成などの情報も、特定の個人が想起される形で入力してしまうとリスクが伴います。
AIは入力された情報をもとに文章を生成するため、意図せず個人を特定できる表現を残してしまう可能性があります。特に訪問看護は在宅でのケアが中心であり、生活の細部に関わるため、発信する情報には慎重さが求められます。この課題への対応策としては、
「匿名化した情報を入力する」
「具体的な個人を想起させる要素は削除する」
といった工夫が不可欠です。さらに、AIで生成した文章を公開する前に必ず確認し、プライバシー侵害の恐れがないかをチェックする体制を整える必要があります。採用広報が信頼を得るためには、情報の魅力性だけでなく、安全性の担保が欠かせません。
生成AI依存による表現の画一化
生成AIを活用すると、多様な文章を短時間で作成できますが、同じパターンの表現が繰り返されるという課題もあります。AIは確率的に「一般的に使われやすい言い回し」を選ぶ傾向が強いため、無難で整った文章になる反面、個性や現場ならではの温度感が失われやすいのです。
例えばスタッフの声をもとに記事を作成した場合、AIが要約しすぎて「どの事業所でも使えそうな一般的な文章」になってしまうことがあります。これでは採用広報に必要な「リアルさ」や「その職場らしさ」が伝わらず、かえって求職者の印象に残らない結果につながってしまいます。
この課題に対処するためには、AIの文章をそのまま使うのではなく、必ず人間が修正を加えることが重要です。具体的には、スタッフの口癖やエピソードの細部を残す、写真や動画と組み合わせて臨場感を補強する、といった工夫が有効です。AIはあくまで「土台づくりの役割」と捉え、最終的な「らしさ」を加えるのは人間の手で行うことが不可欠です。
生成AI導入コストと運用体制の課題
生成AIは無料でも使えるツールがある一方で、業務として本格的に活用するには有料サービスの導入やスタッフの研修が必要になる場合があります。例えば文章生成の上限やカスタマイズ機能を使うためには、一定の費用を支払わなければならないことがあります。小規模な訪問看護事業所では、このコストをどう捻出するかが課題となるでしょう。
さらに、AIを導入しても「誰が使いこなすのか」という運用体制を整えなければ効果は出ません。現場の看護師が日々の業務の合間にAIを使うのは現実的ではなく、採用広報の担当者や管理者が明確に役割を担う必要があります。また、生成AIで作成した文章の最終チェックを誰が行うのかも事前に決めておかなければ、誤情報や不適切な表現が公開されてしまうリスクがあります。
つまり、生成AIの活用には「導入コスト」と「運用体制」という二重のハードルがあるのです。これを乗り越えるためには、まず小規模な範囲で試験的に導入し、徐々に社内でノウハウを蓄積していくアプローチが現実的です。
生成AIは訪問看護の採用広報に大きな可能性をもたらす一方で、正確性・プライバシー・表現の画一化・導入コストといった課題があります。これらを軽視すれば、かえって採用広報の信頼性を損なう危険性があります。だからこそ、AIに全面的に依存するのではなく、人間との役割分担を前提とした「安全で持続可能な運用」が求められます。
次の章では、これらを踏まえて「訪問看護の採用広報における次の一歩」を具体的に考えていきます。
訪問看護の「採用広報×生成AI」における次の一歩

人間の声とAIコンテンツを組み合わせる
生成AIは文章や企画を効率的に生み出せる一方で、現場の温度感や人間らしさをそのまま伝えることは得意ではありません。そこで大切なのは「AIで基盤を作り、人間の声で仕上げる」という考え方です。
例えば、AIに「訪問看護師が感じるやりがい」というテーマで文章を生成させ、その文章にスタッフの実際のエピソードを差し込むと、読み手にとってリアルで共感しやすい内容になります。AIが文章の骨組みを整え、人間が血肉を与える。この協働の形を意識すれば、効率性と信頼性を両立した採用広報が可能になります。
また、現場スタッフのインタビューや日常の写真・動画をAI生成コンテンツと組み合わせることで、表現の幅を広げることができます。人間の声が持つ「唯一性」とAIの持つ「多様性」を掛け合わせることが、これからの訪問看護採用広報における重要な一歩です。
小さな実験から始める
生成AIの導入に抵抗を感じる事業所も少なくありません。新しいツールは慣れるまでに時間がかかり、最初から大規模に活用しようとすると挫折してしまうこともあります。そこで有効なのは、「小さな実験」から始めることです。
たとえば、まずはスタッフ紹介記事を生成AIに下書きさせてみる。あるいはSNS投稿のキャッチコピーだけをAIに生成させる。こうした限定的な活用を繰り返す中で、「どの程度AIを信頼できるのか」「どの部分に人間の修正が必要なのか」が見えてきます。
このような小さな試行を重ねることで、自然とAI活用のノウハウが蓄積され、やがて広報全体に活かせる段階に移行できます。いきなり完璧を目指すのではなく、スモールステップを意識することが、持続可能な運用につながります。
チームでの役割分担を明確にする
AI活用を成功させるには、運用体制の整備が不可欠です。具体的には「誰がAIを使って文章を生成するのか」「誰がその内容を確認し修正するのか」といった役割を明確にする必要があります。これを曖昧にしたまま進めると、誤情報がそのまま公開されたり、AI活用が属人的になってしまう恐れがあります。
訪問看護ステーションでは、経営者が広報を兼任しているケースが多いため、現場の声を拾う人、AIで文章を生成する人、最終的に公開を判断する人といった形で分担すると効率的です。特に最終確認の役割は、専門性を持つ別の看護師や管理者が担うと、正確性を担保しやすくなります。
このようにチームで役割分担を明確にし、AI活用を「個人の作業」ではなく「組織の取り組み」として位置付けることが、長期的な運用を可能にします。
明日から取り組めるNext Action
訪問看護の採用広報に生成AIを取り入れるために、すぐに実行できる具体的な行動を整理します。
- スタッフ紹介記事の下書きをAIに依頼する
インタビュー内容を入力して記事化させ、人間が仕上げる流れを体験する。 - SNS投稿のキャッチコピーをAIに生成させる
「訪問看護のやりがい」などのテーマで複数案を出してもらい、その中から選択して投稿。 - Q&AコンテンツをAIで整える
「未経験でも大丈夫ですか?」といった想定質問への回答をAIに作成させ、求職者向けに公開する。 - 役割分担を話し合う場を設ける
誰が生成するか、誰が確認するかをチームで決める。
これらは大きなコストをかけずに始められる行動であり、まずは一歩を踏み出すきっかけとなります。
訪問看護の採用広報は、仕事内容の特殊性や情報発信の難しさから、従来の方法だけでは魅力を十分に伝えられない側面があります。そこで生成AIの活用は、発信のスピードや多様性を高め、求職者目線のコンテンツを効率的に生み出す手段として有効です。ただし、正確性やプライバシー、表現の画一化など課題も多く、最終的には人間の確認と補完が欠かせません。AIと人の役割をうまく組み合わせ、小さな実験から取り入れていくことが、訪問看護における持続的で信頼性のある採用広報の実現につながります。