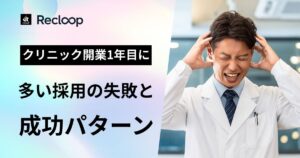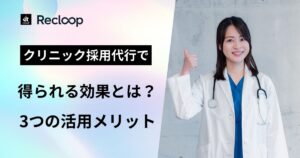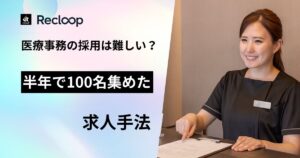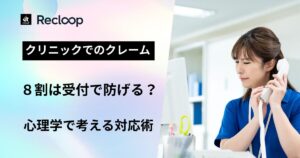多くのクリニックでは、慢性的な人材不足や採用活動の停滞に直面しています。求人を出しても応募が集まらない、面接に来ても辞退される、ようやく採用できてもすぐに退職してしまう。こうした状況は決して珍しくありません。さらに、診療や経営に日々追われる院長が、採用業務まで抱え込んでしまうことで、「患者に向き合う時間」や「経営判断」に割ける力を削られてしまうことも多いのです。
こうした課題を解消する方法として注目されているのが「採用支援の活用」です。求人原稿の作成、応募者対応、採用広報やSNS発信など、専門的なノウハウを持つ外部の支援者を活用することで、採用活動の効率化や成果の安定化を期待できます。ただし、単に任せれば良いというものではなく、自院が何を大切にしたいのか、どこまで支援を受けて、どこを院内で担うのかを明確にする必要があります。
本記事では、クリニックが採用支援を活用する際に押さえておきたい視点を取り上げます。現場でよくあるつまずきを起点に、「なぜ採用が進まないのか」「採用支援をどう使えば成果につながるのか」を具体的に解説していきます。次章ではまず、「なぜクリニックの採用が思うように進まないのか」という根本的な疑問から考えていきます。
なぜクリニックの採用はうまくいかないのか?

クリニックに応募が集まらない背景には何があるのか
クリニックの採用で最も多く聞かれる悩みは「そもそも応募が来ない」という問題です。医療系の有資格者を対象とした求人市場では、常に人材不足が続いており、特に小規模のクリニックでは大手病院や法人グループに比べて知名度や情報量で不利な立場に置かれやすいという現実があります。求職者が求人を探す際、まずは大きな病院や地域でよく知られた医療機関から目に入るため、小規模なクリニックの求人は埋もれてしまいがちです。
さらに、求人票に記載する内容が形式的で似たり寄ったりになっていることも一因です。「残業少なめ」「アットホームな雰囲気」などの表現は、どの医療機関でも見かける定型文になっており、求職者にとっては「どこも同じに見える」と感じやすくなります。その結果、応募につながりにくくなってしまいます。
また、情報発信の手段が限られている点も課題です。ハローワークや求人媒体への掲載だけでは、若い世代やSNSを日常的に活用している層に届きにくい状況があります。応募が集まらない背景には、このように「情報が届かない」「差別化が見えない」といった構造的な問題が潜んでいるのです。
クリニックスタッフが定着しないのはなぜか
仮に採用ができても「数か月で辞めてしまう」というケースも少なくありません。定着率の低さは、採用活動の非効率をさらに悪化させます。求職者は入職前に期待を抱いてクリニックを選びますが、入職後に「思っていた職場と違った」と感じた時点で離職のリスクが高まります。
たとえば「残業はほとんどない」と求人に書かれていても、実際には診療の遅れや事務作業で時間外勤務が発生していると、「話が違う」と不信感が募ります。職場の人間関係についても同様で、求人では「アットホーム」と表現されていても、現実には人間関係の軋轢や上下関係が強いと、早期退職の理由になります。
また、教育体制が十分でないことも定着率を下げる要因です。中途採用者であっても、新しい環境に適応するには一定のサポートが必要ですが、小規模クリニックでは「即戦力」を期待されやすく、研修やフォローの仕組みが整っていないケースがあります。結果として、採用に成功しても長く続かないという悪循環に陥るのです。
クリニック院長が抱え込んでしまう採用業務
クリニックの採用がうまく進まないもう一つの背景に、「採用業務を院長が抱え込みすぎている」という問題があります。日々の診療や経営判断に忙しい中で、求人票の作成、応募者対応、面接調整、内定フォローまでを院長や事務長が一手に担うケースは少なくありません。
採用業務には、求人原稿の見直し、応募者とのやり取り、面接での評価基準の設定など、多岐にわたる細かな作業が含まれます。これらを本業の合間に対応していると、どうしても後回しになりがちで、結果的に「対応が遅れる」「十分な準備ができない」という状態を招きます。応募者からすると、連絡が遅いだけでも「この職場は本気で採用していないのでは」と不安を抱きやすくなり、他のクリニックに流れてしまうこともあります。
さらに、採用基準や評価の視点が個人の感覚に偏ることもあります。面接において「フィーリングが合いそうだから」という理由だけで採用を決めてしまうと、実際に働き始めてから「スキルや適性が合わなかった」と気づくことになり、定着につながりにくくなります。採用を個人の勘頼みで進めることは、長期的な人材確保にとってリスクが大きいのです。
クリニック院長が時代の変化に追いつけていない
最後に見逃せないのは、求人市場や求職者の意識の変化にクリニック側が対応できていないという点です。かつては「給与条件」や「通勤距離」が主な判断基準でしたが、近年は「ワークライフバランス」や「職場の雰囲気」「成長の機会」など、より幅広い価値観が重視されるようになっています。
特に若い世代は、職場を選ぶ際にSNSや口コミサイトを参考にする傾向が強まっています。求人票だけでは伝えきれない日常の雰囲気や働き方が可視化されることで、応募行動に大きな影響を与えるのです。ところが、多くのクリニックでは依然として求人票中心の採用活動にとどまっており、情報発信の幅を広げられていません。
また、働き手のニーズとして「柔軟な働き方」が強く求められている点も重要です。子育てや介護との両立、副業との兼ね合いなど、多様なライフスタイルに合わせた働き方が選ばれやすくなっています。しかし、クリニック側がその変化に対応できていないと、応募を検討する段階で候補から外れてしまうのです。求人市場の変化を正しく理解し、それに合わせた採用活動を行うことが求められています。
クリニックが採用支援活用をどう考えるべきか?

採用支援を単なる「代行」と誤解していないか
「採用支援」と聞くと、「求人作成や応募者対応を丸ごと代わりにやってくれるサービス」と捉える方も少なくありません。しかし、実際にはそれ以上の役割を持っています。採用支援は単に業務を肩代わりするものではなく、クリニックの採用活動を効率化し、成果につなげるための伴走型サポートです。
たとえば求人票を作成する際でも、支援者は「求職者にどう見えるか」「他のクリニックと何が違うのか」という視点で内容を整理してくれます。表面的に「残業少なめ」「駅近」などを並べるのではなく、院内の雰囲気や働き方を伝える工夫を盛り込むことで、応募につながる求人票に変わります。ここには専門的な視点や経験が活かされており、単なる代行では到達できない効果を生み出します。
また、支援は「答えを与えること」ではなく「問いを返すこと」にも重きを置いています。院長自身が、
「どんな人を採用したいのか」
「何を大切にする職場にしたいのか」
を明確にできるように促し、その答えを求人や面接の場に反映させていきます。このプロセスを経ることで、支援を受けた側も採用に対する考え方を深めることができ、結果的に組織全体の採用力を高めることにつながります。
クリニックが抱える課題と採用支援の相性
クリニックの採用課題は、多くの場合「時間不足」「ノウハウ不足」「発信力不足」の3つに集約されます。診療や経営で手一杯の中では、応募者対応や広報活動に十分な時間を割けず、どうしても後手に回ってしまいます。採用に関する知識や経験が限られていると、求人票の内容もありきたりになり、結果として応募が集まりにくくなります。さらに、SNSや採用サイトを通じて求職者に効果的に情報を届けるノウハウが不足していることで、存在を認知してもらえないという問題も起きています。
ここで採用支援の強みが発揮されます。支援者は、求人市場の動向や他の医療機関の取り組みを把握しており、自院に不足している部分を補うことができます。例えば「応募が集まらない」という課題に対しては、求人票の改善に加えて、SNSでの情報発信や職員の声を活用した広報を提案してくれます。「定着しない」という課題に対しては、採用段階でのミスマッチを防ぐ質問例や面接手法をアドバイスしてくれます。
このように、クリニックが抱える課題と採用支援の提供内容は相性が良く、内部だけでは解決しきれない問題を補完してくれる存在といえます。
クリニックが採用支援を受ける際に必要なこと
採用支援を効果的に活用するためには、受ける側の準備も欠かせません。任せきりにするのではなく、支援を受ける前に「自院がどんな人を採用したいのか」「どんな職場でありたいのか」を整理しておく必要があります。
たとえば「即戦力が欲しいのか」「新人を育成して長く勤めてもらいたいのか」という方向性だけでも明確にしておくと、支援者もそれに基づいて求人票や面接の工夫を考えられます。また、
「これまでにどんな人材が定着したのか」
「逆にすぐに辞めてしまった人の特徴は何か」
といった過去の採用の振り返りも重要です。
さらに、院内で協力体制を整えることも準備の一環です。支援を受けて採用活動を進める中で、応募者との面接や見学対応はどうしても現場スタッフの協力が必要になります。支援者がどれだけ工夫しても、最終的に現場が受け入れる体制を持っていなければ、採用活動は実を結びません。採用支援を「外から与えられるもの」ではなく「一緒に取り組むもの」として捉える視点が欠かせないのです。
クリニックが採用支援を活用することで得られる変化
採用支援を取り入れることで、クリニックにはどのような変化が期待できるのでしょうか。
第一に、採用活動の「スピード」が向上します。応募者への対応が迅速になり、面接日程の調整や内定連絡も滞りなく進められるため、求職者の不安を減らすことができます。これは、他の医療機関との競争に勝つ上で大きなポイントです。
第二に、採用活動の「質」が高まります。支援者の視点で求人票や広報がブラッシュアップされることで、応募してくる人材の層が変わり、ミスマッチが減少します。また、面接での質問や評価基準の改善を通じて、入職後に活躍できる人材を見極めやすくなります。
第三に、採用活動の「持続性」が確保されます。支援を受けながら採用の流れを学ぶことで、院内スタッフも採用の進め方に慣れ、次の採用活動に生かせるようになります。「採用のノウハウが院内に残る」という効果は、長期的な視点で非常に価値があります。
結果として、採用支援を活用することは、単に人を集めるための一時的な手段ではなく、クリニック全体の採用力を底上げする取り組みへとつながっていくのです。
採用支援をどう活用すれば効果が出やすいのか?
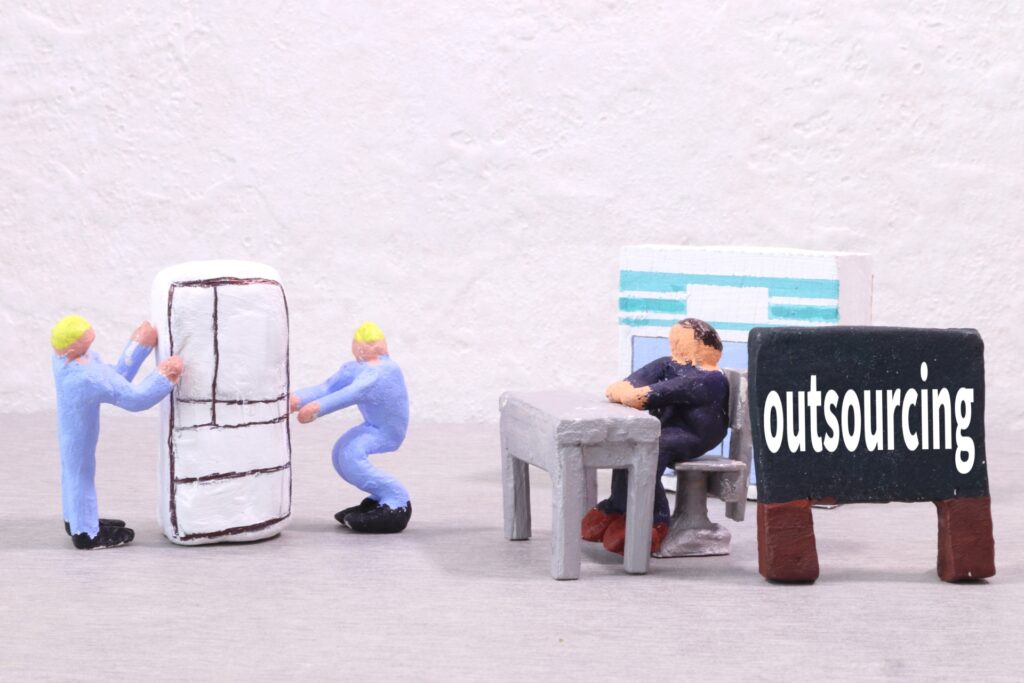
クリニックの採用課題を具体的に言語化する
採用支援を導入する際に最も重要なのは、自院の課題をできる限り具体的に言語化することです。漠然と「人が集まらない」「すぐ辞めてしまう」という状態のまま支援を依頼すると、表面的な改善で終わってしまう可能性があります。支援者は専門的な知識や経験を持っていますが、その力を最大限に発揮するには、依頼側が「今どこでつまずいているのか」を明確に伝える必要があるのです。
例えば「応募が集まらない」という悩みでも、原因は複数考えられます。求人票が魅力的に見えていないのか、発信媒体が偏っているのか、あるいは院内の雰囲気が外部に伝わっていないのか。課題を分解して提示することで、支援者はより的確な提案を行えます。また、定着率に課題がある場合には「入職後のフォローが不足しているのか」「面接時にミスマッチを見抜けていないのか」といった視点で振り返ることが有効です。
この「言語化のプロセス」自体が、院内の採用意識を高めるきっかけにもなります。課題を明確にする段階で、スタッフ間で意見を出し合い、採用に対する共通認識を持てるようになるからです。結果的に、支援を受ける前の段階で組織が一歩進化することになります。
採用支援担当者との情報共有を密に行う
採用支援を効果的に活用するためには、支援者との情報共有が欠かせません。求人票を作成する際に、クリニックの理念や雰囲気、日常の出来事を共有していなければ、一般的な表現にとどまってしまいます。求職者に響く求人を作るには「ここで働くとどんな日常があるのか」「どんなスタッフが活躍しているのか」といったリアルな情報が必要です。
たとえば、「子育て中のスタッフが多く、急な休みにも理解がある」というエピソードや、「院長が週に一度スタッフとランチミーティングをしている」といった日常の取り組みは、求人票やSNS発信で大きな強みになります。こうした情報は外部の支援者からは見えないため、院内から積極的に共有することが求められます。
さらに、採用活動の進捗や応募者からの反応を逐次フィードバックすることも重要です。
「この表現に反応が良かった」
「面接に来た人がホームページを見て印象が良かったと言っていた」
といった声を支援者に伝えることで、次の改善につなげられます。支援者を「外部の人」ではなく「採用チームの一員」として巻き込み、情報を双方向でやり取りすることが効果を最大化するポイントです。
採用支援を受けながら院内にノウハウを蓄積する
採用支援を受ける大きなメリットの一つは、採用ノウハウを院内に残せることです。求人票の作成方法や応募者対応の進め方、SNS発信の工夫など、支援者が行っているプロセスを観察し、学ぶ姿勢を持つことで、次回以降の採用活動に活かせる知識が増えていきます。
例えば、支援者が作成した求人票をただ利用するのではなく、
「なぜこの表現が効果的なのか」
「どんな意図でこのエピソードを入れたのか」
を質問しながら理解することで、自院でも同じように工夫できるようになります。また、面接の場に支援者が同席する場合には、評価の視点や質問の仕方を学び、自院の基準として取り入れることが可能です。
このように、支援を「一時的な解決策」として消費するのではなく、「院内の採用力を高める学びの場」として活用することで、長期的な効果を得られます。採用支援は外部に頼るだけでなく、院内の成長を促す機会でもあると捉えることが大切です。
採用支援活用の成果を測定し改善につなげる
採用支援を導入した後は、その成果をきちんと測定することが欠かせません。単に「人が採用できたかどうか」だけで判断してしまうと、本質的な改善につながらないからです。たとえば、応募数が増えたとしても、入職後すぐに辞めてしまう人が多ければ、採用活動としては不十分といえます。
成果を測定する際には、「応募数」「面接実施率」「内定承諾率」「定着率」といった複数の指標を組み合わせて確認することが重要です。また、採用にかかった期間やコストを振り返ることで、効率性の改善にもつなげられます。支援者と一緒に数値を確認し、
「どの部分は改善できたのか」
「次に取り組むべき課題は何か」
を明確にすることが、支援活用の効果を最大化するプロセスです。
さらに、成果の測定はスタッフの声を取り入れる機会にもなります。「新しく入ってきた人がすぐに馴染めた」「教育の仕組みが以前よりスムーズになった」といった現場の実感は、数値以上に重要な指標です。こうした定性的なフィードバックを支援者と共有し、改善サイクルを回していくことで、採用活動はより持続的なものへと進化していきます。
採用支援会社を活用するメリットとは?

採用支援会社をうまく活用することで、多くの法人が採用課題を解決する突破口を見出しています。以下は、その主なメリットです。
1. 採用ノウハウの外部化による効率化
2.求人の訴求力が飛躍的に向上する
3.採用戦略を客観的に見直せる
4.必要な時だけ利用でき経営リスクが少ない
1. 採用ノウハウの外部化による効率化
医療や歯科の現場では、日常業務そのものが非常に多忙です。経営者もスタッフも採用活動にかけられる時間はごくわずかであり、求人原稿の作成や媒体選定、応募者対応までを社内で完結するのは現実的に困難です。
採用支援会社を活用することで、そうした採用実務を専門家に委ねることができ、限られた人員でも効率的な採用活動を展開できます。また、支援会社は過去の成功パターンや業界特有の傾向を把握しており、スピーディかつ的確な対応が可能です。結果として、採用にかかる時間と労力を大幅に削減し、現場は本来注力すべきケア業務や組織マネジメントに集中することができるようになります。
2. 求人の訴求力が飛躍的に向上する
求人情報は単なる条件提示の場ではなく、「職場の魅力をどう伝えるか」が問われるマーケティング施策の一つです。採用支援会社は、求職者の関心を引き、行動に移させる表現技術に長けています。たとえば、求人原稿では給与・勤務時間だけでなく、職場の雰囲気、スタッフ同士の関係性、日々のやりがいといった“感情に訴える”情報も盛り込むことで、応募率が大きく変わってきます。
また、ビジュアル設計や構成にも一貫した戦略性を持たせることにより、読みやすく印象に残る求人を作成することが可能です。結果として、より自社にマッチした人材からの応募が集まりやすくなり、採用の質も自然と向上していきます。
専門家の手によって設計された求人情報は、単に「条件を伝える」だけでなく、「その職場で働く魅力」や「働く人のリアルな声」を効果的に伝える力を持ちます。文章表現、ビジュアル、ストーリー構成においても一貫したコンセプト設計が可能となり、結果として応募者の質と量を高めることができます。
3. 採用戦略を客観的に見直せる
日々の訪問や診療に追われるなかで、自社の採用活動を客観的に振り返る機会は少ないのが実情です。採用支援会社を活用することで、第三者の視点から自社の採用活動を診断してもらうことができます。
たとえば、「なぜ応募が来ないのか」「なぜ定着しないのか」といった根本課題を言語化し、具体的な改善策を提案してくれるのは外部ならではの価値です。加えて、競合他社の動向や市場の変化も加味したうえで、トレンドを押さえた採用戦略の立案が可能になります。結果として、単なる小手先の改善にとどまらず、中長期的に効果を発揮する“戦略的な採用活動”へと進化させることができます。
採用支援会社は外部の視点を持っているため、これまで気づかなかった採用上のボトルネックや改善ポイントを明確にすることが可能です。「なぜ応募が来ないのか」「辞退が多い理由は何か」などを分析し、改善策を提案してくれる存在としても非常に価値があります。
4. 必要なときに利用でき、経営リスクが少ない
採用支援会社の活用は、常に長期契約を結ぶ必要はありません。採用ニーズが一時的に高まる時期、たとえば新規出店や分院の立ち上げでの人員補充が急務のタイミングなど、スポット的に活用できるのも大きな利点です。
これにより、自社内に採用担当者を増やすなどの固定費を抱えることなく、必要なときに必要な分だけ外部リソースを投入することが可能になります。さらに、採用活動に関するPDCAサイクルを回す際も、支援会社がそのプロセスに加わってくれることで、効果測定や改善提案がスムーズに進みます。結果として、経営資源を効率よく活用しながら、無駄なコストや人的負担を最小限に抑えることができるのです。
優れた採用支援会社は、人材業界の知識に加えてマーケティング領域の視点を持ち合わせています。求職者の行動心理を理解したうえで、検索されやすいキーワードの選定、競合との差別化、SNS運用による接点づくりなど、応募につながる動線設計を行うことが可能です。こうした施策により、自社だけでは到達できなかった求職者層にアプローチできる点は大きなメリットです。
明日から始められる具体的なアクション

採用課題を振り返るためのミニワークを行う
採用改善の第一歩は、自院の課題を把握することです。明日からできる実践的な方法として、院内で「採用課題の振り返りワーク」を行うことをおすすめします。方法はシンプルで、ホワイトボードや紙に「応募が集まらない理由」「定着しない理由」をスタッフと一緒に書き出していきます。
ここで大切なのは、院長だけで考えず、現場スタッフにも意見を出してもらうことです。実際に求職者と接するスタッフや、日々の業務を担っているスタッフだからこそ気づくことが多くあります。たとえば「面接で話していたことと実際の働き方に差がある」「新しく入ってきた人が孤立しやすい」といった指摘は、院長が見落としがちな重要な視点です。
この作業を通じて、課題が「曖昧な不満」から「改善できる具体的なテーマ」に変わります。30分程度の短時間でも構いません。まずは課題を可視化し、院内で共有することが、採用改善に向けた第一歩となります。
求人票を一つ見直してみる
次に取り組みやすいのは、既存の求人票を一つ見直すことです。求人票は求職者にとって最初に接する情報であり、応募の可否を大きく左右します。そこで、まずは「誰に向けたメッセージになっているか」「自院の魅力が伝わっているか」を確認することが大切です。
具体的には、次のような視点でチェックしてみましょう。
・「どこにでもある表現」ばかりになっていないか(例:アットホーム、残業少なめ)
・実際に働いているスタッフの声やエピソードが含まれているか
・勤務条件だけでなく、日常の雰囲気ややりがいが伝わるか
もし改善点が見つかれば、すぐに修正して公開することをおすすめします。求人票は一度出したら終わりではなく、定期的にブラッシュアップすることで効果を高めることができます。明日からできる小さな改善ですが、応募者の反応は確実に変わってきます。
応募者対応のスピードを意識する
応募があった際の対応スピードは、採用成果を大きく左右します。求職者は複数の医療機関に同時に応募していることが多く、返信が遅れると他に決まってしまうリスクが高まります。そこで「応募から24時間以内に返信する」というルールを院内で設定してみることをおすすめします。
もし院長が多忙で即時対応が難しい場合は、一次対応をスタッフに任せる仕組みを作ることも有効です。「応募を受け付けました。近日中に面接日程をご案内します」といった簡単なメッセージを自動で送るだけでも、求職者の安心感は大きく変わります。
さらに、面接日程の調整も迅速に行うことで、応募者のモチベーションを保ちやすくなります。採用支援を利用している場合は、この対応部分を支援者に任せ、院内では面接準備に集中するという分担も効果的です。スピード感のある対応は、それだけで「この職場はきちんとしている」という好印象につながります。
小さな発信から始めてみる
最後に、情報発信を明日から実行に移すアクションとしておすすめなのは、「小さな発信」を一つ始めることです。大掛かりな採用サイトやSNS運用を準備するのは時間がかかりますが、まずは日常の一場面を切り取った発信からでも効果はあります。
例えば、院内での勉強会の様子、スタッフ同士のちょっとしたやりとり、患者さんに喜ばれた出来事(個人情報に配慮した範囲で)などを写真と短いコメントで共有するだけでも、求職者にとっては「ここで働くイメージ」が湧きやすくなります。
また、求人票に載せる「スタッフの声」を1つ追加するだけでも発信効果があります。「子育てと両立しやすい職場です」「スタッフ同士が助け合う雰囲気があります」といった一言が加わるだけで、応募者に安心感を与えられます。大切なのは「完璧な発信を目指さないこと」。まずは小さく始め、少しずつ積み重ねることで、情報発信の習慣が院内に根づいていきます。
クリニックにおける採用は、人材不足が続く医療業界の中でも特に難しさが際立つ領域です。しかし、課題を正しく捉え、採用支援をうまく活用することで、その壁を乗り越えることは可能です。重要なのは「任せきり」ではなく、院内が主体性を持って取り組み、支援を通じてノウハウを蓄積していくことです。求人票の改善や応募者対応の迅速化、日常の小さな発信など、明日からできる工夫を積み重ねることで、応募から定着へとつながる流れが少しずつ整っていきます。採用は一度きりの取り組みではなく、組織を強くする継続的な営みです。本記事を参考に、自院に合った採用の進め方を改めて見直す機会にしていただければ幸いです。
HOAPの採用支援について
Recloop Mediaを運営する株式会社HOAPでは訪問看護や訪問診療、訪問歯科といった在宅医療分野を中心に採用支援を行っております。業界に合わせてサービスを別けることで、各分野の専門性を活かし運営を行っております。業界に合わせてご覧ください。
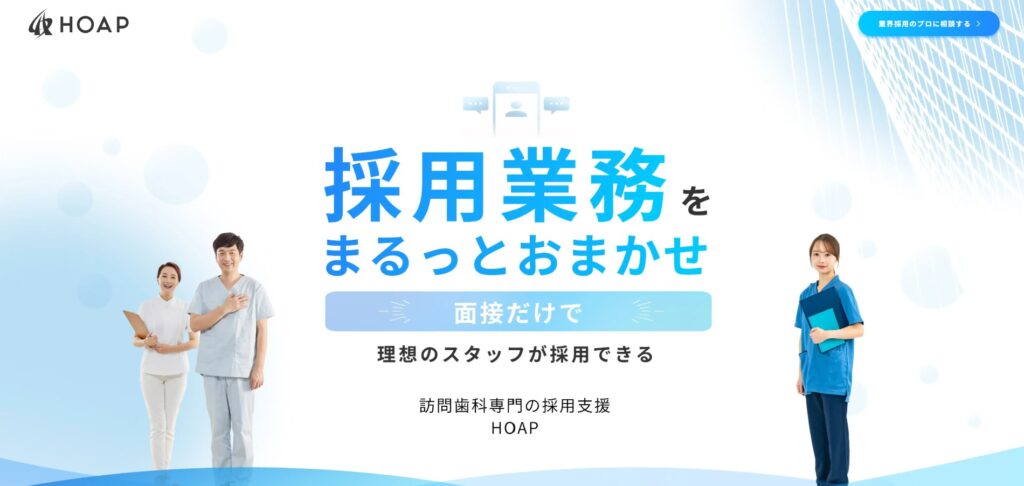
歯科医師や歯科衛生士・歯科助手などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。

看護師やリハビリ職・ケアマネなどの採用にお困りの経営者様はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。
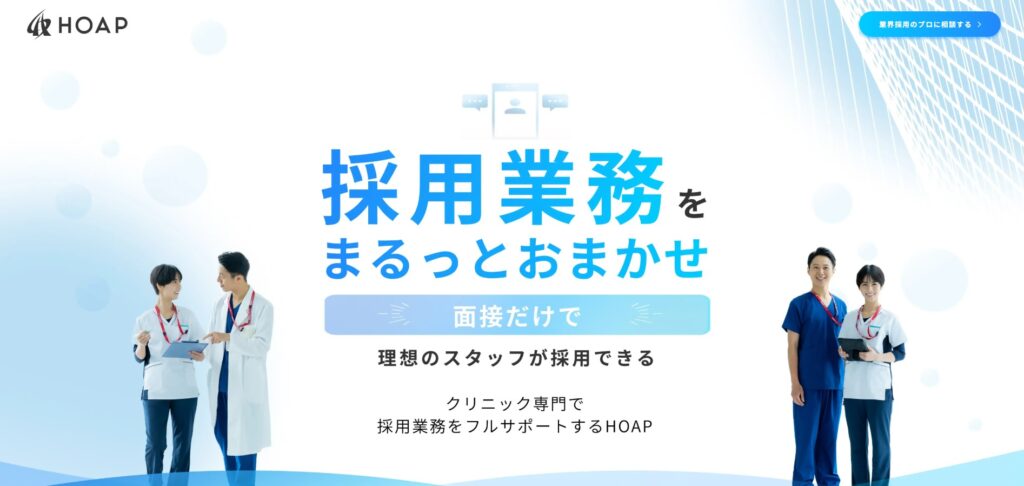
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。