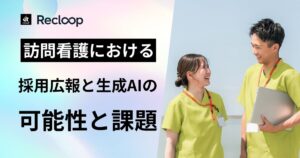「どう評価したらいいのか、正解がわからない」 「スタッフに納得してもらえる評価ができていない気がする」 ──これは、訪問看護ステーションの管理者や主任クラスからよく聞かれる悩みです。評価制度は一応あるものの、現場では忙しさに流されて形だけの運用になってしまったり、スタッフとの面談がただの業務報告で終わってしまったり。こうした状況が続くと、「この評価に意味はあるのか?」と、管理者側もスタッフ側も疑問を抱き始めます。
こうした行き詰まりの原因のひとつは、評価者自身が自分の役割を「点をつける人」「上から判断する人」として受け取ってしまっていることにあります。しかし、本来の評価の意味とは、「スタッフがどう働いていたかを見守り、言葉にして返すこと」ではないでしょうか。つまり、評価者とは「評価を与える人」ではなく、「日々の働きを一緒に見てきた人」として関わる存在であるべきです。
訪問看護ステーションのように、業務が個別性の高い現場では、画一的な評価基準だけではスタッフの頑張りを十分に汲み取ることはできません。また、スタッフが評価に納得しなければ、モチベーションの低下や離職のリスクにもつながります。だからこそ、管理者やリーダーは評価すること以上に、「どう関わるか」「どう伝えるか」に重きを置く必要があります。
本記事では、訪問看護ステーションにおける「評価者の役割」をあらためて見つめ直し、納得感のある評価につながる関わり方を具体的に紹介します。点数では伝わらない価値をどう拾い上げるか。そのヒントを、順を追って考えていきます。
なぜ訪問看護ステーションでは「評価者の役割」がぼやけやすいのか

訪問業務に追われ、評価に意識を向ける余裕がない
訪問看護ステーションでは、管理者やリーダーといった評価者も現場に出ながら業務をこなしていることが多く、いわゆるプレイングマネージャーの形が一般的です。そのため、スタッフの評価にかける時間や気持ちの余白が持てず、結果として「とりあえず期限に間に合わせる」「前回と変わらない内容になってしまう」といった評価制度の運用に陥りがちです。
本来であれば、評価とはスタッフの日々の働きぶりを丁寧に振り返り、その背景や成長のプロセスまで言葉にするべきものです。しかし、目の前の業務を優先せざるを得ない環境では、そこまで丁寧に関わる時間が確保されず、「評価者」という立場が実質的に機能しにくくなっています。
数値では表せない働きにどう向き合うかが難しい
訪問看護という仕事は、病院のように患者数や業務量を指標化しやすい業種と異なり、「どれだけ丁寧に関われたか」「信頼関係を築けたか」といった定性的な要素が大きく影響します。訪問件数や報告書の正確さなど、形式的に評価できるポイントはありますが、それだけではスタッフの頑張りの全体像を把握するのは困難です。
たとえば、「認知症の利用者さんとの関わり方がとても丁寧だった」「家族への説明の仕方が非常にわかりやすかった」など、こうした細やかな配慮や実践は、数字には現れにくいにもかかわらず、チームにとっては極めて重要な価値を持ちます。
このような「見えにくい頑張り」をどう受け止め、評価に反映させるか。その感覚を持てないまま評価を続けると、スタッフの納得も得られず、評価制度そのものへの不信感を招いてしまいます。
「評価は苦手」と感じる管理者の心理的なハードル
さらに、評価に苦手意識を持っている管理者も少なくありません。「何を根拠に評価すればいいのか」「スタッフの反応が気になってうまく伝えられない」といった不安から、評価を避ける傾向が見られることもあります。
とくに、普段からフラットな関係性を意識している管理者にとっては、「評価する立場」として何かを伝えること自体に違和感や戸惑いを覚えることが多いようです。その結果、
「点数をつけるけど理由は曖昧」「言いにくいことはあえて触れない」など、評価がかえって関係性の距離を生む事態にもなりかねません。
評価者の「役割」を言語化できていないことが根本の問題
訪問看護ステーションで評価者の役割が曖昧になっている背景には、「何をもって評価者なのか」という基準や意識の共有がされていないことがあります。「上の立場だから評価をする」「経験が長いから評価を任された」このような受け身の任命では、評価が義務にすり替わってしまい、自分ごととしての意味を持てません。
評価者として大切なのは、「どのようにスタッフを見ていたか」「どんな場面に価値を感じたか」を言葉にして伝えることです。
そのためには、そもそも評価者が自分の役割を明確に持ち、日々の業務の中で「見る視点」を意識していく必要があります。
「評価」を「関わり方のひとつ」と捉え直す

点数をつけることに意識が向きすぎていないか
訪問看護ステーションにおいて評価を行う場面では、「どの項目を何点にするか」といった数値づけに気を取られてしまい、肝心の中身である「その人がどう働いていたか、何を考えて行動していたか」に目が向いていないケースが少なくありません。
評価とは本来、勤務態度や成果を点数で判断する作業ではなく、「この1年間、あなたのこういう行動を見ていた」「この時の判断に、こういう意図があったのではないか」といったスタッフとの向き合いの中から見えてきた「気づき」を、言葉にして返す機会であるべきです。
しかし、点数を基準にして評価結果を出すだけの形になってしまうと、評価そのものがスタッフとの間に距離をつくり、評価面談が“査定の時間”としてだけ受け止められるようになってしまいます。
「どう動いたか」だけでなく「なぜそうしたか」に目を向ける
点数の裏にある背景を拾わなければ、評価者としての役割は果たせません。たとえば、
だけでなく、
といった部分に目を向けることで、スタッフの意識や成長のプロセスが浮かび上がります。
たとえ成果が出ていない場面であっても、「どうしようと悩んでいたのか」「そのときどんな工夫をしていたか」といった視点があれば、評価者としてそのスタッフの“取り組み”を認めることができます。
評価は「うまくできたかどうか」ではなく、「どう考えて取り組んでいたか」にこそ意味があります。
評価とは「何ができて、何ができていなかったかを一緒に確認すること」である
評価を行う側として、ただ記録を読み込んだり、出来事を思い出したりするだけでは片手落ちです。スタッフの行動を見て、受け止めて、それを「何ができて、何ができていなかったかを一緒に確認すること」。特に、具体的なエピソードを持って確認し合うことが重要です。
このやりとりがあることで、スタッフは「見てもらえていた」と感じ、自分の働き方を肯定的に捉えることができるようになります。
「ちゃんと見てくれていた」「覚えていてくれた」という感覚は、数値評価や評価制度の完成度以上に、スタッフの納得や安心感につながります。特別な言葉を使わなくても、「あの時の対応、とても良かったと思ってるよ」とひと言添えるだけで、その評価は意味のあるものに変わります。
評価を通じて「今後どうしていきたいか」を考える場にする
また、評価の場は過去を振り返るだけでなく、これからの働き方や目標について考える機会にもなります。「どんなふうに働いていきたいか」「いま困っていることは何か」といったやりとりを通じて、スタッフ自身が自分の方向性を見直す時間になります。
このようなやりとりは、管理者にとっても、チームとして何を強みにしていきたいかを考えるきっかけになります。評価は管理業務の一部ではありますが、それ以上に“お互いの考えをすり合わせていく時間”として活用していくことが求められます。
評価者に求められているのは「質問力」

一方通行の面談では、スタッフの本音は引き出せない
訪問看護ステーションの評価面談が、管理者からの伝達だけで終わってしまうケースは少なくありません。評価シートに沿って項目を読み上げ、点数とコメントを伝えるだけの時間になってしまえば、スタッフは受け身のまま何も返せず、「結局どう思われているのかわからなかった」と感じることもあります。
スタッフ自身が自分の成長や課題を振り返るきっかけをつかめないまま評価面談が終わると、「納得できないけど、言っても仕方ない」と思わせてしまい、次回の評価や働き方へのモチベーションにも影響が出てきます。
評価面談は、感じていることを引き出す時間に変える
こうした事態を防ぐためには、評価者が「話しかける」だけでなく、「問いかける」姿勢を持つことが重要です。たとえば、
・「この1年で印象に残っている出来事は?」
・「やりがいを感じた場面はどこだった?」
・「振り返ってみて、自分の変化を感じることはある?」
といった質問を投げかけることで、スタッフ自身が言葉にする時間を持てます。
自分の体験をことばにするプロセスは、スタッフにとって内面の気づきを得る機会になります。評価者が一方的に言うのではなく、まずはスタッフが自分で話す。それを受け止めたうえでフィードバックを返す。この順番があることで、評価は一段と意味のある時間になります。
良い質問は、信頼の入り口になる
特別なスキルがなくても、効果的な質問は可能です。重要なのは、正解を引き出そうとするのではなく、「その人自身の言葉」を促すような聞き方を意識することです。
・「あのとき、どう感じてた?」
・「自分ではどう思ってる?」
・「どんなところに難しさを感じた?」
・「もっと教えて!」
このような質問を重ねると、スタッフは「ちゃんと自分のことを見ようとしてくれている」と感じるようになります。評価の場が緊張感だけに支配されるのではなく、働いてきたことを「振り返る場」として信頼が育っていくのです。
評価は「伝える場」ではなく「感じ取る場」にする
評価というと、つい「伝える」「教える」という発想になりがちですが、評価者としてまず大切なのは“感じ取る”ことです。スタッフの話を途中で遮らず、意図をくみ取り、どのようにその行動に至ったのかを丁寧に聞く。これによって、表面的には見えなかった背景や努力が浮かび上がってきます。
たとえば、「報告が遅れてしまった」という出来事があったとしても、その裏に「何度もご家族と連絡をとって状況を把握しようとしていた」という丁寧な対応が隠れていることもあります。数値や事実だけでは見えない部分を、質問を通じて知っていく。それが、評価者に求められる姿勢です。
評価者とは、点数を下す人ではありません。スタッフの経験に関心を持ち、それを言葉にしていくための関わりをする人です。
質問を重ねることは、評価の場を「働きぶりをすくい上げる時間」に変える力を持っています。
信頼される評価者になるために必要な行動とは

「ちゃんと見てくれている」と思われる関わりがあるか
訪問看護ステーションにおいて、評価への納得感を左右するのは、評価基準の内容よりも「ふだんからどれだけ見てもらえていると感じていたか」です。スタッフは、点数よりもその背景にある関心や理解の深さを敏感に感じ取ります。
「何を見られていたかがわからない」「突然の面談で話がかみ合わなかった」といった印象を持たれてしまえば、どんなに精緻な評価項目があっても信頼は築けません。大切なのは、日常的な場面で「見ていたよ」「あなたの頑張りに気づいているよ」というメッセージをどれだけ積み重ねられているかです。
評価面談の場より、日常のひとことが信頼をつくる
評価面談は年1〜2回の限られた機会でしかありません。むしろ、スタッフが信頼を感じるのは、日常のささいな場面での声かけです。
たとえば、
・利用者対応から戻ったスタッフに「今日は大変だったね」と声をかける
・書類の仕上がりを見て「細かく書けていて助かったよ」と伝える
・他スタッフとの連携について「最近、相談の仕方が変わったね」と気づきを共有する
こうした行動は、評価制度とは直接関係ないように見えて、実は「見ている人がいる」という安心感を与える基盤になります。
評価者が意識すべきは「できた/できなかった」より「どう考えて動いたか」
信頼される評価者は、スタッフの表面的な行動だけで判断するのではなく、その背景にある意図や思考にも目を向けています。「その選択をした理由は?」「どんな思いでその行動に至ったのか?」といった観点で働きを受け止めることが、スタッフの自己理解や成長にもつながります。
これは、すべての場面で詳細に見ておくべきという意味ではありません。限られた接点のなかでも、特定の場面にきちんと関心を持ち、「あの時、こう感じて動いていたんじゃないかな?」という想像とことばを添えるだけで、スタッフとの関係性は深まります。
評価コメントには「理由」を添える
スタッフが「自分はちゃんと見られていた」と実感できるのは、コメントの表現にも左右されます。たとえば、「信頼できるスタッフです」という一文だけでは抽象的すぎて、自分のどの働きがそう思われたのかがわかりません。
一方で、
といった具体的なコメントが添えられていれば、自分の働きがどのように見られていたのかが明確になります。これはスタッフにとって、大きな安心と次の行動への手応えになります。
「信頼される評価者」に必要なのは、完璧な判断力ではない
評価する側に立つと、「正しく判断しなければ」「公平に点をつけなければ」と気負ってしまうものです。しかし、
信頼される評価者に必要なのは、完璧な答えを持つことではなく、「ちゃんと関心を持ち続けているか」「どう見てきたかを誠実に伝えようとしているか」
です。
スタッフは、その姿勢を見ています。そして、その姿勢が伝わったときにこそ、「この人の言葉なら受け止められる」「次もがんばろう」という気持ちが生まれます。信頼は制度で作るものではなく、日々の行動で少しずつ築かれていくものなのです。
訪問看護ステーションで実践できる評価者の関わり方5選

評価制度の整備や面談マニュアルの改善ももちろん大切ですが、評価者としての信頼を築くためには、日々の小さな行動の積み重ねが欠かせません。「評価をする」のではなく、「スタッフの働きを受け止めて伝える」ことを意識した関わりを、実際の場面でどのように体現できるか──ここでは、明日からすぐに実行可能な関わり方を5つ紹介します。
1.面談前に必ず「話す時間」を確保する
評価面談の前に、形式的な準備だけでなく、「最近の様子はどうか」「印象に残っている出来事はあるか」など、スタッフの言葉を直接聞く時間を意図的に持ちましょう。
面談当日にいきなり本題に入るのではなく、事前に一度スタッフの声に耳を傾けておくことで、評価者の見え方にも深みが出ます。また、スタッフ側も自分の働きぶりを整理するきっかけになります。
2.評価コメントには「なぜそう思ったか」を添える
コメントを記入する際には、「頑張っている」「信頼できる」といった抽象的な表現で終わらせず、「なぜそう感じたのか」「どの行動にそう思ったか」をできるだけ具体的に書くようにしましょう。
たとえば、
・「訪問中の利用者対応で、本人のペースに合わせた話し方をしていた」
・「家族への報告内容が丁寧で、不安をやわらげていた」
といった描写があれば、スタッフも「自分のやったことがちゃんと伝わっていた」と感じることができます。
3.評価面談後、1ヶ月以内に1on1の場をつくる
評価面談が一度きりの「行事」になってしまわないよう、1ヶ月以内に1on1の時間を設けましょう。「あの評価のあと、何か思ったことあった?」「今、どんなことに力を入れてる?」といったやりとりを行うことで、評価が単発で終わらず、次の行動や成長へとつながります。
このような継続的な接点が、評価制度への信頼性を高めることにも直結します。
4.面談中は目を見て話す時間を意識する
面談中はつい評価シートや画面の確認に意識が向いてしまいがちですが、それだけではスタッフの表情や反応を見逃してしまいます。
大切なのは、一定の時間は手元から目を離し、しっかりスタッフの目を見て話すこと。そうすることで、「ちゃんと向き合ってくれている」「話を受け止めてもらえている」という印象を与えることができます。
5.評価を「上からの判断」ではなく「共に見ていたことの振り返り」として伝える
「この1年を一緒に見てきた立場として伝えたいことがある」といった語りかけを意識することで、評価が命令や指摘ではなく、働きを受け止めた言葉として伝わります。
たとえば、
・「あの対応、よく覚えてる。あの時の動きは印象的だった」
・「自分だったらあんなふうにはできないと思った」
といった個人的な感想を交えることで、評価が機械的なものではなく、関係性の中から生まれたフィードバックになります。
訪問看護ステーションという多忙な現場では、評価が後回しにされがちですが、こうした“小さな関わり方”の積み重ねが、スタッフの安心や信頼、そして定着にもつながります。評価制度をより意味のあるものに変えていくために、まずは一つでも明日から試してみてください。

監修者:牟田 健登(Kento Muta)
株式会社クルージズ・テクノロジーズ代表取締役。2021年に創業し、在宅医療・介護業界に特化した人事コンサルティング・人事評価SaaSを展開。訪問看護ステーションや訪問介護ステーションを中心にサービスを展開中。