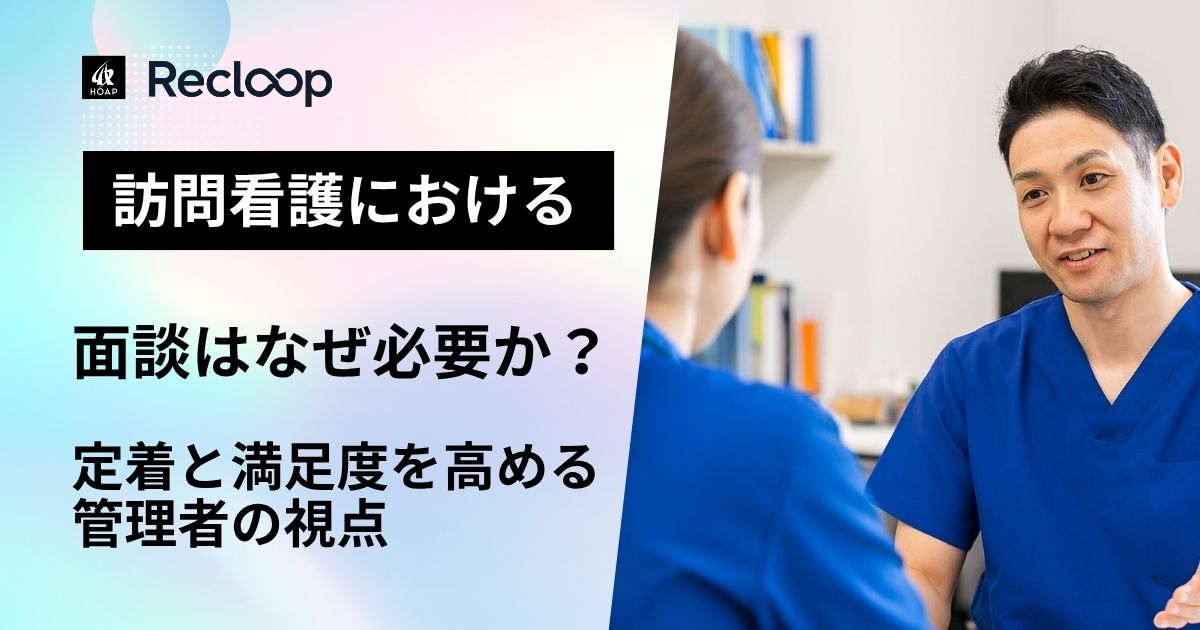「最近、なんとなくスタッフの表情が硬い」
「面談をしても、毎回『とくに問題ありません』で終わってしまう」
そんな違和感を抱えたまま、なんとなく対話の機会をやり過ごしてはいないでしょうか。訪問看護の現場では、看護師一人ひとりが単独で行動する時間が多く、管理者とスタッフが日常的に会話する場面は限られています。だからこそ「定期的な面談」が重要だとされますが、実際にはその「面談」が形だけの時間になってしまっているケースも少なくありません。「状態の確認」や「報告を受ける場」にとどまり、本来期待される「関係性を深める」効果が得られていない。
そうした状況は、面談の「目的」が曖昧なまま進められていることに起因していることが多いのです。本記事では、訪問看護における面談が果たすべき本来の役割について、どのような視点を持ち、どのような問いかけが必要なのかを順を追って整理します。スタッフの本音を引き出し、信頼関係を築くために、面談のあり方を見直してみませんか。
なぜ面談が必要なのか

単独訪問が基本の現場において関係性は自然には育たない
訪問看護という仕事の性質上、看護師一人ひとりが単独で利用者宅を訪問し、ケアを行う時間が多くなります。これは医療機関におけるチーム看護とはまったく異なる勤務形態であり、日常的に同僚や管理者と顔を合わせる機会は少なくなりがちです。 結果として、勤務上のやりとりが必要最低限にとどまり、「仕事は問題なくこなせているけれど、何を考えているのかまではわからない」という状態が、気づかないうちに常態化します。
スタッフがいまどんな気持ちで働いているのか、何か困りごとを抱えていないか、あるいはモチベーションに変化はないか。そういった「心の動き」は、通常業務の中ではほとんど表に出てきません。
つまり、訪問看護においては「ただ一緒に働いているだけ」では関係性が深まらず、意図的に「対話の接点」を設けなければ、いつまでもお互いが見えないままになってしまうのです。
面談は「評価」や「管理」のためではない
よくある誤解のひとつに、面談を「管理者がスタッフの状態を評価するための時間」と捉えてしまうケースがあります。もちろん、業務上の状況確認や目標設定の場面も必要ですが、それだけに終始してしまうと、スタッフにとって面談は「緊張する場」「言いたいことが言えない場」になってしまいます。
面談の本質は、「いま、あなたがどう感じているか」「この職場の中で、どんなことが気になっているか」を、お互いの立場から共有し合うことにあります。つまり、上司が一方的に評価するのではなく、「関係性を確認し合う場」として位置づける必要があります。 とくに訪問看護では、個別性の高い働き方ゆえに、日常的に雑談や相談が生まれにくいため、この面談の時間が「お互いを再接続する機会」になるのです。
このような対話の機会があるかどうかによって、スタッフの安心感や、職場に対する信頼の感じ方は大きく変わります。「聞いてもらえる場所がある」「気にかけてもらえている」と実感できるだけで、日々の業務への姿勢にも前向きな変化が生まれます。
形骸化した面談はかえって信頼を損なう
一方で、「形式的な面談」が続いてしまうと、むしろ逆効果になることもあります。たとえば、「最近どう?」と毎回同じ質問を投げかけて、「とくにありません」で終了する。あるいは、過去の業務ミスを掘り返して指導的な内容になってしまう。このような面談は、スタッフにとって負担でしかなくなります。
さらに悪い循環に入ると、スタッフ側も「本音を話しても変わらない」「話しても覚えてもらえていない」と感じ、徐々に口を閉ざすようになります。結果として、表面的には何も問題がないように見えても、内側では不満や疲弊が蓄積されていく。
このような状態を放置すれば、突発的な退職やチームの信頼崩壊につながるリスクも否定できません。
特に訪問看護は、「チームでいても一人で動く」という矛盾を内包している働き方です。だからこそ、「意図して話す時間」「意識して聴く姿勢」が必要になります。そして、その接点こそが、定期的な面談であるべきなのです。
面談の「目的」を見誤っていないか?必要なのは「対話」

「本人の姿を知る」ことが面談の本質
面談の時間で本当に確かめるべきなのは、単に業務がこなせているかどうかではありません。むしろ注目すべきは、「この人はいま、どんなことを大切にしながら働いているのか」「現場にどんな価値観を持ち込んでいるのか」といった、「その人らしさ」の部分です。
訪問看護は、高度な専門性と同時に、強い個人性によって支えられています。業務がルーティーン化されにくく、日々の判断に個人の感覚や経験が大きく関わるからです。だからこそ、管理者が一人ひとりの考え方や感じ方を把握しておくことが、信頼関係の構築だけでなく、より適切な業務配置や役割調整にもつながっていきます。
たとえば、「小児のケアは緊張する」「精神科の利用者さんとの関わりに手応えを感じている」といった声が出れば、そこから訪問のマッチングを見直すことも可能です。面談とは、目に見える成果や行動だけでなく、内面の価値観やエネルギーの向き先を知るための対話の時間なのです。
「ズレ」に気づくことが面談の目的になる
面談では、スタッフが普段言語化していない小さな違和感や、考えの揺れを拾うことができます。それらは日常業務では表に出にくく、本人も気づいていないこともありますが、会話の中でふとした瞬間に表れます。
たとえば、「最近どうですか?」という問いかけに対して、「まあ、忙しいですけどね」と返されたとき、それを単なる挨拶で流すのか、忙しい「けど」の部分に何かあるのでは?と耳を傾けるのかで、会話の深さは変わります。このとき、重要なのは「言葉にされた内容」よりも「その言葉を選んだ背景」に目を向ける姿勢です。スタッフ自身も気づいていなかったような気持ち、たとえば、「思ったより仕事がうまくいっていない」「もっとこうなってほしいと感じている」などが、対話を通じて少しずつ表に出てきます。
面談は、「答え」を得る場ではありません。「会話」を通じて本人の思考を動かし、その場での気づきにつなげていくものです。その過程にこそ、信頼と成長の芽が隠れています。
面談で何を聞くか?「本音を引き出す質問」とは

本人の思考を引き出す「質問」が関係性をつくる
面談において重要なのは、単に業務上の課題や不満を聞き取ることではありません。むしろ、
「本人が何を大事にして働いているのか」
「どういう瞬間に違和感を抱くのか」
「どんな場面で達成感を得ているのか」
といった、「価値観の輪郭」に触れていくことが求められます。そのためには、質問の精度がカギになります。
「困っていることはありますか?」と聞くのではなく、「最近、少しでもあれ?と感じた場面はありましたか?」と聞けば、本人が言語化しきれていない微細な感情が浮かび上がる可能性があります。つまり、良い質問とは
のではなく、
ものです。
本音は、言葉の「揺れ」や「迷い」の中にある
面談では、はっきりとした意見や希望が出るとは限りません。むしろ本音は、「うまく説明できないけれど…」という前置きや、「なんとなく…」という揺れの中に表れることが多いものです。
たとえば、「最近ちょっと疲れてるかもしれません」という言葉が出たとき、それを事務的に記録するのではなく、「それはどんなときに感じる?」と掘り下げていくことで、仕事とプライベートのバランス、利用者対応へのプレッシャー、組織内の不安など、根底にある要素が見えてきます。
その過程で、本人自身も「そうか、自分はこういうときに疲れを感じやすいんだ」と気づくことがあるのです。
面談とは、相手の「気づきを引き出す場」でもあるという認識が必要です。
良質な質問の例──思考を促す言葉が関係性を育てる
以下のような問いは、業務報告では出てこない本人の価値観や感情を引き出す一助になります。
「最近、自分らしくいられたと思う瞬間はどんなときですか?」
「前よりも少し変わったなと感じることはありますか?」
「”こうなったらいいのに”と思っていることってありますか?」
「迷った場面で、どう判断しましたか? その理由は?」
「あえて言葉にするなら、今のこの職場、どういう場所だと思っていますか?」
これらの問いは、Yes/Noでは終わらず、相手の内面を自然に引き出す効果があります。すぐに答えが返ってこなくても問題はありません。沈黙や迷いも含めて、その人の「今」を見つめる材料となります。
管理者の「姿勢」が質問の効果を決める
質問の質だけでは面談は成り立ちません。もっとも重要なのは、「この人の考えを知りたい」という誠実な関心を持っているかどうかです。問いかける側に「評価の目線」があると、どんなに丁寧な言葉でも、相手は身構えてしまいます。面談の時間は、「話を聞く」のではなく、「その人を見ようとする」姿勢の表れです。
「話してよかった」「ちゃんと受け止めてもらえた」と感じてもらえれば、それは信頼の起点になります。
問いとは関係性の鏡です。質問の内容だけでなく、「どう聞き、どう受け止め、どう返すか」。そのすべてが、チームの信頼を支える「関係づくりの手段」として機能するのです。
話を「整理して返す」ことが信頼になる──面談後の管理者の役割

面談の質は「終わったあとの対応」で決まる
面談の場でどれだけ深い話ができたとしても、それが一度限りの会話で終わってしまえば、スタッフにとっての意味は薄れてしまいます。
むしろスタッフが面談後に感じ取るのは、「あの話をどう受け止めてもらえたか」「話したことがどう扱われたか」といった、「面談後の雰囲気」です。
「何を言っても変わらない」「聞いてもらっただけだった」という印象を与えてしまうと、それは次の面談にも影響します。次第に本音は引き出しにくくなり、関係性の信頼も薄れていくでしょう。
だからこそ、面談の質は「場の雰囲気」だけでなく、「その後どう扱われたか」という一連の流れで評価されるものだと心得る必要があります。
話を「要約して返す」だけで対話の価値が高まる
面談後にできるもっともシンプルで効果的なアクションが、「話の要点を整理して返すこと」です。
たとえば、面談の最後に「今日は〇〇の話が印象的だった」「□□について、来月また確認してみましょうか」と一言添えるだけでも、スタッフは「ちゃんと聞いてもらえた」という実感を持ちます。
このように話を「可視化」することで、面談での対話がその場限りのものではなく、継続的な関係性の一部であることを伝えることができます。
また、記録を簡単に残しておけば、次回の面談でも自然なつながりが生まれます。「前回こう言っていたけど、最近どう?」という声かけは、スタッフにとって非常に大きな安心材料になるのです。
管理者が「抱え込まないこと」も重要なスキル
面談でスタッフの不安や悩みに触れると、つい「自分が解決しなければ」と思い込みがちです。しかし、すべてを一人で背負う必要はありません。
重要なのは、「スタッフの気持ちを共有できる場をつくること」であり、「即答や解決を与えること」ではないのです。
たとえば、本人と話し合った内容を事業所全体の運営にどう生かすか、あるいは他の管理メンバーやリーダー層と共有すべきか。そうした「つなぎの動き」こそが、管理者としての役割です。
また、本人に対しても「すぐに答えが出せる話ではないけれど、一緒に持ち帰らせてほしい」と率直に伝えることが信頼につながります。対応を急ぐことよりも、「真剣に向き合おうとしている」ことが伝わるかどうかが重要なのです。
対話の結果を「動き」に変えるという責任
とくに訪問看護のように現場が分散し、孤立しやすい環境では、「この面談で話したことが、何かに反映されるかもしれない」という希望があるだけで、日々の働き方に前向きな変化が生まれます。
逆に、話すだけ話して何も変わらなければ、スタッフは「もう話す意味がない」と感じてしまいます。これは信頼を失うだけでなく、チームとしての協力体制にも影響を及ぼしかねません。
だからこそ、面談で出た声を「場に返す」「対応の兆しを見せる」ことが必要です。それは具体的な制度変更や仕組みの見直しでなくても、「あなたの声は届いている」と伝える一言や行動でも十分です。
面談を「意味のある時間」に変えるには──管理者が明日からできること

面談の質は「特別なこと」より「積み重ね」で決まる
面談をより意味のあるものにしたいと考えると、「新しい質問を用意しなければ」「ちゃんと準備しないと」と構えてしまいがちです。
しかし、面談の質を左右するのは特別なノウハウや話法ではなく、日常の中でどれだけ「聴く姿勢」を持ち続けられるかにあります。形式やツールに頼らなくても、相手の言葉を受け止めようとする意志があれば、自然と良い対話は生まれていきます。
むしろ一度きりの完璧な面談よりも、「また話せる」「前回の話を覚えていてくれた」という積み重ねの方が、スタッフの安心感につながります。
それが、訪問看護という孤立しやすい働き方において、チームをつなぎ止める大切な接点となります。
忙しい現場でも「やれること」から始める
業務に追われる日々の中で、面談の優先順位を下げてしまうことは珍しくありません。「話す時間がない」「つい後回しにしてしまう」と感じている管理者も多いはずです。
しかし、面談は時間を確保して実施すること自体に意味があります。たとえ10分でも、1対1で向き合う時間を「意図的に取る」という行為は、スタッフにとって大きなメッセージになります。
話の深さや量よりも、「この人は自分に向き合おうとしてくれている」と感じられるかどうか。その実感こそが、面談の成果です。
明日からできるアクション例
ここでは、特別な準備がなくてもすぐに取り組める、面談の具体的な工夫を紹介します。
「今日は話を聴く日」と決める日を1日だけつくる
→ 業務の合間に1人5〜10分でも「最近どう?」と声をかけてみる
「この前の話、どうなった?」と聞いてみる
→ 一度でも言葉を拾っておけば、それだけで信頼の連続性が生まれる
問いかけを“質問”ではなく“感想”から始める
→「あのとき◯◯と言ってたの、気になってたんだけど」など、会話の重心を下げる
面談後に一言メモを残す習慣をつける
→ 自分のための記録でも、「この人の変化」に気づけるようになる
面談の目的をあらためてチーム全体に伝える
→ 「評価の時間ではなく、お互いの理解の時間」と明言することで心理的安全性を高める
「また話したい」と思われる存在に
面談を重ねるうちに、スタッフが「この人には話せる」「また話してもいい」と感じるようになること。それが、管理者にとっての大きな成果です。
訪問看護という仕事は、個人の裁量が大きく、孤独も感じやすい働き方です。だからこそ、対話を通じて「ひとりではない」と実感できる時間が必要です。
面談とは、問題を解決するためのものではなく、「安心して考える場」をつくること。
その場があることで、人は働き方に意味を感じ、関係性の中に自分の居場所を見いだしていくのです。

監修者:牟田 健登(Kento Muta)
株式会社クルージズ・テクノロジーズ代表取締役。2021年に創業し、在宅医療・介護業界に特化した人事コンサルティング・人事評価SaaSを展開。訪問看護ステーションや訪問介護ステーションを中心にサービスを展開中。