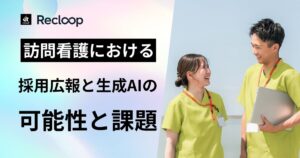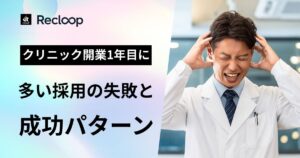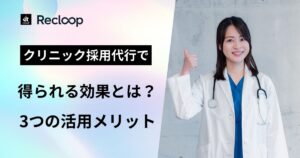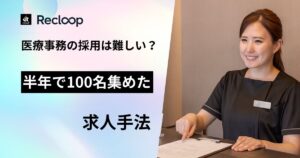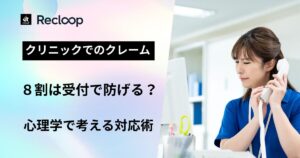『採用活動に割ける時間も人手も限られている』これは多くのクリニックで共通する悩みです。日々の診療に追われる中、採用業務を兼務している院長や事務長、人事担当者からは
「求人原稿を作るだけで何時間もかかる」
「応募者への対応が遅れてしまう」
といった声が聞かれます。特に、小規模組織では採用活動が属人的になりやすく、ノウハウの蓄積や共有が進まないことも少なくありません。
このような状況を受け、注目されているのが「ChatGPT」をはじめとする生成AIの活用です。人間の代わりに判断させるのではなく、「人間の考える時間」を圧縮し、次に進むヒントをくれるツールとして導入されはじめています。採用文のたたき台作成、タイトル案の候補出し、スカウト文面の生成、評価項目の見直しなど、日々の採用業務における多くの場面で、ChatGPTが実務を支える存在となりつつあります。
本記事では、クリニックにおける採用業務の具体的なシーンに沿って、ChatGPTを活用するための5つの方法を紹介します。すべてのノウハウは、採用の専門家やITリテラシーが高くない方でも実践できる内容を前提に構成しています。明日からの業務の効率化に向けて、ぜひ参考にしてください。
ChatGPTを使った求人原稿のたたき台づくり

「書かなければ」と思っても手が止まる現実
求人原稿の作成に時間がかかる。それは、クリニックの院長や採用担当者の間で非常によく聞かれる悩みです。特に小規模の医療機関では、採用専任の担当者がいない場合が多く、院長や事務スタッフが通常業務の合間を縫って原稿を作成しています。そのため、「何を書けばいいか分からない」「毎回同じような内容になってしまう」「そもそも考える時間が取れない」という課題に直面しやすくなります。
求人原稿は、求職者との最初の接点であり、第一印象を決定づけるものです。にもかかわらず、「前回の原稿を流用して済ませてしまう」「なんとなく無難な言葉ばかり並べてしまう」という事例が散見されます。背景には、「自院の魅力をどう言語化すればいいか分からない」という不安や、ゼロから文章を組み立てることへの心理的ハードルがあります。
ChatGPTが「構成」と「表現」の壁を突破する
こうした中で活用が進んでいるのが、ChatGPTによる原稿生成機能です。ChatGPTは、入力されたキーワードや条件に応じて、自然な文章を高速で出力します。たとえば「内科クリニックで看護師を募集。週3日勤務OK。育児中スタッフが多数在籍」といった条件を提示するだけで、それらを含んだ数パターンの原稿を生成することが可能です。
担当者はその中から、自院に合うトーンや言い回しを選び、必要に応じて調整すればよいため、「ゼロから作る」負担が大幅に軽減されます。これまで30分以上かかっていた初稿作成が、10分足らずで完了するケースも珍しくありません。
また、ChatGPTは「言い回しをやわらかくしてほしい」「求職者に親近感を与える表現に変えて」といった要望にも柔軟に応じられるため、硬くなりがちな文章の調整にも有効です。
結果として、読みやすく、心に届きやすい求人原稿を短時間で作成できるようになります。
本当に伝えたいのは「条件」ではなく「理由」
求人原稿で伝えるべきことは、単なる労働条件だけではありません。「なぜこの制度があるのか」「どんな人と働きたいのか」「どのような価値観を大切にしているのか」といった「背景」にこそ、自院の個性や方針が表れます。求職者はそこに共感し、自分が働くイメージを膨らませていくのです。
しかし、原稿作成の時点で「まず文字数を埋めなければ」「他院と差別化しなければ」といった焦りが先に立ってしまうと、こうした本質的な部分にまで手が回らなくなります。ChatGPTにたたき台を任せることで、担当者は原稿の骨格づくりから解放され、その分「どんなメッセージを込めたいか」「自分たちらしさは何か」をじっくり考える余裕が生まれます。
このように、ChatGPTは単なる効率化ツールではなく、「書くことに向き合うための下支え」を担う存在と捉えるべきです。
汎用表現から「自院らしさ」を引き出すプロセスへ
生成された原稿は、あくまで出発点です。そのまま使える場合もありますが、より効果的に活用するには「この表現、自院の雰囲気に合っているか」「もっと具体的なエピソードは盛り込めないか」といった視点での調整が不可欠です。たとえば、「子育て中のスタッフが多い」という事実があるなら、「行事の日はお互いにシフトを調整し合う風土があります」といった実情を追記することで、求職者の共感を得やすくなります。つまり、
ChatGPTが担うのは「言葉のたたき台」を出すことであり、「意味づけ」や「個性づけ」は最終的に人間が行うものです。この役割分担が明確であればあるほど、求人原稿の質は向上しやすくなります。
ChatGPTによるスカウトメールテンプレートの自動生成

スカウトメールが「時間のかかる業務」になっていないか?
スカウトメールは、採用活動の成果を左右する重要な接点です。特に医療業界では、求人広告だけではアプローチできない層に直接働きかける手段として重視されてきました。しかし実際には、「テンプレで送っている」「毎回ゼロから考えるのが大変」「誰に送ったか分からなくなる」といった悩みを抱えているクリニックも少なくありません。
送信数を増やすと、文面の質が下がる。かといって、丁寧に一通ずつ書こうとすると時間が足りない。このジレンマは、限られた人員で採用を行う医療機関にとって大きなハードルとなっています。
ChatGPTは「文面づくりの壁打ち役」として使える
こうした課題に対して、ChatGPTはスカウトメール文面の「型」を作る補助ツールとして有効です。たとえば、以下のような入力を行うだけで、応募者属性に応じたスカウトメールの素案を生成できます。
・対象職種(例:看護師、医療事務)
・アプローチしたい特徴(例:子育て中の方)
・働き方(例:週3日勤務可能、夜勤なし)
・自院の特徴や強み(例:スタッフ定着率が高い、駅近)
これらをChatGPTに投げかけると、「ご覧いただきありがとうございます。◯◯クリニックの採用担当です」といった書き出しから始まり、自院の魅力を短くまとめた文章が複数パターン生成されます。口調の調整や長さの指定も可能なため、「柔らかく、読みやすく、返信しやすい文面」を短時間で整えることができます。
コピペ感のないメッセージをつくるために
スカウトメールの最大の課題は、「テンプレ感が伝わってしまう」ことです。送り手にとっては大量配信でも、受け取り手には一通のメッセージとして届くため、無機質な表現や汎用的な誘導文はすぐに見抜かれます。
ChatGPTを活用することで、「◯◯な背景を持つ方にこそ、当院の◯◯な働き方が合うと思っています」といったような、読み手の状況に寄り添った文脈が自然に盛り込めるようになります。また、「前職の経験を活かしつつ、新しい挑戦をしてみたい方へ」など、心情に訴えるフレーズも短時間で複数提示できるため、テンプレ的な印象を与えない工夫がしやすくなります。
忙しい採用担当者の「質を保った時短」を実現する
スカウト文面の作成は、時間をかければ必ずしも成果につながるわけではありません。
重要なのは、「読み手が反応したくなる一文があるかどうか」です。
ChatGPTを活用すれば、短い時間で質の高い文案を複数生成できるため、比較検討しながら最適な文面を選ぶことが可能になります。
また、頻出するシチュエーション(例:扶養内勤務希望者へのアプローチ、復職希望者への声がけなど)に対して、ChatGPTでテンプレートを事前に複数用意しておけば、状況に応じた再利用も容易です。「少ない工数で精度の高い接触」を実現できる点が、特に多忙な現場における大きなメリットといえるでしょう。
人は「誰に・何を伝えるか」を考え、文章はChatGPTに任せる
スカウトメールの本質は、「誰に・何を・どんな言葉で届けるか」を決めることにあります。そこを担当者が明確にした上で、具体的な言語表現や構成案はChatGPTに委ねる。この役割分担が確立できれば、スカウト業務における「時間と質のトレードオフ」を解消できます。
文面作成に悩んで手が止まってしまう前に、一度ChatGPTに投げかけてみる。この小さな動きが、採用の初動スピードと反応率を大きく変えていく可能性があります。
ChatGPTが提案するクリックされるタイトル案の選び方

タイトル次第で「読まれるかどうか」が決まる
求人原稿の中でも、最も大きな影響力を持つのがタイトルです。実際、多くの求人サイトや求人検索アプリでは、検索結果に表示される情報は「タイトル」「勤務地」「給与」のわずか数行に限られており、タイトルが魅力的でなければそもそも詳細ページを見てもらうことさえできません。
にもかかわらず、タイトルに対して時間をかけられていないケースは多くあります。「職名だけ載せる」「とりあえず無難にまとめた」「他院の表現を参考にしただけ」「毎回似たような言い回しになる」といった状況では、求職者の目に留まる可能性は低下します。限られた文字数の中で、いかに印象に残る言葉を選ぶか。この課題に向き合ううえで、ChatGPTは強力なパートナーとなります。
ChatGPTは「複数の切り口」から案を出せる
ChatGPTの強みは、ひとつの入力に対して複数のアプローチを返せることです。たとえば、「看護師/日勤のみ/週3日~/駅チカ」という条件をもとに、以下のような異なる視点のタイトル案を生成できます。
・感情訴求型:「夜勤に悩まない◎日勤だけの安心勤務!」
・ライフスタイル訴求型:「週3日〜OK|家庭と両立しやすいクリニックです」
・即時メリット型:「駅から徒歩3分/ブランク明けも安心のサポートあり」
・対象明確化型:「子育て中の方歓迎|時短勤務もOK◎」
このように、条件は同じでも、読み手の目のつけどころに合わせて複数の切り口を出せる点が、ChatGPTの大きな利点です。しかもそれを、わずか数秒で生成できます。
「なんとなくの言葉選び」から脱却するきっかけに
タイトル案の検討が難航する理由の一つに、「語彙の選択肢が少ない」ことが挙げられます。たとえば、
といった表現は便利な一方で、どの求人でも多用されており、埋もれやすくなっています。
ChatGPTは、同じ意味を持ちながらニュアンスの異なる表現を数多く提示できます。たとえば、
など、感情や情景を想起させる言葉に言い換えることで、より具体的かつ印象的なタイトルが生まれやすくなります。
また、訴求軸が明確になっていないままタイトルを考えても、表面的な言葉に終始しがちです。
ChatGPTとやり取りする中で、「今回は何を最も伝えたいのか」を逆に自分自身が再確認するプロセスとなることも少なくありません。
比較と選定の精度が上がる
ChatGPTは、タイトル案を一度に10個以上出力することも可能です。その中から「どれが最も自院らしいか」「どれが他院と差別化できているか」を比較しながら選定することで、納得感のあるタイトル決定がしやすくなります。
また、複数の案をスタッフ同士で共有して「どれが刺さるか」を議論することで、主観だけに頼らない意思決定も可能になります。生成されたタイトルは“候補”であり、完成形ではありません。ChatGPTを活用することで、「見比べて選ぶ」という本来あるべきプロセスが実現しやすくなります。
文字数や媒体特性にも柔軟に対応できる
媒体ごとに設定された文字数制限に応じて、ChatGPTは文量の調整も可能です。たとえば、「30文字以内で」「20文字で簡潔に」といった条件を付け加えれば、その制限内で収まる複数パターンのタイトルを生成できます。
また、Indeed・Googleしごと検索・医療系専門媒体・自社サイトなど、掲載媒体の性質に合わせて指示を出し、出力してもらうことも可能です。こうした対応力の高さは、複数チャネルで採用を展開しているクリニックにとって大きな利点になります。
ペルソナ設定におけるChatGPTとの壁打ち活用術

なぜペルソナ設定がうまく言語化できないのか?
「どんな人に来てほしいのか」は明確なつもりでも、それを具体的な言葉で示そうとすると意外と難しい。これは多くの採用担当者が感じていることです。たとえば「協調性のある人」「柔軟な人」といった抽象的な言葉で表現されがちですが、それでは求人原稿や面接評価に落とし込みづらく、現場と人事の間で認識のズレが生まれる要因にもなります。
ペルソナ設定は、採用戦略の起点となる重要な工程です。ここがあいまいなままだと、「誰に向けた原稿か分からない」「面接で何を聞くか定まらない」といった連鎖的な混乱を招きかねません。とはいえ、忙しい業務の中で、時間をかけて一人で言語化するのは困難です。
ChatGPTとの対話が“考えの可視化”につながる
このような状況において、ChatGPTは「問いかけてくれる相手」として機能します。たとえば、「今回の採用で、どんな価値観を持った人を求めていますか?」と入力すれば、ChatGPTはさらに深掘りする質問を返してくれます。
・その価値観が必要なのは、どんな場面で活かされるか?
・これまで採用してうまくいった人と、そうでなかった人の違いは?
・求職者が今いる職場で、どんな悩みを抱えていそうか?
こうしたやり取りを重ねることで、自身の考えが少しずつ輪郭を持って見えてきます。これはまさに「壁打ち」のプロセスであり、ChatGPTが採用の思考整理を支援する相手として有効である理由のひとつです。
「現職の状況」から出発するとリアルな像が見えてくる
求人作成や採用戦略で大切なのは、「理想像」から逆算するのではなく、「今の職場で働く人の現実」を起点にすることです。たとえば、今病院でフルタイム勤務しているが、子育てとの両立に限界を感じている人。ChatGPTにそのような前提を提示すれば、「その人が魅力を感じやすい職場環境とは?」といった設問を提示してくれます。
このように、ターゲット像をストーリーとして構築することができれば、求人原稿のトーンや面接での質問にも一貫性が生まれます。また、「その人が安心して働ける職場とは?」という問いは、組織としての改善ポイントにもつながります。
属人的な感覚を「言語」に変えるための補助線
「うちの職場に合うのは、こういう人だよね」という感覚は、ベテランの中には自然と備わっているものです。しかし、それが言語化されていないと、他のスタッフに共有できず、採用の基準や対応が属人的になってしまいます。
ChatGPTは、「この職場に合わないのは、どんな人ですか?」といった逆方向の問いかけにも対応可能です。たとえば「自分で判断せずすぐ上司に聞くタイプは難しい」といった職場の声を出発点にすれば、それに対する理由や背景を深掘りし、「求める人物像」の輪郭をより鮮明に描くことができます。
この過程を通じて、ベテランの暗黙知が明文化され、新人スタッフや他部門との共有がしやすくなります。これは、採用だけでなく定着や評価の基準整備にも効果的です。
ChatGPTは「考えを引き出す場」を提供する
ペルソナ設定における最大のポイントは、
ではなく、
ChatGPTは、それを一人で抱え込まずに進めるための“補助線”となります。
「ChatGPTに聞いたら答えが出る」ではなく、「ChatGPTとやり取りする中で、自分の考えが言葉になっていく」。この活用スタンスが、ペルソナ設定の質を大きく変えていきます。たとえば求人作成フローで整理されているように、「どんな職場で、どんな違和感を持ち、どんな未来を求めているか」という3点を中心に深掘りしていくと、ChatGPTは非常に有効な壁打ち相手として機能します。
ChatGPTを活用した選考基準の言語化と可視化

面接で「何を見るか」が決まらないまま進んでいないか?
応募者との面接は、採用活動における重要な判断の場です。しかし、現場では「なんとなくの印象」で評価が決まってしまうケースが少なくありません。「人柄は良さそうだった」「現場に馴染めそう」こうした感覚的な判断は、担当者間での基準のばらつきを生みやすく、採用後のミスマッチにもつながります。
とくに医療機関では、採用担当が必ずしも人事の専門家ではなく、現場の管理者や院長自らが面接を行うことも多い状況です。そうした中で、「自分たちの職場に合う人材とはどんな人か」「どこを見て判断すべきか」を言語化し、共有できているクリニックは決して多くありません。
ChatGPTが「基準を言葉にする」手助けをする
選考基準の可視化には、「思考の棚卸し」が必要です。ChatGPTは、この過程を支える補助ツールとして活用することができます。
たとえば、「協調性を重視したい」と入力すれば、ChatGPTは次のような補足質問を提示できます。
・協調性が発揮されるのは、どんな場面か?
・これまで協調性に欠ける人がいたとき、どんな問題が起きたか?
・協調性のある人は、具体的にどんな行動を取っていたか?
このようなやり取りを通じて、抽象的だった「協調性」という言葉が、「報連相を自発的に行う」「他職種と目的共有ができる」といった具体的な行動レベルにまで落とし込まれていきます。
これが、選考基準を「誰が見ても同じように判断できる状態」に近づけるプロセスです。
求める人物像に沿った質問も準備できる
ChatGPTはまた、「求める人物像に合う人かどうかを見極める質問」の準備にも活用できます。たとえば「自立して判断できる人がほしい」と伝えると、以下のような質問案が出力されます。
「これまで仕事で迷ったとき、どうやって判断していましたか?」
「何かを決めるとき、どんな情報を重視しますか?」
「前職で上司と意見が食い違った経験はありますか? そのときどうしましたか?」
こうした質問を用意しておくことで、限られた面接時間の中でも、応募者の価値観や判断軸を引き出しやすくなります。
また、「こういう回答が出たらポジティブに捉えるべき」「この反応がある場合は懸念が残る」といった観点もChatGPTから提案を受けることで、面接官ごとの評価のばらつきを減らす手がかりになります。
感覚を「共有できる基準」に変換するプロセス
選考で本当に見ているのは、「感じ方」ではなく「行動」のはずです。しかし実際には、「なんとなく好印象だった」「返答の仕方が丁寧だった」といった印象評価が基準になりがちです。
ChatGPTは、その「なんとなく」を言語化するための質問や、過去の評価経験から基準を逆算するプロセスをサポートします。たとえば、「最近採用してよかった人」と「採用後に悩みがあった人」の違いをChatGPTに分析させると、その差に含まれる評価軸のヒントが得られることもあります。
また、複数の面接官が同じ質問を用いて評価する仕組みを整えれば、属人性の排除と同時に、組織としての選考方針の軸が生まれます。
書き起こして残すことで、次に活かせる
ChatGPTとのやり取りで生まれた評価基準や質問案は、都度メモや評価シートに反映させることで、次の採用活動に引き継ぎやすくなります。属人的なノウハウを形式知として蓄積していくことが、継続的な採用の質向上につながります。
一度言語化した基準は、求人原稿・面接・内定後フォローにも連動させることができ、採用プロセス全体の一貫性を生み出します。ChatGPTはその起点として、「考えたことを形にする」段階を支援する役割を担うのです。
クリニックにおける採用業務は、人手・時間の制約の中で多くの判断と対応が求められます。ChatGPTはその負担を軽減しつつ、担当者の思考を補助し、質の高いアウトプットを後押しする存在です。求人原稿やスカウト文、タイトル案の作成から、ペルソナの言語化や選考基準の明確化に至るまで、活用できる場面は多岐にわたります。
「人の判断を置き換える」のではなく、「人の考える力を引き出す補助役」としてChatGPTを使いこなすことが、これからの採用活動を前進させる鍵になるでしょう。