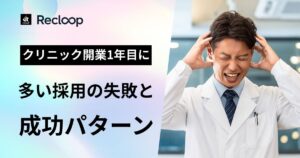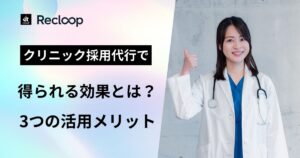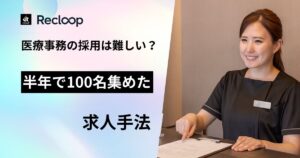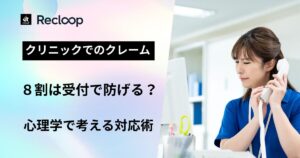クリニックの院長にとって、看護師や医療事務の採用は長年の課題です。求人を出しても応募が集まらない、せっかく採用しても早期離職につながってしまう、応募者がいても求めるスキルや経験と一致しないなど、悩みは尽きません。背景には、全国的な医療人材の不足や、他業種との人材獲得競争の激化、そして少子化による応募母数そのものの減少といった要因があります。
こうした状況を受け、近年注目されているのが「採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)」や「採用支援サービス」です。自院の採用活動をすべて外部に任せるのか、一部を伴走型で支援してもらうのかという違いはありますが、いずれも人手不足が深刻なクリニックにとって有効な選択肢となり得ます。しかし実際には、「採用代行と採用支援はどう違うのか」「費用はどれくらいかかるのか」「どのように活用すれば成果につながるのか」といった疑問を抱く方が少なくありません。
本記事では、クリニックにおける採用代行と採用支援の違いを整理し、看護師・医療事務の採用課題にどう役立つのかを解説します。さらに、サービスの比較ポイントや導入から成果までの流れも具体的に取り上げることで、自院に合った採用方法を検討する手がかりを提供します。次章ではまず、「採用代行」と「採用支援」の違いについて見ていきます。
クリニック採用代行と採用支援の違い

採用代行とは?(求人作成から面接調整まで全面委託)
採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、クリニックにおける採用業務を外部事業者が包括的に引き受けるサービスです。求人票の作成から応募者管理、面接日程の調整、内定通知まで、採用に関わる一連の流れを専門チームが代行します。院長は、本来の医療サービスや経営管理に専念できるのが最大のメリットです。
特に小規模なクリニックでは、採用専任の人事担当を置けないケースが多く、院長や事務長が本業の合間に採用業務を担っている実態があります。そのため応募者対応が遅れたり、面接日程の調整に手間取り、せっかくの候補者を逃してしまうリスクも少なくありません。採用代行を利用すれば、候補者とのやり取りは専門チームが迅速に対応するため、歩留まりを減らし、採用効率を高められます。
また、求人媒体の選定や求人票の文言調整、応募者の書類スクリーニングなど、経験とノウハウを持つ外部事業者が行うことで、応募者の質を高められる点も強みです。たとえば、求める人物像を明確化したうえで求人原稿を最適化すれば、単に応募数を増やすのではなく、ミスマッチを減らし、面接に進む候補者の適合度を高められます。
このように採用代行は、採用活動を全面的に任せたいクリニックに適した選択肢です。ただし、すべてを外注する分、院内の採用ノウハウは蓄積されにくいという側面があるため、その点を理解したうえで利用することが重要です。
採用支援とは?(戦略立案・ツール提供で主体性を残す方式)
もうひとつの典型的な問題は、「誰を採用したいのか」が不明確なまま、求人を出してしまうケースです。特に、看護師や医療事務といった職種では、スキルや経験値、求める人物像に幅があるにもかかわらず、それらを言語化せずに「来てくれれば誰でもいい」というスタンスで進めてしまうことがあります。
結果として、採用した人材が現場にフィットせず、早期離職を招いたり、職場内の雰囲気に悪影響を与えたりといったリスクが高まります。「採ったけれど、続かない」という経験を繰り返すことで、ますます採用への不信感や疲弊感が蓄積されていきます。
費用比較表
採用代行と採用支援の大きな違いの一つは、費用体系にあります。代表的な相場感は以下の通りです。
採用代行(RPO):月額5万円〜15万円程度。求人票作成から応募者対応、面接調整まで一括で代行するケースが多い。
採用支援:月額10万円〜からのコンサルティング×RPO型が一般的。単なる代行だけでなくペルソナ設定や採用戦略全体から考え伴走支援している。
採用代行は「戦略はあるが業務を軽減したい」場合に適し、採用支援は「戦略から見直しつつ業務も減らしたい」場合に向いています。短期的な負担軽減を重視するのか、中長期的な仕組みづくりを優先するのかによって、選ぶべきサービスが異なります。
費用の大小だけでなく、どの範囲まで任せたいのか、どの程度自院で関わりたいのかを明確にすることが、選択の前提となります。次章では、特に深刻な課題である「看護師採用」において、採用代行がどのように役立つのかを掘り下げていきます。
看護師採用代行で解決できるクリニックの課題

看護師不足の現状
看護師の不足は、クリニックに限らず医療業界全体に共通する課題です。近年では、看護職の有効求人倍率は常に2倍前後で推移しており、全国的に「求職者1人に対して2つ以上の求人がある」状態が続いています。つまり、看護師は就職先を選びやすく、クリニックにとっては常に人材獲得競争の真っ只中にあるといえます。
さらに離職率の高さも見逃せません。特に若年層や子育て世代の看護師は、ライフイベントに左右されやすく、短期間で転職する傾向があります。夜勤や残業の少ない働き方を求めて病院からクリニックへ流入するケースもあれば、逆にスキルアップや収入を理由に病院や大規模施設へ転職するケースも少なくありません。こうした流動性の高さが、採用難を一層深刻化させています。
この現状を踏まえると、クリニックが「求人を出せば人が集まる」という発想では採用は成功しません。競争の中で選ばれるためには、採用活動のスピード、応募者との丁寧な対応、そして自院ならではの魅力の打ち出し方が重要になります。ここで効果を発揮するのが採用代行です。クリニックが戦略を持っていても、日常業務の多忙さから対応が遅れれば候補者を逃してしまいます。代行を活用することで、その「スピードと確実性」を担保できるのです。
看護師の採用競争が激化する3つの背景
看護師採用の難しさは、単なる人手不足だけでは説明できません。背景には大きく3つの要因が存在します。
1つ目は「夜勤の有無」です。病院勤務と比べてクリニックは夜勤がない分、ライフスタイルを重視する看護師にとって魅力的です。その一方で、夜勤手当がないため給与水準が低く見られがちで、条件次第では敬遠される場合もあります。
2つ目は「スキル要件の違い」です。クリニックでは病棟勤務ほどの高度医療スキルを必要としない場合も多いですが、逆に少人数体制のため幅広い業務を求められる傾向があります。採血や検査補助に加え、受付対応や医療事務との連携など、マルチタスクが当たり前になる点が、応募者の心理的ハードルとなることがあります。
3つ目は「地域差」です。都市部では求人は多いものの応募者も多く競争が激しい一方、地方ではそもそも看護師の母数が少なく、募集を出しても応募がほとんどないケースが目立ちます。地方クリニックほど採用難が深刻化している現実があります。
こうした背景を理解したうえで戦略を立てることは重要ですが、戦略があっても「応募者対応に時間を割けない」「面接日程をスムーズに調整できない」といった実務の遅れが結果を左右します。採用代行は、こうした「実務の抜け漏れ」を防ぎ、候補者にストレスのない選考体験を提供することで、競争環境を乗り切る力を発揮します。
採用代行活用のメリット
採用代行を活用する最大のメリットは、業務を外部に委ねることで「戦略に基づいた実行精度」を確保できる点にあります。クリニックが採用方針や求める人物像を明確にしていれば、代行業者はそれに沿った候補者スクリーニングを実施します。経験年数や資格だけでなく、勤務条件への適合度や将来的な定着可能性まで見極めることが可能です。
さらに、応募から内定までのレスポンスが早くなることで候補者の満足度が上がり、「他院に決める前にクリニックの選考が進んだ」という成果につながります。採用活動においてスピードは信頼そのものであり、特に競争の激しい看護師市場では重要な要素です。
定着率の改善にも寄与します。採用代行は入職後のフォロー体制まで含む場合があり、初期研修やオンボーディングを支援する事業者も存在します。これにより「入職後のギャップ」が減り、早期離職を防ぐことができます。
結果として、単なる業務軽減ではなく「欲しい人材を効率的に確保し、長く定着してもらう」という採用本来の目的達成に近づけるのが採用代行の強みです。クリニックが戦略を描き、それを実行する力を補う存在として、代行は極めて有効な選択肢となります。
医療事務採用が困難な3つの理由と代行による解決策

応募者減少の背景(少子化・他業種流出)
医療事務はクリニックにとって欠かせない職種ですが、近年は応募者の母数そのものが減少しています。背景には、まず少子化による労働人口の縮小があります。20代〜30代の女性を中心に担われてきた医療事務は、そもそも若年層人口の減少に直撃されており、以前のように「求人を出せば応募が来る」という状況ではなくなっています。
さらに深刻なのは、他業種への人材流出です。特に事務職経験者は、医療以外の一般企業やリモートワークが可能な事務職へ流れる傾向が強まっています。医療事務は専門性がある一方、給与水準は決して高くなく、繁忙期には残業も発生します。働きやすさを重視する人材にとっては、医療事務よりも条件の良い仕事が選択肢に上がるのは自然なことです。
こうした背景の中でクリニックが医療事務を採用しようとする場合、「どのように他業種よりも魅力的に映るか」が鍵となります。しかし、院長や事務長が業務の合間に対応していると、応募者へのレスポンスが遅れたり、求人票の表現が一般事務との差別化につながらないまま公開されてしまうことが少なくありません。採用代行を活用すれば、戦略を持つクリニックが「業務のスピードと精度」を補完でき、応募者を逃さない体制を整えることができます。
資格要件・経験スキルのミスマッチ問題
医療事務の採用が難しい理由の一つが、資格や経験に関するミスマッチです。医療事務には「医療事務管理士」「診療報酬請求事務能力認定試験」など複数の資格が存在しますが、クリニックによって必要とする水準は異なります。求人票に「医療事務経験者歓迎」と記載しても、レセプト業務を一通り経験している人を想定しているのか、受付対応を中心とした経験でも良いのか、曖昧なケースが多く見受けられます。
応募者側も「資格は持っているが実務経験が浅い」「病院では経験があるがクリニックでの流れは分からない」といった事情を抱えている場合が多いです。その結果、応募段階で「自分は対象外ではないか」と感じて応募を控える人も少なくありません。
このようなミスマッチは、求人票の設計段階から明確にすることで防ぐことが可能です。採用代行を活用すれば、クリニックが求めるスキル水準を具体的にヒアリングし、それを応募者が誤解しない表現で求人票に反映できます。さらに応募後のスクリーニングでも「資格はあるが経験が浅い人材」と「即戦力を期待できる人材」を適切に仕分けることができ、結果として面接の質が向上します。
採用支援を組み合わせれば、そもそもの戦略段階で「資格重視か、人物重視か」という方針を明確化できます。戦略を持ちつつ業務を軽減したいクリニックには採用代行、戦略から見直したい場合は採用支援と、目的によって使い分けることが重要です。
採用支援で解決できるプロセス改善
医療事務採用の難しさは、単に「応募が来ない」だけでなく、「誰でも採る」という姿勢からミスマッチが増えやすい点にもあります。実際、応募が少ないからといって条件を広げすぎると、結果的にクリニックの雰囲気や求めるスキルと合わない人材を採用してしまい、短期間で再び欠員が出ることも珍しくありません。
ここで有効なのが採用支援です。採用支援では、まずクリニックの採用戦略を明確にし、求める人材像(ペルソナ)を定義します。「受付対応を笑顔でこなせる人物」「レセプト経験を重視」「子育てと両立しやすい環境を望む層」など、ターゲットを具体的に描くことで、求人票の書き方や打ち出すポイントが変わります。
このアプローチにより、従来の「くるもの拒まず」の採用から一歩進んで、「自医院に合う人材を選べる」体制が整います。応募者の数を追うのではなく、ペルソナに沿った応募を集めることができるため、結果として採用の質と定着率が向上します。
つまり採用支援は、応募母数を増やすだけではなく、「誰を採るか」の選択精度を高めるサポートです。戦略から見直しつつ業務を軽減したいクリニックにとって、採用支援は長期的に効果を発揮する手段といえます。
クリニック採用代行・採用支援サービスの選び方と比較ポイント

チェックすべき5つの基準
クリニックが採用代行サービスを検討する際には、どの事業者を選ぶかが成果を大きく左右します。単に「費用が安いから」「知名度があるから」といった理由だけではなく、複数の観点から比較することが重要です。
まず確認すべきは専門性です。医療業界、とりわけクリニックの採用に知見がある事業者かどうかを見極める必要があります。一般企業の採用代行とは異なり、医療職特有の資格要件や勤務条件、そして応募者が重視するポイントを理解しているかどうかで、成果は大きく変わります。
次に実績です。過去にどのようなクリニックや医療法人で採用を支援してきたのか、具体的な事例を確認すると安心です。同じ規模や診療科のクリニックで成果を出している実績があれば、自院でも再現性を期待できます。
費用も大切な判断基準です。採用代行の相場は月額5〜15万円程度、採用支援は10万円〜が一般的です。費用の大小よりも「業務範囲と費用が見合っているか」を確認することが欠かせません。
さらにサポート体制も注視しましょう。単に業務を代行するだけでなく、状況に応じて柔軟に対応できるか、定期的に報告や改善提案をしてくれるかどうかがポイントです。
最後に忘れてはならないのがカルチャーマッチです。代行事業者がクリニックの文化や価値観を理解し、求人票や候補者対応に反映できるかどうかで、応募者の印象が変わります。候補者にとって最初の接点となるのは代行業者であることも多く、そこでの対応が「このクリニックで働きたい」と思えるかどうかに直結します。
クリニックの採用支援「HOAP」の特徴
数ある事業者の中で、HOAPの採用支援サービスには独自の強みがあります。第一に挙げられるのがカルチャーマッチ重視の姿勢です。単に「人を採用すること」ではなく、「その人が長く働き続けられるか」に重点を置きます。これは単なるスキルマッチングではなく、クリニックの価値観や文化に合う人材を見極めるプロセスを伴走するということです。
また、HOAPは相談型のコンサルティングを基盤にしているため、院長と対話を重ねながら「なぜ応募が集まらないのか」「本当に欲しい人材はどんな人物か」を一緒に考えます。その上で求人票の表現や発信の仕方を調整し、自院に合う応募者を増やすことを目指します。これにより、従来の「来た人を採用する」から「自院に合う人を選べる」採用体制へとシフトできます。
費用体系についても、月額固定というシンプルな設計で、成果に対して過度な成功報酬が発生しない点が特徴です。予算を明確にしやすく、長期的な採用活動を計画的に進めやすい仕組みといえます。
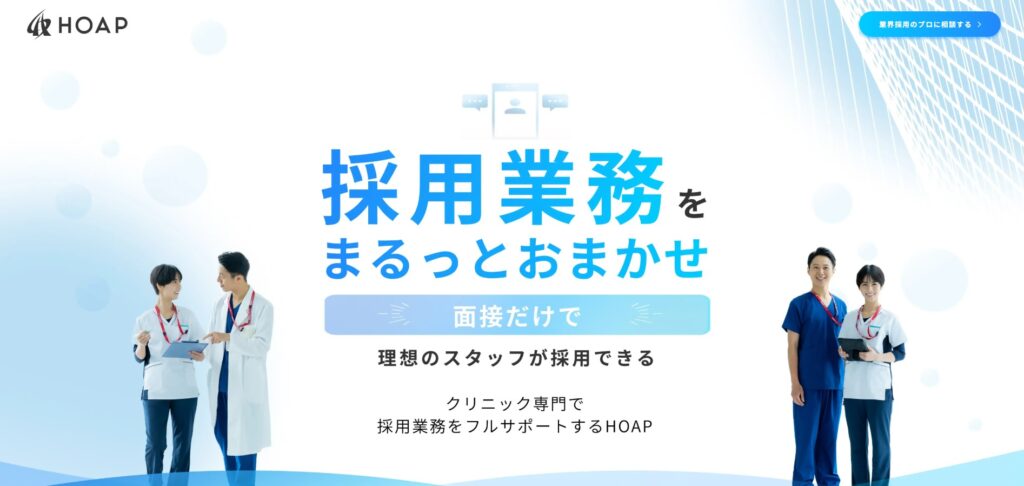
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。
採用代行・採用支援サービス選定のステップ
クリニックが採用代行サービスを検討する際、次に取るべきステップを整理します。
・採用課題を整理し、「戦略はあるが業務を軽減したい」のか、「戦略から見直したい」のかを明確にする
・医療専門型か一般型か、サービス提供範囲を比較表にまとめてみる
・候補者対応の品質やスピード感を重視し、代行事業者との面談で確認する
・費用が妥当かどうかは「業務範囲」「サポート内容」と照らし合わせて判断する
・リニックの文化や雰囲気をどれだけ理解してもらえるかを重視し、カルチャーマッチを必ず確認する
これらを踏まえて比較検討すれば、単なるコスト削減ではなく「採用成功に直結するパートナー」を見つけられます。次章では、実際に採用代行・採用支援を導入してから成果を得るまでの具体的なステップを解説していきます。
採用代行・採用支援導入から成果までのステップ
導入前の準備
サービスを導入する前に欠かせないのが、自院の現状把握と課題整理です。どの業務を外部に委託すべきかを見極めるためには、まず「現状の採用活動でどこに滞りがあるか」を明確にする必要があります。
たとえば、「求人票を出しても応募が来ない」のか、「応募はあるが面接に進まない」のか、「採用できてもすぐ辞めてしまう」のか。課題の所在によって依頼すべき範囲は異なります。応募者対応に手が回らないなら業務代行、応募自体が少ないなら採用支援による戦略見直しが必要になります。
ここで重要なのは、単に「人が足りない」という表現ではなく、具体的な状況を数字で把握することです。応募数、面接数、内定率、定着率といったデータを整理しておくことで、外部事業者にも課題を正確に伝えられます。結果として、無駄のない支援につながります。
準備段階で院内のスタッフと共有することも大切です。「なぜ採用代行を導入するのか」「なぜ採用支援を導入するのか」を現場が理解していないと、協力が得られずに情報提供が滞り、効果が出にくくなります。導入前の合意形成と課題の可視化こそ、成功の第一歩です。
導入プロセス
導入が決まれば、実際のプロセスに入ります。基本的な流れは、求人票の作成から始まり、具体的な実務と進みます。
まず求人票作成です。ここでは単なる業務内容の羅列ではなく、自院の魅力や働くメリットを明確に打ち出すことが必要です。採用代行・採用支援事業者は、これまでの成功事例や市場動向を踏まえて、ターゲットとなる看護師や医療事務に響く言葉を選びます。これにより、従来は応募に至らなかった層からも反応が得られる可能性が高まります。
次に候補者集客です。求人媒体でのスカウト活動、SNSなど複数のチャネルを活用し、ターゲット層に届く形で求人や情報を発信します。特に最近では、InstagramなどのSNSを活用した情報発信も効果を上げています。支援事業者はその運用ノウハウを持っているため、クリニック単独では難しい広がりを生み出せます。
そして面接調整です。応募者との連絡が遅れると、他院に先に決められてしまうリスクが高まります。採用代行では、この部分を迅速かつ丁寧に行い、応募から面接までのタイムラグを最小限に抑えます。これにより候補者の離脱を防ぎ、採用成功率を高められます。
成果測定と改善
サービスを導入したら、それが本当に効果を上げているのかを測定する必要があります。ここで注目すべき指標は大きく3つです。
1つ目は歩留まり率です。応募から面接、内定、入職に至る各段階でどれだけ候補者が残っているかを数値化することで、どの工程に課題があるかが見えてきます。
2つ目は定着率です。採用してもすぐ辞めてしまっては意味がありません。半年や1年といった区切りで定着している割合を測定し、求人票の内容や採用時の説明が実態と一致しているかを検証します。
3つ目は採用単価です。1人の採用にかかった総コストを算出し、過去と比べて改善しているかを確認します。サービスを導入することで短期的には費用が増える場合もありますが、定着率が改善すれば結果的にコスト削減につながります。
ここで気をつけるべきことは、代行会社の場合、業務の代行を目的にしており、分析を行わないところもあるので注意しましょう。このように指標を設けて定期的に改善サイクルを回すことで、業務軽減ではなく「成果を生み出す投資」へと変わります。
まとめ|クリニックの採用を成功に導くために
採用代行・支援を正しく使い分ける重要性
これまで見てきたように、採用代行と採用支援は同じ「外部サービス」であっても、その役割と効果は大きく異なります。クリニックが採用において成果を出すためには、この違いを正しく理解し、状況に応じて使い分けることが不可欠です。
採用代行は「戦略はあるが業務を軽減したい」場合に適しています。応募者対応や面接調整といった日常業務はスピードが命ですが、院長や事務長が多忙で手が回らないケースは少なくありません。ここを外部に委託することで、候補者の離脱を防ぎ、戦略を確実に実行できます。
採用支援は「戦略から見直しつつ業務も減らしたい」場合に力を発揮します。ペルソナ設定を行い、自院に合う人材像を明確化することで、従来の「来た人を採用する」姿勢から脱却し、「自院に合う人を選べる」採用へシフトできます。長期的な定着を重視するなら、この体制づくりは欠かせません。
つまり、採用代行は実務の抜け漏れを補う「短期的な加速装置」、採用支援は採用戦略そのものを刷新する「中長期的な基盤づくり」と位置づけられます。クリニックが直面している課題がどちらに近いのかを見極めることが、失敗しないための第一歩です。
看護師・医療事務採用で失敗しないためのポイント整理
クリニックの採用が難航する理由は、看護師・医療事務それぞれに異なる要素がありますが、共通して意識すべきポイントがあります。
まず、求人票の内容と現場の実態を一致させることです。応募者が「思っていた働き方と違う」と感じる瞬間に、早期離職のリスクが高まります。現場スタッフの声を反映した表現にすることで、採用後のギャップを最小限に抑えられます。
次に、候補者対応のスピードと丁寧さです。看護師は有効求人倍率が高く、医療事務は他業種と競合します。どちらも候補者が複数の選択肢を持っているため、レスポンスの速さと安心感のあるやり取りが採用成否を分けます。
さらに、ペルソナに沿った採用活動の重要性です。採用支援を通じて「どんな人に応募してほしいか」を明確にすれば、応募数を追うのではなく、自院に合う人材の獲得につながります。結果として、採用コストの無駄を減らし、定着率を上げることができます。
失敗しない採用は「人を集める」ことではなく、「合う人を選ぶ」ことに尽きます。そのために代行と支援をどう活用するかが、クリニックの未来を左右するのです。
看護師・医療事務の採用に困ったらHOAPへの相談
採用課題を自院だけで抱え込むと、時間も労力もかかり、解決の糸口が見えなくなることがあります。そんなときは、医療業界に特化した採用支援を提供するHOAPへの相談を検討するのも一つの方法です。
HOAPは「戦略を一緒に考えること」と「業務をまるっと支援し診療に集中すること」を両立させる支援スタイルをとっています。ペルソナ設定を通じて、自院に合う人材を明確にし、応募者対応や求人票の改善までを伴走します。その結果、応募数を追いかけるのではなく、長く働いてくれる人材を選べる体制が整います。
相談のハードルは高くありません。「応募が集まらない」「人が辞めてしまう」といった現状を率直に共有すれば、課題の整理から始められます。具体的な改善策を一緒に検討し、必要に応じて業務代行を組み合わせることも可能です。
まずは「自院の採用にどんな課題があるのか」を知るところから始めましょう。その第一歩として、HOAPに相談し、外部の視点を取り入れることが、採用成功への近道になります。
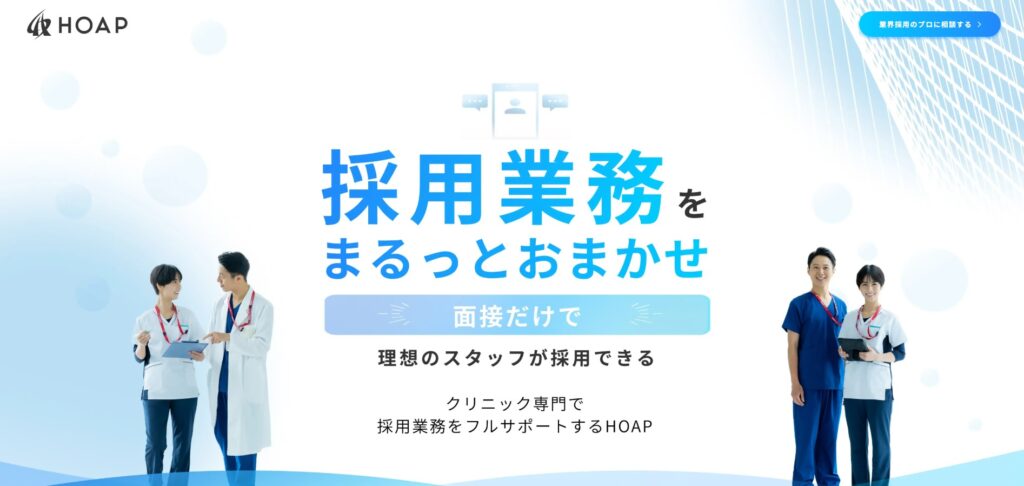
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。