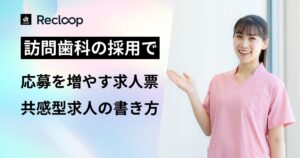「診療が忙しくて、なかなか採用にまで手が回らない」「求人を出しても応募が来ず、改善の打ち手も見えない」——こうした声は、歯科クリニックの現場で頻繁に聞かれるものです。採用の重要性は理解していても、日々の診療やスタッフ対応に追われ、つい後回しにされがちなのが現実です。
さらに、採用に関する情報は複雑化しています。媒体選定、求人原稿の作成、スカウト対応、面接調整……やるべきことは多岐にわたりますが、専任の採用担当を雇うほどの規模ではない、という医院も多いでしょう。そんな中、最近注目されているのが「採用業務をフリーランスや外部の専門家に委託する」という選択肢です。
一見すると合理的な解決策に思えるこの方法ですが、実際には「うまくいくケース」と「成果につながらないケース」がはっきり分かれています。特に歯科業界のような専門職採用では、その傾向が顕著です。委託にかかる費用や成果の不確実性、外部担当者の知識不足など、慎重な判断が求められます。
本記事では、歯科クリニックが採用をフリーランスや外部の専門家に業務委託する際のメリットとデメリットを具体的に整理し、成果を出すために必要な「見るべきポイント」について考えていきます。
歯科医院で採用業務の外注化が急増している4つの背景

歯科医院で完結できない採用業務の現実的な課題
歯科医院の現場では、「診療に追われて採用どころではない」という声が後を絶ちません。限られたスタッフ数で日々の診療・事務・雑務をまわす中、採用活動は「重要だが緊急ではない」領域として後回しにされがちです。しかし、必要な人材が確保できなければ、既存スタッフへの負担は増え、さらなる退職リスクにつながるという悪循環を招きます。
院長や事務長が「採用担当」を兼任するケースも少なくありませんが、応募者対応に手が回らなかったり、媒体掲載の更新が滞ってしまったりと、採用機会を逸しているケースも多く見られます。人手不足の中で現場をまわすことに意識が集中しすぎると、「そもそも人を増やすための動き」が後手に回ってしまうのです。
求人媒体・SNS運用の複雑化と専門性の必要性
一昔前は「求人サイトに掲載して待つ」スタイルでも一定の応募が見込めました。しかし現在では、求人市場が飽和し、競合も多様化しています。単に募集をかけるだけではなく、SNSでのブランディング発信や、採用LP(ランディングページ)の整備、スカウトメールの活用など、「攻めの採用」が必要とされる時代になっています。
さらに、求職者が職場の雰囲気や人間関係を重視する傾向も強まり、応募前の段階で「この職場なら大丈夫そう」と思わせる情報が不可欠になっています。これは単なる求人出稿とは異なる領域であり、情報発信のプロフェッショナルとしての視点が求められるフェーズです。
このように採用活動が多面的かつ戦略的になっている今、「片手間では到底カバーしきれない」ことが、採用外注を検討する理由のひとつになっています。

専任採用担当を雇えない中小歯科医院のジレンマ
本来であれば、こうした業務には採用のプロを常勤で配置するのが理想です。しかし、常勤1名の人件費(年間400万〜500万円程度)を支出する余裕のある歯科医院は多くありません。繁忙期以外は業務が少なくなる可能性があるため、フルタイム雇用の投資判断が難しいという現実もあります。
このような状況下で、必要なタイミング・必要な業務だけを外部に委託するという「部分外注」や「プロジェクト単位での依頼」が注目されるようになっています。特に採用分野に詳しいフリーランスや、小規模な採用支援会社の存在が、歯科業界でも徐々に知られるようになってきました。
地方・個人経営クリニックでの深刻な人材不足
採用難の傾向は都市部に限らず、むしろ地方の小規模医院でより深刻化しています。新卒採用が困難な地域では、転職市場に頼らざるを得ず、限られた応募者の中でいかに魅力的に見せるかが問われます。このような地域では、求人広告を出しても反応がない、という事態が日常的に起こっており、自院の情報発信力を底上げする外部支援の必要性が高まっています。
さらに、地方では「人を雇いたくても、教えられる人がいない」という課題もあります。経験者の採用が前提となる中で、採用要件の精度を上げる必要があり、そのための採用戦略策定においても外部の知見が求められます。
採用プロセスを仕組み化する必要性の高まり
採用を外注化する動きの根底には、「属人的な採用から脱却したい」という問題意識があります。院長が頑張っても結果が出ない、事務長が退職してしまうとノウハウが途絶える——そうした人任せの限界を痛感した医院が、「採用の仕組みそのものを外部と一緒に整える」という方向にシフトしているのです。
この流れの中で、フリーランスや外部の採用パートナーを活用する動きが、今後さらに一般化していくと考えられます。
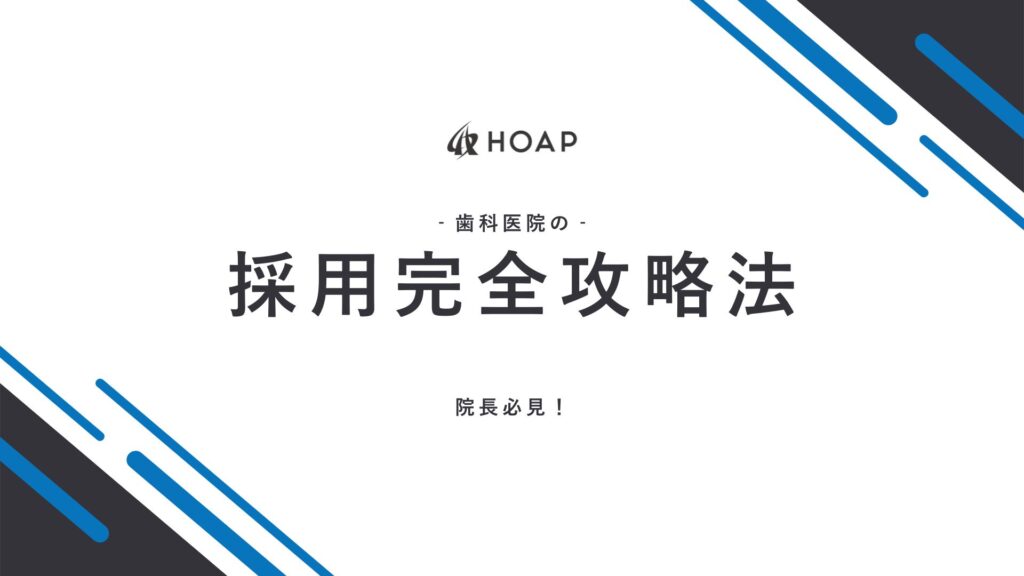
本資料では歯科医院の採用を成功させる採用戦略の立て方から、実際の成功手法について解説しています。
歯科クリニックが採用をフリーランスに委託する3つのメリット

院長が診療と経営に集中できる環境の構築
最も大きな利点は、院長が本来の役割である診療・マネジメントに専念できる点です。採用は労力も時間もかかる業務です。媒体選定、原稿作成、スカウト対応、応募者対応、日程調整、面接評価、採否連絡……これらをすべて一人でこなすには無理があります。
特に採用市場が活発な時期は、求人を出してから1日以内に初動対応しないと応募者の離脱につながるため、即応性が求められます。フリーランスの採用担当であれば、そうしたスピード感ある対応が可能になり、採用のチャンスを取り逃がすことが減少します。
また、採用に関する提案や媒体との交渉、効果検証も代行できるため、院内の負担は大幅に軽減され、より高い次元で経営判断に集中できる環境が整います。
採用専門人材を社員化せずコスト効率よく活用
採用を正社員として抱えることには、採用ボリュームの波に対応しきれないという問題があります。年間を通じてコンスタントに募集する必要がない歯科医院では、常時雇用しておくのはコスト過多になる可能性が高く、「忙しい時期にだけスポットで支援してもらえる」フリーランスの存在は非常に有効です。
特に、月数万円〜十数万円程度の業務委託契約であれば、採用1名あたりに換算してもコストパフォーマンスは高く、無駄な固定費をかけずに済むというメリットがあります。
また、業務委託契約であれば社会保険や福利厚生といった間接コストも不要です。実働ベースで報酬が発生する仕組みにすれば、「使った分だけ支払う」形での合理的な運用が可能となります。
求職者に合わせた柔軟な時間帯での対応が可能
フリーランスの採用担当者は、多くの場合フレックスタイム制で働いており、夜間や土日の応募対応にも対応できるケースがあります。これは歯科クリニックにとって大きな利点です。というのも、求職者の多くは現職中のため、日中の連絡が取りにくく、夜間や週末にようやく連絡できるというケースが多いからです。
社員担当者の場合、終業後の対応が難しいため、返信が翌日以降になってしまいがちですが、フリーランスであれば「求職者の動きに合わせた時間軸」で採用活動を進めることができます。この柔軟性が応募者の離脱防止や、意思決定の後押しにつながるのです。
また、フリーランスは契約上「成果」で評価される傾向が強く、受け身ではなく自走型で提案してくる担当者が多いことも特長です。求人原稿の改善提案、スカウト文面の最適化、応募率や面接率の数値管理など、「やりっぱなし」ではなく「改善しながら進める」スタンスを持った人材であれば、内部スタッフ以上に成果を出すこともあります。
小さな医院こそ「業務委託」で機動力を高める
歯科医院は、その規模からして人員配置に余裕があるケースは稀です。だからこそ、すべてを内部で抱えるのではなく、専門性のある外部リソースを「使いどころを見極めて取り入れる」ことが、採用力の底上げに直結します。
院長が直接応募者と向き合うことで魅力を伝えられる部分と、フリーランスが担うべき実務部分を切り分けることで、医院全体としてのパフォーマンスが最適化されていく
——この考え方が、今後の歯科クリニック経営に求められる視点といえるでしょう。
採用外注で失敗するデメリットと注意すべき5つのリスク

歯科業界知識不足による表面的対応のリスク
採用を外部に委託する最大の落とし穴は、「業界への理解度」が不足していることによるミスマッチです。歯科業界は医療系専門職の中でも独自性が強く、例えば歯科衛生士と歯科助手の役割の違いや、保険診療と自費診療の比率、勤務形態の慣習など、業界特有の事情を正確に把握していないと、的外れな提案や誤解を招く求人になりかねません。
応募者に対して「専門的な現場説明ができない」「医院の魅力をうまく伝えられない」といった状況では、せっかく応募が来ても辞退される確率が上がります。また、職種ごとの希望条件(勤務日数や担当業務の明確化など)を把握せずにスカウトを打つと、応募以前に「不信感」を与えてしまい、逆効果になることもあります。
「採用のプロ=どの業界でも通用する」とは限らないのが、歯科業界の難しさです。フリーランスであっても、業界理解や職種理解があるかどうか、またその中でどんな成果を出してきたかの確認は必須です。
業務委託契約特有の責任範囲の曖昧さ
業務委託契約では、成果に対して明確な責任を問うことが難しいケースがあります。例えば、「求人媒体への掲載作業はやったが、応募がなかった」「スカウト配信は実施したが、反応が悪かった」といった状況でも、業務自体は遂行されているため、契約上は問題なしとされてしまうことがあります。
これが、社員や院内スタッフと異なる点です。内部担当であれば「どうすれば改善できるか」と一緒に考える姿勢が期待できますが、外注の場合、「そこまでの責任は契約に含まれていない」というスタンスを取られることもあります。つまり、成果への温度差が生まれやすいのです。
この点を見誤ると、「採用は任せたはずなのに、成果が出ない」「こちらの期待と動き方が合わない」といった不満が募る原因になります。
フリーランス特有の継続性とコミュニケーションリスク
フリーランスとの契約において、もう一つ懸念されるのが「継続性」のリスクです。業務に慣れてきた頃に連絡が取れなくなった、繁忙期に他案件を優先されて放置された、急に辞退された——こうしたトラブルが起こる可能性があります。
特に個人フリーランスの場合、体調や家庭の都合によって稼働できなくなることもあり、業務の安定供給が難しいという側面があります。また、副業で活動しているフリーランスでは、稼働時間が限定されていたり、急な対応に柔軟さを欠くこともあるため、初期段階でのヒアリングや契約内容の明文化が重要です。
「飛ばれるリスク」をゼロにすることはできませんが、事前に「緊急時の連絡手段」や「業務のバックアップ体制」を確認しておくことが、トラブル回避の鍵になります。
成果の見えにくさと評価の難しさ
採用という業務は、「やったか/やっていないか」よりも、「成果が出たか/出ていないか」で評価されるべき分野です。にもかかわらず、業務委託では「実行した事実」だけで満足されてしまうことがあり、経営側が「何をどう判断すればいいのか分からない」という状況に陥ることがあります。
これを防ぐには、KPI(重要指標)をあらかじめ設定しておくことが有効です。たとえば、
・月間応募数の目標
・スカウト配信後の返信率
・面接設定率・辞退率の推移
・求人原稿改善の提案頻度
やミーティングの頻度などを契約前に明示しておくことで、取り組みの進捗や成果を定量的に評価しやすくなります。こうした可視化の努力を怠ると、「どこまで責任を持って動いてくれているのか分からない」という不透明感に直結してしまいます。
信頼関係構築の重要性と注意点
結局のところ、フリーランスや外部業者との関係性は、「どれだけ本気で向き合ってくれるか」に尽きます。契約書の有無や単価以上に、コミュニケーションの密度や、採用を「自分ごと」として動いてくれるかどうかが、成否を分ける最大の要因です。
そのためには、
「まずは小さく始める」
「初期段階でのすり合わせを丁寧に行う」
「定例ミーティングなどを通じて状況を共有する」
といった基本動作を丁寧に行うことが、リスク回避と成果創出の両面において不可欠です。
採用委託で成果を出すための外注先選定5つのポイント

成果を出せる担当者と単純作業者の見分け方
採用を外部委託する際、最も重要なポイントは「誰に依頼するか」です。同じように「採用代行」をうたっていても、動き方や関与の深さは大きく異なります。極端な例では、求人原稿を媒体に掲載するだけで終わり、応募がなければ「媒体が悪いですね」と片づけてしまうケースもあります。
こうした作業請負型の外注先では、採用戦略の改善提案や、応募者対応の工夫、院内体制のアドバイスなどに踏み込んだ支援は期待できません。一方で、採用全体の成果を見据え、自ら課題を見つけて提案し、伴走するタイプの支援者も存在します。
この違いを見極めるには、事前のやり取りの中で
「こちらの話をどれだけ深く理解しようとしているか」
「課題に対して具体的な提案があるか」
「成果に責任を持とうとしているか」
を観察することが有効です。単に「やりますよ」と応じるだけでなく、「何のために」「どうやってやるか」まで言語化できるかが、判断基準になります。
実績数字よりも重要な背景説明の説得力
支援者を選ぶ際、「過去の実績」は一つの指標になりますが、それだけでは不十分です。
というストーリーが説明できるかどうかを確認する必要があります。
例えば「月5件の応募が取れました」という数字だけでは、業界背景や難易度が分かりません。むしろ、「その医院ではなぜ応募が来なかったのか」「何を変えたことで反応が改善したのか」といった因果関係を論理的に語れる支援者の方が、信頼性は高くなります。
数字の裏側にある考え方・着眼点こそが、その人の力量を示す要素です。単なる実績アピールではなく、「なぜそうしたのか」というプロセスを語れる相手を選びましょう。
委託業務範囲と期待値の明確なすり合わせ方法
業務委託契約では、どこまでを依頼し、どこからを医院側が担うのか、その境界線を明確にする必要があります。「求人作成〜応募者対応」までか、「スカウト送付〜面接調整」までか、「採用戦略の策定から関与してもらう」のか。業務範囲を明確に定めないまま契約すると、「そこまではやってくれないのか」といった認識齟齬が生じやすくなります。
特に、「応募は来たけれど、面接が決まらない」「面接をしても辞退が多い」といったプロセス全体の最適化を目指す場合は、部分業務の切り出しではなく「採用全体の伴走」ができる相手を選ぶことが効果的です。
期待する成果が“採用人数の達成”である場合、単なる作業外注ではなく、戦略的支援にコミットできるパートナーが必要です。
契約形態と報酬設定で失敗しないための注意点
フリーランスや外注先との契約形態には、主に「固定報酬型」と「成果報酬型」があります。どちらにも一長一短があり、目的や支援範囲に応じて選択すべきです。
固定報酬型:月額◯万円で特定の業務を継続して依頼する形。業務量の安定性がある一方で、成果が出なかった場合の不満が残ることも。
成果報酬型:採用決定時に1名あたり◯万円を支払う形。短期的には成果志向になりやすいが、長期的な改善や戦略的提案には向かない傾向も。
また、「成果報酬」といっても、応募者対応や辞退フォローの有無など、対応範囲に違いがあるため、契約前に「成果の定義」と「支援範囲」を明文化しておくことが重要です。
「思っていたより何もしてくれなかった」という事態を避けるには、契約書に業務内容とアウトプット項目(例:週1回の報告、スカウト文面の作成、数値指標のレポート)を明記しておくべきです。
最終判断は対話力と思考の深さで決める
最後に強調したいのは、採用を委託する際に最も頼りになるのは「この人となら考えながら前に進めそう」と思えるかどうかです。表面的なやり取りではなく、背景まで掘り下げて質問してくれる相手、思考のズレを放置せずに言語化しようとする相手こそ、信頼できるパートナーになり得ます。
提案資料や料金表だけでは見抜けない部分だからこそ、最初の打ち合わせや面談でのやり取りを通じて、“話していて納得感があるか”“違和感を指摘してくれるか”という視点で判断していくことが重要です。
歯科採用に強い専門法人を選ぶべき理由と見分け方

属人化リスクを回避する法人体制のメリット
フリーランスに採用を任せる際、しばしば問題になるのが「属人化による不安定さ」です。たとえば、あるフリーランス担当者に依存していた場合、その人が突然稼働できなくなったりすれば、採用業務自体がストップする可能性があります。
これに対し、採用支援を専門とする法人であれば、複数名の体制で業務を遂行するため、担当者の交代やリソース不足にも柔軟に対応できます。特定の個人に頼るのではなく「チームとして継続的に動いてもらえる」安心感は、長期的な採用力強化を目指す上で大きな利点です。
また、法人は業務内容や成果物の品質を「社内基準」として定めていることが多く、支援の一貫性やクオリティが保たれやすい点も見逃せません。特定の担当者のスキルに依存することなく、一定の水準での支援を継続できるという点で、歯科医院にとっては“業務の仕組み化”にもつながる選択肢です。
医療・歯科領域に特化した専門知見の価値
採用支援の専門法人は、歯科業界を含む医療領域に特化しているケースも多くあります。こうした法人は、過去に多数のクリニック・医院と関わってきた実績があり、医療職特有の採用要件や業界動向に通じています。
例えば、歯科衛生士が応募を検討する際に重視するポイント(教育体制・担当制の有無・診療スタイルなど)、歯科助手志望者の志向(キャリアパスの明確さ・勤務時間帯の柔軟さなど)など、実務レベルでの情報を熟知しているため、求人原稿の内容やトーンも的確にチューニングできます。
さらに、他院でうまくいった事例や、失敗したケースから得た学びを汎用化し、横展開できる点も法人の強みです。これは、1医院の枠にとどまらず「歯科業界全体の動向を踏まえて提案できる」ことを意味しており、単発の採用活動ではなく、中長期的な採用戦略を描く上でも有益です。
以下記事はクリニック向けの内容となっておりますが、歯科医院でも活用できる内容となっております。是非一読ください。

業務透明性と契約上の信頼性の確保
法人との契約には、「万が一」のリスクを軽減できるという側面もあります。たとえば、
といったフリーランスにありがちなトラブルも、法人であれば責任の所在が明確なため、安心して任せることができます。
また、法人は社会的信用やコンプライアンスにも配慮しているため、個人事業者と比較して契約・業務管理が体系化されていることが多いです。業務内容の合意、成果物の納品、定例報告の実施、個人情報の管理など、安心してやり取りできる体制が整っている点は、特に医療機関にとって重要な判断材料となります。
さらに、万が一問題が発生した場合でも、法人であれば交渉窓口や相談先が明確であり、トラブルの際の対処もスムーズです。
専門法人では、多くの場合、採用活動を「やりっぱなし」にせず、改善サイクル(PDCA)を意識した支援が組み込まれています。たとえば、月次での効果測定や、応募者データの分析、改善ポイントのフィードバックなど、医院側では手が回らない部分をカバーしながら、採用力の底上げを図ってくれます。
「この原稿はどこで離脱が起きているか」「スカウトの反応率が下がった理由は何か」といった視点での提案があるかどうかは、単なる業務代行と、本質的な支援の違いを分けるポイントです。
法人には、そうした提案力のある担当者を育成する仕組みもあり、支援の質が属人的にならない工夫がされています。結果的に、医院にとっては「頼んで終わり」ではなく、「一緒に採用力を育てていく」パートナーとしての関係が築きやすくなります。
継続的な改善サイクル(PDCA)の組み込み
フリーランスと法人、どちらが優れているという単純な話ではありません。ただ、医療機関としての責任や患者への影響を考えたとき、「信頼性」「継続性」「専門性」という観点で法人に依頼するメリットは明らかです。
特に、採用を“一時的な作業”ではなく“医院の未来をつくる活動”と捉えるのであれば、単なる外注ではなく、「継続的に支援し続けてくれる存在」であることが重要です。結果を出すことはもちろん、その過程を見える化し、次の一手を共に考えてくれる。そうした支援ができるのは、体制を持った法人ならではの価値です。
歯科クリニックにおける採用活動は、限られた人員と時間の中で行われるため、外部委託が現実的な選択肢となりつつあります。フリーランスに任せることで診療に集中できる一方、業界知識や責任範囲の曖昧さがリスクとなる場面も少なくありません。確実に成果を求めるのであれば、歯科業界への理解と継続性のある体制を持つ“専門法人”への依頼が最適です。採用を単なる作業ではなく、医院の未来への投資として捉える視点が今、求められています。
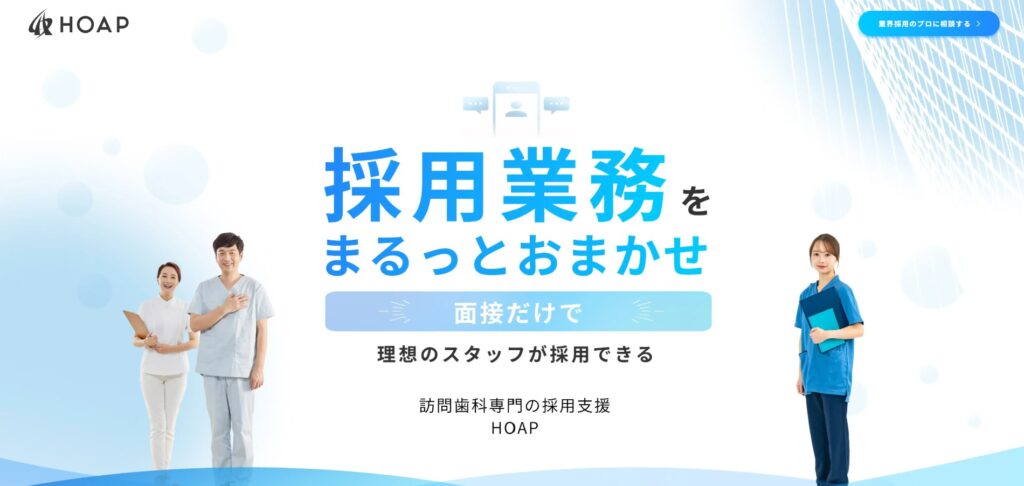
歯科医師や歯科衛生士・歯科助手などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。