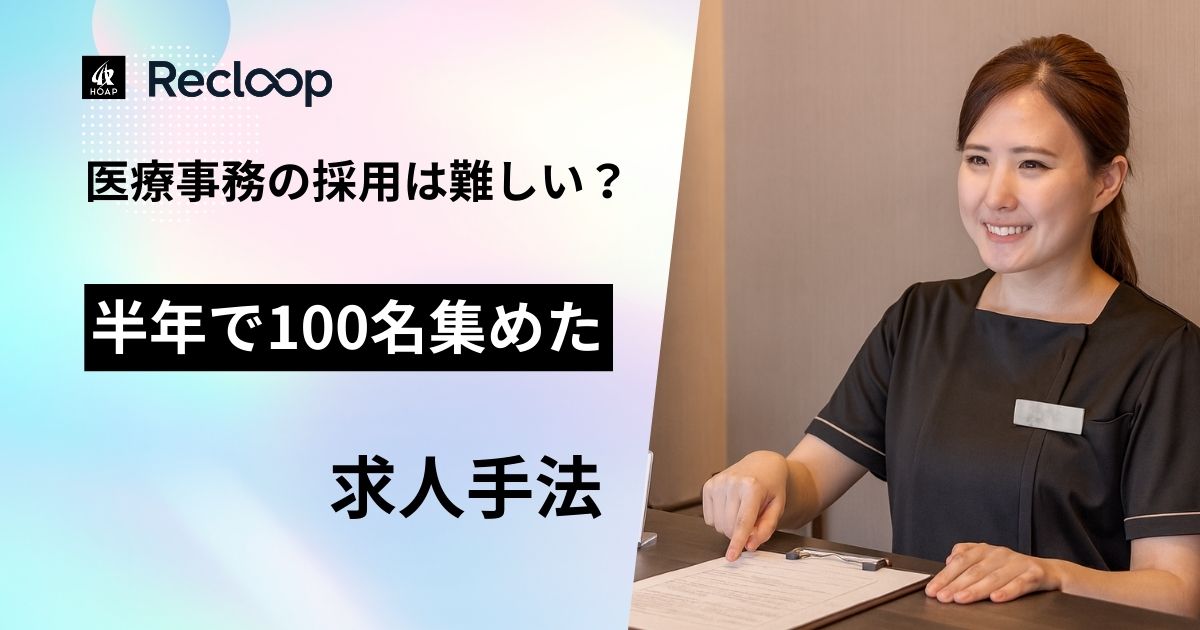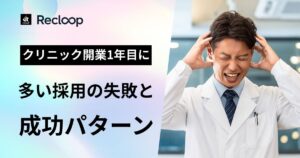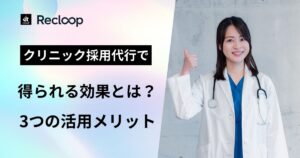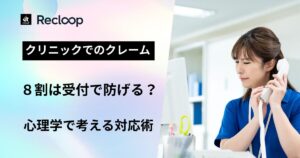医療事務の採用に苦労しているクリニックは少なくありません。「求人を出しても応募が来ない」「ようやく面接に来ても定着しない」といった声は日常的に耳にします。実際、他業種に比べて給与や条件面で優位性を打ち出しにくい職種であるため、人材不足が慢性的に続いているのが現状です。さらに求人票を見比べても、どれも似たような文言が並び、差別化が見えづらいという課題があります。その結果、求職者に「どこで働いても同じだ」と思われてしまい、応募につながらないケースが多発しています。
しかし一方で、同じ医療事務でも「半年で100名以上の応募を集めた」というクリニックが存在します。条件や待遇を大幅に改善したわけではなく、求人票の伝え方を工夫しただけで大きな成果を出したのです。鍵となったのは「差別化」と「メリット訴求」です。どのクリニックにも共通する制度や条件を並べるのではなく、「ここで働くと自分の生活がどう良くなるのか」を具体的に描写し、それを通じて共感を生んだのです。
本記事では、医療事務の採用が難しいと言われる背景を整理しつつ、成功したクリニックが実践した「求人で差別化する方法」を具体的に解説します。条件を大きく変えなくても、求人票の書き方次第で応募数は大きく変わります。次章では、なぜ医療事務の採用が難しいのか、その根本原因を順に掘り下げていきます。
なぜ「医療事務の採用は難しい」と言われるのか

応募が集まりにくい背景にある人材不足
医療事務の採用が難しいとされる大きな理由のひとつは、人材不足そのものです。医療業界全体で人材確保が困難になっており、看護師や医師だけでなく、医療事務も慢性的に不足しています。特に近年は、コロナ禍を契機に医療業界での働き方を見直す人が増え、一般事務や接客業など別業種に流れるケースも目立ちます。そのため、求人を出しても母集団形成が十分にできず、応募数が少ない状況に陥りがちです。
さらに、他業種に比べると給与面での優位性を打ち出しにくいことも要因です。例えば、大手企業の一般事務や派遣スタッフであれば同等以上の給与を提示していることも多く、医療事務をあえて選ぶ動機が弱くなっています。このような市場環境の中で、従来通りの求人票を出しても目立たず、結果として「採用は難しい」という印象が強まっているのです。
求人を出しても反応がない理由
求人を出しても応募が集まらないのは、人材不足だけが原因ではありません。実際には、求職者の心に響く表現が欠けているケースが多いのです。求人票の多くは「仕事内容」「勤務時間」「休日」「給与」といった条件面に終始し、読んだ人が「ここで働いてみたい」と感じる情報が不足しています。
特に医療事務の仕事は、業務内容がどのクリニックでも大きく変わらないため、求人票の文章だけでは違いが伝わりにくい職種です。その結果、応募者は「条件だけで比べる」傾向が強まり、給与や通勤距離で判断されやすくなります。これは採用担当者にとって非常に不利であり、「出しても反応がない」という悩みに直結しています。
どの求人も同じに見えてしまう問題
もうひとつの大きな問題は、どの求人も似たように見えてしまう点です。「明るく元気な方歓迎」「未経験でも安心の研修あり」といった表現は、多くの求人に共通して掲載されています。一見すると魅力的に思えますが、結果として差別化にならず、応募者に「結局どこで働いても同じ」という印象を与えてしまいます。
例えば、休日数や福利厚生を強調しても、それは大手病院や他業種でも提示されている一般的な条件です。こうした横並びの情報では、求職者の選択基準に食い込むことはできません。つまり「差別化要素が見えない」という状況そのものが、医療事務採用を難しくしている本質的な原因といえるのです。
母集団形成ができない典型的パターン
応募者が集まらない背景には、ターゲット設定が曖昧なまま求人を出していることも影響しています。「誰に届けたいか」が定まっていないと、文章が抽象的になり、誰にも刺さらない求人になってしまいます。
例えば、「医療事務経験者歓迎」と書けば対象は広がるように思えますが、逆に「どの経験者に来てほしいか」が伝わらなくなります。また、「子育てと両立できる職場」と打ち出すなら、実際に働いているスタッフのエピソードを添えなければリアリティが欠け、求職者にとっては魅力的に映りません。こうした抽象的な求人は、結果として応募母集団を十分に形成できず、採用難につながるのです。
この章では、医療事務の採用が難しいとされる要因を「人材不足」「求人の反応が弱い理由」「差別化の欠如」「母集団形成の失敗」という4つの角度から見てきました。次章では、そうした中でも応募を集めているクリニックと、そうでないクリニックの違いを具体的に掘り下げていきます。
応募が集まるクリニックと集まらないクリニックの違い
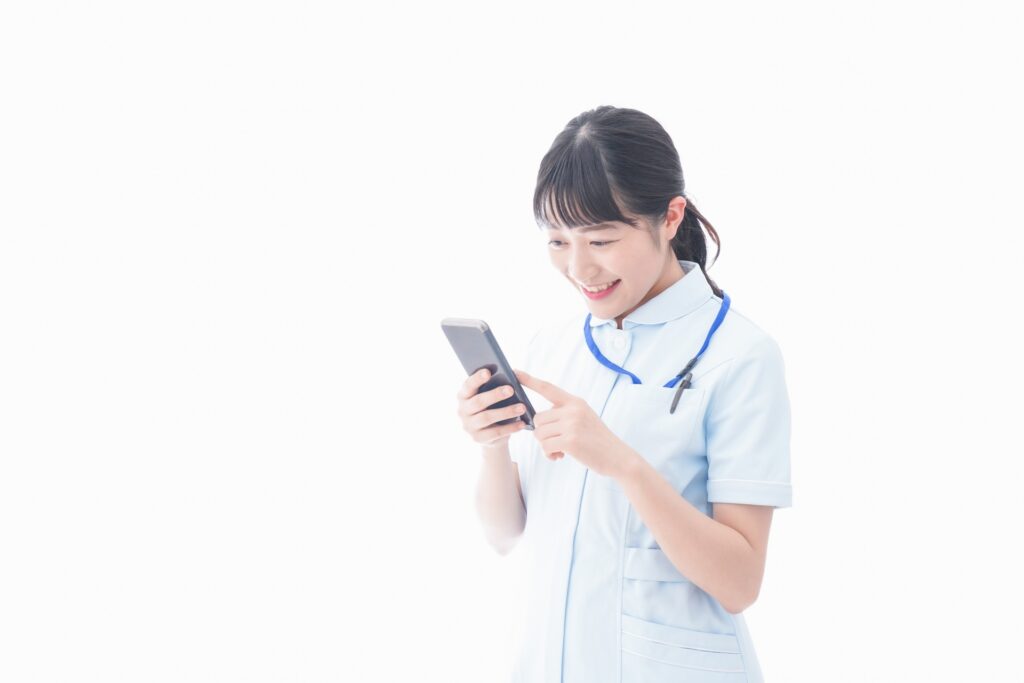
条件提示だけでは動かない求職者
医療事務の求人において、最もよく見かけるのは「勤務時間」「休日」「給与」といった条件の列挙です。しかし、条件提示だけでは応募者の行動を促す力は弱いのが現実です。理由は明確で、条件面での比較は他業種や大規模病院に劣ることが多く、求職者にとって決定打になりにくいからです。
例えば、「完全週休2日制」「社会保険完備」と書かれていても、ほとんどの職場で同様に用意されているため、特別な魅力としては映りません。結果として、「どこも似た条件なら、自宅から近い場所でいい」と判断され、応募が分散してしまいます。つまり、条件提示型求人は、求職者の比較対象を増やすだけで、応募動機を強める効果が限定的なのです。
メリットを提示し、そこに共感を生ませる
応募が集まるクリニックには共通点があります。それは「条件の羅列」ではなく、「この職場で働くメリット」を具体的に提示していることです。ポイントは、単に制度を説明するのではなく「制度がどのように生活を変えるのか」を描写している点にあります。例えば、
ではなく
と表現すると、求職者は自分の生活に置き換えてイメージできます。このように「メリット提示型」の求人は、読む人にとって具体的な未来像を描かせ、その結果として「共感」を生むのです。
つまり、共感を得るために最初から「共感型」を狙う必要はなく、まずはメリットを提示し、その内容に共感してもらうという流れが効果的なのです。
院長やスタッフの雰囲気を「見える化」する
条件や制度だけでは伝わらない魅力を補うのが、院長やスタッフの人柄や雰囲気です。クリニックに応募する求職者は、給与や休日と同じくらい「人間関係」や「働きやすさ」を重視しています。しかし、求人票の文字だけでは「ここで働く人たちがどんな人か」は想像しにくいものです。
そこで有効なのが、院長やスタッフの声を求人票に盛り込む方法です。例えば、
「スタッフ同士で相談しやすい雰囲気」
「院長が子育て世代に理解がある」
といった一文を加えるだけでも印象は大きく変わります。さらに写真やインタビューを掲載すれば、求職者は「ここで働く自分」を具体的にイメージできます。これこそが、応募を集めるクリニックが実践している”見える化”の取り組みです。
集まるクリニックと集まらないクリニックの分岐点
まとめると、応募が集まるかどうかの分岐点は「求人票に求職者視点を取り入れられているかどうか」にあります。条件提示型では、他院と比較されて埋もれてしまいます。一方で、メリット提示型であれば「ここなら自分の望む生活が叶う」と感じてもらえます。さらに院長やスタッフの人柄を伝えられれば、応募者は安心感を持ち、応募のハードルが下がります。
実際に応募が集まっているクリニックは、「給与や制度は他院と同程度」であっても、求人票の書き方を工夫することで成果を出しています。つまり、採用難とされる医療事務でも、伝え方次第で十分に応募を集められるのです。
ここでは「条件提示型」と「メリット提示型」の違い、そして「院長やスタッフの雰囲気の見える化」が応募数に直結することを整理しました。次章では、実際に半年で100名以上を集めたクリニックの事例をもとに、そのポイントをさらに深掘りしていきます。
半年で100名以上を集めた事例から見えたポイント

応募が殺到した求人票の特徴
半年で100名以上の応募を集めたクリニックの求人票には、いくつかの共通した特徴が見られます。まず大きな違いは、条件面をただ並べるのではなく「この職場で働いているイメージ」を描いている点です。
例えば「完全週休2日制」と記載するのと同時に、
を伝えています。これは単なる条件提示ではなく、働く未来を想像させる情報であり、応募者の行動を後押しします。
また、スタッフの声を積極的に取り入れ、リアルな体験談を求人票に反映させている点も特徴的です。「前職では休みが取りづらく、子どもの行事に参加できなかったが、今は安心して休める」といったエピソードは、数字や制度説明よりも強い説得力を持ちます。こうした描写が「ここでなら働きたい」という気持ちを引き出す原動力となっているのです。
差別化を実現する「メリット訴求」の力
応募が殺到した最大の要因は「メリット訴求」による差別化でした。他の求人票が条件の羅列に終始する中、このクリニックは「うちで働くと、どんな暮らしが実現できるか」という点を前面に押し出しました。
たとえば「残業が少ない」という条件を、そのまま書くだけでは他院との差は出ません。ところが
と書けば、読んだ人は自分の生活に置き換えてイメージできます。これは数字以上に強力な差別化要素になります。
「給与」「休日」「福利厚生」などの条件は横並びになりやすいからこそ、それらを「生活への影響」に変換することが差別化の鍵です。メリット訴求とは、制度や条件そのものではなく、それを通じて得られる未来を提示する発想なのです。
「働くとどう変わるか」を描写する求人票
成功したクリニックの求人票は、一貫して「働くとどう生活が変わるのか」を描いていました。これは求職者にとって、最もイメージしやすく、また行動につながりやすいポイントです。
例えば、「有給休暇取得率100%」と数字で書くのではなく、
と具体的に描写しています。これにより、数字に弱い求職者にも直感的に理解されやすくなります。
また「新人研修あり」ではなく、「入職初日は院長が直接オリエンテーションを行い、その後は先輩スタッフが1対1でサポートする」といった流れを明示することで、不安を持つ求職者が「ここなら安心して始められる」と思えるのです。条件を数字や制度名で示すのではなく、生活や働き方の変化として描写することが、応募数増加に直結した要因でした。
応募が集まる求人票に共通する要素
ここまでの成功事例を総合すると、応募を集める求人票には次のような要素が共通していました。
・未来像を提示:「この職場で働くと、こういう生活になる」という具体的な絵を描いている。
・リアルな声を反映:スタッフや院長の言葉を直接盛り込み、求職者の不安を解消している。
・数字より実感を重視:制度や条件を数字で示すだけでなく、そのおかげで得られる実体験を伝えている。
・差別化要素を前面に:同じ条件を掲示していても、表現次第で「ここにしかない魅力」として伝えている。
半年で100名以上を集めたクリニックの成果は、特別な給与や福利厚生によって生まれたものではありません。求人票の「見せ方」と「伝え方」を工夫しただけで、これほどの結果が出せることを示した好例です。
この章では、応募が殺到したクリニックの事例から「メリット訴求の力」と「生活を描写する求人票の重要性」を整理しました。次章では、クリニックが明日から実践できる具体的な改善アクションについて整理します。
明日から取り入れられる求人改善の具体行動

魅力を一瞬で伝えるキャッチコピーの工夫
求人票において最初に読まれるのはキャッチコピーです。ここで求職者の関心を引けなければ、その後の文章を読んでもらうことは難しくなります。よくある「スタッフ募集中」「医療事務経験者歓迎」といった表現は無難ですが、差別化要素を欠いており印象に残りません。
応募を集めているクリニックは、この一文に生活者視点を取り入れています。例えば
といった具合に、求職者が「これは自分のことだ」と感じるフレーズを前面に出しています。キャッチコピーは条件の羅列ではなく、未来像を端的に表現する場として活用するのが効果的です。
スタッフエピソードを簡単に集める仕組み化
求人票の説得力を高めるためには、スタッフのリアルな声が欠かせません。しかし「忙しくて取材の時間が取れない」という課題は現場あるあるです。そこでおすすめなのが、エピソード収集を簡単に仕組み化する方法です。具体的には、毎月のミーティングで
「最近ありがたかったこと」
「入職してよかったと思った瞬間」
を一言ずつ出してもらい、記録しておくこと。これをそのまま求人票や採用広報に活用すれば、自然で信頼性の高い文章が生まれます。長時間のインタビューを設定する必要もなく、スタッフにとっても負担が少ない形でエピソードが集められるのです。
制度紹介を「生活の実感」に書き換える
求人票では「研修制度あり」「福利厚生あり」といった制度説明が多く見られますが、これだけでは具体的な魅力が伝わりません。改善策は、制度を「求職者にどう役立つか」に書き換えることです。
例えば「新人研修あり」を「入職初日は院長が直接オリエンテーションを行い、その後は先輩スタッフがマンツーマンで半年間サポート」とすれば、不安を抱える応募者に安心感を与えられます。また「産休育休制度あり」を「2年前に産休に入ったスタッフが、今も時短勤務で子育てと両立している」と表現すれば、制度の実効性が伝わります。制度を生活の実感に変換することで、求職者に「ここなら自分もやっていけそう」と思わせることができるのです。
忙しい院長は採用業務を外注する選択肢も
ここまで改善策を挙げてきましたが、「実際に時間をかけて求人票を工夫するのは難しい」と感じる院長も少なくありません。日々の診療で忙しく、採用活動に割ける時間は限られているのが現実です。その場合、採用業務を外部に委託するのも有効な手段です。
外部の専門家に求人票の作成や採用広報を任せることで、院長は診療に集中できます。採用は事業を継続するために欠かせない要素ですが、院長がすべてを背負う必要はありません。「院長の仕事は採用ではなく診療にある」という視点に立ち、外注を活用することで採用力を維持しながら、現場の医療提供に集中できる体制を整えることが可能です。
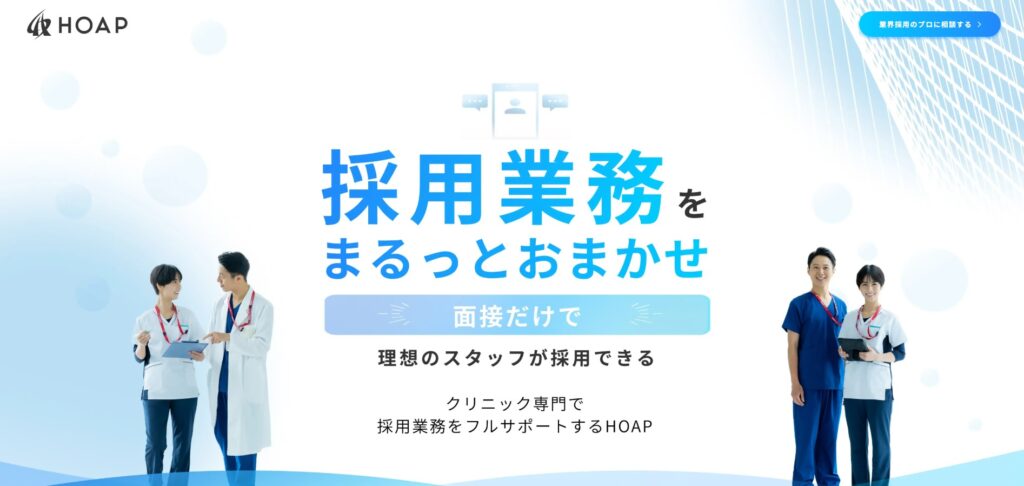
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。
ここでは「キャッチコピーの工夫」「エピソード収集の仕組み化」「制度を生活の実感に変える」「院長は外注を活用する」という具体的な改善行動を紹介しました。これらはすぐにでも取り入れられる実践的な方法であり、採用に悩むクリニックにとって有効な一歩となります。
医療事務の採用は「難しい」と言われますが、その多くは求人票が他院と差別化できていないことに原因があります。本記事で取り上げたように、半年で100名以上を集めたクリニックは、特別な待遇を用意したわけではなく、求人の伝え方を工夫しただけでした。条件を羅列するのではなく「ここで働くとどんな生活ができるか」を具体的に描写し、その内容に共感を生ませることが応募につながります。さらに、院長やスタッフの声を反映することで信頼感が高まり、応募のハードルを下げることも可能です。診療に忙しい院長であれば外注という選択肢も現実的です。採用難を前提にするのではなく、伝え方を変えることで未来を切り開けることを押さえておくことが重要です。