訪問看護の現場では、慢性的な人材不足に悩む事業所が少なくありません。とくに看護師の採用については、「求人を出しても応募が来ない」「問い合わせはあるが面接につながらない」といった声が多く聞かれます。その背景には、医療機関や介護施設との人材獲得競争が激しさを増していること、そして求職者側が「働きやすさ」や「自分に合った職場の雰囲気」を重視するようになったことがあります。
一方で、採用活動の入り口として多くの事業所が利用しているのがハローワークです。国の機関であり、利用が無料という大きなメリットがあるため、地域での求職活動では依然として重要な役割を果たしています。しかし実際には、「ハローワークに出しているのに応募がない」と感じている担当者も少なくありません。その理由は、単に掲載しているだけでは十分に求職者の目に届かず、また求人票の書き方次第で応募意欲が大きく変わるためです。
訪問看護の求人は、仕事内容がイメージしにくい点や「大変そう」という先入観があることから、他業種や病院勤務に比べて応募が集まりにくい傾向があります。だからこそ、求人票の作成に工夫を凝らし、求職者に「ここで働きたい」と感じてもらう工夫が欠かせません。実際、ハローワークの求人票には3,000字以上の自由記載欄が用意されており、書き方次第で事業所の魅力を十分に伝えることができます。
本記事では、訪問看護の採用担当者がハローワークを効果的に活用し、看護師の応募を増やすための具体的な方法を解説します。応募が集まらない理由を正しく理解し、求人票をどう工夫すればいいのか、さらにSNSや写真の活用まで含めて、実践的なポイントを順を追って紹介していきます。
なぜ「ハローワーク求人」で応募が集まらないのか?

求人票が「非公開」になってしまう掲載停止の罠
「ハローワークに求人を出しているのに応募が全然ない」と悩む訪問看護の採用担当者は少なくありません。その原因のひとつが、求人票の更新を怠ったことによる自動停止です。ハローワークでは求人票を3か月ごとに更新しなければならず、手続きをしないまま放置すると公開が停止されてしまいます。
現場が忙しい訪問看護事業所では、日々の運営に追われ求人管理が後回しになりがちです。その結果、「求人を出しているつもり」でも実際には非公開になり、求職者からはまったく見られない状態に陥ることがあります。これは「応募ゼロ」が続く最大の落とし穴です。
さらに、求人票は更新のたびに内容を見直すことが望ましいとされています。制度変更や勤務条件の改善、直行直帰の導入など、職場の魅力が増しているにもかかわらず、古い求人内容のままでは求職者に正しく伝わりません。定期更新を「義務」ではなく「魅力を最新化するチャンス」と捉えることが、応募数を増やす第一歩です。
求人票を継続的に公開し、最新の情報を反映させる。これを怠ると、どんなに条件の良い職場であっても求職者には届かず、「ハローワークでは人が採れない」という誤解を生んでしまいます。
「紹介状必須」がつくる高すぎる応募ハードル
もうひとつ応募が集まらない原因として大きいのが「紹介状の扱い」です。本来ハローワークの求人は、設定次第で「オンライン自主応募」が可能です。しかし、このチェックを忘れたり、求人票に「紹介状が必要」と記載されると、求職者はハローワークに来所して紹介状を受け取らなければ応募できなくなります。
現在は病院や施設で働きながら転職活動をする看護師も多く、限られた時間で求人を探しています。そんな中、「紹介状を取りに行くために平日に時間をつくらなければならない」となれば、多くの求職者が応募を諦めてしまいます。とくに子育て世代やダブルワークを検討している層にとって、紹介状の取得は非常に大きな負担です。
さらに「紹介状必須」という条件は、事業所に柔軟性がない印象を与えてしまう可能性もあります。訪問看護の魅力は本来、直行直帰や多様な働き方にあります。そのイメージと真逆の「手間が多い」入口を設定してしまうと、応募意欲を削ぐ要因になってしまうのです。
設定を確認して「紹介状不要」とすることは、応募数を左右する基本中の基本です。わずかな設定の違いが、大きな結果の差を生む典型的なポイントと言えるでしょう。
「どこも同じ」に見える求人票の問題
ハローワークの求人票はフォーマットが決まっているため、どうしても横並びに見えがちです。職種欄には28文字の余白がありますが、多くの求人はただ「看護師」とだけ記載しています。求職者からすれば、似た条件の求人が一覧に並び、どれをクリックすべきか判断できません。
そこで重要になるのが、職種欄や仕事内容欄を活用した差別化です。例えば「【18時退勤・土日休み】訪問看護師」「〈賞与3か月分・未経験歓迎〉訪問看護師」といった工夫を加えることで、「ちょっと気になる」「詳しく見てみたい」と思わせることができます。
仕事内容も同様です。「バイタルチェック、服薬管理」と羅列するだけでは病院との違いが見えず、応募につながりません。訪問件数や1日の流れ、利用者層の特徴を具体的に記載することで、「自分にできるか」「家庭と両立できるか」を想像しやすくなります。
他社と同じ情報を並べるだけでは埋もれてしまいます。訪問看護ならではの働き方や職場の雰囲気を「文字」で伝える意識が、求人票の効果を左右するのです。
訪問看護だからこその応募ハードルを理解する
訪問看護の求人が応募につながりにくい背景には、業種そのものが持つ特性もあります。病院勤務しか経験のない看護師から見ると、「一人で訪問に行くのは不安」「責任が重そう」「未経験では無理ではないか」といった心理的ハードルがあります。
この不安を軽減するには、「未経験歓迎」と書くだけでは不十分です。むしろ「誰でも簡単にできる仕事」という誤解を招き、応募意欲を下げる場合もあります。求職者が求めているのは「安心してスタートできる根拠」です。
例えば、「入職後3か月は先輩と同行訪問」「ICTシステムで24時間相談可能」「緊急対応は管理者がサポート」といった情報を具体的に記載すれば、不安を払拭できます。訪問看護ならではの働き方の魅力(直行直帰、柔軟な勤務体制)とあわせて伝えることで、「大変そう」という先入観を上書きすることができます。
訪問看護の採用では、この「不安の壁」をいかに下げられるかが最大の鍵です。求人票にその工夫がなければ、応募数は伸びないままです。

本資料ではハローワークで他社と差をつけ採用を強化するテクニックをご紹介!
応募につながる「ハローワーク求人票の書き方」

自由記載欄をフル活用する
ハローワークの求人票はフォーマットが決まっているため「差別化が難しい」と感じる採用担当者は多いですが、実際には3,244文字もの自由記載欄が用意されています。このスペースをどう活用するかで、応募数は大きく変わります。
例えば、仕事内容欄(600文字)では、単に「バイタルチェック、服薬管理」と書くだけでは病院勤務との差が分かりません。訪問看護ならではの流れや特徴を具体的に書く必要があります。「午前中は利用者宅を2~3件訪問、昼休憩後にチームミーティング、午後に2件訪問、17時半に直帰」といった一日の流れを描くと、求職者は自分の働き方を想像しやすくなります。
また、事業所からのメッセージ欄(600文字)では、管理者やスタッフの声を盛り込むと効果的です。「小さなお子さんがいるスタッフも多く、学校行事の参加に柔軟に対応しています」といった一文は、条件表だけでは伝わらない安心感を与えます。
さらに「求人に関する特記事項」欄(600文字)は、訪問看護未経験者への研修体制や同行訪問の有無などを説明する絶好の場所です。不安を払拭できる具体的情報をあらかじめ記載することで、応募意欲を高めることができます。
自由記載欄を「余白」と捉えるのではなく、「職場のリアルを伝える場」としてフル活用することが、求人票を強みに変える第一歩です。
職種欄で「クリックしたくなる」工夫を入れる
職種欄は28文字の枠しかありませんが、求人一覧画面で最も目立つ箇所です。多くの事業所が「看護師」とだけ入力していますが、これでは他求人と並んだときに違いが出ません。求職者に「この求人を詳しく見てみたい」と思わせるためには、働き方や条件を織り込んだキャッチコピーが必要です。たとえば、
・【18時退勤・土日休み】訪問看護師
・〈賞与3か月・未経験OK〉訪問看護師
といった工夫が考えられます。重要なのは「自分の希望条件に合っているかもしれない」と思わせることです。求職者は短時間で多くの求人を比較しており、最初に目にする職種欄が興味を引かなければ、そもそも詳細ページまで進んでもらえません。
訪問看護は「病院よりも家庭と両立しやすい」「夜勤がない」といった強みがあります。これを職種欄に組み込むことで、求職者にクリックしてもらえる確率が高まります。職種欄は短いからこそ、「端的に魅力を伝えるコピーライティング」が勝負になるのです。
推奨ワードを盛り込み、検索に引っかかる工夫をする
求人票の記載内容は、そのまま検索に影響します。求職者がフリーワード検索を使ったときにヒットするかどうかは、求人票に含まれる言葉次第です。そこで活用したいのが「推奨ワード」です。
ハローワーク攻略法では、応募につながりやすいワードとして次の7つが紹介されています:
・紹介状は不要です
・オンライン面接可
・スキルアップ
・キャリア継続可能
・時短正社員
たとえば、「オンライン面接可」と記載すれば、就業中の転職希望者が応募しやすくなります。「キャリア継続可能」は産休・育休からの復職を考える層に響きますし、「時短正社員」は子育て世代のニーズに直結します。
また、近年はSNSで求職活動をする人も増えているため、求人票に「詳細はインスタグラムで発信中」と書き、QRコードやURLを添えるのも効果的です。求職者は求人票だけでなく、写真や動画で雰囲気を確認して応募を決めるケースが増えているからです。
推奨ワードを戦略的に組み込むことは、単に検索対策にとどまらず、求職者に「この事業所は自分に合いそうだ」と思わせるきっかけになります。
NGワードを避け、不安を与えない求人票にする
一方で、求人票に書いてしまうと応募が減る「NGワード」も存在します。具体的には以下の6つです:
・オンライン自主応募不可
・紹介状が必要です
・事前にお問い合わせください
・未経験可!経験者優遇
・急募
・誰にでも簡単にできます!
これらの表現は、求職者に余計な不安や疑念を与えます。例えば「急募」と書くと「人がすぐ辞める職場では?」と疑われる可能性があります。「誰にでも簡単にできます!」は、一見間口を広げるようでいて、むしろ「教育してもらえないのでは」と感じさせてしまいます。
また、「未経験可!経験者優遇」という書き方は対象が曖昧で、結局誰に向けているのかが伝わりません。訪問看護の場合は「未経験でも安心して始められる理由」を具体的に書く方が効果的です。
応募者は「わずらわしい」「信用できない」と感じた瞬間に他の求人へ流れてしまいます。だからこそ、NGワードを避けるだけで応募数は確実に増えるのです。求人票は「求職者に安心感を与える文章」であるべきだと意識する必要があります。

本資料はハローワーク求人を作成する際の推奨ワード、NGワードをご紹介します。
応募者に届くハローワークでの工夫:写真・SNS・導線の構築

ハローワークで写真10枚を活用して「働く場のリアル」を見せる
ハローワークの求人票は文字情報だけではなく、最大10枚まで写真を登録できます。それぞれに30文字のコメントを付けることもできるため、単なる条件提示の場を「ビジュアルで伝える求人」に変えることが可能です。
訪問看護の場合、求職者が一番不安に感じるのは「実際の現場がどんな雰囲気なのか」という点です。そこで、スタッフの集合写真、事業所の外観や内装、ICT端末を活用している様子、研修中の場面などを掲載することで、「安心して働けそう」という印象を与えられます。
さらに、1日の流れを写真で並べるのも効果的です。例えば「朝のミーティング → 利用者宅での訪問 → 昼休憩 → チームでの情報共有 → 直帰」の順で写真を配置し、コメントで簡単に補足すれば、文字だけでは伝わりにくい働き方が直感的に理解できます。
訪問看護は「一人で働く孤独な仕事」と誤解されやすいですが、チームでサポートし合う姿を写真で示すことで、そのイメージを払拭できます。写真は「百聞は一見にしかず」の最も強力な武器です。求人票に登録できる限界まで使い切りましょう。
Instagramと連携し「日常感」を発信する
近年は、求職者が求人票だけで応募を決めることはほとんどありません。「この職場で働く自分がイメージできるか」を確かめるために、必ずといっていいほどSNSやホームページをチェックします。とりわけInstagramは、医療・介護分野の採用ブランディングで効果を発揮しています。
ハローワークの求人票には「インスタグラム」というワードを入れるだけでも検索対象になりやすくなります。さらに、写真欄にQRコードを載せてInstagramへ誘導すれば、求人票を見た求職者がスムーズにアカウントにアクセスできます。
Instagramでは、制度や条件を紹介するのではなく「制度がどう役立ったか」をストーリーとして伝えることが重要です。例えば「子どもの急な発熱時に直行直帰できて助かった」という投稿や、「育休から復帰して管理者を務めているスタッフの声」は、同じ境遇の求職者に強い共感を生みます。
求人票は「入口」、Instagramは「理解と共感を深める場」として連動させることで、応募につながる確率は格段に高まります。
応募前の不安を解消する「導線構築」
求人票を見て興味を持ったとしても、応募に至らない理由の多くは「不安の放置」です。「本当に自分にできるだろうか」「職場の雰囲気が合わなかったらどうしよう」といった疑問を解消できなければ、応募ボタンは押されません。
ここで効果を発揮するのが「応募の前に接点を持てる導線」です。ハローワークの求人票には「求人に関する特記事項」欄があり、ここに「見学のみでも可能」「LINEでカジュアル相談受付中」といった文言を入れるだけで、心理的ハードルは大きく下がります。
また、オンライン面接やZoomでの説明会を用意するのも効果的です。子育て中や現職を続けながら転職活動をする層にとって、来所せずに説明を受けられるのは大きな安心材料です。ハローワークの求人票自体に「オンライン面接可」と明記しておけば、検索にもかかりやすくなります。
訪問看護は仕事内容のイメージが持ちにくいため、「まずは見学から」という柔軟な導線を設けることは特に重要です。応募者が「とりあえず一歩踏み出せる」状況を作ることが、採用成功への近道になります。
求人票を「条件表」ではなく「プレゼン資料」にする
最後に強調したいのは、求人票を「条件の羅列」としてではなく「自社をアピールするプレゼン資料」として捉える姿勢です。給与や休日数といった条件はもちろん重要ですが、求職者が知りたいのは「ここで働くと自分の生活がどう変わるか」です。
そのため、写真やSNS連携、導線構築を総合的に組み合わせて、「ここなら安心して働けそう」「この職場でキャリアを続けたい」と感じてもらう必要があります。例えば「スタッフ全員にiPadを支給しており、訪問記録や勤怠管理はすべてデジタル化」「子育て世代が多く、学校行事はお互いにシフト調整して参加している」など、日常に根差した情報を伝えると効果的です。
また、写真10枚のうち1枚に採用サイトやInstagramのQRコードを組み込み、説明文で「詳しくはSNSでご覧ください」と案内すれば、求人票から自然に次の行動へつなげることができます。
求人票を単なる「条件通知」ではなく「共感を呼ぶプレゼン」に変えることが、訪問看護の採用で成果を出すための決定的な差になります。
訪問看護で採用を成功させるためのハローワーク施策

求人票を「まず直す」具体的チェックポイント
訪問看護での採用を前進させるために、最初に取り組むべきは求人票の見直しです。ハローワークの求人は無料で何度でも修正できるため、「一度出したら終わり」ではなく、常に改善する姿勢が大切です。
具体的なチェックポイントとして、まず「紹介状不要」の設定がされているかを確認してください。紹介状必須のままだと就業中の転職希望者の応募を大幅に逃してしまいます。また、職種欄は「看護師」だけで終わらず、「【18時退勤・土日休み】訪問看護師」といった一目で条件が分かる工夫を加えることが重要です。
次に、仕事内容欄や特記事項に「未経験者への研修体制」を必ず記載しましょう。例えば「入職後3か月は先輩と同行訪問」「ICTシステムで24時間相談可能」といった一文があるだけで、不安を抱える求職者の心理的ハードルは大きく下がります。
最後に、写真やQRコードの活用です。10枚の枠を最大限に使い、職場の雰囲気を見せると同時にInstagramや採用サイトに誘導することで、応募者が次の行動をとりやすくなります。
こうした「小さな修正」が積み重なることで、求人票は「ただの条件表」から「応募を生む資料」へと変わります。

スタッフの声を採用活動に組み込む
訪問看護の求人票に応募が集まりにくい理由のひとつは、仕事内容がイメージしにくいことです。この課題を解決する最も有効な方法が「現場スタッフの声」を盛り込むことです。
リアルなスタッフの体験談は求職者に強い共感を与えます。例えば「子どもの発熱時に直行直帰できた」「育休から復帰して管理者を務めている」といったエピソードは、同じ境遇にある看護師にとって応募を後押しする材料となります。
求人票の「事業所からのメッセージ」欄にスタッフの声を一文だけでも加えると、読み手は「ここには自分の理解者がいる」と感じやすくなります。また、SNSや採用ページと連携してスタッフインタビューを掲載すれば、求職者が安心して応募できる流れを作ることが可能です。
訪問看護は「一人で働く大変な仕事」という誤解を受けがちですが、スタッフの声を通じて「チームで支え合っている」「研修体制がある」と伝えることができれば、その不安を解消できます。つまり、スタッフの言葉を採用戦略の中心に置くことが、応募を増やす最短ルートなのです。
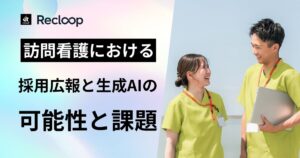
応募を増やす「小さな接点」を用意する
求人票から応募までの流れを考えると、「いきなり応募するのは不安」という心理的な壁が存在します。この壁を越えるためには、「応募前に軽く関われる接点」を複数用意することが有効です。
たとえば、求人票に「見学のみでも歓迎」と記載する、LINEやメールで「相談だけOK」と案内する、といった工夫です。こうした接点があることで、求職者は「まずは話を聞いてみよう」という気持ちになり、応募へと進みやすくなります。
また、オンライン面談やZoom説明会も効果的です。特に子育て世代や現職を続けながら転職を検討している層にとって、来所せずに情報を得られることは大きな安心材料となります。求人票に「オンライン面接可」と入れるだけでも検索にヒットしやすくなり、応募数増加につながります。
訪問看護は仕事内容の理解に時間がかかるため、こうした「軽い接点」があることで、応募のハードルを大きく下げられます。最初の一歩を踏み出しやすい仕組みを整えることこそ、採用成功の近道です。
明日から実践できるNext Action
最後に、訪問看護ステーションがすぐに取り組める具体的なアクションを整理します。これは「求人票を出しても応募が来ない」と悩む担当者にとって、明日から実行できる改善策です。
- 紹介状不要に設定する:オンライン自主応募を可能にし、就業中の転職希望者を逃さない。
- 職種欄を工夫する:「看護師」だけでなく「【土日休み・直行直帰OK】訪問看護師」といったキャッチを入れる。
- 仕事内容を具体的に書く:訪問件数や1日の流れ、同行研修の有無を明記する。
- 写真10枚を登録する:職場の雰囲気や研修風景を見せ、安心感を与える。
- SNSへ誘導する:Instagramや採用ページへのQRコードを貼り、リアルな声に触れてもらう。
- 応募前の接点を用意する:「見学歓迎」「LINE相談可能」など心理的ハードルを下げる。
これらの取り組みは大掛かりな仕組みづくりを必要とせず、既存の求人票に少し手を加えるだけで実行できます。小さな工夫を積み重ねることで、訪問看護の採用は確実に成果へとつながります。
訪問看護における看護師採用は、人材不足が続く中で多くの事業所が直面する課題です。しかし「ハローワークでは人が採れない」と決めつけるのではなく、求人票の書き方や設定、写真・SNSとの連携を工夫することで成果を上げることは十分可能です。紹介状不要の設定や職種欄の工夫、具体的な仕事内容の記載はすぐに取り組める改善点です。さらに、スタッフの声や日常の発信を加えることで応募のハードルを下げ、職場の魅力をリアルに伝えられます。こうした改善を継続的に実行することで採用は確実に前進します。
もし「自社に合ったやり方を整理したい」「専門的な視点で伴走してほしい」と感じたら、HOAPの採用支援サービスを活用することも選択肢の一つです。現場に即した実践的なサポートで、採用の仕組みづくりを後押しできます。

看護師やリハビリ職・ケアマネなどの採用にお困りの経営者様はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。












