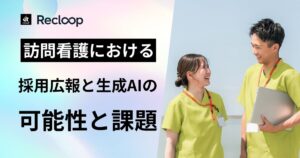「求人を出しても応募が来ない」
「条件は悪くないはずなのに反応が薄い」
訪問看護の現場で、こんな悩みを抱えている経営者や採用担当者は少なくありません。実際、基本給や福利厚生を整えても、他社と大きな差が出るわけではなく、「求人票に書いてあることが似たり寄ったり」になっているケースも多く見られます。 一方で、同じような条件でも、なぜか応募が集まる事業所も存在します。両者の違いはどこにあるのでしょうか?
それは「求人票の書き方」にあります。単に制度や条件を並べるのではなく、「誰に向けて」「どんな感情に触れ」「どんな行動を促すか」を明確に意識して作成された求人票は、読み手に強く届きます。
特に、AIで求人票の自動生成も可能になりつつある今だからこそ、「AIには出せない人間味」「共感される言葉」「安心を与えるリアルさ」が一層求められています。
本記事では、訪問看護業界における求人票の作成で重要な3つの鉄則を中心に、求職者の心を動かすポイントを順を追って見ていきます。
「条件」だけでは届かない?求人票が読まれていない本当の理由

表面的な情報だけでは読み手の心には届かない
「訪問看護師 求人」と検索すれば、条件の整った求人票がいくつも並びます。しかしその多くは、「基本給○○円以上」「残業ほぼなし」「福利厚生充実」など、事実の羅列にとどまっています。条件面での比較はある程度できても、それだけで「ここで働きたい」と思わせるには不十分です。なぜなら、読み手である求職者はすでに、似たような求人票を何十件も見ているからです。
求人票を見て「ここはちょっと違うかも」と感じるのは、たいてい数秒以内。つまり、どれだけ条件が良くても「読まれなければ存在していない」のと同じです。
求職者は「情報」よりも「感情」で動く
採用担当者が見落としがちなのが、「求職者は感情で動く」という前提です。
たとえば以下の2つの文を比べてみてください。
- 「有給取得率80%以上!プライベートとの両立も安心です」
- 「子どもの急な発熱で、すぐ帰れる職場です。『今日もありがとう』と送り出されました」
どちらが印象に残るでしょうか。後者には、読み手の過去の体験や価値観とつながる余地があり、自分ごととして受け止めやすくなります。実際、多くの求職者は「条件がいいから」ではなく、「この職場でなら自分も安心して働けそう」と感じたときに行動に移します。
情報過多の時代に差がつくのは「人間らしい言葉」
求人票が読まれない最大の要因は、「見た瞬間に、よくある内容だと感じさせてしまうこと」です。これは情報の質ではなく、「語り方」によって起こります。
AIやテンプレートで作られた求人票が増える中、差が出るのは「人間らしい言葉」です。たとえば、
・「先輩の背中を見て育ちました」という新人の声
・「この制度に助けられました」という一言のリアルさ
・「この職場に向いてない人もいます」という正直さ
こうした言葉は、求人票の中で特に目を引きます。そして読まれた先に、「話を聞いてみたい」という一歩が生まれます。
求人票の役割は「行動のきっかけを作る」こと
求人票は、採用活動の「出発点」です。ゴールは応募や面接ではなく、「接点をつくること」にあります。つまり、求職者が「この求人、ちょっと気になる」と感じた時点で、すでに求人票の役割は半分以上果たされています。
この視点を持つと、単に情報を並べるだけではなく、「読み手が自分のこととして捉えられるか」「感情が動く内容になっているか」といった観点で見直すことが重要になります。
「誰に向けて書くか」が求人票の質を決める

書き手の都合ではなく「読み手の視点」で構成する
求人票の作成において、最も基本でありながら、多くの事業所が見落としているのが「ターゲットの明確化」です。採用担当者がよく口にするのは、「誰でもウェルカムです」「とにかく人手が足りない」という言葉。しかし、実際に読み手である求職者は、自分に合う職場かどうかを極めて慎重に見極めています。
たとえば、現在特養で働いている看護師が「夜勤続きで疲弊している」「子育てとの両立が難しい」と感じている場合、その人にとって響く求人票は、「訪問看護のやりがい」や「多職種連携の魅力」ではなく、「夜勤なし」「家庭との両立が可能」という視点で書かれたものです。
つまり、「誰に読まれるか」を意識せずに書かれた求人票は、結果として「誰にも刺さらない内容」になりがちです。
「今、どんな環境にいて、どんな違和感を持っているか」を想像する
ターゲットを定める際は、単に「子育て中の女性」や「20代の若手」といった属性だけでなく、現在の勤務先で感じているであろう悩みや違和感まで想像することが重要です。
以下はその具体例です。
- 【現在の勤務状況】:総合病院で3交代勤務。急性期の現場で心身共に疲弊気味。
- 【感じているモヤモヤ】:患者との関わりが断片的。仕事の意味が見えづらい。
- 【理想としている働き方】:患者とじっくり関われる職場で、日中勤務が中心。
このように読み手の「背景」「不満」「未来の理想像」までイメージすることで、求人票の言葉選びは大きく変わります。
求職者が「自分ごと」として読み進められるかがカギ
読み手が求人票を読み進めるのは、「これは自分に関係あるかもしれない」と感じたときです。逆に言えば、初めの数行で「自分には関係ない」と思われた時点で、どれほど制度や条件が充実していても、読み進められることはありません。
たとえば以下のような書き出しではどうでしょうか。
「病棟勤務で“もっと患者さんと向き合いたい”と感じたことはありませんか?」
この一文に引っかかる人は、自身の過去や悩みを重ね合わせる可能性が高く、「続きを読んでみよう」という動機が生まれます。求人票においては、この「自分ごと化」をどれだけ設計できるかが鍵となります。
書き手の都合ではなく「相手の現実」から始める
求人票は、採用したい側が作るものではありますが、書き出しや構成の起点はあくまで「相手の現実」であるべきです。「どんな人に」「どんな想いで」「どんな働き方をしてほしいのか」というメッセージが、読み手に自然に届くようにするには、構成全体を「相手の生活」に沿わせる必要があります。
そのためには、実際に働いている職員からのヒアリングや、入職前後でどんな変化があったかといったエピソードを積み上げておくことも有効です。求職者は、自分と似た境遇の人の声に、強く共感します。
決め手になるのは「この職場なら自分も働けそう」と思えるかどうか
求人票は、正確な情報を伝えるだけでなく、「不安をやわらげ」「行動への一歩を後押しする」役割を担っています。そのためには、「職場が求める人物像」に寄せるのではなく、「今、働き方に悩んでいる誰か」が読みやすく、自分の未来を想像できるような構成にしていくことが求められます。
求人票の質を決めるのは、
ではなく、
という起点そのものです。その精度を高めていくことが、結果として読まれる求人票につながっていきます。
リアルなエピソードこそが「信頼」と「安心」を生む

求職者が求めているのは「本当の職場の姿」
訪問看護という働き方に興味を持っていても、実際の現場がどのような雰囲気なのか、どんな人たちが働いているのかが見えなければ、応募に踏み切れないという声は多く聞かれます。求職者の立場からすれば、制度や条件が整っているかどうか以上に、「この職場でうまくやっていけるか」という感覚的な判断が非常に重要です。
そのため求人票では、形式的な紹介文よりも、実際に働くスタッフの「リアルな声」を通じて職場の雰囲気を伝えることが効果的です。
「うちはこういう職場です」と言うより「誰かの体験」を伝える
読み手は、企業や事業所が発信する言葉には慎重です。どれだけ「働きやすい職場です」とアピールしても、それが自画自賛に見えると信頼感にはつながりません。反対に、実際のスタッフが語る等身大のエピソードは、読み手に安心を与えます。
たとえば、以下のような内容です。
「病棟勤務で疲弊していた頃、この仕事はいつまで続けられるんだろうと感じていました。転職して訪問看護に来て、1日4〜5件の訪問の合間に、落ち着いて記録が書ける時間があることに驚きました。何より、1人の利用者さんとじっくり向き合えるのが、自分には合っていたと思います。」
このような一人称の語りは、条件の説明以上に職場の姿を具体的に想像させる力を持っています。読み手はその人の視点を通して、「自分がここで働いたらどうなるか」を思い描くことができるのです。
読み手は「良い話」より「リアルな話」に惹かれる
求人票に掲載するスタッフの声は、「前向きな内容でないといけない」と思われがちですが、それは誤解です。むしろ、失敗や悩み、不安から始まるエピソードこそが、読み手の共感を得やすくなります。
たとえば次のような話も、信頼につながる一例です。
「全盲の利用者さんの家で、落ちていたライターを拾って机に置いたことがありました。すると『そこに置くと生活が崩れるから、そのままでいい』と言われて…。良かれと思った行動が迷惑だったんだと学びました。」
このような体験談は、「この職場には学びの機会がある」「失敗も共有できる文化がある」と読み手に伝えることができます。
「スタッフの言葉」は職場の証明になる
制度や理念は、どの事業所でもある程度整っています。だからこそ、「この制度は本当に機能しているのか」「理念は現場で生きているのか」という点が、読み手の関心になります。これを伝える最も有効な手段が、実際にその環境で働いている人の声です。
たとえば、「急な休みにも対応してもらえた」という声や、「ブランクがあっても受け入れてもらえた」という実例は、言葉の裏にある信頼を強めます。エピソードの中に、「制度がどう使われているか」どんな雰囲気で仕事が進んでいるかが自然に織り込まれていれば、読み手の不安を解消しやすくなります。
スタッフの言葉を集めること自体が組織の振り返りにもなる
スタッフの声を求人票に反映するには、日頃から小さな体験談を集める仕組みが必要です。たとえば、面談時や定期的な振り返りの場で「最近仕事で嬉しかったことは?」「困ったけれど乗り越えた場面は?」といった問いを設けておくと、自然とエピソードの蓄積につながります。
これらの語りは、求人票だけでなく、Instagramや採用ページなど、他の媒体でも活用できます。結果的に、採用活動そのものが「日々の積み重ね」となる仕組みが生まれます。
AIを活用した求人作成術

求人作成におけるAI活用は補助であり代替ではない
近年では、AIライティングツールを使って求人票を自動生成する企業も増えてきました。タイトル、募集要項、福利厚生の説明など、定型的な情報を整える点ではAIのスピードと精度は確かに有用です。特に、複数職種や事業所を同時に管理する中で、ベースとなるフォーマットを量産するためには効果的です。
ただし、読み手に届く求人票に必要なのは「その職場の雰囲気」「スタッフのリアルな姿」「文化として根付いた価値観」であり、これはAIの生成だけでは伝わりません。
AIの言葉では伝わらない「その職場ならでは」の雰囲気
たとえば、「育児と仕事の両立ができる」という情報を伝える際、AIは「時短勤務制度あり」「急な休みにも対応可」など、文脈を拾って整った文章を出力することはできます。しかし、
「保育園からの呼び出しで早退した日、先輩が“うちはそういうとき助け合うからね”と笑ってくれた」
というような雰囲気を含んだ一文は、人からしか生まれません。求職者が安心できるのは、制度名ではなく「その制度がどう使われ、どう受け止められているか」です。
AIは「ベース」に、人は「感情とリアルな描写」に注力
実際の求人作成においては、AIと人との役割を明確に分けることが重要です。
・AIでベースの構成や文型を整える
・人が現場のリアルな声や体験談を肉付けする
・表現のトーン・順番・伝わり方を編集者視点で仕上げる
このように、AIはあくまで「土台作り」に活用し、感情を動かす「言葉選び」や「語りの構成」は人の仕事として残すことで、情報と感情のバランスが取れた求人票になります。
AIを活用するなら「下書き」まで
AIは、求人票の構成や文型を整える点では強力な補助ツールです。しかし、生成された文章をそのまま使うことには注意が必要です。というのも、AIが出力する文章は、情報としての精度はあっても、その職場の「らしさ」や「リアルな雰囲気」までは反映されていないからです。
求人票の最終的な役割は、「この職場で自分が働くイメージを持ってもらうこと」です。そのためには、単に条件を提示するだけではなく、読み手が感情的に共鳴できるような表現や語りが必要です。たとえば、「制度あり」ではなく、「実際にどんな人が、どんな場面で助かったのか」を描く視点は、AIには出せません。
実際の運用としては、AIを「下書き担当」と捉え、構成や定型項目の叩き台を生成してもらい、そこに現場のストーリーや言葉を加えて仕上げていくのが理想的です。誰かのセリフや感情が含まれることで、求人票の読みやすさや共感性は格段に高まります。整ったフォーマット以上に、言葉選びや順番に「人の視点」があることが、読み手の行動を引き出す鍵になります。
AIで求人作成する鉄則3原則——人の言葉とAIの力を両立させる視点

【原則①】AIは「整理」まで、人が「共感」をつくる
AIは情報の収集や構造の整理、文章の生成といった整える作業に長けています。職種、勤務地、条件、制度といった定型項目を一貫性のある形式で出力することには向いています。
しかし、求人票に求められるのは、単なる「情報」ではなく「感情へのアプローチ」です。AIはあくまで下書きまでを担うツールであり、「どんな働き方を求めている誰に届けたいのか」という視点や、「その制度がどう活かされているか」といった語りの部分は、人の経験・思考・観察からしか生まれません。
求人票の読み手が求めているのは、「この職場なら自分でもやっていける」という確信です。それを届けるには、人の視点が不可欠です。
【原則②】AI任せでなく語り・ストーリーを後から重ねる
AIが出力する文章には、表情がありません。だからこそ、読み手の記憶に残る求人票を作るには、AIが生成したベースに、実際のエピソードや感情を重ねる編集が欠かせません。
たとえば、「育児と両立できます」ではなく、
「お迎えに間に合わないかも…と思っていた日、“早く行ってあげな”と送り出された。あのとき、この職場にしてよかったと思った」
というような一文があると、求人票全体に温度が生まれます。
これはAIには書けません。求職者の不安や希望を想像し、共感される語りに変える編集は、人にしかできない工程です。
【原則③】行動を引き出す仕組みは人が担う
求人票の目的は
ではなく
です。いかに情報が整理されていても、読み手が動けなければ意味がありません。ここで必要なのが、行動に繋げる仕組みです。
たとえば、
- 「応募の前に、まずはLINEで話してみませんか?」
- 「事業所見学、カジュアル面談も歓迎しています」
といった選択肢があることで、求職者は「今すぐ応募する以外の行動」が取れるようになります。これはAIが自動で判断することは難しく、職場の状況やターゲット像に応じて人が設計すべき領域です。
「どんな入口を用意するか」「どこで一歩踏み出してもらうか」を設計できてはじめて、求人票は「採用に効くツール」になります。
これからの求人票作成は、「人」か「AI」かの選択ではなく、「人とAIが何を分担すべきか」の時代に入っています。AIが得意とする文章整理や言い回しの整形は積極的に任せてよい領域です。反対に、「誰に届けたいのか」「どんな言葉が動機づけになるのか」といった内容と編集は、必ず人が担うべき仕事です。
求人票は単なる募集要項ではなく、読み手との「はじめての対話」です。その言葉の選び方、語りの順番、語らないことをあえて残す判断——こうした判断には、現場を知る人の感性が不可欠です。
条件面を整えるだけでは、人は動きません。今の時代に必要なのは、「スタッフのリアルな情報」や「職場の雰囲気」が伝わる求人票です。そして、AIの力を借りながらも、最後に言葉を整え、感情を乗せられるのは「人」の仕事です。採用に正解はありませんが、「何を伝えれば、どんな人が動くのか」を丁寧に考えることが、応募数や定着率を大きく変えていきます。求人票は、採用のスタート地点ではなく、信頼関係の最初の1ページです。