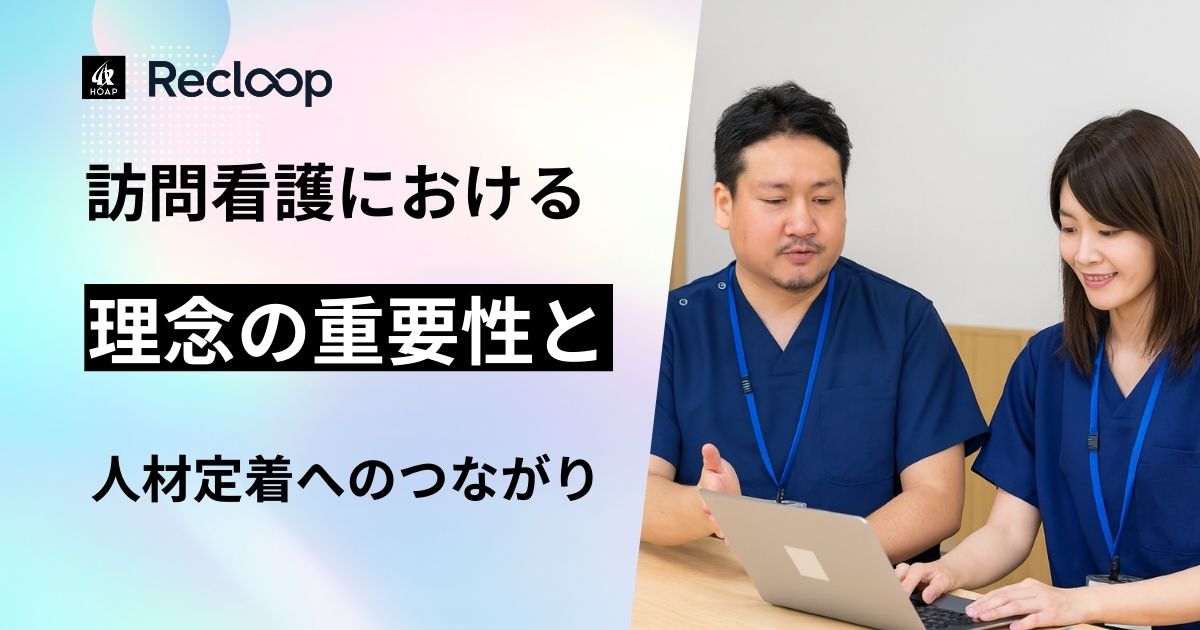訪問看護事業を運営する中で、多くの経営者や管理者が頭を悩ませているのが「採用してもすぐに辞めてしまう」「スタッフの方向性がまとまらない」といった課題です。条件面を改善しても人材が定着しない、教育の仕組みを整えても思ったように現場に根づかない、といった声は少なくありません。その背景には、組織としての「理念」が十分に浸透していないことが関係している場合があります。
理念は単なるスローガンではなく、スタッフ一人ひとりが「なぜこの仕事を選んだのか」「利用者にどのように向き合いたいのか」を確認する拠り所になります。理念が曖昧なままでは、スタッフは待遇や条件といった目に見える部分だけで職場を判断しがちになり、価値観のずれによって早期離職につながります。逆に、理念が共有されている組織では、スタッフは自らの行動を判断する基準を持つことができ、日々の業務に意味づけを見いだしやすくなります。
訪問看護は、病院と異なりスタッフが単独で利用者宅に向かうことが多い職種です。そのため、現場での判断や行動が理念と結びついていなければ、個々の看護師によってサービスの質がばらつきやすくなります。理念は、そうした現場の不安定さを補い、共通の方向性を示す「羅針盤」としての役割を果たします。
本記事では、訪問看護における理念の重要性と、採用・定着へのつながりを順を追って見ていきます。まずは「なぜスタッフが定着しないのか」という現場で頻発する課題から確認し、その後に理念の意義、浸透が難しい理由、実践的な工夫、そして明日からできる行動へと進んでいきます。
「なぜ訪問看護でスタッフが定着しないのか?」

条件だけで選んだスタッフは早期離職しやすい
訪問看護に限らず医療・介護業界では、人材不足から採用条件を前面に押し出した求人が増えています。「給与水準が高い」「休日が取りやすい」「残業が少ない」といった待遇はもちろん重要ですが、それだけを理由に入職したスタッフは短期間で離職しやすい傾向があります。なぜなら、訪問看護という仕事には、待遇だけでは補えない「日々の判断力と利用者との関係性」が求められるからです。
実際の現場では、急変に対応することもあれば、利用者や家族から感情的な反応を受けることもあります。そのような時に「なぜ自分は訪問看護を選んだのか」「どんな看護を届けたいのか」という拠り所がないと、ストレスが大きくなり「条件に惹かれて来たけれど、自分には合わない」と感じやすくなります。つまり、給与や休日などの条件は入口にはなるものの、定着の理由にはなりにくいのです。理念がスタッフの内面に働きかけることで、初めて条件と実際の働きが結びつき、長期的な勤務につながります。

現場で孤独を感じやすい訪問看護の特性
病院勤務との大きな違いは、訪問看護師が単独で利用者宅に訪れる場面が多い点です。チームで支え合う病棟と比べ、現場で孤独を感じやすく、精神的な負担が離職につながるケースは少なくありません。同行訪問やカンファレンスといった仕組みが整っていても、最終的には一人で判断しなければならない状況が生じます。
ここで重要なのが「組織として何を大切にするか」という共通の基準です。理念がしっかり根付いていれば、スタッフは「自分の判断は理念に沿っているのか」と確認しながら行動できます。逆に理念が曖昧な場合、判断の軸を持てずに不安が募り、「一人で責任を負っている」という感覚が強まります。孤独感や責任感の重さが続くと、やりがいを感じる前に心が折れてしまい、結果として早期離職につながります。理念が共有されていれば、一人で訪問していても「自分は組織全体の考え方を背負っている」と安心でき、離職のリスクを下げることができます。
理念が浸透していないと価値観のミスマッチが起きる
訪問看護の利用者は、高齢者、難病患者、在宅医療を受ける子どもなど多岐にわたり、その生活背景や家族の価値観もさまざまです。看護師はその一人ひとりに合わせた対応が求められますが、理念が浸透していない組織では、スタッフごとに対応の姿勢がバラバラになりやすい傾向があります。あるスタッフは「効率重視」で訪問を進め、別のスタッフは「時間をかけて傾聴する」ことを優先する。結果として利用者や家族が受け取る印象が異なり、「この事業所は一貫性がない」と不信感を抱かれることもあります。
さらに、スタッフ同士でも価値観の食い違いが表面化します。「あの人の対応は遅い」「自分ばかり忙しい」といった不満が蓄積し、人間関係のトラブルへ発展します。このようなズレを防ぐには、「利用者にどう向き合うのか」という理念が共通の土台になる必要があります。理念が共有されていれば、個人のやり方の違いがあっても方向性は同じであると確認でき、ミスマッチを最小限に抑えることが可能です。理念の欠如は、スタッフ間の摩擦を増幅させ、定着率を下げる大きな要因となります。

短期的な採用活動が長期定着を妨げている
慢性的な人材不足から、多くの訪問看護事業所では「まずは人を採用すること」が優先されがちです。その結果、面接で理念や価値観を十分に伝える時間を取れず、条件だけでマッチングしてしまうケースが少なくありません。こうした短期的な採用は、入職直後は人員不足を補えたとしても、定着しなければ再び採用活動に追われる悪循環を生みます。
この背景には、経営者や採用担当者自身が「理念は後から伝えればいい」と考えていることも影響しています。しかし実際には、理念を共有できるかどうかは採用の初期段階でこそ確認が必要です。理念を共有できる人材を迎え入れることで、現場に合った働き方ができ、長期的な勤務につながります。逆に、理念を軽視した採用は、いくら条件を整えても定着には結びつきにくいのが現実です。採用から定着までを一本の流れとして捉えることが、訪問看護における人材課題の解決に不可欠です。
訪問看護に理念が必要な理由

理念は現場の判断を支える「羅針盤」
訪問看護師は、利用者宅で一人きりで判断を下す場面が多々あります。体調の変化に気づき医師に報告すべきか、家族への声かけをどうするか、服薬管理で少し迷いが生じたときにどう対応するか――その一つひとつはマニュアルだけでは解決できません。そこで役立つのが、組織全体で共有された理念です。理念が「私たちは利用者の自立を尊重する」「生活に寄り添う看護を大切にする」といった方向性を示していれば、スタッフは迷ったときにその理念に照らして考えることができます。
理念が存在しない、あるいは形だけのものであれば、スタッフは判断の根拠を持てず、不安を抱えたまま業務にあたることになります。これはストレスを増大させ、離職リスクを高める要因にもなります。理念は現場の細かな判断を支える「羅針盤」であり、スタッフを孤独にさせない見えない支えとして機能するのです。
理念は組織の「一体感」を生み出す
訪問看護は個別性の高いサービスでありながら、組織全体としての一貫性が求められます。理念を共有することは、スタッフ同士が「自分たちは同じ方向を向いている」という安心感を持つことにつながります。理念があることで、スタッフ同士の判断や対応が大きくぶれることなく、利用者や家族からも「この事業所は方針が一貫している」と信頼を得やすくなります。
逆に理念が浸透していない場合は、スタッフごとに価値観が異なり、業務の進め方や利用者への接し方に差が出ます。その結果、利用者に不安を与えるだけでなく、スタッフ同士の摩擦が生まれやすくなります。理念を土台にした一体感は、トラブルの予防や人間関係の安定にも直結します。組織としての方向性を明確に示す理念は、看護の質とチームワークを両立させるうえで欠かせない存在です。
理念は採用・育成の基準になる
採用の場面において理念を明確に伝えることは、応募者が「この組織は自分に合うかどうか」を判断する材料となります。条件だけでなく理念に共感して応募してきた人材は、仕事への動機づけが強く、入職後も定着しやすい傾向があります。また、育成の場面でも理念は重要な役割を果たします。新しく入ったスタッフに「この場面ではどうすればいいのか」と問われたとき、理念を基準に答えることができれば、単なる技術指導を超えて「この組織の看護観」を伝えることができます。
理念は評価基準としても機能します。スタッフの行動を振り返るときに「理念に沿った働きができているか」を軸にすれば、数値では測れない部分も含めてフェアに評価できます。採用・育成・評価といった人事の流れ全体を支える基準として、理念は欠かせない存在です。
理念は利用者・家族への信頼を高める
理念が明確に打ち出されている事業所は、利用者やその家族からも安心感を得やすくなります。「この事業所はこういう考え方で看護をしている」と伝わることで、サービスに対する期待が具体化し、信頼関係の構築がスムーズになります。例えば「その人らしい暮らしを支える」という理念を持っている事業所であれば、家族は「生活全体を尊重してくれる」という安心感を抱きます。
理念がない場合、利用者や家族はスタッフごとの対応の差に戸惑い、「誰を信じていいのか分からない」と感じることがあります。これは事業所の評価を下げるだけでなく、クレームや利用中止といった事態につながることもあります。理念を明確に打ち出し、スタッフ全員が共有していることは、利用者との信頼関係を築き、事業の安定につながる大きな要素です。
理念が現場で形骸化してしまうのはなぜか?

経営層の言葉で止まってしまうから
多くの訪問看護事業所では、理念そのものは存在しています。しかし、その理念が現場で共有されず、経営者や管理者の口から語られるだけで終わっていることが少なくありません。理念は経営層が掲げるだけでは意味を持たず、現場スタッフが「自分ごと」として理解して初めて力を発揮します。
例えば、経営者が「地域に寄り添う看護を大切にしたい」と言っても、それが現場スタッフの日々の訪問にどう関係するのかが具体的に示されなければ、理念は抽象的な標語にすぎなくなります。スタッフは「また経営者が立派なことを言っている」と受け止め、距離感を覚えてしまうこともあります。こうして理念は経営層の言葉にとどまり、現場に浸透せず形骸化していくのです。
日常業務に落とし込めていないから
理念が形骸化するもう一つの理由は、日常業務とつながっていないことです。訪問看護は時間管理が厳しく、次々と利用者宅を訪問しなければなりません。その中で理念を意識する余裕がなければ、理念は掲示板やパンフレットに書かれているだけの存在になります。本来であれば「訪問先での声かけ」「利用者への接し方」「記録の取り方」といった日常的な行為に理念を結びつける必要があります。
たとえば「自立支援を大切にする」という理念があるなら、訪問時に利用者の動作を手伝いすぎないように意識する、といった具体的な形で日々の業務に反映させなければなりません。業務の一つひとつに理念を重ね合わせる工夫がない限り、理念は「現場に関係のない言葉」として扱われてしまいます。
現場の経験や利用者の声と結びついていないから
理念が浸透しない背景には、現場での体験や利用者の声とリンクしていないことも挙げられます。スタッフにとって最も心に残るのは、利用者や家族からの感謝の言葉や、自分が判断に迷った経験などです。理念をただ読み上げるだけではなく、そうしたリアルな経験と照らし合わせて語られることで初めて納得感が生まれます。
例えば「私たちは生活に寄り添う看護を大切にする」という理念があるなら、実際に「利用者が自宅で最後まで過ごせたのは、スタッフが生活を重視した関わりをしたから」というエピソードを紹介することが効果的です。現場での出来事や利用者の声と結びつかない理念は、スタッフにとって「現実と乖離した理想論」に見え、日常の中で活かされなくなってしまいます。
理念を確認する機会が少ないから
理念が掲げられていても、日常的に確認する機会が少なければ、自然と忘れられてしまいます。朝礼や会議で理念が一度も触れられない、研修でも理念の話が出ない、といった状況では、スタッフが理念を意識することは難しいでしょう。理念は一度伝えれば浸透するものではなく、繰り返し触れることで徐々に根づいていくものです。
例えば、定例会で「最近の訪問で理念に沿った行動はあったか」を振り返る、あるいは新人研修で理念を題材にしたケーススタディを行うなど、具体的な取り組みが必要です。理念を日常の会話や業務の中で自然に思い出せる環境を作らなければ、スタッフの頭から薄れていき、結果的に形骸化してしまいます。
理念を現場で活かすための具体的な方法

採用面接で理念を伝える工夫
理念を現場で活かすためには、まず採用の段階から理念を伝えることが重要です。多くの事業所では給与や勤務形態といった条件面に焦点が当たりがちですが、それだけでは「条件が良ければ働く」「合わなければ辞める」という短期的な関わりに終わりやすくなります。採用面接では、事業所が大切にしている理念を具体的な言葉で説明し、それに共感できるかどうかを応募者に確認する姿勢が欠かせません。例えば
「私たちは利用者の自立を支えることを大切にしていますが、あなたが看護をする上で大切にしていることは何ですか?」
といった質問を投げかけることで、応募者の価値観を見極めることができます。理念に共感できる人材を採用できれば、その後の教育や現場での成長がスムーズになり、定着にもつながります。
新人研修やOJTで理念を具体的行動に紐づける
入職後の研修やOJTで、理念を「日常の行動」に落とし込むことが必要です。理念を掲げるだけでは抽象的で理解しづらいため、具体的な行動と結びつけることで初めて実感が伴います。
例えば「生活に寄り添う看護」を理念とする場合、研修では
といった具体例を示すと効果的です。OJTでは、先輩スタッフが訪問先で実際に理念を体現している場面を解説しながら同行することで、新人は理念を行動として学ぶことができます。理念を研修と業務の両方で繰り返し確認する仕組みがあれば、理念は自然と現場に根づき、形骸化せずに日常の判断基準として活かされていきます。
スタッフ同士で理念を語り合う機会をつくる
理念を現場で活かすためには、スタッフが互いに理念を語り合える場を設けることも有効です。日常業務に追われると「理念について話す時間なんてない」と思われがちですが、むしろそのような場がないと理念は表面的なものになり、スタッフ同士の価値観の違いがそのまま衝突につながります。
例えば月に一度のミーティングで「最近の訪問で理念を意識できた場面」を共有する時間を設けると、理念が現場のエピソードと結びつき、具体性を帯びていきます。語り合う中で「自分の解釈はこうだったが、他の人はこう考えている」と気づくことができれば、理念の理解はより深まります。理念を共有する時間は、単なる話し合いではなく、組織の一体感を育てる貴重な機会でもあります。
広報やSNSで理念をストーリーとして発信する
理念を現場に浸透させるだけでなく、外部に発信することも重要です。求人票や採用サイトに理念を掲載することはもちろん、SNSや広報活動を通じて「理念が日々の現場でどう生きているのか」をストーリーとして伝えると効果的です。
例えば、スタッフの体験談を紹介する形で「理念があったからこそこの判断ができた」「利用者から感謝された」というエピソードを発信すれば、外部に対しても理念が「生きている」ことを示せます。これにより、理念に共感する求職者を惹きつけるだけでなく、既存スタッフも「自分たちの理念が外に届いている」と誇りを持つことができます。理念を単なる言葉でなく「ストーリー」で示すことは、現場のモチベーション維持にも直結します。
明日からできる理念浸透の第一歩

理念を一文にまとめ直し共有する
理念を現場に浸透させる第一歩は、複雑な表現を削ぎ落とし、誰もが覚えやすい一文にまとめ直すことです。長い理念文や抽象的なフレーズでは、スタッフが日常業務の中で思い出すことは難しくなります。例えば
という理念を
という一文に言い換えれば、現場で思い出しやすくなります。まとめ直した理念をカードやポスターにして事業所内に掲示したり、訪問バッグに忍ばせたりするだけでも、スタッフは常に理念を意識できるようになります。理念を一文で共有することは、浸透のための最も手軽で即効性のある方法です。
一日の振り返りで理念を確認する
理念を習慣的に意識するためには、日々の振り返りの場面で理念を確認するのが効果的です。終礼や日報の記入時に「今日の訪問で理念に沿った行動はあったか」と問いかけるだけで、スタッフは自分の行動を理念と結びつけて振り返ることができます。この小さな習慣を積み重ねることで、理念は単なる言葉から「行動を評価する視点」へと変わっていきます。
管理者がスタッフに「今日の訪問で理念を感じた瞬間はあった?」と尋ねるだけでも、理念を思い出すきっかけになります。こうした振り返りは特別な時間を必要とせず、既存の業務フローに組み込めるため、明日からでも始められる実践的な方法です。
朝礼や定例で理念にまつわるエピソードを紹介する
理念を日常に根づかせるもう一つの方法は、朝礼や定例ミーティングの場で理念に関するエピソードを紹介することです。例えば
「先日の訪問で、利用者が『自分で歩けるようになったのはあなたが見守ってくれたから』と言ってくれた。これは私たちの『自立支援を大切にする』理念が現れた瞬間だ」
と共有するだけで、理念が具体的な体験と結びつきます。エピソードの共有はスタッフ全体のモチベーションを高める効果もあり、「理念は現場で生きている」という実感を広げます。短時間でもよいので、定例的に理念に触れる習慣を持つことが、形骸化を防ぎ、理念を自然に意識させるきっかけになります。
求人票や採用サイトに理念を盛り込む
理念浸透の第一歩は内部にとどまらず、外部に向けても行うことができます。求人票や採用サイトに理念を盛り込むことで、「この事業所はどんな価値観を持っているのか」が明確に伝わり、理念に共感する人材を呼び込むことができます。
例えば「私たちは、その人らしい暮らしを支えることを大切にしています」という一文を求人票の冒頭に置くだけで、条件だけではなく理念に惹かれて応募する人が増える可能性があります。また、理念を外部に発信することは、既存スタッフにとっても「自分たちの理念が社会に伝わっている」と感じられる機会になり、誇りや定着意識を高める効果があります。採用活動と理念浸透を連動させることは、組織全体の一体感を強めるうえで大きな意味を持ちます。
訪問看護における人材課題の背景には、待遇や制度だけでは解決できない「理念の浸透不足」があります。理念は、スタッフが日常の判断を行うための基準であり、組織の一体感や利用者からの信頼を支える要素でもあります。しかし、経営層の言葉にとどまったり、日常業務に結びついていなかったりすると、形骸化しやすいのも事実です。本記事で示したように、採用段階から理念を伝え、研修やOJTで行動に落とし込み、日々の振り返りやエピソード共有で繰り返し確認することが、理念を「生きたもの」にする鍵となります。理念を明日からの小さな実践に結びつけることで、スタッフの定着と看護の質の向上を同時に実現することが可能です。

監修者:牟田 健登(Kento Muta)
株式会社クルージズ・テクノロジーズ代表取締役。2021年に創業し、在宅医療・介護業界に特化した人事コンサルティング・人事評価SaaSを展開。訪問看護ステーションや訪問介護ステーションを中心にサービスを展開中。