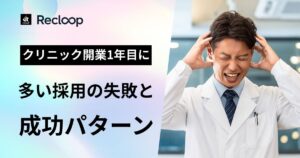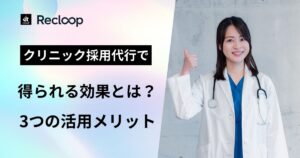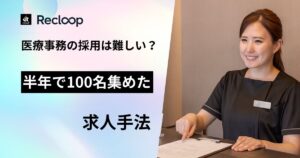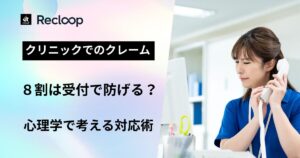クリニックの院長の間でよく聞かれる悩みのひとつが、「せっかく採用した看護師や医療事務がすぐ辞めてしまう」という問題です。数ヶ月以内での退職はもちろん、早ければ試用期間の途中で辞めてしまうケースもあります。人材不足が慢性的に続く医療現場において、この早期離職は経営に直接的なダメージを与えるだけでなく、残されたスタッフの負担増やモチベーション低下にもつながりかねません。
なぜこのような短期離職が起こるのでしょうか。多くの経営者は給与条件や労働時間といった「待遇面」に原因を求めがちですが、実際にはそれだけではありません。面接時の印象と実際の職場環境のギャップ、人間関係の不一致、または職場文化への違和感が退職理由として挙げられることが少なくないのです。
特に看護師や医療事務といった職種は、患者対応や多職種連携を日常的に行うため、人間関係やチームの雰囲気が働きやすさに直結します。そのため、「自分には合わない」と感じた瞬間に退職を選択するケースもあります。つまり、採用時にスキルや経歴だけで判断してしまうと、早期離職のリスクを高めることになるのです。
本記事では、看護師や医療事務が短期間で辞めてしまう原因を掘り下げ、定着率を上げるために採用の段階から取り入れるべき工夫について解説します。まずは「なぜすぐ辞めてしまうのか」という根本的な疑問から考えていきましょう。
なぜクリニックの看護師・医療事務は「すぐ辞める」のか?

看護師・医療事務がすぐ辞める背景にある「職場とのギャップ」
看護師や医療事務が短期間で辞めてしまう最大の理由のひとつは、採用段階で伝えきれなかった「職場とのギャップ」にあります。面接の場では、求職者は緊張していたり、好印象を残そうと振る舞ったりするため、職場のリアルな課題までは見えにくいのが現実です。
たとえば看護師の場合、求人票では「残業ほぼなし」と記載されていたのに、実際は患者数の増加や急な処置対応で定時を過ぎることが日常的にある。医療事務の場合も「受付・会計業務が中心」と伝えていたはずが、入職してみると電話応対・レセプト請求・診療補助まで担う必要があり、想定以上に業務が広がっていた。こうした小さなズレが重なると「聞いていた話と違う」と感じ、数ヶ月で退職を考えるきっかけになってしまいます。
また、入職直後の新人は「自分に合うかどうか」を日々敏感に感じ取っています。人間関係や職場の雰囲気は、求人票や面接では完全に把握できない要素です。採用段階でこうした部分に十分に触れられていないと、本人の中に不信感が生まれやすくなり、「すぐ辞める」という判断につながるのです。
医療事務がすぐ辞める原因は「人間関係」と「業務範囲の広さ」
医療事務は「受付で患者さんとやり取りする」というイメージが強いですが、実際のクリニックでは役割が非常に多岐にわたります。患者の対応、電話応対、診療補助、レセプト請求、場合によってはカルテ管理や在庫確認まで任されることもあります。こうした幅広い業務に慣れていない人にとっては「思っていた以上に大変」という印象となり、早期退職の理由となりやすいのです。
さらに医療事務は、患者対応とスタッフ対応の両方が求められる職種です。受付で患者に厳しい言葉を浴びせられることもあれば、看護師や医師から迅速な対応を求められることもあります。板挟みのような状況が続くと、「自分はここに向いていない」と感じやすくなり、結果として「すぐ辞める」という選択をしてしまいます。
また、人間関係も大きなポイントです。クリニックは少人数で運営されるケースが多く、相性の合わない同僚や上司が一人いるだけで職場全体が働きにくくなることがあります。大規模病院であれば異動や配置換えの余地がありますが、クリニックではその余地が少ないため、「環境を変える=辞める」という判断が早くなりやすいのです。採用段階で「この職場はどのような連携スタイルなのか」を正直に伝えることが、医療事務の早期離職を防ぐうえで不可欠だといえます。
看護師がすぐ辞めるのは「働き方の相性」が合わないから
看護師がクリニックに転職してすぐ辞めてしまう背景には、「働き方の相性」の問題があります。病棟勤務の経験がある看護師にとって、クリニックは「定時で帰れる」「比較的落ち着いている」というイメージを持たれることが多いですが、現実には異なる側面もあります。
例えば、午前と午後にそれぞれ外来診療がぎっしりと詰まっているクリニックでは、短時間で患者を効率よく対応する力が求められます。点滴・採血・処置を限られた時間で行いながら、急患が飛び込むこともある。さらに、医師の診療スタイルによっては看護師がサポートに回る場面が多く、裁量が少なく感じることもあります。こうした現場の特徴を理解せずに入職すると、「思っていた働き方と違う」というギャップが強くなり、すぐに辞めてしまうケースが生まれます。
また、ライフステージの変化も影響します。子育てや介護と両立する目的でクリニックに転職した看護師にとって、柔軟なシフト対応がない職場は致命的です。急な休みに理解がない、残業が続く、といった状況は「家庭と両立できない」と感じる要因になり、結果として短期離職につながります。採用時点で「どのような働き方が可能か」を具体的に示すことが重要です。
採用基準が「スキル重視」すぎるとすぐ辞めるリスクが高まる
採用の場面で「即戦力が欲しい」という思いから、資格や経歴ばかりに目を向けるケースは少なくありません。しかし、看護師・医療事務の定着率においてはスキルだけでなく「人柄」や「価値観」が極めて重要です。
たとえば、医療事務であればレセプト業務の経験が豊富な人材を採用しても、患者への対応が冷たいとクリニック全体の雰囲気が悪化します。看護師であれば技術は優れていても、院長や他の看護師との連携を軽視するタイプであればチームワークに支障をきたします。いくらスキルが高くても文化や人間関係に合わなければ「すぐ辞める」可能性が高いのです。
逆に、経験が浅くても素直に学ぶ姿勢があり、院長やスタッフと価値観を共有できる人材は長期的に定着する傾向があります。採用の際に「この人はスキルがあるか」だけでなく「この職場に馴染めそうか」「患者やスタッフと円滑にやり取りできそうか」といった視点を持つことが、早期離職の防止につながります。
採用活動を「人材の補充」としてではなく「職場文化に合う仲間を見つける取り組み」と捉えることで、結果的に定着率を高めることができます。
面接での見極め方:応募者の価値観に注目する
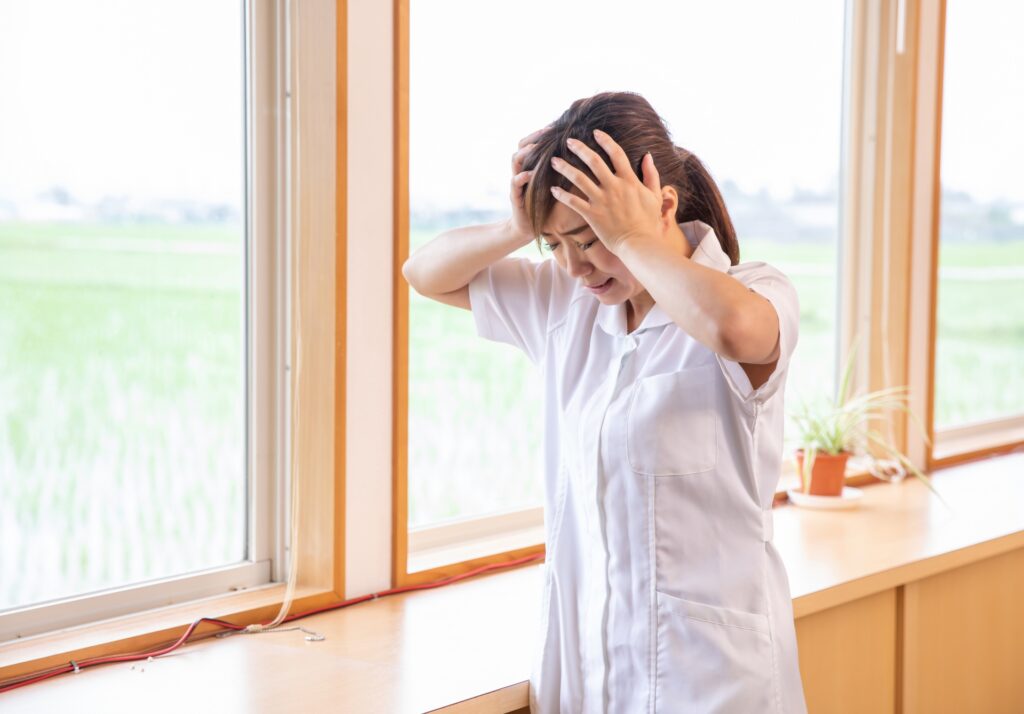
看護師・医療事務の採用で大切なのは「価値観の一致」
採用面接において、多くのクリニックは職務経験や資格を中心に確認します。もちろん必要なスキルや知識を持っているかどうかは重要ですが、それだけでは定着率は上がりません。むしろ看護師や医療事務が「すぐ辞める」背景には、仕事内容や条件よりも「価値観の不一致」があることが多いのです。
例えば、看護師が「患者一人ひとりと丁寧に関わりたい」と考えていても、実際の現場ではスピード重視で短時間対応を求められることがあります。逆に医療事務が「効率的に事務処理を進めたい」と思っていても、実際には患者との対話や柔軟な対応が必要とされる場面が多い。こうした価値観の食い違いは、数ヶ月で辞める原因になります。
面接の際は、応募者がどんな価値観を持っているのかを掘り下げて聞くことが欠かせません。「あなたがやりがいを感じる瞬間はいつですか?」「前職で働きづらいと感じたことは?」といった質問を投げかけると、応募者の本音が見えてきます。条件やスキルではなく価値観の一致こそが、採用の成否を左右する要素といえるでしょう。
医療事務がすぐ辞めるのを防ぐための質問例
医療事務は患者とクリニックの「顔」となる存在であるため、人との関わり方や考え方を見極めることが重要です。スキルや経験だけで採用すると、入職後に「思っていた仕事と違う」と感じてすぐ辞めるケースが少なくありません。
面接では、以下のような質問が効果的です。
「患者から不満を言われたとき、どのように対応しましたか?」
「チームで意見が分かれたとき、どのように調整しましたか?」
こうした質問に対する答えから、応募者が「感情的にならず冷静に対応できるタイプ」なのか、「すぐに人のせいにしてしまうタイプ」なのかが見えてきます。医療事務は日々の小さなやり取りが積み重なる仕事だからこそ、採用段階で人柄や価値観を把握しなければなりません。条件に惹かれて入職しても文化や人間関係に合わなければ、数ヶ月で辞める可能性が高いのです。
看護師の採用面接で確認すべき「働き方のスタンス」
看護師を採用する際、採血や点滴の経験などの技術的な確認は必要ですが、それ以上に重視すべきは「働き方のスタンス」です。すぐ辞める看護師の多くは「チームとの関わり方」や「働き方への期待値」がずれていることが原因です。
面接では、「忙しい時間帯に同僚が困っていたらどうしますか?」「自分のミスで患者に迷惑をかけたとき、どう対応しましたか?」といった質問を投げかけてみましょう。こうした質問に対して「私は私の仕事を優先します」と答える人と、「まず助けに入ります」と答える人では、文化へのフィット感が大きく違います。
さらに「前職を辞めた理由」を深掘りすることも有効です。待遇や条件だけを理由に挙げる人は、同じような不満があればまた辞める可能性があります。一方で「人間関係がうまくいかなかった」「価値観が合わなかった」と答える人は、その経験から学んでいるかどうかを確認することで、定着の可能性を見極めることができます。
採用面接は「質問」ではなく「対話」の場にすることがポイント
面接を単なる質問の羅列にしてしまうと、応募者は準備された答えを並べるだけで終わってしまいます。その結果、スキルや条件しか見えず、価値観や人柄を掴むことができません。採用で大切なのは「この人が本当にこの職場でやっていけるか」を知ることであり、そのためには面接を「対話の場」に変える必要があります。
具体的には、院長や採用担当者が自分の価値観を話し、それに対して応募者がどう感じるかを聞くのも効果的です。「うちのクリニックは患者さんとの対話を大事にしていますが、あなたはどう思いますか?」といった形で投げかけると、応募者の価値観とのズレが浮かび上がります。
また、短時間ではなく余裕を持って会話することも重要です。10分程度の面接では見えない部分も、30分以上の対話の中で自然と出てきます。応募者の価値観やスタンスを知るためには、形式的な面接ではなく、双方向のコミュニケーションを意識することが不可欠です。
入職後の定着率を高めるサポート体制

看護師・医療事務がすぐ辞めるのを防ぐには「初期サポート」が欠かせない
入職後の最初の数週間は、看護師や医療事務が職場に馴染めるかどうかを決める重要な期間です。この段階で安心感を持てないと、「ここは自分には合わない」と感じてすぐ辞める可能性が高まります。
看護師の場合、初日から医師の補助や処置を任されると不安が強くなりがちです。医療事務も、受付業務に加えてレセプトや電話対応まで一度に求められると「ついていけない」と感じやすくなります。そこで必要なのが、業務を段階的に教える初期サポート体制です。
例えば「最初の1週間は受付業務のみ」「2週目からレセプトの補助」といった流れを明確にすることで、新人が安心して学べます。さらに「困ったことがあれば誰に相談すればよいか」を最初に伝えておくことで孤立感を防げます。採用の段階だけでなく、入職直後のサポート体制が定着率を左右するのです。
医療事務が定着するためには「フォロー体制」と「感謝の言葉」が重要
医療事務は患者やスタッフからの依頼が集中しやすく、業務量の多さに圧倒されて辞めるケースが目立ちます。特に入職したばかりの頃は、電話や会計に追われる中で「誰も助けてくれない」と感じるとモチベーションが下がりやすいのです。
そこで必要なのが「フォロー体制」です。具体的には、1人のベテランスタッフがメンター役として新人の相談役になる方法があります。「何かあればこの人に聞けば大丈夫」という安心感は、入職後の定着を大きく後押しします。
また、忙しい現場では感謝の言葉が省かれがちですが、「ありがとう」という一言は非常に大きな効果を持ちます。特に医療事務は縁の下の力持ちとして働く場面が多いため、感謝を口にする文化があるかどうかで職場の印象は大きく変わります。採用だけでなく、日々のフォローと感謝の積み重ねが定着率を高めるカギになります。
看護師がすぐ辞めるのを防ぐ「教育と相談の場」
看護師は医療行為に直接関わるため、失敗に対する不安や責任感から早期退職につながることがあります。とくに新しい職場では「前の病院ではこうしていたが、このクリニックでは違う」という戸惑いが生まれやすく、その違いに慣れるまでが大きな壁になります。
ここで有効なのが「教育と相談の場」を意識的に用意することです。例えば週に一度、先輩看護師が新人と15分だけ振り返りの時間を持つ仕組みを作ると、悩みを早期に解消できます。小さな疑問が放置されると不安が膨らみ、「すぐ辞める」という判断につながるため、日常的に声をかけることが大切です。
さらに、研修の進め方もポイントです。一度に多くを詰め込むのではなく、段階的にスキルを習得させることで「できることが増えている」という成長実感を持たせられます。この小さな成功体験が積み重なることで、職場への信頼感が強まり、定着率が高まります。
採用後に必要なのは「評価と成長の実感」を与える仕組み
入職後の看護師や医療事務がすぐ辞めるのは、「努力が認められていない」と感じることも一因です。毎日忙しく働いても、誰からも評価されないと「ここにいる意味がない」と思ってしまいます。
そこで重要なのが「評価と成長の実感を与える仕組み」です。例えば、1か月ごとに院長や管理者が面談を行い「ここができるようになったね」とフィードバックするだけでも効果があります。形式的な評価制度を作る必要はなく、日常的に成長を言葉にして伝えることが大切です。
また、新しい業務を任せる際には「これはあなたに期待しているからお願いする」と伝えることで、本人のモチベーションが高まります。採用で迎え入れた人材を「仲間」として扱う姿勢が、安心感につながり、長く働き続けたいという気持ちを引き出すのです。
定着率を上げるためにクリニックで明日からできること

看護師・医療事務を採用したら「歓迎の場」を必ず設ける
看護師や医療事務が入職した直後は、期待と不安が入り混じる時期です。このタイミングで「歓迎されていない」と感じると、孤立感が強まり、すぐ辞める可能性が高まります。小さなことですが「歓迎の場」を用意するだけで定着率は変わります。
例えば昼休みにスタッフ全員で一緒に食事をする、終業後に10分だけ歓迎ミーティングを行うなど、特別な準備は不要です。「あなたを仲間として迎え入れている」という雰囲気をつくることが目的です。
歓迎の場を持つことで、看護師や医療事務は「ここでやっていけそう」と感じやすくなります。採用活動のゴールは「入職」ではなく「定着」です。歓迎の一歩を踏み出すだけで、長期的な安心感につながります。
医療事務がすぐ辞めるのを防ぐ「相談できる仕組み」
医療事務は患者やスタッフからの依頼が集中しやすく、ストレスを抱えやすい職種です。入職直後から一人で業務を抱え込むと、「助けてもらえない」と感じ、すぐ辞める理由になります。
そこで重要なのが「相談できる仕組み」です。例えばLINEやチャットツールで「業務の悩みを気軽に相談できる窓口」を設けること。あるいは、毎週決まった時間に短い面談を実施し、「最近どう?」と声をかけるだけでも効果があります。医療事務は「忙しいから仕方ない」と放置されがちですが、気軽に相談できる環境があれば踏みとどまれる可能性が高まります。
採用段階で「うちは相談できる仕組みがあります」と伝えておけば、応募者も安心して入職を決めやすくなります。制度そのものは小さな工夫で十分ですが、実際に運用しているかどうかが定着率を左右するのです。
スタッフの行動を「カルチャーの表現」として肯定する
カルチャーは「理念」ではなく、「日々の行動の積み重ね」によって表現されます。そのため、スタッフが取った行動の中に「うちらしい」と感じたものがあれば、それを言葉にして返すことが大切です。
たとえば、「忙しいときに、自然と周りを見て声をかけてくれて助かりました」「患者さんの不安に一言添えていたのを見て、うちの良さが出ていると感じました」といった具体的なフィードバックは、スタッフの自信につながるとともに、他の人にも“こういうのがうちらしさなんだ”と伝わります。
このように「行動→肯定→共有」のサイクルがまわることで、カルチャーは自然と浸透していきます。
看護師の採用後は「小さな成功体験」を積ませる
看護師がすぐ辞める理由のひとつに「自分は役に立てていないのでは」という不安があります。クリニックは病院と比べて業務範囲が限られている反面、スピードと正確さが求められるため、慣れるまでにプレッシャーを感じやすいのです。
そこで効果的なのが「小さな成功体験」を意識的に積ませることです。例えば「今日は採血を3件担当してもらう」「受付の患者さん対応を一人でやってみる」といった小さな課題を与え、それができたらしっかりと褒める。これを繰り返すことで「自分もこの職場で役立っている」という実感が生まれます。
小さな成功体験が積み重なると、看護師は「自分はここで成長できている」と感じ、辞める理由が減っていきます。採用の場で「教育の流れ」を説明し、入職後にその流れを実践することが、長期的な定着につながります。
採用した人材をすぐ辞めさせないための「日常の工夫」
定着率を上げる取り組みは、大がかりな制度ではなく日常の小さな工夫から始められます。例えば、忙しい診療の合間に「ありがとう」と声をかけること。ミスを責めるのではなく「次はこうしてみよう」と前向きな言葉を使うこと。昼休みに雑談を交えてスタッフ同士がリラックスできる時間を持つこと。
これらは一見些細ですが、積み重なると「この職場は居心地がいい」と感じる大きな要素になります。看護師や医療事務がすぐ辞める理由は、待遇ではなく「人間関係や雰囲気」に起因するケースが多いため、日常的な工夫が何よりも効果的です。
また、患者からのクレームや急な対応でスタッフが疲れているときこそ、院長や管理者が声をかけることが大切です。採用で迎え入れた人材を守り、安心させるのは職場全体の責任です。明日からできる小さな行動が、長期定着への最短ルートとなります。
看護師や医療事務がすぐ辞める背景には、給与や待遇ではなく「職場文化との相性」や「入職後の安心感」の不足が大きく関わっています。採用の段階で価値観を見極め、入職後には段階的な教育やフォローを行うことが、定着率を高めるための鍵です。また、日常の小さな工夫や感謝の言葉が「居心地の良さ」を生み、長く働きたいと思える職場へとつながります。採用活動を条件だけで行うのではなく、クリニックのありのままを伝える姿勢こそが、信頼できる仲間を集める最短ルートです。
ただし、院長自身が診療の合間にその準備や発信を続けるのは現実的に難しい場合もあります。そこで採用業務をアウトソーシングすることで、第三者の客観的な視点から正しくクリニックの魅力を伝えることが可能になります。忙しい院長に代わり、HOAPが採用をまるごと支援します。
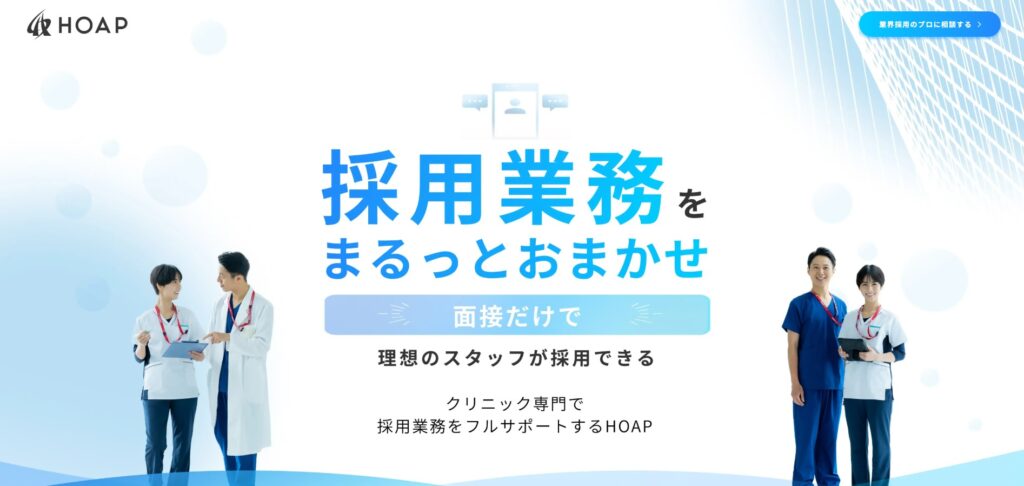
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。