訪問看護の現場では、新人や若手スタッフの教育に悩む声が少なくありません。「病院での経験があるのに、訪問では戸惑っている」「先輩が付きっきりで指導する時間が確保できない」といった課題は、多くの事業所で共通しています。背景には、病棟と在宅とで求められる役割が大きく異なること、そして現場の多忙さから従来の指導スタイルが機能しにくくなっている現状があります。
従来は「先輩の後ろを見て学ぶ」OJTが教育の中心でした。しかし、利用者ごとに状況が大きく異なる訪問看護では、単なる模倣だけでは対応しきれません。また、世代の変化により、若手スタッフは「なぜそうするのか」を理解しながら学ぶことを求めています。教える側も「感覚で伝える」方法では十分に伝わらず、互いに負担を感じやすい状態が続いています。
一方で、時代の流れとともに教育の在り方も変わりつつあります。研修を「一方向の指導」ではなく「双方向の学び合い」に転換する動きや、デジタルツールを活用した事例共有、ケース会議を教育の場に変える取り組みなど、新しい工夫が生まれています。教育の方法を時代に合わせて見直すことは、定着率やモチベーションの向上にも直結する重要なポイントです。
本記事では、訪問看護における教育がどのように変化してきたのかを整理し、従来のやり方が抱える課題、新しい学び方の方向性、そして明日から現場で活かせる工夫について解説していきます。
なぜ訪問看護の「教育」が難しいのか?

訪問看護における教育・研修は、病院や施設とは大きく異なる難しさを抱えています。病棟勤務では複数のスタッフが同じ患者を担当し、同じ空間で共通の経験を積むことができます。しかし訪問看護では、利用者の自宅という多様な環境に一人で入り、看護師自身が即座に判断しなければならない場面が多く発生します。そのため、従来の「先輩に付き添って学ぶ」教育方法だけでは不十分であり、時代の変化とともに学び方の見直しが求められています。以下では、教育が難しい理由を4つの視点から掘り下げていきます。
個別性が高い在宅環境が新人を戸惑わせる
訪問看護では、利用者ごとに生活環境や疾患の背景が大きく異なります。例えば、同じ「糖尿病」と診断されていても、一人暮らしの高齢者と家族に支えられている中年層とでは、支援の方法が全く違います。新人が現場に入ると、「教科書に書かれている通りに進めても通用しない」という壁に直面します。
病院勤務であれば、マニュアルや先輩の指示に従えば同じ対応を再現できますが、訪問看護では利用者の家の広さ、家族の関わり方、経済状況、宗教的な背景まで影響するため、画一的な方法では成り立ちません。これにより、教育担当者も「どこまでを標準として教えればいいのか」「個別対応の経験をどう伝えればいいのか」と迷いやすいのです。
このように、個別性の高さが教育を難しくしており、訪問看護の教育の方法は時代の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。
OJT中心の指導では限界がある
従来の訪問看護の研修はOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が中心でした。先輩看護師の訪問に同行し、実際の現場で学ぶという方法です。しかし、OJTには以下の課題があります。
・先輩の指導スタイルに依存しやすく、内容にばらつきがある
・忙しい業務の中で十分な解説や振り返りができない
・新人が「質問してはいけない」と萎縮しやすい
特に人手不足が続く現在、教育担当者がゆっくりと時間をかけて新人を育てることが難しくなっています。結果として、新人は「同行の回数が終わったら一人立ち」という形になりやすく、不安を抱えたまま訪問に出るケースが少なくありません。
OJTが全く不要になるわけではありませんが、それだけに頼る教育方法はすでに限界を迎えています。今後はOJTを補完する体系的な訪問看護の研修の仕組みを整えることが不可欠です。
世代ごとの学びの価値観の違い
教育が難しいもう一つの理由は、世代ごとの学び方の価値観の違いです。かつては「先輩の背中を見て覚える」「失敗から学ぶ」が当たり前でした。しかし近年の若手看護師は、根拠を理解し納得しながら学ぶことを重視します。
「なぜその判断をするのか」を明確に説明できなければ、新人は自信を持って行動できません。逆に説明が不足すると「言われた通りに動くしかない」と考え、主体性を失いやすくなります。
また、近年は働き方改革やワークライフバランスの意識も高まっており、「長時間かけて経験で学ぶ」スタイルは敬遠されがちです。こうした価値観の変化は、訪問看護の教育・研修にも大きな影響を与えており、従来型の指導だけでは人材が定着しない要因にもなっています。
教える側も教育スキルを求められている
訪問看護に長く従事してきたベテラン看護師であっても、「人に教える」スキルは別の能力です。経験豊富だからといって、自動的に教育担当者として適任になるわけではありません。
例えば、感覚的にできることを言語化できず「こういう時はこうするもの」と伝えてしまうと、新人は納得できず不安が残ります。また、教育担当者自身が「教える負担」を強く感じ、燃え尽きてしまうケースもあります。教育は「知識や技術を伝えること」だけでなく、「相手の理解度に合わせて伝え方を変えること」
も含まれます。そのため、訪問看護における教育担当者には、臨床経験に加えて教育の視点を持つことが求められるようになっています。
訪問看護の教育・研修が難しい理由は、
①個別性の高い在宅環境
②OJT中心の限界
③世代ごとの学び方の違い
④教育担当者自身の課題
という4点に集約されます。これらの要素は訪問看護の教育・研修に関する悩みの根本であり、従来のやり方だけでは対応しきれません。
次の章では、こうした課題を踏まえて「従来型の指導がなぜ限界を迎えているのか」について、さらに掘り下げていきます。
従来型の指導が限界を迎えている理由
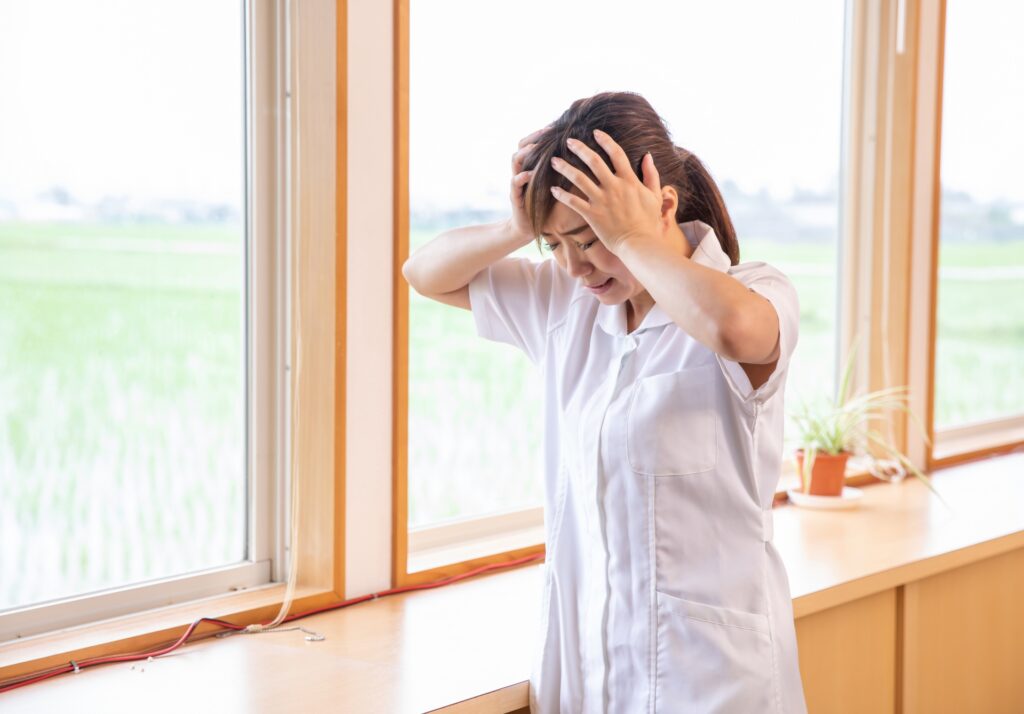
訪問看護における教育・研修の中心は、長らくOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に支えられてきました。先輩看護師に同行し、現場を見て学ぶことは確かに効果的です。しかし、時代の変化とともに従来の指導スタイルでは限界が見えるようになっています。本章では、その理由を4つの視点から解説します。
業務の多忙化で「教える余裕」が失われている
訪問看護の現場は慢性的な人手不足に直面しています。利用者数の増加に加え、医療依存度の高いケースも増えており、看護師一人ひとりの負担は年々大きくなっています。
本来であれば、教育には「立ち止まって解説する時間」が必要です。しかし実際には、次の訪問に追われる中で十分な指導を行うことが難しく、「この場面はこうして」と指示を出すだけになりがちです。新人からすると理由が分からず、先輩からすると説明できなかったことに後ろめたさを感じるという双方の不満が残ります。
こうした状況が積み重なると、「新人が定着しない」「ベテランも疲弊する」という悪循環を招き、結果的に教育体制そのものが機能しなくなります。訪問看護の教育が従来型では限界を迎えている理由の一つは、この「教える余裕の欠如」にあります。
感覚依存の指導が再現性を持たない
従来のOJTでは、ベテランが自分の経験や感覚に基づいて指導することが一般的でした。例えば「この患者さんの顔色を見て異変を察知する」といったスキルは、確かに重要ですが言語化されにくく、学び手には伝わりづらい部分です。
結果として、新人は「なんとなく先輩がそう言ったから」という理由で動くことになり、状況を判断する力が育ちにくくなります。感覚依存の教育は、指導者の質に大きく左右されるため、組織全体として均一な研修効果を得ることができません。
時代の変化に伴い、看護の現場では「根拠をもって説明する」姿勢が求められるようになっています。にもかかわらず、従来型の教育ではその基盤が欠けており、再現性のある学びにつながりにくい点が限界として浮き彫りになっています。
学びのスタイルが世代の価値観とずれている
教育の限界を示すもう一つの要因は、若手世代との学びのスタイルの不一致です。かつては「とにかく経験して覚える」ことが当たり前でした。しかし、今の新人は「なぜそうするのか」を理解し、納得して動きたいというニーズを持っています。
この違いを軽視して「昔はこうだった」と押し付けると、新人は不満を抱き、職場に馴染む前に離職してしまうリスクが高まります。また、ワークライフバランスを重視する傾向も強く、「時間をかけて慣れる」というスタイルは敬遠されがちです。
つまり、時代の変化によって研修の在り方を見直さなければ、次世代の人材確保が難しくなります。教育の手法が若手の価値観に合わないままでは、人材が定着しないという現実が限界を物語っています。
教える人材の育成が追いついていない
訪問看護における教育は、ベテランが担うケースが多いのが現状です。しかし、経験が豊富だからといって必ずしも教育スキルがあるとは限りません。むしろ、長年の感覚で動いてきたからこそ、初心者にどう説明すればよいのか分からないこともあります。
さらに、教育担当者自身が業務に追われて余裕を失い、負担感を強めるケースも少なくありません。その結果、「教えるのは大変だからやりたくない」という空気が広がり、教育体制そのものが弱体化してしまいます。
訪問看護の教育・研修が限界を迎えている背景には、教える人材を育成する仕組みが不足していることも大きく影響しています。
従来型の指導が限界を迎えている理由は
①業務の多忙化
②感覚依存による再現性の欠如
③世代との価値観のズレ
④教育担当者の育成不足
の4点に整理できます。これらは訪問看護の教育・研修が直面する根本的な問題であり、時代の変化に合わせた新しい学びの形が求められていることを示しています。
次の章では、この限界を乗り越えるために必要な「新しい学び方」について具体的に掘り下げていきます。
訪問看護に必要な「新しい学び方」とは?

訪問看護の教育・研修は、これまでのOJT中心のやり方では限界を迎えていることを前章で確認しました。では、その課題を乗り越えるために、これからどのような「新しい学び方」が必要とされるのでしょうか。時代の変化に合わせ、現場ではすでにいくつかの工夫が始まっています。本章では、訪問看護に適した新しい学び方を4つの観点から整理していきます。
双方向の学び合いによる教育への転換
従来の教育は「先輩が教え、後輩が学ぶ」という一方向的なものでした。しかし、訪問看護では状況が多様であるため、教える側にも「学び直し」が必要になる場面が少なくありません。
例えば、新人が大学で学んできた最新の知見やICT活用のスキルを共有することで、ベテランにとっても新しい発見が生まれることがあります。こうした双方向のやりとりは、単なる知識伝達ではなく「共に考える」教育に変わっていく鍵になります。
つまり、訪問看護の教育においては「上下関係の中で学ぶ」から「対話を通じて学び合う」スタイルへの転換が必要なのです。これが新人に安心感を与えるだけでなく、ベテランにとっても成長の機会となり、組織全体の活性化につながります。
失敗を振り返り成長につなげる仕組み
訪問看護の研修で重要なのは「失敗をどう扱うか」です。従来は失敗がタブー視されやすく、「できなかった自分」を責める文化が根強くありました。しかし時代の変化とともに、失敗を共有し学びに変えることが重視されるようになっています。
具体的には、事例検討会やケースカンファレンスを「ミスを隠す場」ではなく「学びを深める場」として位置づける取り組みです。失敗を共有し、「なぜ起こったのか」「次にどう活かすのか」をチームで考えることで、再発防止とスキル向上の両方を実現できます。
このような「失敗を成長に変える仕組み」は、新人の不安を軽減し、安心して挑戦できる教育環境を整えるうえで欠かせません。
デジタル教材や事例共有の活用
訪問看護の教育を効率化する上で、ICTの活用は欠かせません。近年では、動画教材やオンライン研修システムを取り入れる事業所も増えています。
例えば、先輩の訪問場面を動画で撮影し、解説を付けて共有すれば、新人は自分のペースで何度でも学び直すことができます。さらに、全国の訪問看護事業所が参加できるオンライン勉強会やケーススタディのプラットフォームを活用すれば、地域を超えた知識の交換が可能になります。
デジタルツールの導入は「時間や場所に縛られない学び」を実現するため、業務が多忙な訪問看護師にとって有効な研修手段です。これはまさに、時代の変化に沿った新しい学び方といえるでしょう。
利用者・家族との対話から学ぶ姿勢
訪問看護の現場における最大の教材は、実は利用者やその家族です。利用者の生活背景や価値観を理解する過程で、新人は「マニュアルにない答え」を数多く見つけ出します。
例えば、服薬管理が難しい高齢者に対し、ただ指示を繰り返すのではなく、家族と協力して習慣化の工夫を探る過程は、教科書では得られない学びです。この「生活に寄り添う看護」こそ訪問看護の本質であり、利用者・家族との対話は教育そのものといえます。
従来の「先輩から学ぶ」だけでなく、「利用者と向き合う中で学ぶ」という姿勢を組み込むことが、新しい訪問看護教育の柱となります。
訪問看護に必要な新しい学び方は
①双方向の学び合い
②失敗を振り返る仕組み
③デジタル教材の活用
④利用者や家族との対話
という4つの視点に整理できます。これらは訪問看護の教育・研修の課題を乗り越え、時代の変化に即した学びの形を実現するものです。
次の章では、こうした学び方を実際の現場でどう研修体制に組み込むか、その具体的な工夫について解説します。
訪問看護の現場でできる研修体制の工夫

訪問看護の教育・研修を時代の変化に合わせて強化するには、「新しい学び方」を現場でどう実践に落とすかが重要です。いくら理念や理想を語っても、日々の業務の中に浸透しなければ教育効果は得られません。本章では、現場で取り入れやすい研修体制の工夫を4つの観点から解説します。
ケース会議を「学びの場」に変える
訪問看護ステーションでは定期的にケース会議が行われますが、多くは「情報共有」にとどまっています。これを「教育の場」として活用する工夫が有効です。
例えば、単に「この利用者にこう対応した」と報告するだけでなく、なぜその判断をしたのか、どのような選択肢があったのかを振り返り、全員で検討します。これにより、報告者自身が学び直すだけでなく、他のスタッフも自分の現場に置き換えて考えることができます。
さらに、会議の中で「成功例」だけでなく「迷った場面」「失敗した経験」を積極的に取り上げることも大切です。これにより、「失敗を共有して学ぶ文化」が育ち、教育効果が高まります。
新人・中堅・ベテランの役割分担を明確にする
訪問看護の教育体制では、誰がどのように指導に関わるかが不明確なままになりがちです。その結果、特定のベテランに負担が集中し、教育が継続できなくなることがあります。
これを防ぐには、新人・中堅・ベテランそれぞれの役割を明確にすることが重要です。例えば、
新人教育:基礎的な業務や記録の書き方は中堅が担当
専門性の高い判断:ベテランがケースごとに指導
振り返りや相談:管理者が面談でフォロー
このように分担することで、教育の負担が分散し、誰もが無理なく関われる体制になります。また、中堅スタッフに教育を任せることで、彼ら自身の成長機会にもなります。
教育担当者を支援する仕組みを整える
教育担当者が安心して指導できるように、支援体制を整えることも欠かせません。具体的には以下のような工夫が考えられます。
指導マニュアルやチェックリストの整備:何をどの順番で教えるかを明確にしておく
教育担当者同士の情報交換会:教え方の工夫や悩みを共有する場を設ける
外部研修や講座の活用:教育スキルを磨く機会を提供する
訪問看護の教育は「経験豊富だから教えられる」という単純なものではありません。教える側も学び続ける必要があります。教育担当者への支援が不足すると、指導者が燃え尽きてしまい、教育体制全体が崩れるリスクがあります。したがって、「教える人を育てる」視点を持つことが、長期的な研修の成功には不可欠です。
外部の知見や仕組みを積極的に取り入れる
訪問看護は事業所ごとに規模が小さいため、教育や研修をすべて自前で賄うのは難しい場合が多いです。そこで、外部の仕組みや専門家を活用することも有効です。
例えば、地域の訪問看護ステーション同士で合同勉強会を開けば、異なる事例に触れる機会が増えます。また、医師やリハビリ職といった多職種と連携した研修を行えば、利用者支援の幅広い視点を学ぶことができます。さらに、オンライン研修サービスやeラーニングを導入すれば、隙間時間を使って知識をアップデートできます。
このように「外に開く」姿勢を持つことが、教育体制を強化する近道です。自分たちだけで抱え込むのではなく、外部の知見を取り入れることで、時代の変化に柔軟に対応できる教育が実現します。
訪問看護における研修体制の工夫は
①ケース会議を学びの場にする
②役割分担を明確にして負担を分散する
③教育担当者を支援する仕組みを整える
④外部の知見を取り入れる
という4つの視点が重要です。これらを実践することで、日々の業務の中で教育を継続できる環境が整い、訪問看護の教育・研修が時代の変化に対応したものへと進化します。
次の章では、こうした研修体制を踏まえ、実際に現場で明日からできる具体的な教育改善アクションについて解説します。
明日からできる訪問看護の教育改善アクション

ここまで、訪問看護における教育や研修が抱える課題と、時代の変化に合わせた新しい学び方や体制の工夫について解説してきました。しかし、現場にいる管理者や教育担当者が最も知りたいのは、「では明日から何をすればよいのか」という具体的な一歩でしょう。本章では、すぐに取り組める教育改善のアクションを5つ提示します。
教え方を「一律」から「相手に合わせる」へ
訪問看護の教育では、新人や若手の背景や理解度に応じた指導が不可欠です。病棟経験が豊富な人と、訪問未経験の新人とでは、必要な研修内容もペースも異なります。
明日からできる工夫としては、同行訪問の後に「理解度チェック」の時間を短く設けることです。単に「わかった?」と聞くのではなく、実際に言葉で説明してもらうことで理解の深さが確認できます。その上で、相手が不足している部分を補う形で指導すれば、効率的に教育を進められます。
このように「一律に教える」のではなく「相手に合わせる」ことが、訪問看護 教育の質を高める最初のアクションです。
成功より「失敗の共有」を歓迎する文化をつくる
訪問看護の研修で軽視されがちなのが「失敗談」の共有です。成功例ばかりを発表する場では、新人は「自分だけできていない」と孤立感を抱きやすくなります。
そこで、ケース会議や振り返りの時間に「一番悩んだこと」「困ったこと」を出し合う場を設けるのが効果的です。失敗を否定せず、「その経験から何を学んだか」を語り合うことで、職場全体が学びの共同体として機能します。
明日からできる小さな取り組みとして、「今日の訪問で戸惑ったことを一つ共有してください」と問いかけるだけでも、教育の質は大きく変わります。
デジタルを活用して「隙間時間に学べる」仕組みを導入する
業務の多忙さを理由に研修が後回しになりがちですが、時代の変化に合わせてデジタル活用を進めることで改善できます。例えば、先輩の対応を短い動画で撮影し、社内共有フォルダやクラウドにアップロードすれば、新人は訪問の合間や移動時間に学習できます。
また、外部のオンライン研修サービスを利用すれば、最新の知識を効率的に取り入れることが可能です。「教育は時間が取れないからできない」という言い訳を減らすためには、学びを日常業務の中に自然に組み込む工夫が必要です。
小さな一歩としては、「まずは月に1本、動画教材を共有する」といった取り組みから始めると無理なく浸透していきます。
教える側も「学び続ける姿勢」を示す
訪問看護の教育は、新人だけが学ぶのではなく、教える側も常に成長し続ける必要があります。ベテランが「私はもう十分知っている」と構えてしまうと、現場に新しい発想が入らなくなります。
そこで、教育担当者自身が「最近の研修で学んだこと」「自分が苦手だと感じること」を率直に共有することが有効です。これにより、新人も「完璧でなくてもいい」「一緒に学んでいける」と安心します。
明日からできる行動としては、指導の最後に「私も最近こんなことを学んだよ」と一言添えるだけで、教育の空気が大きく変わります。
訪問看護における教育改善のアクションは
①相手に合わせた指導
②失敗共有の文化
③デジタル活用
④教える側の学び直し
の4点に整理できます。これらはすぐに始められる実践的な取り組みであり、時代の変化に対応した訪問看護の教育・研修の基盤をつくることにつながります。
訪問看護の教育と研修は、従来のOJT中心では限界を迎え、時代の変化に即した新しい形が求められています。背景には、在宅環境の多様化や人材不足、世代ごとの学び方の違いがあります。その中で、双方向の学び合い、失敗の共有、デジタル活用、役割分担の明確化といった工夫が効果的です。大切なのは「どう教えるか」を一律に決めることではなく、相手や状況に合わせて柔軟に変化させる姿勢です。訪問看護の教育が進化すれば、現場で働く人材が安心して成長でき、結果として利用者への支援の質も高まっていきます。

監修者:牟田 健登(Kento Muta)
株式会社クルージズ・テクノロジーズ代表取締役。2021年に創業し、在宅医療・介護業界に特化した人事コンサルティング・人事評価SaaSを展開。訪問看護ステーションや訪問介護ステーションを中心にサービスを展開中。










