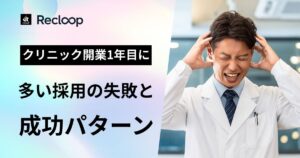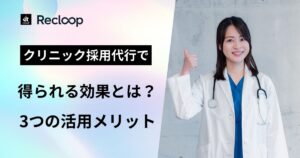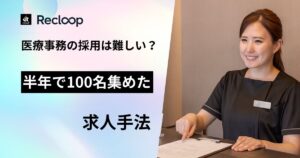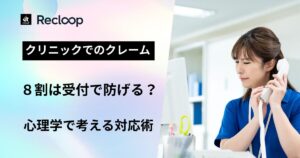スタッフが定着せず、採用してもすぐに辞めてしまう。この悩みは多くのクリニックで共通しています。求人を出しても応募が少なく、せっかく採用できた人材が短期間で退職してしまえば、現場は常に人手不足に追われることになります。残されたスタッフへの負担は増し、さらなる離職につながるという悪循環が生まれてしまいます。
なぜこのような事態が繰り返されるのでしょうか。給与や休暇といった待遇面だけが理由ではありません。人間関係のトラブル、教育やサポートの不足、キャリアの見通しが描けない不安、さらには経営者や管理者との信頼関係の欠如など、複数の要素が重なって「ここで働き続ける理由が見つからない」と感じさせてしまうのです。
実際、現場スタッフの声をたどると「忙しさで新人教育に手が回らない」「相談しにくい雰囲気がある」「先輩との価値観が合わない」といったリアルな課題が浮かび上がります。これは一見、個々の問題のように思えますが、経営や組織の仕組みとして改善できる部分が多く含まれています。
本記事では、クリニックでスタッフが定着しない理由を分解しながら、改善に向けた視点を提示します。そして「定着率を高めるために必要な考え方」「背景にある人間関係や教育の課題」「実際に現場で取り入れられる5つの解決策」を順に解説し、最後に明日から取り組める行動のヒントを示します。現場の課題を具体的にとらえ、解決に向けて一歩を踏み出すきっかけとしてください。
なぜクリニックのスタッフが定着しないのか?

クリニックで繰り返される「すぐ辞めてしまう」現象
クリニックにおいて、採用後まもなく退職してしまうケースは珍しくありません。せっかく時間とコストをかけて採用したスタッフが短期間で離職すれば、現場は大きなダメージを受けます。残された人材に業務が集中し、疲弊や不満が積み重なり、さらに離職者を生むという連鎖が起こります。これが「人材が定着しない職場」の典型的な流れです。
この現象の根底には、スタッフと組織との間にある「期待のずれ」が存在します。採用段階で描いた理想の働き方と、実際に経験する日々の業務との間にギャップがあると、スタッフは早い段階で失望してしまいます。「思っていた職場と違う」と感じた瞬間から、退職へのカウントダウンが始まっているのです。待遇や福利厚生だけでなく、仕事の進め方や教育体制、職場の雰囲気など、想定外の部分で違和感を覚えることが多く見られます。
また、現場では「即戦力を求めるあまり、新人を十分にフォローできない」という声もよく聞かれます。業務が回らない状況で新人教育に割ける時間は限られており、その結果「教えてもらえない」「質問しにくい」という不満を抱えやすくなります。こうした初期段階の失望や孤立感が、離職につながる大きな要因です。
クリニックでの給与や待遇だけでは解決できない理由
スタッフの定着について語られる際、「給与を上げれば解決するのでは」という単純な発想が出てきます。確かに待遇改善は重要な要素ですが、実際には給与や休暇制度だけで定着率が大幅に改善されるケースは限られています。なぜなら、働き続けるかどうかの判断には「心理的な安心感」や「成長の実感」といった無形の要素が強く影響しているからです。
例えば、同業他院と比較して給与が大きく劣っていなければ、金銭的な理由で退職する人は多くありません。それよりも「院長に相談できない」「スタッフ間の人間関係にストレスを感じる」といった日々の積み重ねが離職の引き金になります。給与は転職のきっかけにはなり得ますが、定着を左右する決定打にはなりにくいのです。
さらに、待遇改善は経営の負担も大きく、単独で長期的な効果をもたらすのは難しい現実があります。昇給や手当を厚くしても、働きにくい職場環境が変わらなければ、結局は離職が続いてしまいます。スタッフが「ここで働き続けたい」と思うためには、金銭以外の要素を満たす必要があるのです。
つまり、定着率向上のためには「給与や休暇」などの目に見える条件と同時に、「人間関係」「教育」「キャリアの展望」「職場の信頼感」といった目に見えにくい条件を満たすことが求められます。ここを軽視すると、いくら表面的な待遇を整えても根本的な解決にはつながりません。
クリニックでの人間関係と組織文化が与える影響
クリニックの現場において、離職理由の多くを占めるのが「人間関係」です。特に少人数で構成される組織では、一人ひとりの関係性が職場全体の雰囲気を左右します。チームワークが円滑であれば日々の業務もスムーズに回りますが、逆に一部の不和が職場全体をぎくしゃくさせることもあります。例えば、
「ベテランと新人の価値観の違い」
「管理職の指示が一方的」
「相談や意見を言いづらい雰囲気」
といった状況は、スタッフの働きやすさに直結します。誰かが孤立している状態が放置されると、安心して働ける環境は失われ、早期離職につながります。また「ミスを責められる」「失敗が許されない」といった職場風土では、チャレンジが難しくなり、学びの機会が減少します。その結果「ここで成長できない」と感じ、転職を選択するスタッフも少なくありません。
人間関係は「個人の性格」に帰属させてしまいやすい問題ですが、実際には組織のあり方によって大きく左右されます。風通しの良いコミュニケーションや、意見を尊重する文化があれば、多少の相性の違いがあっても大きなトラブルには発展しません。逆に、閉鎖的な環境では小さな誤解や摩擦が拡大しやすくなります。したがって、院長は「人間関係は自然に良くなるものではない」という前提を持ち、意識的に働きやすい文化をつくる必要があります。
クリニックでの教育・サポート不足が招く早期離職
新人スタッフが最も不安を感じるのは「自分がこの職場でやっていけるのか」という点です。十分な教育やフォロー体制が整っていないと、入職直後から孤立感や不安を抱えることになります。特にクリニックは限られた人数で業務を回しているため、「新人教育に割ける時間がない」という声が現場から多く上がります。その結果、スタッフは「教えてもらえない」「質問するのが気まずい」と感じ、職場に馴染む前に辞めてしまうのです。
教育不足の影響は単なるスキルの問題にとどまりません。適切に教えてもらえない環境は、スタッフに「自分は必要とされていない」という印象を与えます。また、失敗してもフォローしてもらえない場合、「ここで続けていくのは難しい」と早い段階で判断されてしまいます。これは離職の大きな要因のひとつです。
逆に、教育やサポートが整っている職場では、スタッフは安心して挑戦し、失敗から学ぶことができます。安心感があることで成長の実感を得やすくなり、働き続けたいという意欲が高まります。つまり、教育体制の不足は離職を加速させ、充実した教育は定着を後押しする分岐点となるのです。
以上のように、スタッフが定着しない背景には「待遇だけでは測れない職場のリアル」が存在します。次章では、こうした要因を踏まえたうえで、経営者が意識すべき考え方について掘り下げていきます。
クリニックでの定着率を高めるために院長が意識すべき視点
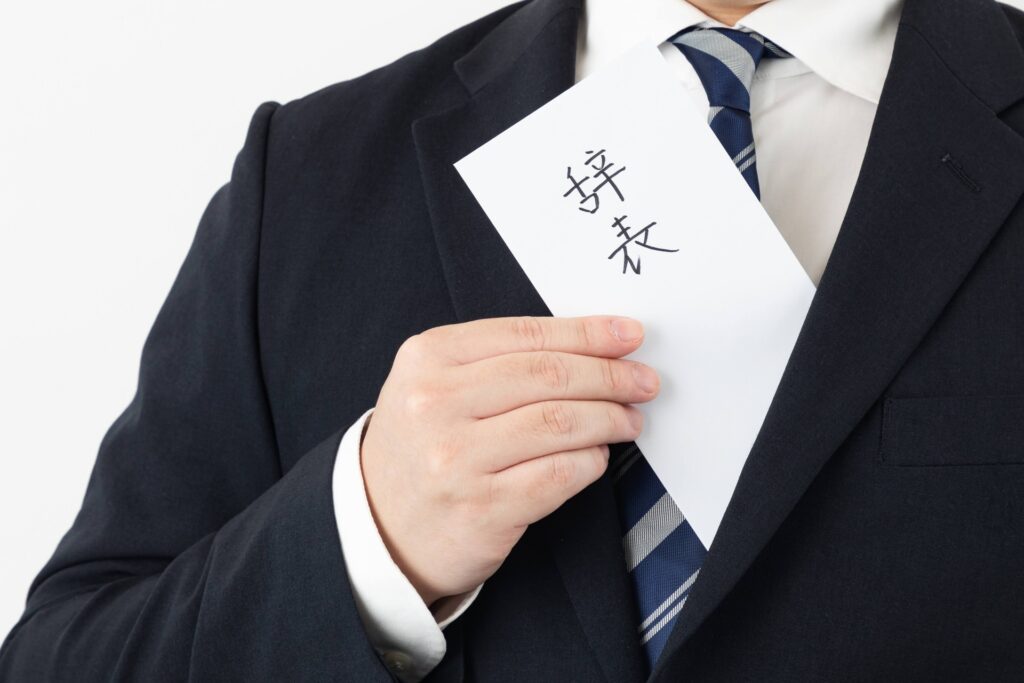
「働き続けたい」と思えるクリニックづくりの重要性
院長にとって最も大きな課題のひとつは、採用したスタッフをいかに長く働き続けてもらうかという点です。医療の現場は、患者対応、診療補助、事務処理など幅広い業務が同時進行するため、スタッフの入れ替わりが多いと常に混乱が生じます。新人が定着しない状況では、残されたスタッフが過度に負担を抱え、疲弊し、さらに離職が進むという悪循環が起こります。
定着率を高めるために必要なのは、「この職場なら長く働ける」とスタッフ自身が思える環境をつくることです。給与や休暇などの条件も重要ですが、実際には「安心して働けるか」「ここで成長できるか」という心理的な要素が大きな影響を与えます。特にクリニックは規模が小さい分、一人ひとりの存在感が大きく、組織の雰囲気に左右されやすい特徴があります。
そのため、院長は「診療を回すリーダー」であると同時に「スタッフが安心して力を発揮できる場を整える責任者」という視点を持つことが求められます。スタッフが退職を意識するのは、必ずしも大きな不満があるからではなく、小さな不安や違和感が積み重なった結果です。日々の働きやすさや人間関係への気配りこそが、長期的な定着につながります。
院長が持つべきクリニックでの心理的安全性
心理的安全性とは、誰もが安心して意見を出し合い、失敗を恐れずに行動できる状態を指します。これはチーム医療を支えるうえで欠かせない基盤です。心理的安全性が低い職場では、スタッフが自分の考えを発言できず、問題点が共有されないまま業務が進み、結果的に患者対応の質にも影響します。
院長が意識すべきは、「意見や相談が歓迎される雰囲気をつくること」です。たとえば、スタッフがちょっとした疑問や改善提案を話したときに「余計なことを言うな」と否定してしまえば、次からは口を閉ざしてしまいます。逆に「それはいい視点だね」「一緒に考えてみよう」と受け止めるだけで、安心感は大きく変わります。
また、ミスが発生した際の対応も重要です。ミスを責めるのではなく、「次にどう防ぐか」を共に考える姿勢を見せることで、スタッフは学びながら成長できます。失敗を共有できる環境があれば、スタッフは孤立感を抱かず、自分の役割に自信を持つようになります。
心理的安全性は一度失われると回復に時間がかかります。だからこそ院長は日常的にスタッフとコミュニケーションを取り、安心して働ける状態を守ることが欠かせません。安心感があれば、多少の困難があっても「ここで頑張ろう」と思える土台になります。
クリニック勤務でキャリアの見通しを描ける仕組みづくり
クリニックのスタッフが「長く働きたい」と思うためには、自分の未来を職場に重ねられることが大切です。給与や休日の条件が整っていても、「ここにいても成長できない」「役割が広がらない」と感じれば、将来を見据えて転職を考えてしまいます。
院長が意識すべきは「キャリアの見通しを提示すること」です。たとえば、新人には「入職1年目は基礎を学び、2年目からは業務の幅を広げる」といったロードマップを示す。ベテランには「後輩指導やチームリーダーの役割に挑戦してほしい」と伝える。こうした明確なステップがあることで、スタッフは自分の成長を実感しやすくなります。
さらに、定期的な面談を通じてスタッフの希望や不安を聞き取ることも欠かせません。「将来どうなりたいか」「どんな働き方を望んでいるか」を把握し、可能な範囲でサポートすることが、長期的な信頼関係につながります。キャリアの見通しがあることで、スタッフは「この職場に居続ける意味がある」と感じられるのです。
一方で、キャリア支援は大規模な仕組みを整える必要はありません。むしろクリニックの小規模性を活かし、一人ひとりに合わせた柔軟な働き方を提案できることが強みになります。院長の一言やちょっとした承認が、スタッフの未来へのモチベーションを大きく左右するのです。
クリニック院長自身の姿勢が定着率を左右する
最終的に、スタッフの定着に最も大きな影響を与えるのは院長自身の姿勢です。院長は診療のリーダーでありながら、職場全体の空気をつくる存在でもあります。スタッフは院長の言動から「この職場の価値観」を敏感に感じ取っています。
たとえば、患者対応に追われる中でもスタッフの努力を労う一言があるかどうかで、働き続けたいという気持ちは変わります。逆に、院長が常に忙しさを理由にスタッフとの対話を避けてしまうと、「ここでは大事にされていない」と感じ、退職のきっかけになりかねません。
また、院長が「定着はスタッフ次第」と考えてしまうと改善は進みません。定着率を高めるためには、院長自身が「スタッフの働きやすさを守るのは自分の役割」と捉えることが必要です。リーダーとしての姿勢を示すことで、スタッフは安心して職場に根を張ることができます。
さらに重要なのは「完璧である必要はない」という点です。院長が自らの弱みや課題を認め、スタッフと一緒に改善していく姿を見せることで、チームに一体感が生まれます。スタッフは「この院長についていこう」と思えるようになり、それが強固な定着につながります。
クリニック退職背景に潜む「人間関係」と「教育体制」

クリニック離職理由の大半を占める「人間関係のストレス」
クリニックにおける離職の大きな要因として最も頻繁に挙げられるのが「人間関係」です。スタッフ数が限られている小規模組織では、一人ひとりの関係性が職場全体の雰囲気を大きく左右します。少人数だからこそチームワークが発揮されやすい一方で、相性の悪さや価値観の違いが強く影響しやすいという側面もあります。
例えば、ベテランスタッフと新人の関わり方に温度差があるケースです。ベテランは「自分の経験を早く身につけてほしい」という思いから厳しい指導をすることがありますが、新人はそれを「威圧的」「相談しにくい」と感じやすくなります。また、院長が現場に細かく関与できない状況では、スタッフ同士の摩擦が放置されやすく、対立が深刻化することもあります。
このような人間関係のストレスは、仕事内容や待遇に不満がなくても離職を決断させるほど大きな要因です。どれだけ好条件の職場であっても「毎日一緒に働く人との関係」がぎくしゃくすれば、長く働き続けたいと思えません。つまり、院長がスタッフの定着を考える際には、人間関係をどう健全に保つかという視点が不可欠なのです。
クリニックで孤独感を生む「相談できない雰囲気」
人間関係の問題の背景には「相談できない雰囲気」があります。スタッフが疑問や悩みを抱えても、気軽に口にできない状況は大きなストレス要因です。特に新人にとっては「質問したら迷惑かもしれない」「こんなことも分からないと思われたくない」という不安が強く、結果として孤立感を深めてしまいます。
孤立したスタッフは、自分の居場所を見つけられず「この職場ではやっていけない」と判断することが多いものです。さらに厄介なのは、このような雰囲気が一度広がると、新しく入った人も同じように遠慮するようになり、職場全体に「声を上げにくい文化」が定着してしまうことです。
院長としては「相談できる雰囲気づくり」を意識的に行う必要があります。日常的にスタッフに声をかける、ミーティングで小さな疑問や意見も拾い上げる、個別面談で不安を聞き取るなど、コミュニケーションの場を設けることが有効です。声を上げやすい職場では、トラブルや不満が大きくなる前に対処でき、結果として定着率が高まります。
クリニックの教育体制の不足が離職を加速
クリニックの現場では「教育体制の不足」が定着を妨げる大きな要因です。新人スタッフは、業務の進め方や患者対応に慣れるまでに時間がかかります。しかし、現場が常に忙しく教育の余裕がない場合、十分な指導が行われないまま業務を任されることがあります。その結果「教えてもらえない」「失敗してもフォローがない」という不満が積み重なり、早期離職へつながってしまいます。
教育不足はスキル習得の問題にとどまりません。十分に指導されない状況は、スタッフに「自分は歓迎されていないのでは」「ここで成長できないのでは」という不安を抱かせます。心理的な負担が大きいまま働き続ければ、いずれ「この環境では長く働けない」と判断するのは自然な流れです。
一方で、教育体制が整っているクリニックでは、新人が安心して成長できるため、離職率は大きく下がります。マニュアルや研修があることはもちろん、先輩スタッフが積極的に声をかける、フォローアップ面談を行うなど、小さな工夫の積み重ねが定着を後押しします。教育体制の有無が、職場の未来を左右する要素といえるでしょう。
クリニック院長の関与が職場文化を変える
人間関係や教育体制の問題を解決するために欠かせないのは、院長自身の関与です。院長が現場に関心を持ち、スタッフと直接コミュニケーションを取ることで、職場文化は大きく変わります。逆に、院長が診療や経営に追われ、スタッフとの接点を持たない状況では、小さな不満や摩擦が放置されがちです。
院長が「この職場は相談していい」「失敗しても成長のチャンスにできる」という姿勢を示せば、スタッフは安心して働けるようになります。たとえば、定期的に新人と面談を行い「最近困っていることはある?」と声をかけるだけでも効果は大きいものです。また、教育に関しても「先輩スタッフに丸投げする」のではなく、院長が体制を整える責任を持つことが重要です。
院長の関与は必ずしも大規模な施策である必要はありません。小さな気配りや姿勢の変化が、職場文化に大きな影響を与えます。スタッフは院長の態度から「この職場で大事にされているかどうか」を敏感に感じ取っているため、院長が積極的に関与する姿勢こそが、定着率向上の鍵となるのです。
クリニックスタッフ定着に効果的な5つの解決策

1.定期的な面談で不満を早期に把握する
スタッフが辞めてしまう背景には、日常的な小さな不満が積み重なっていることが多くあります。その不満は「残業が多い」「教育が足りない」といった明確なものから、「相談しにくい」「自分の努力を認めてもらえない」といった感情的な部分まで多岐にわたります。こうしたサインを見逃さないために有効なのが、定期的な面談です。
面談では、業務上の課題だけでなく「最近どう?」という雑談から始めることが効果的です。形式ばった評価面談では本音が出にくいため、気軽に話せる雰囲気づくりが重要になります。特に院長自身が直接時間を取ることで「自分を大切にしてもらえている」という安心感が生まれます。
早期に不満を把握できれば、大きなトラブルになる前に対応できます。例えば「残業が続いている」という声を聞けば業務配分を見直す、「相談できない」という声があれば先輩スタッフのフォロー体制を強化するといった具体的な対応が可能になります。小さな違和感を拾い上げる仕組みが、長期的な定着につながります。
2.新人教育とフォロー体制を整える
新人スタッフが早期に辞めてしまう最大の理由は「教育不足」と「孤立感」です。入職直後は覚えることが多く、不安も大きいため、十分なサポートがなければ「ここでは続けられない」と判断してしまいます。そのため、教育体制の整備は定着率を高めるうえで不可欠です。
効果的なのは、先輩スタッフを「教育担当」として明確に位置づけることです。新人が困ったときに誰に相談すればよいかが分かるだけで、不安は大幅に軽減されます。また、業務の習得度をチェックするシートを活用し、進捗を可視化することで本人も成長を実感できます。
さらに、入職から1か月後や3か月後にフォロー面談を行うと「自分の悩みを聞いてもらえる」という安心感が生まれます。教育やフォローは一度きりで終わるものではなく、継続的に支える仕組みが必要です。院長が「新人を見守る文化」を根づかせることで、離職を防ぎやすくなります。
3.チーム内のコミュニケーションを強化する
人間関係のトラブルは、クリニックにおける離職理由の大半を占めます。そのため、スタッフ同士が気持ちよく働ける環境をつくることが、定着に直結します。具体的には「情報共有の仕組み」と「感謝を伝え合う習慣」を整えることが有効です。
情報共有については、日々の申し送りや週1回の短時間ミーティングを活用すると効果的です。小さな問題や改善点を気軽に話せる場を設けることで、不満や誤解が大きくなる前に解消できます。また、スタッフの成功や努力を共有する時間を持つと「自分の働きが認められている」という実感につながります。
加えて、感謝を伝える習慣も重要です。「今日のサポート助かったよ」といった一言が職場全体の雰囲気を和らげます。院長自身が率先して感謝の言葉を口にすることで、スタッフ同士も自然と声を掛け合うようになり、良好な関係が築かれます。人間関係の改善は一朝一夕にはできませんが、日常の小さな積み重ねが大きな効果を生むのです。
4.キャリアアップの道筋を明確にする
スタッフが長く働き続けるためには、「ここで成長できる」という実感が必要です。単に同じ業務を繰り返すだけでは、将来への不安から転職を考えてしまいます。そこで院長が意識すべきは、キャリアアップの道筋を明確に示すことです。
例えば「1年目は基本業務に慣れる」「2年目は後輩指導に挑戦」「3年目にはリーダーとしてチームをまとめる」といったロードマップを提示すると、スタッフは未来を描きやすくなります。また、資格取得や外部研修の機会を支援することも有効です。小規模なクリニックだからこそ、柔軟に一人ひとりの希望に寄り添ったキャリア支援が可能です。
キャリアの展望を持てると、スタッフは「この職場に居続ける理由」を見いだせます。単に業務をこなす場ではなく、自分の成長を支えてくれる場であると認識できれば、離職を考える動機は大幅に減少します。院長が「あなたの未来を応援する」という姿勢を示すことが、定着の強力な後押しになります。
5.院長が率先して「働きやすさ」を守る
最終的に、定着率を高める取り組みを実行に移せるかどうかは、院長の姿勢にかかっています。スタッフの働きやすさを「現場任せ」にしてしまえば、改善は進みません。院長が「定着を重視する」という意思を明確に示し、具体的な行動を取ることが必要です。
たとえば、長時間労働が常態化しているなら業務フローを見直す、意見が出にくい雰囲気があるならミーティングで発言を促す、といった対応が求められます。院長が「この職場を良くしよう」という姿勢を日常的に示すことで、スタッフは安心して働けるようになります。
また、スタッフの努力や成果をその都度認めることも重要です。小さな一言の積み重ねが「ここで働いていてよかった」という気持ちを育てます。院長の姿勢は職場全体の空気をつくるため、率先して「働きやすさ」を守る姿を見せることが、最も効果的な定着策になります。
クリニックで「スタッフが定着しない」という課題は、待遇の問題だけではなく、人間関係や教育体制、院長の姿勢など複数の要素が絡み合って生じています。定着率を高めるには、スタッフが安心して働ける心理的な環境を整えることが不可欠です。定期的な面談や教育体制の充実、チーム内のコミュニケーション強化、キャリアの見通しを示す工夫、そして院長自身の積極的な関与が効果的な解決策となります。小さな取り組みの積み重ねが「この職場で働き続けたい」という気持ちを生み、長期的な安定につながります。