看護師を採用する際、「1人あたり100万円を超えるコストがかかる」と耳にしたことはないでしょうか。実際、人材紹介会社を利用すると年収の20〜30%が手数料として発生し、1人の採用だけで100万円を超えることも珍しくありません。さらに求人広告の掲載料、面接対応にかかる人件費、入職後の研修コストなどを含めると、採用活動は経営にとって大きな負担となります。
一方で、こうした高額なコストをかけても早期離職が起きてしまえば、再度採用をやり直す必要があり、結果的に費用が積み重なります。「採用しても定着しない」「広告を出しても応募が少ない」といった悩みは、訪問看護をはじめとする多くの医療事業所が抱える共通の課題です。
本記事では、看護師採用にかかる費用の内訳を具体的に整理したうえで、コストを抑えるための工夫や、訪問看護ステーションで実際に取り組まれた削減事例を紹介します。さらに、明日からすぐに取り入れられる改善のヒントまでを提示し、経営者や採用担当者が「採用コストを正しく把握し、効率的に活用する」ための視点を提供します。
なぜ看護師採用コストは100万円かかるのか?

人材紹介会社の手数料が大きな負担
看護師採用で最も大きな割合を占めるのが、人材紹介会社に支払う成功報酬です。一般的に報酬率は採用者の年収の25〜35%で設定されており、年収400万円なら100〜140万円、年収500万円であれば125〜175万円もの費用が発生します。紹介会社によっては保証期間(一定期間内に離職した場合の返金規定)が設定されていますが、半年程度で辞めてしまえば返金対象外となるケースもあります。その場合、再度別の候補者を採用するために新しい紹介料を支払わなければならず、二重三重にコストが発生します。
また、訪問看護事業所の多くは採用担当者が専任ではなく、管理者や現場スタッフが兼任しているため、採用活動を内製化する体制が整っていないことも背景にあります。その結果、紹介会社に依存せざるを得ず、紹介料の高さを理解しながらも利用せざるを得ない状況に追い込まれやすいのです。「人がいないよりは高額でも採用したほうがいい」という判断になりやすい点が、看護師採用コストが突出して高くなる最大の理由といえるでしょう。
求人広告費用と掲載媒体の多様化
人材紹介以外にも、求人広告費が大きな負担となります。看護師向けの有料求人媒体は、1求人あたり30〜80万円程度が相場で、掲載期間は1〜2ヶ月程度が一般的です。複数職種を同時に募集する場合はその分コストが積み重なり、年間で数百万円規模になることも珍しくありません。しかも広告を出したからといって必ず応募があるわけではなく、掲載料を支払ったまま成果ゼロというリスクも常にあります。
さらに最近では、求人媒体以外にWeb広告やSNS広告を並行して利用するケースが増えています。Google広告やIndeedのクリック課金型広告では、クリック数が多ければその分費用がかさみますし、ターゲットがずれると「応募に至らない広告費」が膨らみがちです。InstagramやFacebookなどのSNS広告は、若手層の認知獲得には有効ですが、広告運用スキルが必要なため外部委託コストも加算されることがあります。このように媒体が多様化した結果、経営者は「どのチャネルに投資すべきか」の判断が難しくなり、費用をかけても十分な応募が得られない事態に直面するのです。
面接・採用プロセスにかかる人件費
直接支払う費用に加えて、採用プロセスに伴う人件費も見逃せないコストです。候補者との面接は1回につき1〜2時間かかるのが一般的で、管理者や現場責任者が同席すれば、それぞれの時給換算で数万円規模の負担になります。応募者が多ければ多いほど、面接・選考に割く工数は膨らみ、日常業務への影響も大きくなります。
さらに、面接だけではなく、条件提示や内定通知、入職日調整といった事務作業にも時間が必要です。看護師採用は一般企業と比べて条件交渉が複雑になることが多く、勤務シフトやオンコール体制、夜勤の有無など細かい調整が必要となります。これらの作業を担当するスタッフの人件費は、表に出る請求書には現れませんが、経営全体で見れば確実にコストとして蓄積されていきます。採用が長期化すればするほど、こうした「隠れコスト」は雪だるま式に膨らみます。
教育・研修コストと早期離職リスク
採用コストは採用決定で終わるわけではありません。むしろ、入職後の教育・研修にかかるコストが加わることで、1人の採用コストはさらに増大します。訪問看護では医療スキルだけでなく在宅特有の判断力や対応力が求められるため、OJT(現場研修)に長い期間を要します。教育担当者となるベテランスタッフは、その間自分の担当件数を減らさざるを得ず、事業所全体の収益に影響することもあります。
さらに深刻なのが、早期離職によるコストの損失です。入職後半年以内で退職されると、教育に投じた時間と費用はすべて無駄となり、再び採用活動を行う必要が生じます。結果として「紹介料+広告費+教育コスト」が重なり、1人採用するごとに100万円をはるかに超える負担になる場合があります。このリスクを考慮すると、採用活動は単なる「採用成功」で終わらせるのではなく、「いかに定着させるか」までを含めてコスト管理することが不可欠だと言えるでしょう。
採用コストを下げるための工夫とは?
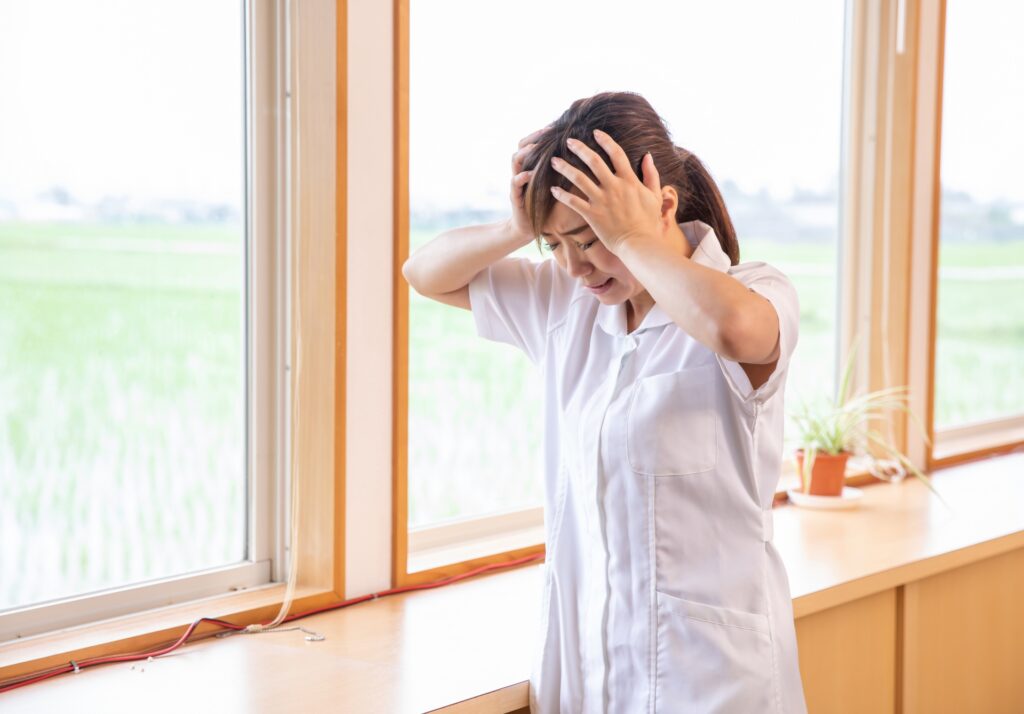
ダイレクトリクルーティングの活用で「母集団形成」を変える
看護師採用の現場で最も高額な費用となるのは人材紹介会社への依存です。そこから抜け出すための有力な手段が、ダイレクトリクルーティングです。ダイレクトリクルーティングとは、求人媒体を通じて、事業所が求職者に直接アプローチできる仕組みのことです。
この方法の大きな特徴は「採用単価が下がるほど効果が積み重なる」点にあります。紹介会社の場合、1人採用するたびに100〜140万円程度の紹介料が発生しますが、ダイレクトリクルーティングは成果報酬でありながらも人材紹介よりも安価に採用が可能です。
例えば、ある訪問看護ステーションでは成果報酬型の求人媒体に掲載し、定期的にスカウトを送る仕組みを取り入れました。結果として、年間で数十件の応募を獲得でき、紹介会社を介した採用を半減させることに成功しました。紹介料に頼らない採用経路を確立することが、長期的なコスト削減の鍵となります。
また、ダイレクトリクルーティングでは応募者とのやり取りが直接発生するため、事業所側が「どのような価値を伝えるか」を磨く必要があります。そこで力を発揮するのが、求人票や採用ページの情報発信の工夫です。給与や条件だけではなく「どんな利用者層が多いのか」「スタッフの働き方の特徴」「ライフスタイルに合う環境が整っているか」といった要素を丁寧に伝えることで、応募者の安心感が増し、結果的に内定辞退や早期離職の防止にもつながります。
内定後フォローで早期離職を防ぐ
採用コスト削減を考えるうえで軽視できないのが「内定後フォロー」です。採用活動に100万円単位の費用をかけても、半年以内に退職されてしまえば再び採用活動を行う必要があり、コストは倍増します。そこで重要になるのが「採用して終わり」ではなく「入職後の定着」を見据えた仕組みづくりです。
具体的な施策としては、内定から入職までの間に定期的に連絡を取り、業務内容や勤務条件の再確認を行うことがあります。入職前に不安を解消しておくことで、内定辞退を防げます。また、入職後1ヶ月以内にオリエンテーションや面談を設けることで「困っていることはないか」「現場に馴染めているか」を早期に把握し、フォローを強化することができます。
さらに、3ヶ月・半年といった節目ごとに面談やフィードバックの機会を用意することで、スタッフが孤立することなく安心して働き続けられる環境を整えることができます。こうしたフォロー施策に直接的な費用はほとんどかかりませんが、離職率を下げる効果は非常に大きく、結果的に「再採用にかかる100万円規模のコスト」を防ぐことにつながります。コスト削減は採用経路の工夫だけでなく、定着支援の強化によっても実現できるのです。
広告・発信の仕組みを「単発」から「資産」へ
最後に重要なのが、広告や情報発信の在り方を「単発消費型」から「資産蓄積型」に転換する視点です。求人広告は掲載期間が終われば情報が消えてしまい、費用対効果が短期に限られます。一方、自社の採用ページやオウンドメディア、SNSでの発信は、積み重ねることで長期的な資産として機能します。
例えば、Instagramでスタッフの日常や職場の雰囲気を継続的に投稿すれば、広告を出さなくても自然に応募者の目に触れる機会が増えます。さらに、TikTokで職場の雰囲気をショート動画として発信し、Instagramで詳細を伝え、最終的に自社サイトの採用ページに誘導する導線を整えることで、応募者は「この職場で働くイメージ」を持ちながら応募することができます。
こうした情報発信の仕組みを整えることは、単なる応募獲得手段ではなく、採用ブランディングにも直結します。「この事業所で働きたい」と思って応募してくる人材は、条件だけでなく価値観や働き方への共感を持っているため、定着率が高まりやすいのです。結果的に採用コスト削減と定着率向上の両立が可能となり、採用活動そのものが長期的な投資へと変わっていきます。
訪問看護での看護師採用コスト削減事例

訪問看護ステーションA:紹介会社依存からハローワークと求人媒体強化へ
訪問看護ステーションAは、以前は採用活動のほぼ100%を人材紹介会社に依存していました。その結果、1人の採用につき100万円以上の紹介料が発生し、年間の採用コストは数百万円規模に膨れ上がっていました。そこで経営者は「このままでは人件費と同じくらい採用費にお金を取られてしまう」と危機感を抱き、方向転換を図ります。
具体的には、まずハローワークを積極的に活用しました。無料で掲載できるうえ、地域の求職者にリーチできる点が強みです。またリクエスト求人などを強化し、母集団形成を行います。さらに、成果報酬型求人媒体を複数比較し、費用対効果の高い媒体に絞って出稿しました。単発的に求人を出すのではなく、1年間の掲載計画を立て、時期ごとの応募傾向に合わせて求人文の見直しやスカウト文の分析を実施する方法を採用したのです。
その結果、紹介会社からの採用依存度は大幅に下がり、年間で数百万円のコスト削減につながりました。加えて、紹介経由ではなく自社経由で応募してきた人材は「条件ではなく職場の雰囲気や地域性に惹かれて応募した」ケースが多く、定着率が向上するという副次的効果もありました。採用コスト削減と同時に、職場に合う人材を採用できるようになったのです。
訪問看護ステーションB:ダイレクトリクルーティングとSNSの組み合わせ
訪問看護ステーションBでは、求人広告や紹介会社に多額の費用を投じても応募が集まらない状況が続いていました。採用担当者は「看護師が少ないから仕方ない」と諦めかけていましたが、思い切ってダイレクトリクルーティングの導入に踏み切ります。スカウト型のサービスを活用し、事業所から候補者へ直接アプローチすることで、「応募を待つ」姿勢から「探しにいく」姿勢へ変わったのです。
しかし、スカウトだけでは十分に応募につながらないこともありました。そこで同ステーションはSNS、特にInstagramを強化しました。投稿では「1日の仕事の流れ」「スタッフの看護観」「子育てと両立して働く様子」など、リアルな日常を発信。これにより、スカウトを受けた看護師が「どんな職場か気になる」とSNSを訪問し、具体的なイメージを持ってDMで応募する流れが生まれました。
結果的に、紹介会社に頼らなくても応募が安定的に増え、紹介料の支払いを大幅に削減。さらに、SNSを通じて応募した人材は「ここで働きたい」という意欲が高く、面接辞退や早期離職が減少しました。コスト削減と同時に、採用の質が改善した成功例です。またSNSを通じて訪問看護ステーションの掲げる理念や代表の想いに共感して入社しているのでミスマッチもなく、離職率も激減しました。
訪問看護ステーションC:TikTokとInstagramを組み合わせた多段階導線
訪問看護ステーションCは、若手人材の応募を増やしたいと考えていました。しかし、従来の求人媒体では年齢層が高く、思うような結果が出ません。そこで採用担当者は発想を転換し、TikTokを活用した動画発信に挑戦しました。
動画では「看護師が共感する面白いトーク」や「病院あるある」などを短くまとめ、親しみやすさと面白さを意識。TikTokの拡散力によって、従来接点を持てなかった20〜30代の看護師層にリーチすることができました。動画をきっかけに認知を広げ、その後Instagramに誘導して具体的な働き方や制度、スタッフの声を伝える導線を設計しました。最終的には公式サイトへ誘導し、直接応募につなげています。
この流れを確立した結果、若手層からの応募が増加し、しかも紹介会社を通さない「直接応募」が増えたため、採用単価が大幅に下がりました。SNSを通じた応募者は職場の雰囲気を理解したうえで面接に来るため、面接通過率も高く、定着率の改善にもつながりました。ステーションCの事例は「SNSを採用導線の中心に据える」という新しい戦略の有効性を示しています。
事例から見える「削減=採用力低下ではない」事実
3つの事例に共通するのは、「紹介会社に依存せず、複数のチャネルを組み合わせて採用導線を意識して創った」という点です。ステーションAはハローワークと媒体の活用、ステーションBは媒体とSNS、ステーションCはTikTokとInstagram。どのケースも「費用をかけない=応募が減る」ではなく、むしろ応募数や質が改善しました。
これは、採用活動を単なる「人を集める作業」と捉えるのではなく、「求職者に自分たちの職場を知ってもらい、共感してもらう場」として準備したことが大きな要因です。費用を削減しても、その分SNSや自社メディアに投資することで、結果的に採用力が上がる。つまり「削減=力の低下」ではなく「削減=選択と集中」だったのです。
訪問看護の現場では、採用費用に対して「必要経費だから仕方ない」と考えがちですが、工夫次第で十分に削減でき、しかも応募数や定着率まで改善できる可能性があることが、この事例から明らかになりました。
明日からできる採用コスト削減の施策

採用コストや採用動線の現状を正しく把握
最初の一歩は、現状の採用活動にどれだけのコストがかかり、どのような導線で応募が来ているかを可視化することです。多くの訪問看護ステーションでは「紹介料にいくら払ったか」までは把握していても、面接や研修にかかる人件費、早期離職による再採用コストなどは見落とされがちです。これらを含めた「実質採用単価」を算出することで、初めて改善ポイントが見えてきます。
具体的には、過去1年分の採用活動を振り返り、
「紹介会社経由は何人」
「広告経由は何人」
「自社経由は何人」
とルート別に整理します。その上で、応募から採用までの流れをフローチャート化し、どの段階で離脱が多いか、どのルートが費用対効果が高いかを確認します。たとえば「紹介会社経由は高コストだが定着率が高い」「広告経由は応募は多いが内定辞退が多い」といった傾向が見えるはずです。この“現状把握”こそが、次の一手を考える土台になります。
成果報酬型求人媒体やハローワークの強化
次に着手すべきは、低コストで効果を発揮しやすい採用チャネルの活用です。代表例が成果報酬型の求人媒体とハローワークです。成果報酬型の媒体は「入職が決まった時点で課金」となるため、無駄打ちのリスクが少なく、紹介会社の高額報酬と比べてもコストパフォーマンスが高いケースが多くあります。
ハローワークは無料で求人を掲載できる公共サービスであり、特に地域密着型の訪問看護ステーションには相性が良い媒体です。応募数が爆発的に増えるわけではありませんが、地元で長く働きたいと考える人材と出会える確率が高く、定着率の高さにもつながります。さらに、職業相談窓口の担当者に自社の特徴を丁寧に伝えておくと、求職者に対して積極的に紹介してもらえることもあります。
成果報酬型媒体とハローワークを戦略的に活用することで、紹介会社依存から脱却し、安定的かつ低コストで応募を得られる体制を作ることができます。

SNSの強化
応募の量と質を安定的に確保するには、SNSを活用した発信が欠かせません。InstagramやTikTokは、求人広告では伝えきれない「働く人のリアル」や「職場の雰囲気」を可視化できる強力なツールです。特に若手看護師は求人票の文字情報だけではなく、写真や動画から職場をイメージして応募を判断する傾向が強いため、SNSが採用導線の起点になるケースが増えています。
効果的な活用方法としては、Instagramでは「日常の小さなシーン」「スタッフの声」「1日の流れ」を定期的に投稿し、求職者に“ここで働くイメージ”を持たせます。TikTokでは「訪問看護師の1日」「訪問バッグの中身紹介」といった短い動画で認知を広げ、興味を持った人をInstagramや採用サイトに誘導する流れを設計します。
こうしたSNS運用は広告費をかけなくても継続的に効果を発揮し、紹介料に頼らず応募を獲得する仕組みづくりにつながります。単なる情報発信ではなく「応募への入り口」としてSNSを位置づけることが、採用コスト削減の要です。

採用サイトやオウンドメディアの強化
SNSで認知を広げた後、求職者が必ず訪れるのが採用サイトやオウンドメディアです。ここで魅力的な情報を伝えられなければ、せっかくの関心が応募につながりません。採用サイトは単なる求人票の羅列ではなく、「自分が働いたときの姿を具体的に想像できるコンテンツ」を載せることが重要です。
たとえば、スタッフインタビュー、1日の業務フロー、制度を利用した具体的なエピソードなどを掲載すると、リアリティが増し「この職場なら続けられる」と感じてもらいやすくなります。また、オウンドメディアでは「訪問看護のやりがい」「地域で働く魅力」など、職場を越えたテーマも取り上げることで、検索流入からの認知獲得にもつながります。
採用サイトやオウンドメディアは一度作れば資産として残り、継続的に応募を生み出す仕組みになります。広告のように期限が切れることがないため、中長期的に見ればコスト削減効果が大きいのです。

プロと伴走し最速で強化
最後に意識すべきは、「自力だけで全てをやろうとしない」ことです。SNS運用や採用サイトの改善には専門的な知識やノウハウが必要で、試行錯誤だけで数ヶ月を費やすことも少なくありません。その間にも採用の機会は失われ、結果的に紹介会社に頼ることになり、高額な費用を払うという悪循環に陥ってしまいます。
そこで有効なのが、採用コンサルタントや外部の専門家と伴走する方法です。自社の採用課題を整理し、優先順位をつけ、最短で成果につながる導線を設計してもらうことで、無駄なコストを削減できます。外部の力を借りることは一時的に費用がかかるように見えますが、結果的に「最速で採用チャネルを強化できる」「紹介依存を脱却できる」という点で大きなリターンを生みます。
「プロと伴走して短期間で仕組みを整える」ことは、訪問看護において採用コストを削減するうえで最も確実な近道と言えるでしょう。

看護師やリハビリ職・ケアマネなどの採用にお困りの経営者様はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。
看護師採用コストを下げるためには、まず現状を正しく把握することが出発点です。そのうえで、成果報酬型媒体やハローワークを強化し、SNSや採用サイトを資産として育て、さらに必要に応じてプロと伴走する。この流れを実行することで、紹介会社への依存を減らしながら応募数を確保し、長期的に採用単価を下げることが可能になります。
採用コスト削減は「節約」ではなく「投資の最適化」です。仕組みを整えれば、経営の安定だけでなく「ここで働きたい」と思ってくれる人材との出会いも増え、結果的に事業の成長を後押しします。












