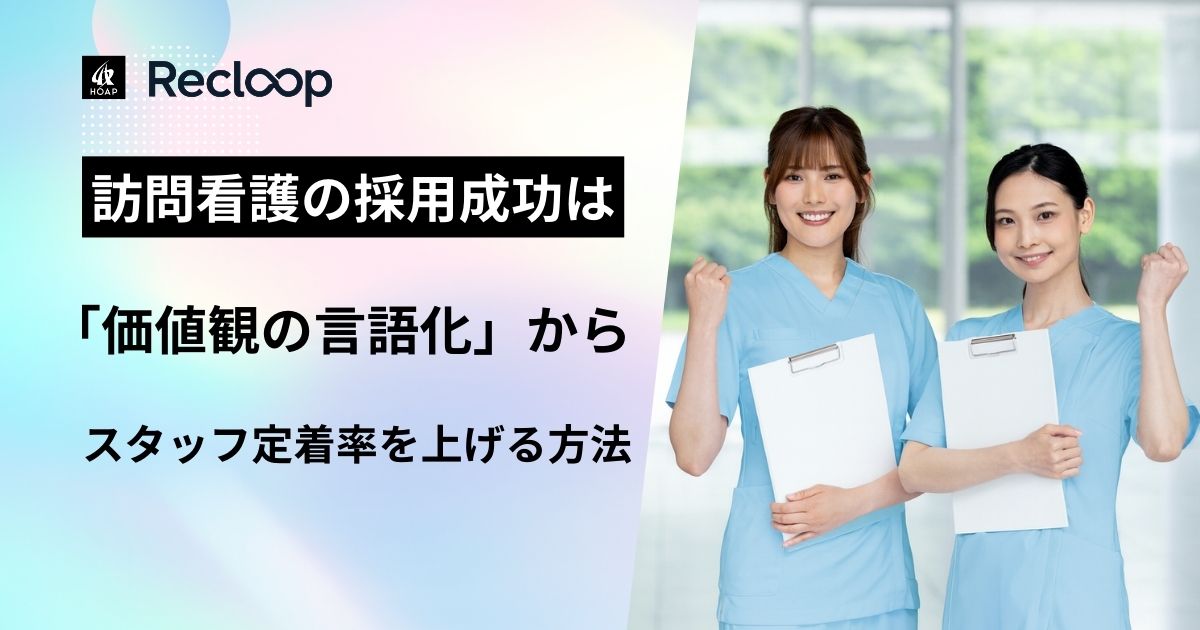訪問看護の採用において「応募はあるのに定着しない」「なぜか面接で意欲が伝わらない」といった悩みを抱えるステーションは少なくありません。制度や待遇を整えても、なぜか採用が長続きしない。そんなときに見落とされがちなのが「価値観の共有」です。
訪問看護は、病院や施設勤務とは違い、一人で利用者の自宅を訪問し看護を提供します。そのため、看護師としての技術だけでなく、「利用者や家族とどう関わるか」「チームでどう支え合うか」といった考え方が日常の行動に直結します。つまり、職場ごとの価値観にフィットできるかどうかが、働きやすさや定着率を大きく左右するのです。
しかし実際の採用活動では、理念や文化の言語化が後回しになり、給与・休日・福利厚生といった条件面だけが前面に出るケースが多く見られます。その結果、応募者は「条件は良いけれど、働くイメージが湧かない」という状態で入職し、入職後に「思っていた職場と違った」と感じてしまいます。これが離職につながる典型的なパターンです。
採用成功の鍵は、条件の提示以上に「この職場で大切にしている価値観」を具体的な言葉で伝えることにあります。理念を抽象的に掲げるのではなく、日常のエピソードやスタッフの声に落とし込みながら言語化し、求職者に届けること。これによって応募段階から「自分に合うかどうか」を判断でき、入職後のミスマッチを防ぎやすくなります。
本記事では、訪問看護の採用で価値観の言語化がなぜ重要なのか、そしてそれがスタッフの定着率向上につながる理由を解説します。さらに、実際にどのように価値観を発信すれば良いか、明日から取り組めるステップも紹介していきます。次章ではまず、「なぜ訪問看護の採用は難しいのか?」について掘り下げていきます。
なぜ訪問看護の採用は難しいのか?

病院や施設との違いが求職者に伝わりにくい
訪問看護の採用が難しい理由の一つは、仕事内容や働き方が病院や施設と大きく異なるにもかかわらず、その違いが応募者に十分に伝わっていない点にあります。病棟勤務であれば、看護師同士が同じフロアに集まり、目に見える形で「チーム医療」を体験できます。施設であれば、日常的に同僚や利用者と顔を合わせるため、自然とサポート体制や雰囲気を感じ取れます。
一方、訪問看護では一人で利用者宅を訪問する場面が中心となり、「現場でどのように動くのか」「チームでどう連携するのか」が想像しづらいのが実情です。採用の場で求人票や面接だけを頼りに判断せざるを得ない求職者にとって、訪問看護の仕事は具体的なイメージを描きにくい領域といえるでしょう。その結果、「入職してみたら想像以上に孤独感があった」「サポート体制がわかりにくかった」といったギャップにつながることがあります。
採用活動においては、こうした「見えにくさ」をどう補うかが重要です。日常の業務をどのように共有しているのか、訪問から戻ったときにチームでどんなやり取りをしているのかなど、リアルな描写を伝えることが求職者の理解を深めます。
条件面だけでは差別化できない現実
もう一つの要因は、求人情報が条件面に偏りやすい点です。給与、休日、福利厚生といった待遇条件はもちろん大切ですが、それだけで応募を引き寄せるのは難しくなっています。なぜなら、訪問看護業界では全国的に人材不足が続いており、どのステーションも似たような条件を掲げているからです。
結果として、求職者の目には「どこも同じように見える」求人が並び、事業所ごとの違いや強みが見えなくなります。この状況で応募を勝ち取ろうとすると、給与や休暇の水準をさらに上げる「条件競争」に陥りやすく、経営面で持続不可能になるリスクもあります。
実際に、条件だけを前面に出した採用は短期的な応募数を増やすことはできますが、定着にはつながりにくいことが多いのです。応募の段階で「この職場で働きたい」という納得感を持てないまま入職すると、何か不満があったときに離職を選びやすくなります。だからこそ、条件以外の魅力をどう言葉にするかが、訪問看護の採用成功に直結します。
求職者の「不安」を解消できていない
訪問看護に挑戦したいと思う看護師は多い一方で、「自分にできるのだろうか」という不安を抱える人が非常に多いのも事実です。病院で培った経験をどう在宅の現場で活かせるのか、急変時に一人で対応できるのか、利用者や家族との関わり方に自信が持てないなど、心配の種は尽きません。
しかし採用活動の現場では、こうした不安に寄り添う情報提供が不足していることが少なくありません。「教育体制は整っています」「フォローします」といった表現だけでは、応募者が自分の不安を乗り越えられるイメージを持つには不十分です。
本来なら、実際に働いているスタッフが「未経験でもこう成長できた」「困ったときに先輩がこう支えてくれた」といった経験を語ることが、不安を解消する最も有効な手段です。それを言語化して伝えられないと、応募者は「入職後に一人で苦労するかもしれない」という印象を拭えず、応募に踏み出せなくなります。
採用活動で理念や想いが後回しになっている
最後に見逃せないのが、採用の場面で「理念」や「価値観」が十分に伝えられていないことです。求人票や面接で条件や仕事内容の説明に時間を割きすぎ、なぜその事業所が存在するのか、どんな看護を大切にしているのかといった根本的な部分が言葉にされないままになっているケースが多いのです。
理念や想いが伝わらなければ、応募者は「どんなチームに参加するのか」という判断基準を持てません。結果として「条件で選んだだけ」の入職となり、働くうちに考え方のズレが露呈し、早期離職につながってしまいます。
訪問看護は、単に医療行為を提供する場ではなく、人生に寄り添う看護を実践する現場です。その意味で、事業所ごとに大切にしている価値観は必ず存在します。採用成功のためには、その価値観をどのように言葉にして伝えるかが欠かせません。ここで後回しにされた理念や想いこそ、次章で述べる「価値観の言語化」に直結するテーマなのです。
以上が「訪問看護の採用が難しい理由」の整理です。次章では、こうした課題を乗り越えるために不可欠な「価値観の言語化」について、なぜそれが採用成功のカギとなるのかを詳しく見ていきます。
価値観を言語化することが採用成功のカギ

訪問看護の求職者は「条件」より「価値観」に共感して応募する
訪問看護に関心を持つ看護師の多くは、「給与」や「休日数」だけで職場を選んでいるわけではありません。むしろ、在宅での看護という環境に挑戦したいと考える人は、自分の働き方や人生観と合うかどうかを重視する傾向があります。例えば「利用者の生活に寄り添いたい」「一人ひとりに丁寧な看護を届けたい」と考えて転職を検討する人にとっては、その思いを尊重する文化があるかどうかが重要です。
しかし求人票や説明会では、条件面の数字や制度ばかりが並び、肝心の価値観や理念が十分に伝えられないケースが少なくありません。結果として、応募者は「条件は理解できたが、自分に合うかどうかはわからない」と感じてしまいます。この不安を解消する唯一の方法が、事業所の価値観を具体的に言語化し、外に発信することなのです。
求職者は、制度の有無よりも「その制度がどんな思いから生まれたのか」「どんな人が安心して働いているのか」に共感します。数字よりもストーリーに心を動かされるという点を採用活動で忘れてはいけません。
訪問看護での言語化不足がミスマッチを生む
採用がうまくいかない事業所の多くは、理念を掲げていても、それを日常の言葉に落とし込めていません。「利用者本位の看護」「地域に貢献する」といったスローガンだけでは、応募者にとって具体的にどんな働き方になるのか想像がつきません。その結果、面接や入職後に「考えていたものと違う」と感じるミスマッチが起こります。
例えば「チームワークを大切にする」と言いながら、具体的にどのような関わり方をしているのかが伝わらなければ、応募者は漠然としたイメージでしか判断できません。実際の現場では、訪問から戻った看護師同士が情報共有をする習慣があるのか、困ったときにすぐ相談できる仕組みがあるのかなど、日常の一場面を言葉で表現することが欠かせません。
言語化が不足していると、採用は「条件」や「雰囲気」だけで進みがちになり、入職後のギャップが生まれやすくなります。価値観を具体的なエピソードや行動に置き換えて伝えることが、ミスマッチ防止の第一歩です。
訪問看護の採用広報の重要性
価値観を言語化して外部に発信すると、事業所は「選ばれる職場」へと変わります。なぜなら、情報が溢れる採用市場の中で、応募者は「自分に合うかどうか」を判断する基準を求めているからです。制度や条件はどの事業所も似通っているため、価値観を具体的に提示できるかどうかが差別化の要素となります。
例えば「子育て中のスタッフが安心して働けるよう、直行直帰を推奨している」といった具体的な取り組みを発信すれば、同じ状況にある求職者に強く響きます。また「利用者との関わりを大切にしているので、訪問時間を無理に短縮しない」と伝えることで、業務効率よりも人との関わりを重視したい人が集まります。
このように、採用広報(価値観を明確に言語化して外に伝えること)は、「合う人が集まり、合わない人は自然と応募しない」というフィルターの役割を果たします。結果として、採用後の定着率も高まりやすくなります。
訪問看護での採用活動は「価値観の合致」を見極める場
採用活動は、単に「人を集める」だけではなく、「互いの価値観が合うかどうかを確認する場」でもあります。応募者が「この職場でなら自分らしく働ける」と確信できるようにすることが、入職後のモチベーションや定着に直結します。
面接の場では、事業所側が「どんな人に活躍してほしいのか」「どんな考え方は合わないのか」を率直に言葉にすることが大切です。たとえば「一人で黙々と働きたい人よりも、チームで相談しながら進めたい人が合う」といった表現は、応募者にとって判断材料となります。
この過程を通じて、応募者も「自分の考えと一致しているかどうか」を整理できます。価値観の一致が採用の段階で確認できれば、入職後に生じるギャップを減らし、長期的な活躍につながるのです。
以上のように、訪問看護における採用成功のカギは「価値観を言語化すること」にあります。次章では、この価値観の言語化が実際にどのようにスタッフの定着率向上につながるのか、その理由を掘り下げていきます。
訪問看護で価値観を伝える具体的な方法

訪問看護スタッフのリアルなエピソードを活用する
訪問看護の採用において最も効果的なのは、現場で働くスタッフ自身の言葉を使って価値観を伝えることです。ステーションの理念やビジョンは経営者や管理者が語ることも大切ですが、それだけでは抽象的になりがちです。応募者が知りたいのは「実際に働いている人がどんな思いで日々の看護をしているのか」「その現場で働くことが自分に合うのか」というリアルな姿です。
例えば、「子どもが熱を出したときに直行直帰で対応できた」「利用者との会話から学びが多く、病院勤務では得られなかった喜びがある」といった具体的な体験談は、応募者に強い共感を生みます。数字や制度ではなく、エピソードが感情に訴えるからです。
また、「こんな人は合わないかもしれない」といったネガティブな視点を含めることも価値観を伝える重要な要素です。たとえば「一人で黙々と働きたい人には向かないが、チームで相談し合いたい人には合う」と表現すれば、応募者は自分の働き方との相性を判断できます。あえてリアルな側面を示すことが、結果的にミスマッチを防ぎ、定着につながるのです。
こうしたスタッフの声を拾うには、定期的なインタビューやアンケートを実施し、日常のエピソードを言葉に残すことが有効です。その積み重ねが「私たちの価値観」を形づくり、採用活動に活かせる財産になります。
SNSや採用サイトでステーションのリアルを発信する
価値観を伝える方法として欠かせないのが、SNSや採用サイトを活用した発信です。現代の求職者は求人票だけでなく、ネット上の情報から職場の雰囲気を読み取ろうとします。つまり、オンライン上にどのような言葉や写真、エピソードを残すかが、採用の成否に直結します。
Instagramを例にとると、単なる制度紹介よりも「制度のおかげでどんな理想が実現できたのか」をストーリーとして描くことが効果的とされています。たとえば「育休から復帰して管理者として働いている」といった投稿は、「キャリアを諦めずに働ける環境がある」という価値観を端的に伝えます。また「趣味のウクレレを仕事に活かしたい」といったスタッフ紹介は、その職場が個性を大切にしていることを自然に表現します。
採用サイトでも同様に、経営理念を羅列するのではなく、スタッフの声やエピソードを中心に構成することが重要です。文章は一人称で書かれた体験談が効果的であり、「私はこう感じた」「こういう場面で支えられた」といった言葉は、読み手に強い臨場感を与えます。
発信のポイントは「情報」ではなく「感情」に触れることです。制度名や方針だけでは伝わらない「なぜそれを大切にしているのか」という背景を盛り込み、応募者が「自分もその価値観に共感できる」と感じられるようにすることが求められます。
言語化した価値観をステーション全体に浸透させる
価値観を発信するだけでなく、それを日常業務にどう根づかせるかも重要です。外部に向けて言葉を掲げても、内部で共有されていなければ形だけになってしまいます。
具体的には、定期的なミーティングやケースカンファレンスで「私たちが大切にしている考え方」を確認する時間を設けることが効果的です。例えば「利用者の生活を尊重する」という価値観を掲げているのであれば、事例を持ち寄り「この対応はその考え方に沿っていたか」を振り返ります。
また、新人教育の場面で「この職場が重視しているのはこういう姿勢です」と伝えることで、入職直後から価値観を共有できます。研修内容に理念を組み込み、実際のエピソードを交えて説明することで、言葉が単なるスローガンではなく具体的な行動基準として浸透していきます。
さらに、ポスターや社内掲示板に「私たちの大切にしていること」を短いフレーズで掲示するのも有効です。日常的に目に入る場所に置くことで、スタッフの意識に自然と残ります。こうした積み重ねによって、価値観は組織文化として根づき、採用後の定着につながっていきます。
以上のように、訪問看護で価値観を伝える具体的な方法は「スタッフの声を拾い、リアルを発信し、合わない人も正直に伝える」こと、そして「それを日常の中で根づかせる」ことに尽きます。次章では、これらを踏まえて明日からすぐに実践できる小さなステップについて提案していきます。
訪問看護で取り組むべきポイント

スタッフ同士でステーション「らしさ」を言葉化
価値観を外に伝えるためには、まず内部でその言葉を持つことが必要です。とはいえ、いきなり理念を文章化するのは難しいものです。そこで取り入れやすいのが、スタッフ同士で「この職場の好きなところ」「働きやすいと感じる瞬間」「自分たちらしさ」を出し合うことです。
例えばミーティングの冒頭に「最近、この職場でありがたいと思ったことを一言ずつ話そう」といった時間を設けます。誰かが「子どもが急に熱を出したとき、シフトを柔軟に調整してもらえた」と話せば、それは「家庭との両立を大切にしている」という価値観を言葉にしたものになります。別のスタッフが「訪問から帰ったときに必ず声をかけてもらえる」と話せば、「孤立させないチーム文化」が言語化されます。
このような小さな対話を積み重ねることで、スタッフ自身が「自分たちの職場の強みや特徴」を自覚し、それを共有できるようになります。外部への発信は、その延長線上にあるべきです。まずは内部での言語化から始めることで、発信内容が自然に整い、リアルな言葉として外に出ていきます。
求職者との面談で「大切にしていること」を最初に伝える
面接や面談の場では、条件や業務内容の説明をする前に「私たちがこの職場で大切にしていること」を率直に伝えることが有効です。応募者にとっては、数字や制度よりも、最初に耳にする理念や姿勢のほうが印象に残ります。
例えば「私たちは、訪問時間を効率化するよりも、利用者さんとの関わりを大切にしています」と最初に伝えるだけで、応募者は「ここでは人との関わりを重視する文化がある」と理解できます。逆に「件数を重ねることが評価される」と説明すれば、効率性を重視する文化があると明確に伝わります。このように、冒頭で価値観を示すことで、応募者は自分の考え方と照らし合わせながら判断できるのです。
さらに、「こういう人は合わないかもしれない」といった率直な表現を面談で伝えることも重要です。「一人で判断したい人より、チームで相談しながら進めたい人のほうが活躍できる」と伝えれば、応募者にとって自分のスタイルが合うかどうかの判断材料になります。最初に誠実に価値観を提示することで、後々のミスマッチを防ぐことができ、結果的に定着率向上につながります。
ステーションとして採用広報を実施する
価値観を伝える取り組みは、一度だけ大きな発表をすれば良いわけではありません。むしろ「小さな発信を継続すること」に意味があります。採用サイトにスタッフの声を掲載し定期的に更新する、ステーションのニュースをSNSで週に一度紹介する、といった習慣が大切です。
発信内容は立派なものでなくて構いません。例えば「今週はスタッフ全員で訪問の振り返りをしました。そのときに出た『一人で抱え込まない』という言葉を大切にしています」といった短い投稿で十分です。小さくても定期的に続けることで、「この職場はいつもリアルを伝えている」という印象が積み重なります。
また、採用ページに「うちの職場はこういうところ」といった固定メッセージを掲載するだけではなく、定期的に新しい声やエピソードを追加することも効果的です。情報を更新し続けることで、応募者は「今も変わらずこの価値観を大事にしている」と信頼できます。
小さな発信の積み重ねが「価値観が根づいている職場」というイメージを強化し、求職者の安心感を高めることにつながります。
ステーションで明日からできる実践例
最後に、訪問看護ステーションがすぐに取り組める実践例を整理します。抽象的なスローガンではなく、具体的な行動に落とし込むことがポイントです。
・ミーティングで「今週、この職場でありがたいと感じたこと」を一人ずつ共有する時間を設ける
・面談の冒頭で「私たちが大切にしていること」を2分以内で伝える習慣をつくる
・スタッフインタビューを月1回行い、社内やSNSで公開する
・「こういう人は合わない」という一文を求人票や面接で率直に伝える
・採用サイトやSNSの情報を定期的に更新し、新しいエピソードを追加する
・新人研修に「価値観共有セッション」を組み込み、具体的な行動事例を一緒に振り返る
これらは大規模な仕組みを整える必要はなく、明日からでも始められる小さな取り組みです。しかし、この積み重ねが「価値観を言語化し、共有し、定着させる」という流れを支え、採用成功とスタッフの定着につながります。
訪問看護の採用において、条件や制度だけでは人材は定着しません。大切なのは「この職場でどんな看護を大事にしているか」という価値観を具体的に言葉にし、応募者と共有することです。入職前から価値観を明示すれば、ミスマッチを防ぎ、スタッフが安心して働き続けられる基盤ができます。さらに、その価値観を日常で確認し合い、小さくても発信を続けることで、共感できる人材が集まりやすくなります。採用成功と定着率向上は、価値観を言語化し、組織全体で育てていく姿勢にかかっているのです。