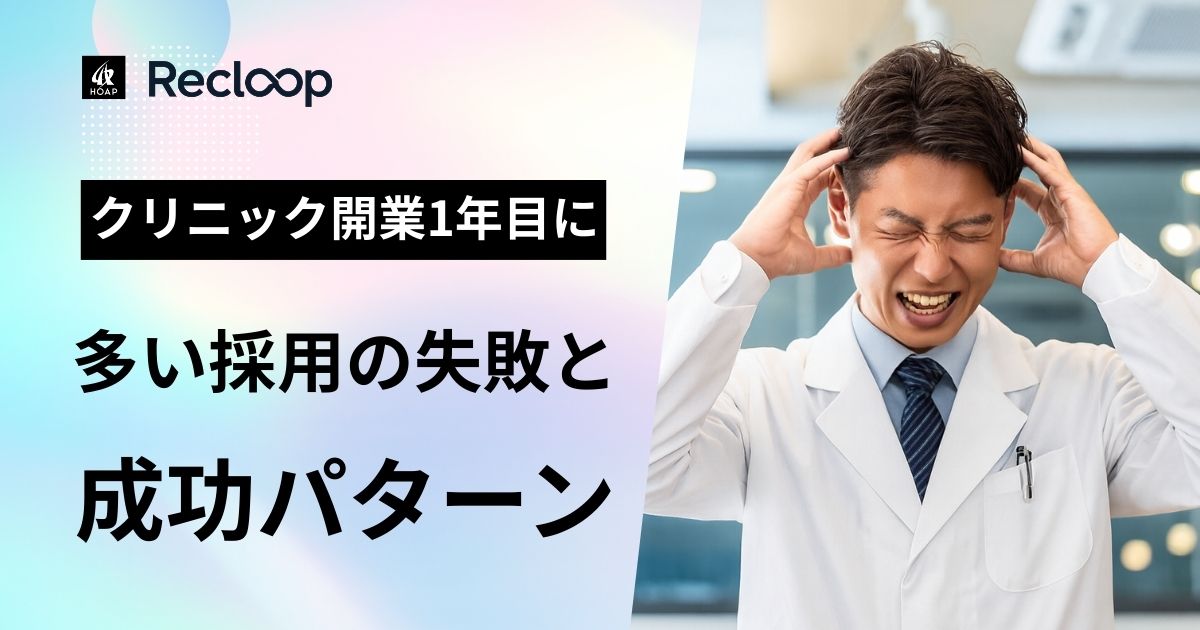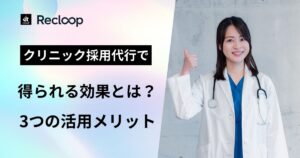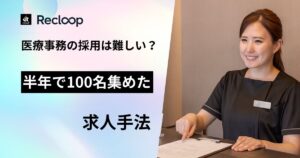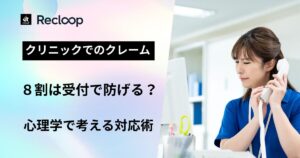クリニックを開業して1年目、多くの院長が直面するのは「スタッフ採用」の難しさです。診療設備を整え、診療体制を整備したとしても、現場で働くのは看護師や医療事務をはじめとしたスタッフです。彼らの採用と定着がうまくいかなければ、診療の質や患者対応にも影響が出てしまいます。特に開業直後は「早く人を揃えなければ」という焦りから、応募者の条件だけを見て採用を決めることが少なくありません。しかし実際には、価値観の相違や職場の雰囲気とのミスマッチによって、数か月で辞めてしまうケースも多く見られます。
また、求人広告に頼りきりで「誰にどう働いてほしいのか」というメッセージが不十分なまま募集を出してしまうと、応募自体が集まらない、あるいは本来求めていない層からの応募が増えるなど、採用効率が下がります。さらに、採用に必要な時間を院長自身が確保できず、面接が形骸化してしまうのも失敗につながる大きな要因です。
一方で、成功しているクリニックは「人数を揃える」こと以上に「相性」や「職場の未来像」を重視しています。看護師や医療事務が安心して働き続けられるかどうかを判断軸にし、求人や面接の段階からその観点を持ち込んでいます。また、SNSなどを活用して「リアルな職場感」を伝えることで、応募者が自分に合っているかを事前に判断できるようにしている事例も増えています。
本記事では、クリニック開業1年目に多い採用の失敗と成功の具体例を取り上げ、どのようにすれば「辞めない人材」を採用し、定着させられるのかを順に見ていきます。
なぜクリニック開業1年目は採用定着が難しいのか?

オープニング採用に潜む落とし穴
クリニックの開業時には「オープニングスタッフ募集」という形で看護師や医療事務を集めるケースが一般的です。一見すると「新しい職場を一緒に作れる」という魅力があり、応募は集まりやすいように思われます。事実オープニングは採用しやすい傾向にあります。しかし現実にはこのオープニングが定着を難しくする要因になることが少なくありません。
理由のひとつは、院長自身もまだ診療体制や方針を固めきれていない段階であることです。業務の流れや担当範囲が明確でない状態で入職したスタッフは、「思っていた業務と違う」「役割がはっきりしない」と不安を感じやすくなります。特に病院勤務の経験が長い看護師にとっては、システムやマニュアルが整っていない環境はストレスの原因になります。
さらに、開業直後は患者数の変動も大きく、忙しさの波に耐えられない人が出やすい時期です。繁忙時には十分な教育やフォローができず、逆に閑散期には「このクリニックは安定しているのか」と疑念を抱かれることもあります。こうした環境の揺らぎは、せっかく採用したスタッフが短期間で辞めてしまう理由につながります。
看護師採用でよく起きる初期離職
クリニックにとって看護師は診療の中心を支える存在ですが、開業1年目は看護師の定着率が特に低い傾向があります。その背景には「役割の過重」と「キャリアとのミスマッチ」があります。
例えば、病院勤務では医師の指示のもとで明確な分業体制がありますが、クリニックでは看護師が幅広い業務を担うことになります。採血や処置だけでなく、患者への説明、予約対応、時には会計や備品管理まで任されることも珍しくありません。こうした幅広さにやりがいを感じる人もいれば、「ここまでやるとは思っていなかった」と離職につながる人もいます。
また、キャリア志向の強い看護師の場合、クリニック勤務は「学びや専門性の幅が狭い」と感じられることもあります。開業直後のクリニックは教育体制が十分でないことが多く、病院での経験を活かしきれないと判断して転職してしまうケースもあります。特に1年目は「まずは開業を軌道に乗せる」ことが優先されるため、教育やキャリア支援にまで手が回らず、結果として定着率が下がりやすいのです。
医療事務スタッフが続かない理由
看護師に比べて採用しやすいと考えられがちな医療事務も、開業1年目は定着が難しい職種です。医療事務の離職理由として多いのは「業務範囲の不明確さ」と「人間関係への不安」です。
まず業務範囲について、レセプト業務や受付だけでなく、患者対応、電話応対、時には看護師のサポートまで求められることがあります。人数が限られる開業クリニックでは、どうしても“なんでも屋”としての役割が発生しやすいのです。しかし、入職前の説明が不十分だと「思っていた仕事と違う」という不満につながります。
また、人間関係の影響も大きい要因です。クリニックは少人数体制であるため、1人でも合わない人がいると雰囲気が一気に悪化します。とりわけ開業1年目は院長や看護師も余裕がなく、医療事務へのサポートやコミュニケーションがおろそかになりがちです。その結果、孤立感を覚えたスタッフが短期間で離職することが多くなります。
加えて、給与や労働条件に関する不満も見過ごせません。大規模病院と比べて福利厚生が整っていないクリニックも多く、「安定性」を重視する人材には選ばれにくい傾向があります。こうした点を事前に伝えず採用してしまうと、ミスマッチによる早期離職につながります。
定着の難しさが経営全体に及ぼす影響
開業1年目にスタッフが定着しないことは、単なる人員不足にとどまらず、経営全体に大きな悪影響を及ぼします。まず直接的な影響は、再採用にかかるコストです。求人掲載費用や面接に割く時間、教育のやり直しなど、短期間に何度も発生すると金銭的・時間的な負担は膨大になります。
さらに、患者体験にも影響が出ます。受付や診療補助のスタッフが頻繁に入れ替わると、患者は安心感を得られません。特に地域密着型を目指すクリニックにとって「顔なじみのスタッフがいる」というのは信頼構築に直結する要素であり、定着率の低さは患者離れを招くリスクとなります。
また、残ったスタッフに過度な負担がかかることで、モチベーションの低下や二次的な離職が発生する悪循環に陥ります。院長自身も診療に加えて採用・教育に追われ、本来注力すべき医療の質向上や経営戦略に時間を割けなくなります。
このように、開業1年目における採用定着の難しさは、単なる人材管理の問題ではなく、クリニックの存続に直結する経営課題といえます。次章では、この状況を打破するために成功しているクリニックがどのように「相性」を重視した採用を行っているのかを見ていきます。
採用成功クリニックが重視した「相性」とは?

クリニックの理念とスタッフの価値観
採用で失敗するクリニックと成功するクリニックの差は「理念の共有度」に表れます。採用の段階で、院長がどのような医療を提供したいのか、どんな患者層に寄り添いたいのかを言語化し、それに共感できる人を選んでいるかどうかが大きな分かれ目です。
と条件だけで採用すると、業務は回っても職場に一体感が生まれにくくなります。逆に
など、院長の理念を前面に出して採用したスタッフは、その姿勢を自然と日常業務に持ち込むため、働くモチベーションが長続きしやすくなります。
理念と価値観が共有できていると、細かい業務マニュアルがなくてもチームが一体となりやすく、結果として定着率が高まります。理念が曖昧なまま採用を進めることが、初期離職の根本原因になっていることは見逃せません。
看護師とのチームワークを築く採用視点
看護師採用の成功には、単なるスキルや経験年数よりも「チームワークの相性」を重視する姿勢が不可欠です。クリニックは病院に比べて少人数体制であるため、1人の看護師が職場全体の雰囲気を左右します。
成功しているクリニックでは、採用面接の際に「技術チェック」だけでなく「価値観のすり合わせ」を丁寧に行っています。例えば
「患者さんとの会話で大切にしていることは何か」
「忙しいときにどう周囲と連携してきたか」
といった問いを投げかけることで、その人がチームに馴染めるかどうかを見極めています。
また、オープニング段階で採用する場合は「院長と一緒にクリニックを形作りたいかどうか」という意欲も重要です。新しい仕組みを一緒に作る姿勢を持った看護師は、多少の不便や混乱があっても前向きに取り組むため、定着しやすい傾向があります。

医療事務に求められるコミュニケーション力
医療事務の採用では「事務スキル」だけで判断すると失敗しやすくなります。クリニックの顔として患者と最初に接するのは受付であり、電話対応や会計の場面でも患者の印象を大きく左右します。そのため、数字や入力スピードよりも「人とのやり取りに安心感を与えられるかどうか」が定着を左右するカギとなります。
成功しているクリニックでは、面接の段階で「患者対応のロールプレイ」を取り入れたり、「これまでで一番難しかった対応と、そのときどう乗り越えたか」を質問したりして、応募者の人柄や対応力を確認しています。
また、院長や看護師との距離感も重要です。医療事務は業務上、診療補助や看護師との連携が欠かせないため、内部コミュニケーションを円滑に進められる人を採用できると定着率が高まります。逆に事務作業だけに集中したい人を採用すると、現場との摩擦が増え、短期離職につながりやすくなります。

人数より相性を優先した結果の定着率
採用活動では「今すぐ人が欲しい」という焦りから、応募があればすぐに採用してしまいがちです。しかし、成功しているクリニックほど「人数合わせではなく相性重視」で採用を進めています。
例えば、面接後にすぐ採用を決めるのではなく、見学や体験勤務を取り入れて「実際に一緒に働いたときの印象」を確認するクリニックがあります。このプロセスを経ることで、お互いに「合う」「合わない」を事前に判断でき、結果的に入職後のギャップを減らすことができます。
また、採用に時間をかけてでも相性の良い人材を選んだ方が、長期的に見れば再採用コストや教育負担を大幅に減らすことができます。人数重視の採用で頻繁に離職が発生するよりも、相性を重視した少数精鋭の方が安定しやすいという事例は少なくありません。
こうした「相性重視」の姿勢は、看護師・医療事務のどちらにも有効であり、結果として高い定着率を実現する大きな要因になっています。次の章では、開業クリニックが実際に採用で失敗した事例を具体的に見ていきます。
開業クリニックが採用で失敗する事例

採用にかける時間の欠如
開業直後の院長は診療・経営・事務作業など、あらゆる業務を同時並行でこなしています。その結果、採用活動に十分な時間を割けず「とりあえず人を入れる」という流れになりがちです。
面接を短時間で済ませたり、履歴書の経歴だけを見て採否を決めたりすると、応募者の人柄や職場との相性を見極められません。その結果、採用後に「患者対応が合わない」「チームワークが取れない」といった問題が浮上し、短期離職につながります。
また、教育やフォローの時間を確保できないことも大きな失敗要因です。特に看護師や医療事務はクリニックごとに業務フローが異なるため、十分な説明がないまま現場に放り込まれると混乱や不満を抱きやすくなります。「採用して終わり」ではなく、入職後のフォローまで時間を確保できるかどうかが定着に直結するのです。
採用ノウハウの欠如
医療機関であっても、採用は専門的な知識と工夫が求められる領域です。しかし開業1年目の院長は、診療には精通していても「どうやって応募を集め、どう見極めればよいか」という採用ノウハウを持たないことが少なくありません。
よくある失敗は、求人広告に条件や待遇だけを並べてしまうことです。応募者にとって「どんな職場なのか」「どんな人と働けるのか」という情報が不足しており、結果的に応募が集まらない、あるいは定着しない人材を採ってしまいます。
また、面接の場で適切な質問ができないことも課題です。経験やスキルだけを確認し、人柄や働き方の志向を見極めないまま採用すると、現場での摩擦が起きやすくなります。採用ノウハウを持たないまま勢いで決めてしまうことが、早期離職の連鎖を招く大きな原因となります。
採用戦略の欠如
という採用戦略がないまま求人を出すのも、開業クリニックでよくある失敗です。明確な戦略がないと、求人媒体や募集文の方向性が定まらず、結果的に「誰にでも当てはまるが、誰の心にも響かない」求人になってしまいます。
例えば、地域に根ざしたファミリー層中心のクリニックであれば、患者との会話や柔軟な対応力が求められます。一方、専門診療を強みとする場合は、特定分野の経験や専門性を持つスタッフが必要です。こうした違いを考慮せず「経験3年以上」「勤務時間に柔軟な方」など曖昧な条件だけで採用を進めると、ミスマッチが起きやすくなります。
戦略不在の採用は、スタッフの定着率を下げるだけでなく、院長の理念やクリニックの方向性を職場に浸透させる機会を失うことにもつながります。
中長期計画の欠如
採用を短期的な「人員補充」として捉えてしまうと、数年先を見据えた人材確保ができません。開業1年目は目の前の診療を回すことで精一杯になりがちですが、中長期的な視点を持たないと「人が辞めるたびに急募を繰り返す」状況に陥ります。
例えば、将来的に外来患者数が増える見込みがあるのか、専門診療を拡大する予定があるのかによって、必要な人材像は大きく変わります。こうした予測なしに採用すると、2年目・3年目で業務量に対応できず、追加採用や人員入れ替えが頻発するリスクが高まります。
また、スタッフのキャリア形成を考えずに採用すると、本人が「この職場では成長できない」と感じて離職する要因になります。特に看護師は専門性やスキルアップを重視する傾向が強く、中長期的な育成方針を持たない採用は定着に結びつきにくいのです。
結果として、採用を「今この瞬間の補充」だけで考えることが、クリニックの持続的な成長を妨げる失敗につながります。次章では逆に、採用で成功しているクリニックの具体的な事例を見ていきます。
開業クリニックが採用で成功する事例

採用戦略の立案
採用に成功しているクリニックは例外なく、明確な採用戦略を持っています。開業直後から
を具体的に描き、その方針に基づいて求人内容を設計しています。
例えば、地域密着型で患者との関係性を重視するクリニックであれば「コミュニケーションを大切にできる人」を第一条件に掲げます。一方、専門性を武器にしたクリニックであれば「特定の診療分野の経験やスキル」を前提にするなど、戦略の方向性が明確です。
戦略を立てることで、求人媒体の選定や募集文の書き方にも一貫性が生まれ、結果として「クリニックに合う人材」が応募してきやすくなります。採用を戦略的に捉えているかどうかが、開業1年目の成功と失敗を分ける大きなポイントです。
ペルソナの明確化
採用成功のもう一つの共通点は「ペルソナ=理想の応募者像」が明確であることです。単に「経験のある看護師」や「医療事務スキルがある人」という条件ではなく、「子育てと両立しながら長く働きたい30代の看護師」や「患者さんに安心感を与えられる受付経験者」といった具体的な人物像を設定しています。
ペルソナを細かく設定することで、求人原稿の書き方や面接時の確認ポイントが変わります。応募者側も「自分に合っている職場かどうか」を判断しやすくなり、結果的に入職後のギャップを減らすことができます。
ペルソナを明確にする過程では、既存スタッフへのヒアリングが効果的です。「どんな人が合うのか」「どんな人が続いているのか」を現場から吸い上げることで、机上の理想像ではなくリアルな採用ターゲットを描けるようになります。
院長の時間を確保するか代行か
採用の成否は、院長がどれだけ採用活動に関わるかで大きく変わります。成功しているクリニックでは、院長自身がしっかりと時間を確保して面接や見学対応に臨むか、あるいは外部の専門家に代行を依頼しています。
院長が直接関わることで、応募者は「この院長と働きたいか」を判断できますし、院長も「この人と一緒にやっていけるか」を肌感覚で確かめられます。一方、診療で手一杯の院長が採用に関われない場合は、採用代行サービスや人事経験のあるスタッフに一部を委ねることで、応募者への対応を疎かにしないようにしています。
「面接が形式的で終わった」「院長と話す機会がなかった」という印象を持たせると、応募者は不安を覚え、辞退や早期離職につながります。時間を確保するか、信頼できる代行者を置くか。この判断を早めに下すことが成功クリニックの共通点です。
採用を投資として考えているか
成功するクリニックほど、採用を「コスト」ではなく「投資」と捉えています。求人広告の出稿や採用ツールの導入、面接や教育にかける時間を単なる出費とせず、将来的な安定経営につながる投資と考える姿勢です。
特に最近では、SNSを活用した採用ブランディングが成果を上げています。例えば、インスタグラムでスタッフの日常や院長の想いを発信することで、応募者は「この職場で働く自分」をイメージしやすくなります。単なる条件提示の求人よりも、「雰囲気や価値観に共感して応募した」という人材の方が定着率は高い傾向にあります。
また、採用を投資と考えるクリニックは、入職後の研修やフォロー体制にも力を入れています。初期段階でしっかりと教育コストをかけることで、短期離職を防ぎ、長期的に安定したチームを作り上げています。採用活動にどれだけ先行投資をできるかが、開業クリニックの成否を大きく左右します。
クリニック開業1年目における採用は、人数を揃えること以上に「相性」や「理念の共有」を意識できるかどうかで明暗が分かれます。看護師や医療事務が短期で辞めてしまう原因の多くは、採用戦略や時間不足にあります。一方で、成功しているクリニックは明確なペルソナを描き、院長が関わるか信頼できる代行を立て、採用を投資として捉えています。とはいえ、開業直後の院長が診療と採用を同時に抱えるのは現実的に難しいのも事実です。本来注力すべきは診療とクリニックの仕組み化であり、採用は専門家に任せる方が効率的です。HOAPでは、採用戦略の立案から候補者対応まで一貫して代行し、院長の貴重な時間を「患者と向き合う」ために使えるよう支援しています。採用の悩みを手放すことで、開業後の成長に専念できる環境を整えていきましょう。
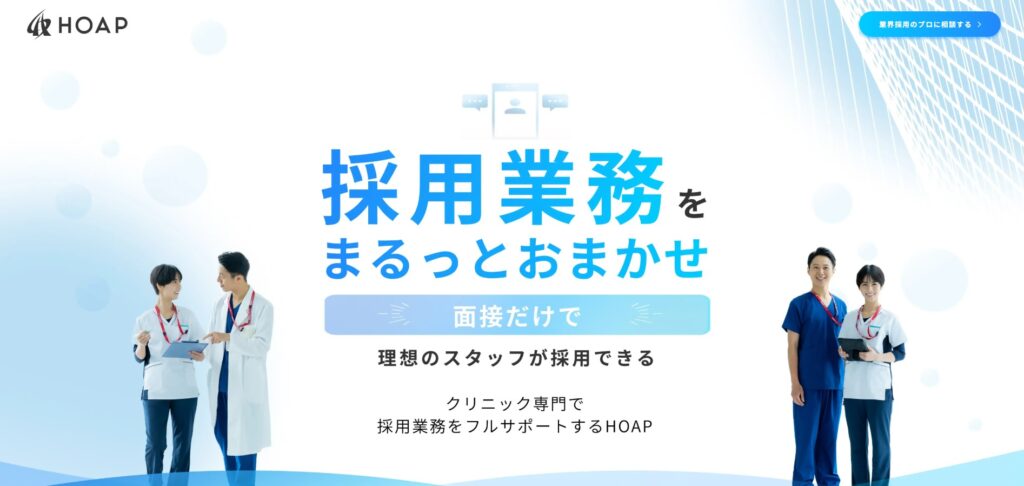
看護師やリハビリ職・医療事務などの採用にお困りの院長先生はこちらから採用支援サービスをご確認いただけます。