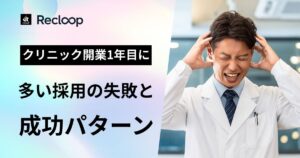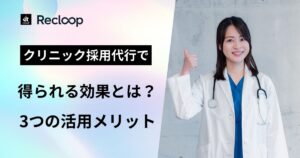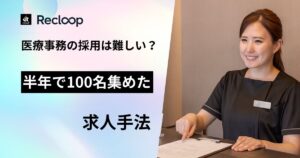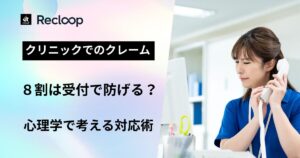「医療事務の採用が難しい」と感じているクリニック経営者や採用担当者は少なくありません。求人を出しても応募が集まらない、せっかく採用しても早期に離職してしまう、といった悩みは多くの現場で共通しています。特に医療事務は業務の幅が広く、患者対応からレセプト業務まで多岐にわたるため、ミスマッチが起こりやすい職種でもあります。
一方で、給与や勤務条件といった待遇面だけでは他院との差別化が難しくなってきています。求職者は複数の医療機関を比較しながら、「この職場で働く自分の姿が想像できるか」を重視しているのが現状です。つまり、条件の提示だけではなく「働く環境のリアルな姿」や「職場の価値観」を伝えることが、採用活動における大きなカギとなります。
ここで重要になるのが、ブランディングの視点です。医療事務の仕事に興味を持つ人に対して、クリニックとしてどのような雰囲気を持ち、どんな人が働いているのかを具体的に発信することが求められます。スタッフの声や日常の風景、院長の想いなど、リアルな情報を外部に届けることで「ここなら安心して働けそう」と感じてもらえるのです。
本記事では、医療事務の採用難を背景に、クリニックが実践すべきブランディング戦略について解説していきます。まずは「なぜ医療事務の採用が難しくなっているのか」を押さえ、そのうえで「求職者が知りたい情報」「SNSや広報での発信方法」「運用を続ける体制づくり」へと順を追って見ていきましょう。
なぜ医療事務の採用が難しくなっているのか

人材市場の変化と慢性的な医療事務不足
医療事務は医療機関に欠かせない職種であるにもかかわらず、慢性的な人手不足が続いています。背景には、少子高齢化による労働人口そのものの減少、医療機関の数が地域ごとに増加していること、そして他業種への人材流出があります。特に若年層の就職希望先として、医療事務は必ずしも第一候補ではありません。多くの学生や転職希望者は、柔軟な働き方やキャリア形成が見えやすい業界に流れる傾向が強まっているため、医療事務の採用は他職種以上に難易度が高くなっています。
また、医療事務は資格を持たなくても応募できるケースが多いため、「誰でもできる仕事」という誤解を持たれがちです。その一方で、実際には保険制度や診療報酬に関する知識が必要であり、専門性を身につける努力が欠かせません。この「イメージと実態のギャップ」も、採用のハードルを高めている要因です。クリニックにとっては、この状況を理解したうえで、自院で働く価値をどのように伝えていくかが重要になります。
医療事務の仕事内容と待遇のミスマッチ
医療事務の採用が難しいとされる理由のひとつに、仕事内容と待遇のバランスがあります。患者対応から受付業務、レセプト処理まで幅広いスキルが求められる一方で、給与水準は決して高いとはいえません。特に都市部では生活コストが高いことから、給与だけで比較すると他業種に流れてしまうケースも少なくありません。
また、職場環境においても、繁忙期には残業が発生しやすく、患者からのクレーム対応など精神的な負担も大きくなります。こうした現場の実態と、求人票で伝わるイメージが一致しないことが、入職後の早期離職につながることも多いのです。求職者にとって「想像以上に大変だった」と感じられてしまうと、採用の努力は水の泡になってしまいます。クリニック側は、仕事内容や負担の大きさを隠すのではなく、リアルな姿を伝えつつ「だからこそ支え合って働ける職場である」と補足する姿勢が求められます。
求職者の価値観と情報収集行動の変化
かつては求人広告やハローワークといった限られた情報源が主流でしたが、今の求職者はSNSや口コミサイト、スタッフブログなど多様な情報を参考にしています。給与や休日といった条件面だけでなく、どんな人が働いているのか、院内の雰囲気はどうか、実際の業務はどの程度忙しいのかといった「リアルな情報」に敏感です。
特に若年層の求職者は「共感」を重視する傾向が強く、制度の説明よりも「それを使ったスタッフの声」に惹かれることが多いといえます。つまり、従来型の求人票では求職者の期待に応えきれなくなっているのです。この価値観の変化に気づかず、従来のやり方を続けていると「応募が集まらない」「面接につながらない」という現象が起こります。クリニックが医療事務を採用するためには、求職者が情報を集めるプロセスそのものを意識した発信が欠かせません。
医療事務の定着率の低さと採用コストの負担
採用が難しいのは「入り口」だけでなく「定着」の問題も大きく関わっています。せっかく採用しても、数ヶ月から1年以内に退職してしまうケースが目立ちます。理由としては、仕事内容の過重感、人間関係の不一致、働き方の柔軟性の欠如などが挙げられます。特に小規模クリニックではスタッフ数が限られるため、一人の退職が大きな業務負担増につながり、さらに採用難を加速させるという悪循環に陥りやすいのです。
また、採用活動そのものにかかるコストも無視できません。求人広告費や飲料の時間、面接や教育にかかる労力などを考えると、定着しないことによる損失は非常に大きいといえます。そのため、採用の段階で「入職後も安心して長く働けるかどうか」を伝えられることが重要になります。ブランディングを通じて「この職場なら続けられそう」と思ってもらう工夫が、結果的に採用コスト削減にもつながるのです。
以上のように、医療事務の採用が難しい背景には、人材市場の変化、仕事内容と待遇のギャップ、求職者の情報行動の変化、そして定着率の低さが複雑に絡み合っています。次の章では、こうした現状を踏まえ、医療事務が本当に知りたい「働く環境」について掘り下げていきます。
医療事務が知りたい「働く環境」とは

人間関係とクリニックの雰囲気
医療事務の求職者が最も気にするポイントのひとつが「人間関係」です。受付や会計業務は患者との接点が多いだけでなく、看護師や医師との連携も欠かせません。そのため、チームワークが円滑であるかどうかが、働きやすさを大きく左右します。実際に求人応募前の相談では「スタッフ同士の雰囲気はどうですか?」「長く働いている人は多いですか?」といった質問がよく寄せられます。
こうした問いに対して、給与や制度の説明だけでは十分ではありません。求職者は「このクリニックで一緒に働いたらどんな人間関係が待っているのか」をイメージしたいのです。たとえば、先輩スタッフが丁寧に新人をサポートしている様子や、定期的にランチ会を開いて交流していることなど、日常の中で見える雰囲気を伝えることが効果的です。言い換えると、数字や制度よりも「人の表情」や「日々のやりとり」の方が求職者に響くのです。
さらに、働くスタッフのリアルな声を積極的に発信することも重要です。「入職して一番うれしかったことは?」「大変な時にどう支えてもらえたか?」といったエピソードを取り上げることで、応募者に安心感を与えられます。クリニック側が伝える「うちはアットホームです」という言葉より、実際のスタッフの具体的な体験談の方が信頼性を持つのです。
クリニックでの柔軟な働き方や制度の実際
医療事務の仕事はフルタイム勤務だけでなく、パートやシフト制など多様な働き方が存在します。特に子育てや介護をしながら働く人にとって、勤務時間の柔軟さや急な休みに対応できるかどうかは大きな関心事です。求人票に「シフト応相談」と書かれていても、実際にどこまで融通が利くのかはわかりにくいため、リアルな事例を発信することが求められます。
たとえば、「子どもの発熱時にはスタッフ同士でシフトを調整し合っている」「家庭の事情で一時的に短時間勤務を選べる」といった具体的な例があると、求職者は自分の生活と重ね合わせて働く姿を想像しやすくなります。また、産休・育休の取得実績や復職後のキャリアの描き方も、応募を後押しする大切な情報です。
重要なのは「制度の存在」ではなく「制度がどう使われているか」です。制度紹介だけでは「実際に使えるのだろうか」と不安を残しますが、実際に制度を活用したスタッフの体験談を共有することで、安心感と信頼性を高めることができます。これにより「ここなら自分も長く働けそうだ」と思ってもらえる可能性が高まります。
医療事務としての成長機会と学びの環境
医療事務は単純作業の繰り返しに見られがちですが、実際には医療制度や診療報酬の改定など、常に新しい知識が求められる職種です。だからこそ、求職者は「この職場で成長できるかどうか」に強い関心を持っています。単に「研修制度あり」と記載するだけでは不十分で、実際にどのような学びの機会が提供されているのかを示すことが重要です。
たとえば、「新人にはベテランスタッフがマンツーマンで指導する体制がある」「定期的に外部研修への参加を推奨している」といった取り組みを明示することが効果的です。また、「未経験からスタートして、今では受付リーダーとして活躍している」といった成長エピソードは、応募者にとって自分の未来像を描くヒントになります。
このように、キャリアやスキルアップの道筋が具体的に見える職場は、長期的に働きたいと考える人材を惹きつけやすくなります。逆に「ただの事務作業」で終わるイメージを持たれてしまうと、応募意欲は低下してしまいます。だからこそ、学びや成長を支える環境をどう発信するかが大きな鍵になります。
クリニックで安心して働ける体制とサポート
最後に、医療事務が知りたいのは「安心して働けるかどうか」です。これは給与や制度に限らず、日常の中で感じるサポート体制が含まれます。たとえば、新人が業務でミスをしても一人で抱え込まず、すぐに相談できる仕組みがあるかどうか。あるいは、患者対応で困った時に同僚や上司がどのようにフォローするか。こうした具体的なサポートのあり方は、求人票だけでは伝わりません。
実際に求職者は「困ったときに助けてもらえるか」を強く気にしています。なぜなら、受付や会計業務は患者の目の前で行われるため、失敗が目立ちやすいからです。心理的に安心できる環境が整っているかどうかが、定着率に直結します。
また、働きやすさの一環として「意見を言いやすい雰囲気」も大切です。小さな改善点をスタッフが気軽に提案でき、それが反映される職場は、自然と信頼感が醸成されていきます。安心感を与える職場は、応募の段階で「ここなら大丈夫」と思ってもらえる大きな要因になります。
このように、医療事務が知りたいのは条件や給与だけではなく、「どんな人たちと働くのか」「制度は実際に使えるのか」「成長のチャンスがあるのか」「安心して働けるのか」という点に集約されます。次の章では、こうした要素をどう外部に発信するか、特にSNSや広報を通じた伝え方を掘り下げていきます。
SNSと広報でクリニックをブランディング

エピソードでクリニックの魅力を発信
求職者にとって、求人票に並ぶ「福利厚生」「勤務時間」といった条件だけでは、実際の働き方や雰囲気は想像しづらいものです。だからこそSNSや広報では、数字ではなくエピソードを軸に伝えることが重要になります。たとえば「急な子どもの発熱で早退したスタッフを、他のメンバーが自然にフォローしてくれた」という事例を紹介すれば、制度の説明以上に「助け合える職場」という印象を与えることができます。
また、日常の小さな出来事を切り取って発信することも効果的です。スタッフの誕生日を皆で祝った様子や、診療終了後に残ったメンバーで雑談しているシーンなどは、読み手に「ここでなら安心して働けそうだ」と感じさせます。つまり、制度や条件を並べるよりも「人と人との関わりがどのように表れているか」を示すことで、リアルな魅力が伝わるのです。
エピソードは、求職者の「感情」に働きかけます。特に医療事務は患者対応が多い職種であり、人との関わりに価値を見いだす人が多いため、職場でのやり取りがどのように行われているかは非常に大きな判断材料になります。だからこそ、日常のエピソードを積み重ねて発信することが、採用につながる広報活動の基盤となります。
院長やスタッフの想いを発信
クリニックにおけるブランディングでは、院長やスタッフの「想い」を伝えることが欠かせません。経営理念や診療方針といった抽象的な表現だけではなく、「なぜこのクリニックを立ち上げたのか」「どんな人と一緒に働きたいのか」といった具体的な言葉が、求職者の心に届きます。
例えば院長が「地域に根ざした医療を続けたい」という信念を語れば、単なる診療所ではなく「地域の生活に寄り添う存在」としてのクリニック像が浮かび上がります。またスタッフが「患者さんに笑顔で帰ってもらえる瞬間が一番うれしい」と話せば、その職場に流れる価値観が伝わります。求職者は「自分も同じ思いで働けるだろうか」と自分に引き寄せて考えるのです。
さらに、想いを語ることは定着率の向上にもつながります。働く理由や方向性が共感できる職場は、困難に直面したときでも「この場所で頑張ろう」と思いやすいからです。つまり、理念や制度よりも「誰とどんな思いで働くか」を伝えることこそが、SNS広報において最も効果的なメッセージなのです。
写真や動画でクリニックのリアルを発信
文字だけの情報では伝わりにくいのが、クリニックの雰囲気です。SNSでは写真や動画を活用し、働く姿を視覚的に届けることが効果的です。例えば、受付で患者を迎えるスタッフの笑顔や、カルテ入力に集中する様子など、実際の業務風景を切り取った写真は、求人広告にはないリアリティを生みます。
動画はさらに強い説得力を持ちます。スタッフ同士のやり取りや、1日の流れをダイジェストにした短い動画は、文章では伝えきれない雰囲気を一目で感じさせます。特に最近は短尺動画の需要が高まっているため、数十秒程度のクリップでも十分に効果を発揮します。
重要なのは「完璧に整えた映像」である必要はないということです。むしろ日常の自然な瞬間を切り取る方が、求職者にとって信頼できる情報になります。過度に演出された映像は「本当は違うのでは」と疑念を抱かせることもあるため、あくまで自然体での発信を心がけることが大切です。写真や動画を通じて「ここで働く自分の姿」をイメージさせることが、応募につながる第一歩になります。
クリニック全体で広報活動を日常化
SNSや広報は「特別な活動」ではなく、日常の一部として取り入れることが成功の鍵です。採用のためだけに取り繕った発信は、長続きしないだけでなく、求職者にも見抜かれてしまいます。そこで、日々の診療やスタッフのやり取りを自然に発信していく仕組みが必要です。
例えば「週に1回はスタッフ紹介を投稿する」「毎月1回は院長が一言メッセージを発信する」といったルールを決めることで、無理なく続けられるようになります。また、写真撮影を担当するスタッフを固定せず、持ち回り制にすることで、様々な視点から職場を表現でき、発信の幅が広がります。
さらに、発信した内容をスタッフ全員で共有し「こんな反応があった」とフィードバックを行うことも有効です。成果が見えることでモチベーションが高まり、発信が組織文化として根付いていきます。広報を日常化することは、結果的に「ありのままのクリニック像」を持続的に届けることにつながり、採用力を高める大きな武器となります。
このように、SNSや広報を通じて伝えるべきは「制度や条件」ではなく「エピソード」「想い」「働く姿」「日常の積み重ね」です。次の章では、これらを継続的に発信するための院内体制づくりについて掘り下げていきます。
明日からできるクリニック採用ブランディング

スタッフ紹介から始めるシンプルな発信
最初の一歩として取り入れやすいのが「スタッフ紹介投稿」です。特別な設備や大規模なイベントがなくても、働いている人の姿を伝えるだけで、求職者にとっては大きな情報になります。たとえば「趣味はランニングで、休日は近くの公園を走っています」といった日常的なプロフィールを加えるだけでも、読み手に親近感が生まれます。
ポイントは、堅苦しい経歴紹介ではなく「人となり」が見える内容にすることです。勤務歴や資格だけでなく「朝は必ずコーヒーを飲んでから仕事に入ります」といった一言の方が、雰囲気を伝える力を持ちます。また、写真も正装した集合写真より、普段の笑顔や作業中の自然な姿を選ぶ方がリアルさを感じさせます。
こうした投稿は、採用希望者にとって「この人たちと一緒に働くのだろう」というイメージを形づくる材料になります。特に医療事務はチームで動く場面が多いため、人柄が伝わる情報は非常に重要です。小さな紹介の積み重ねが「雰囲気が良さそう」という印象を強め、応募のきっかけになるのです。
制度を使ったエピソードを発信する
次の一歩として効果的なのが、制度を「紹介」ではなく「活用エピソード」として発信することです。求人票に「産休・育休制度あり」と書かれていても、それだけでは実際に利用できるかどうかは伝わりません。しかし「昨年育休を取得したスタッフが無事に復帰し、今は時短勤務で活躍しています」といった事例を共有すれば、制度が実際に機能していることが具体的に伝わります。
さらに、「資格取得支援制度を利用して医療事務検定に合格したスタッフがいる」といった発信は、成長のチャンスがある職場であることを示せます。単なる制度一覧ではなく「誰が、どんな状況で、どう助かったのか」を描くことが大切です。
こうしたエピソードは、同じ状況にある求職者の共感を呼びやすく「自分も安心して働けそう」と感じさせます。制度を紹介するだけでは弱かった説得力が、エピソードとして描くことで一気に強まります。求職者の関心を動かすのは「制度そのもの」ではなく「制度を通じて得られる安心や成長」なのです。
応募前の不安を解消する情報提供
医療事務を志望する人の多くは、応募前に「自分に務まるだろうか」という不安を抱えています。業務内容の幅広さや患者対応の難しさに対する心配が、応募をためらわせる要因になるのです。こうした不安を和らげる発信は、応募数を増やすうえで効果的です。
例えば「未経験で入職したスタッフが3ヶ月で受付業務を一人でこなせるようになった」という成長エピソードを発信すれば、同じような立場の人に勇気を与えられます。また「入職初日はベテランが横についてフォローする」「ミスをしても一緒に原因を振り返る文化がある」といった安心感のあるサポート体制を伝えるのも有効です。
さらに、よくある質問をまとめて発信する方法もあります。「医療事務は資格が必要ですか?」「残業はどのくらいありますか?」といった疑問に、クリニック独自の答えを示すことで「応募してみよう」という一歩を後押しできます。不安を取り除く発信は、応募率を高めるだけでなく、入職後の定着にもつながります。
小さな習慣を積み重ねる
採用ブランディングを定着させるには、特別な取り組みではなく「小さな習慣」を積み重ねることが重要です。毎日の診療の中で「これは伝えられそうだ」と思った瞬間を写真に収めておく。週に一度はスタッフから短いコメントをもらう。こうした習慣が積み重なることで、自然に発信素材が蓄積されていきます。
小さな習慣は、無理なく続けられることがポイントです。最初から完璧を目指すと挫折しやすいため「週に1回投稿できれば十分」といった緩やかな目標設定が適しています。継続することで発信そのものが日常化し、やがて「広報活動は特別なものではない」という感覚が院内に根づいていきます。
また、こうした小さな習慣はスタッフの主体性を育む効果もあります。「自分が提案したアイデアがSNSに反映された」という体験は、自分事として広報に関わる意識を高めます。採用ブランディングは、特別な担当者だけが担うものではなく、院内全体で作り上げていくものです。習慣の積み重ねこそが、最も確実な一歩なのです。
医療事務の採用難は、単なる人手不足ではなく「働く環境が伝わらない」ことに起因しています。給与や制度だけでは差別化が難しい今、求職者が知りたいのは「どんな人と働くのか」「自分もここで成長できるのか」というリアルな姿です。そのためには、エピソードや日常の風景をSNSや広報を通じて発信し、クリニックの雰囲気や価値観を外部に届けることが不可欠です。役割分担やルールを整えて発信を継続すれば、採用活動は単発ではなく積み重ねとして機能し、応募数の増加や定着率の向上につながります。小さな一歩の積み重ねこそが、医療事務に選ばれるクリニックづくりの近道なのです。