訪問看護ステーションでは、
「応募数がなかなか集まらない」
「面接をしても入職後すぐに退職してしまう」
「求める人材像と応募者の価値観がずれている」
といった看護師採用の悩みが後を絶ちません。
背景には、ステーションが掲げるケアの「あり方」や「存在意義」が求職者に十分に伝わっておらず、単に条件面だけで比較されてしまうことがあります。本記事では、訪問看護におけるパーパス(存在意義)を明確にし、それを軸としたブランディング手法『パーパスブランディング』を活用して、応募者の共感を呼び、ミスマッチを減らし、長期的な定着につなげるポイントを解説します。「パーパスブランディングとは何か」「必要性」「実践ステップ」「5つのポイント」を順に見ていきましょう。
パーパスブランディングとは?

「なぜ存在するのか」を明確にする視点が採用の質を変える
訪問看護ステーションの採用現場で、応募者から「どんな職場ですか?」と聞かれたとき、何と答えているでしょうか。アットホームな職場、成長できる環境、多職種連携が円滑。こうした表現は、他のステーションでも多く見られるものです。結果として、「差別化できない」「印象に残らない」という課題に直面することになります。
ここで重要なのが、「パーパス(Purpose)」の明確化です。パーパスとは、訪問看護ステーションが社会や地域、利用者にとって「なぜ存在するのか」という意義そのものであり、単なるビジョンや理念とは異なります。個別のミッションや価値観といった内面的な要素を、対外的に言語化し、発信し、スタッフや求職者と共有していく。その中心的な考え方が「パーパスブランディング」です。
ブランディングの本質的な転換──「見せ方」ではなく「あり方」を示す
一般的に「ブランディング」という言葉が示すのは、ロゴやWebデザイン、キャッチコピーなどの「視覚的な統一性」や「印象操作」といった面です。もちろん、それらも重要な要素ではありますが、本質的な魅力を伝えるには不十分です。
パーパスブランディングでは、“どう見せるか”ではなく“なぜこの事業を行っているのか”を問い直し、それをメッセージとして明確に発信します。例えば、「最期の時間を安心して自宅で過ごせる地域をつくる」「家族とともに人生に寄り添う看護を提供する」といった言葉がそれに該当します。
これらは単なるスローガンではなく、日々の実践の中で繰り返し表出している「行動の理由」です。
このような「在宅ケアの中で私たちが果たすべき役割」を明文化することで、求職者は単なる条件比較から一歩進んで、「この価値観に共感できるか」という判断軸で応募を検討するようになります。
訪問看護の特性を踏まえたパーパスの核とは
訪問看護は、医療提供の場でありながら、「生活の延長線上」にあるという特性を持っています。つまり、患者だけでなくその家族も視野に入れた支援、地域との関わり、本人の人生観や生活観に即した関わりが求められます。これは、病院などの医療機関とは大きく異なる点です。
この文脈を踏まえると、訪問看護ステーションのパーパスは、以下のような要素を含むものとなる傾向があります。
・利用者の“その人らしい時間”を守る
・在宅で最期を迎える“選択肢”を地域に届ける
・家族も看護の対象として包括的に支える
・地域とともに“人生の締めくくり”に伴走する
これらの価値観は、言語化されなければスタッフ間でも曖昧なままに留まり、ましてや採用の場で応募者に伝えることは困難です。パーパスを明確に言葉にして示すことは、職場の価値観を社内外に可視化し、『共感による採用』を成立させる第一歩になります。
看護師も「共感」で職場を選ぶ時代
現在、求職者である看護師の多くは、「どのような環境で働くか」だけでなく、「どのような意味のある仕事に関われるか」を重視する傾向にあります。特に20代後半から30代の層では、「自分の信じる看護を実現できる職場かどうか」を基準に転職先を選ぶケースが増えています。
こうした価値観に応えるには、給与や福利厚生といった条件面の訴求だけでは不十分です。むしろ、「このステーションがなぜ存在するのか」「どんな社会的役割を果たしたいのか」といった事業の根幹に真正面から向き合い、その答えを伝えていく姿勢こそが、求職者との深い接点になります。
また、パーパスは掲げて終わりではありません。現場のスタッフがその意義を共有し、日々のケアの中で実感できるものでなければ、外部への発信にも真実味が伴いません。だからこそ、採用活動におけるキーワードとしてだけでなく、ステーション全体の「共通言語」として機能させていく必要があります。
パーパスブランディングの必要性

求職者の「選ぶ基準」が変化している
近年、訪問看護ステーションにおける採用活動では、従来の手法が通用しにくくなっています。特に顕著なのが、「条件提示」だけでは応募に至らないという現象です。かつては給与や勤務時間といった待遇面で他社と差をつけることが一定の効果をもたらしていましたが、現在では「働く理由」や「共感できる価値観」が職場選びの重要な判断基準となっています。
たとえば、ある訪問看護師が転職を決意する際、「これまでの職場ではマニュアル通りのケアに終始してしまい、自分らしい看護ができなかった」と語ることがあります。こうしたケースでは、次の職場に「看護の意味を感じられる環境」を求める傾向が強く、まさにパーパスが明確に発信されているかどうかが、応募の動機づけにつながります。
つまり、パーパスは単なる理念ではなく、看護師にとって「働く意義を感じられる場所かどうか」を見極める基準になっているのです。
数だけでなく質を高める採用へのシフト
応募数の確保だけに注力した採用は、ミスマッチや短期離職の温床となります。特に訪問看護は、病院勤務と異なり一人で判断を下す場面が多く、価値観や行動指針に共感できていないスタッフが入職すると、現場での孤立や業務負荷の偏りにつながりやすくなります。
パーパスを軸にしたブランディングは、このような「ミスマッチによる離職」のリスクを低減させる手法としても有効です。なぜなら、パーパスに共感して応募した人材は、あらかじめステーションの方向性や看護観を理解しており、入職後のギャップが少ないからです。
また、こうした共感ベースの採用が広がることで、結果として定着率も安定し、現場の人員構成にも中長期的な見通しが立てやすくなります。パーパスがあることによって、看護師自身が「ここで働く意味」を見出しやすくなり、それが持続的なモチベーションにつながるのです。
競争環境の中で「選ばれる理由」を明確に
訪問看護ステーションの数は年々増加しており、都市部を中心に求職者が「選ばれる側」から「選ぶ側」への主導権の変化が進んでいます。特にSNSや口コミを通じて情報収集を行う層にとって、各ステーションがどのような姿勢で訪問看護に取り組んでいるのかが大きな判断材料になります。
こうした背景では、「他とは違うから応募したい」と感じさせる独自性が不可欠です。単なる制度面の工夫や福利厚生の充実だけでは、他ステーションとの差別化は困難です。一方で、「家族の物語に寄り添う看護を大切にしている」「その人らしい生き方を支えることを使命とする」といった明確なパーパスが提示されていれば、他にはない魅力として強く印象づけられます。
また、面接時の対話でも、パーパスが共有されていれば話の軸がぶれません。
志望動機が曖昧な応募者に対して、「私たちはこのような想いをもって日々のケアにあたっていますが、どのような価値観を大切にしていますか?」と問いかけることで、価値観の一致・不一致を初期段階で見極めることができます。
組織内の一体感にもつながる
パーパスの発信は、外部に対する採用広報の手段であると同時に、内部における『共通認識の軸』にもなり得ます。訪問看護は、看護師個々の裁量が大きい働き方であるがゆえに、「自分の判断がステーションの方針とずれていないか」という不安が生まれやすい職場でもあります。
こうした不安に対して、明確なパーパスが浸透していれば、個々の判断や行動にも一貫性が生まれます。日々の意思決定において「これは私たちのパーパスに沿っているか?」という問いが持てるようになり、組織全体の方向性もぶれにくくなります。
また、入職者が「自分もこの一員として意味のある仕事をしている」と感じられることで、職務満足度も高まり、離職防止にも寄与します。採用から定着、さらには現場力の強化へとつながるこの流れは、単なるスローガンではなく実務に生きるパーパスであることを物語っています。
パーパスブランディングを始めるには?
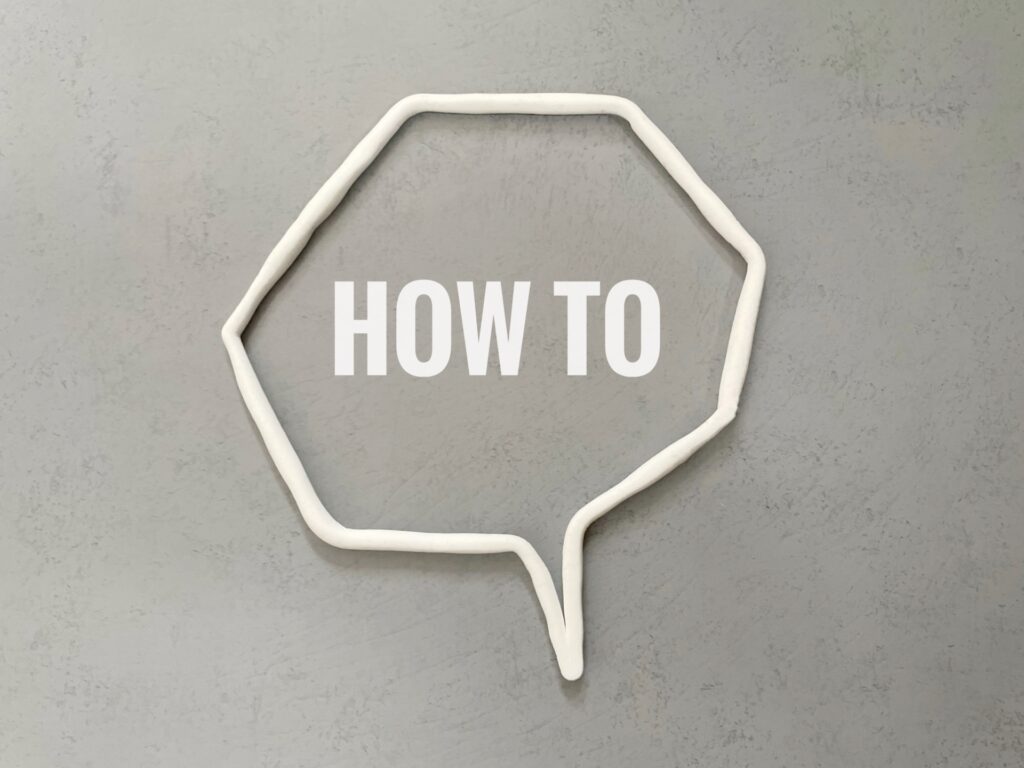
「意味」から始める採用活動:パーパスの起点は「理念」ではなく「実感」
パーパスブランディングを実践するうえで最も重要なのは、「理念を考えること」ではなく、「現場で日々実感している意味を言葉にすること」です。ステーションとして掲げる理念があっても、それが現場の看護師や求職者に伝わっていなければ、採用にはつながりません。
したがって、まず必要なのは「そもそも私たちは何のためにこの仕事をしているのか」「どんな瞬間にこの仕事をやっていて良かったと感じたか」といった問いを関係者で共有し、現場起点でパーパスを再確認する作業です。
特に訪問看護のように、一人ひとりの関わりがケアの質に直結する職種では、管理職や経営層の独断ではなく、実際に現場でケアにあたるスタッフの視点が不可欠です。
ステップ1:パーパスを「言語化」するための対話
言語化の第一歩は、「ストーリーの共有」です。採用担当者や管理者だけでなく、看護師や療法士など現場スタッフを含めて、「印象的だったエピソード」や「関わりの中で生まれた気づき」を振り返る場を設けましょう。
たとえば、「利用者の最期に立ち会った際、家族から家で看取れてよかったと感謝された」「独居高齢者が少しずつ笑顔を取り戻していく様子に寄り添えた」など、日々のケアに宿る価値は、実はそのままステーションのパーパスになり得ます。
これらを単なる「感動話」として終わらせるのではなく、「なぜそれが心に残ったのか」「その背景にあるステーションとしての考え方は何か」といった深堀りを通じて言語化していくことが求められます。この過程を経ることで、スタッフ一人ひとりの内にある「暗黙の価値観」が、組織全体で共有できる言葉へと変わっていきます。
ステップ2:パーパスを「体現」する日常づくり
言語化されたパーパスは、それだけで採用力を生むものではありません。
重要なのは、その言葉が実際に日常業務の中で「体現されているかどうか」です。
求職者は求人票やホームページだけでなく、見学時の雰囲気やスタッフの言動からリアリティを感じ取ります。
たとえば、「利用者の尊厳を大切にしたケア」をパーパスとして掲げていても、現場での声かけや業務進行が機械的であれば、矛盾を感じさせてしまいます。反対に、スタッフの表情や言葉遣い、申し送りの内容までがそのパーパスと一致していれば、自然と一貫性のある印象を与えることができます。
このように、「言っていること」と「やっていること」が一致していることが、パーパスブランディングを機能させる最低条件です。
ステップ3:パーパスを「届ける」採用コミュニケーション
パーパスを体現できるようになったら、それを採用活動の中でどう伝えるかが次の課題です。最も基本的なのは、求人票や採用ページの構成にパーパスを組み込むことです。冒頭に「私たちの訪問看護は、こういう想いから始まりました」と明示するだけでも、読み手の印象は大きく変わります。
また、SNSやブログなどを活用し、日々のケアを通じてパーパスがどのように息づいているかを発信することも効果的です。とくに最近では、InstagramやYouTubeなどのビジュアルメディアを通じて、現場のリアルな雰囲気を伝えるステーションも増えており、応募前の情報収集の手段として定着しつつあります。
さらに、面接の中でも「当ステーションでは、こうした考え方を大切にしています」とパーパスを起点に対話を始めることで、応募者の価値観との重なりを確認しやすくなります。こうした積み重ねにより、単なる“説明”ではなく、「共鳴」を生む採用活動へとシフトしていきます。
実施にあたっての留意点
パーパスブランディングの実践は、短期的なキャンペーンではありません。継続的な対話と見直しを通じて、徐々に浸透させていく取り組みです。言葉として一度完成させたものが、そのまま何年も通用するとは限りません。地域やスタッフ構成の変化に応じて、パーパスの内容や伝え方もアップデートしていく必要があります。
また、経営層と現場スタッフの間でパーパスへの理解や温度差がある場合には、無理に統一しようとするのではなく、「それぞれの立場でどう捉えているか」を擦り合わせる対話が求められます。実際にケアを担う現場と、運営を支える経営が同じ方向を見ているかどうかが、ブランディングの根幹にかかわるためです。
パーパスブランディングの5つのポイント

抽象論では機能しない。実行可能な「5つの視点」で取り組みを進める
パーパスブランディングは「理念を掲げるだけ」で効果が出るような施策ではありません。理念を具体的な行動に変え、採用や組織運営のあらゆる場面に“浸透”させて初めて、共感を生み出す力を持ちます。そのためには、「どう伝えるか」よりも、「どう感じ取られるか」を起点とした仕組みが必要です。
以下では、訪問看護ステーションでパーパスブランディングを実践する際に重要となる、5つの視点を紹介します。それぞれが独立しているのではなく、相互に関係しながら全体の一貫性を支える要素となります。
1. 目的の共創:現場との対話から始める
もっとも基本となるのが、「パーパスを上から与えるのではなく、共につくる」という姿勢です。経営陣が一方的に理念を決定するのではなく、現場スタッフが日々の業務の中で大切にしている価値観や実体験をもとに、ステーション全体で「何のために存在しているのか」を再確認することが求められます。
このプロセスを経ることで、パーパスが共感される言葉としてスタッフの中に根づきます。とくに中堅層やリーダー層の巻き込みは欠かせません。彼らの納得感は、後の採用面接や新人教育の場面でも自然ににじみ出るため、パーパスの実行力を高める基盤となります。
2. ストーリーテリング:ケアの背景を言語化する
理念を伝える際に有効なのが、ストーリーを通じた表現です。単に
と言うのではなく、
など、実際のケアの背景にある想いを具体的に語ることが大切です。
人は物語を通じて意味を理解し、共感を深めます。採用候補者にとっても、「そのような関わり方を自分もしたい」と感じられるストーリーは、動機形成の決定打になり得ます。また、こうしたエピソードを蓄積していくことで、ステーション独自の「語り継がれる文化」が形成されていきます。
3. スタッフエンゲージメント:内部意味”を浸透させる工夫
外部にパーパスを発信する前に、まず内部のスタッフがその意味を実感し、納得していることが不可欠です。たとえば、定例のミーティングやカンファレンスの中で、「このケースは私たちのパーパスにどうつながっているか」といった問いを自然に取り入れることで、日常的な価値の再確認が可能になります。
また、新人研修やOJTの場面でも、単なる業務マニュアルではなく、「なぜこのケアが必要なのか」「この対応が私たちの理念とどう結びついているのか」といった視点を加えることで、仕事への意味づけが強まります。このような内的動機付けの積み重ねが、離職の抑制や組織への信頼感につながります。
4. マルチチャネル発信:統一された語り口で外に届ける
求人票、採用サイト、SNS、事業所パンフレットなど、さまざまな接点で一貫したメッセージを発信することが重要です。とくにSNSは、見学や応募の前段階で求職者が「どんな職場なのか」を垣間見る手段として重視されています。
ここで気をつけたいのは、トーンの統一です。Webサイトでは理念を語っているのに、求人票では事務的な表現に終始しているようでは、一貫性が失われ、信頼性も低下します。どの媒体においても、「私たちはこういう想いでこの仕事をしている」という軸が伝わるよう、言葉選びを丁寧に行う必要があります。
さらに、動画や写真といったビジュアルコンテンツを用いることで、言葉だけでは伝わりにくい「雰囲気」や「空気感」も補完でき、よりリアルな訴求が可能となります。
5. 効果測定と改善:語って終わりにしない仕組みづくり
パーパスブランディングは一度表現すれば完了というものではありません。継続的にその成果を測定し、改善していくことが求められます。具体的には、以下のような視点での効果測定が考えられます。
・パーパスを明記した後の求人応募数・応募者の傾向の変化
・面接時における志望動機の深度(理念への言及の有無)
・入職者の定着率や離職理由の質的変化
・スタッフアンケートにおける組織への共感度・理解度の推移
これらの指標をもとに、言葉の表現を微調整したり、伝える媒体を見直したりすることで、パーパスが“生きた言葉”として機能し続けます。何より大切なのは、「伝えるためのブランディング」ではなく、「働く人と意味を分かち合うブランディング」であるという姿勢を持ち続けることです。












