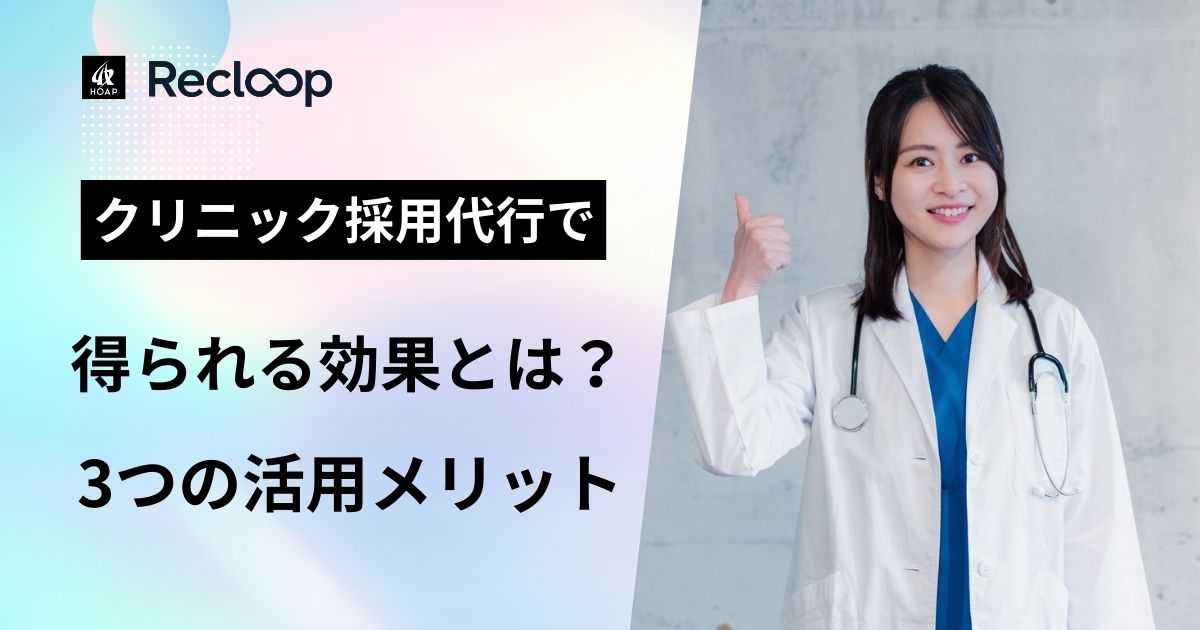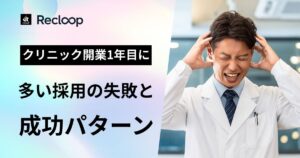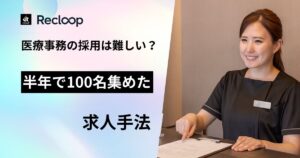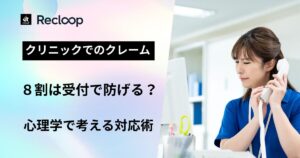クリニック経営において避けて通れない課題のひとつが「人材採用」です。診療体制を維持するために必要な人材を確保しようとしても、思うように応募が集まらない、採用できてもすぐに辞めてしまう、といった声は少なくありません。特に小規模クリニックでは、院長自身が診療と経営の両方を担っているため、採用活動に割ける時間が限られているのが実情です。そのため、求人票の作成や応募者対応が後回しになり、結果として採用機会を逃してしまうケースも多く見られます。
こうした背景から注目されているのが「採用代行」という方法です。採用代行とは、求人作成・応募者対応・面接日程の調整など、採用業務の一部または全部を外部の専門家に任せる仕組みです。近年では医療業界に特化した採用代行サービスも増えており、クリニックが直面する課題に即したサポートを受けられるようになってきました。
採用代行を導入することで、院長やスタッフの負担を軽減しつつ、応募数の増加やマッチング精度の向上を実現できる可能性があります。さらに、採用にかかるコストや時間を最適化することも期待できます。本記事では、クリニックが採用代行を活用することで得られる効果を3つの観点から解説し、院長が知っておくべき活用メリットを整理していきます。
なぜクリニックに採用代行が必要なのか?

採用に悩むクリニックの現状
クリニックにとって「人材が集まらない」という悩みは、年々深刻化しています。求人を出しても応募が数件にとどまり、しかもその中から本当に欲しい人材を選べるほどの余裕はない、という声をよく耳にします。背景には医療業界全体の人手不足があり、とりわけ看護師や医療事務は他院との競争が激しくなっています。さらに、応募が来ても面接の辞退や内定辞退が続き、採用活動が空回りすることも少なくありません。
こうした状況に直面している院長の多くは「求人広告を出しただけでは効果が出ない」という実感を持ちつつも、他に方法がなく足踏みしてしまうのです。その結果、欠員を抱えたまま診療を続けざるを得ず、既存スタッフにしわ寄せがいき、離職を招くという悪循環に陥るケースもあります。このような現実が、クリニックにおける採用の難しさを物語っています。

院長が抱える採用業務の負担
小規模クリニックでは、採用活動の大部分を院長が担っている場合が少なくありません。診療の合間に求人票を作成したり、応募者の対応をしたりするのは容易ではなく、後回しになってしまうことも多いのが実情です。特に求職者からの問い合わせや応募が入った際、すぐに対応できなければ他の医療機関に流れてしまう可能性が高まります。しかし、日々の診療を抱える院長が即応できる体制を整えるのは現実的に難しいのです。
また、採用活動は求人広告の出稿だけでなく、媒体の選定、原稿の修正、応募者とのやり取り、面接の日程調整、選考の進捗管理など多岐にわたり、想像以上に時間と労力を必要とします。こうした雑務に追われることで本来の業務である診療や経営判断に支障をきたすこともあり、結果的にクリニック全体のパフォーマンス低下につながるリスクがあります。採用代行を導入すれば、これらの事務的な業務を外部に任せ、院長は「最終判断」と「面接での直接確認」といった本質的な役割に集中できるようになるのです。
採用市場の変化と競争の激化
医療従事者の採用市場は、かつてと比べて大きく変化しています。以前は「資格を持っていれば職場はいくらでもある」という状況が一般的でしたが、現在は働く人が職場を選ぶ時代です。求職者は複数の求人を比較し、給与だけでなく職場の雰囲気や柔軟な働き方、福利厚生の充実度などを重視して選択する傾向があります。クリニックにとって、このような価値観の変化に合わせた情報発信は欠かせませんが、院長やスタッフが日常業務の合間に最新の採用トレンドを把握し、効果的な発信を続けるのは困難です。その結果、求人票が「条件を羅列しただけ」の内容になり、求職者に選ばれないケースが多発しています。
採用代行を活用すれば、こうした市場動向に精通した担当者が、求職者の視点に立った求人原稿を作成し、適切な媒体で発信してくれます。結果として、クリニック単独では届かなかった層にアプローチでき、採用のチャンスを広げることが可能になります。
採用代行導入の必然性
以上のように、クリニックの採用活動は
「応募が集まらない」
「時間が足りない」
「市場の変化に追いつけない」
という三重苦に直面しています。この状況を打開するには、従来の院内完結型の採用体制だけでは限界があります。採用代行は、単なる外部委託ではなく、こうした課題を現実的に解決するための手段です。院長が担っていた膨大な事務作業を外部に任せられることで、診療や経営判断に集中でき、スタッフの負担も軽減されます。
また、専門的な知見を持つ代行会社は、求人の訴求力を高め、採用市場の最新動向に即した戦略を立てることができます。その結果、応募者の数と質の両方を改善し、定着につながる採用を実現できる可能性が高まります。採用代行は「やるかやらないか」の選択肢ではなく、変化の激しい採用市場に対応し、クリニック経営を安定させるために必要不可欠な仕組みだといえるでしょう。
採用代行を使うことで得られる3つの効果

業務効率化による時間の確保
採用代行を導入する最大の効果のひとつは、院長やスタッフが採用業務に費やす時間を大幅に削減できる点です。クリニックの採用活動では、求人媒体の選定や原稿作成、応募者対応、面接の日程調整など、多くの細かい作業が発生します。これらは一つひとつは単純に見えても、積み重なると相当な負担となり、診療や院内運営に支障をきたす要因になります。
採用代行を利用すれば、これらの雑務を外部の専門チームが代行し、クリニックは最終面接や採否判断といった本質的な業務に専念できます。例えば、求人票の修正を依頼したその日のうちに対応が完了することもあり、スピード感を持った採用活動が可能になります。その結果、応募者を取り逃すリスクを減らし、同時に院長の時間を診療や経営に集中させられるという二重のメリットが生まれるのです。
応募数とマッチング精度の改善
採用代行を利用すると、応募数が増えるだけでなく、クリニックに合った人材に出会える可能性が高まります。理由のひとつは、専門の担当者が求職者の視点を理解した求人原稿を作成できる点にあります。多くのクリニックが求人票で条件や業務内容を羅列するだけになりがちですが、代行業者は「どのような職場なのか」「ここで働くとどんな未来が得られるのか」といったメッセージを盛り込み、応募者の共感を引き出す表現に変換します。
さらに、媒体選びも重要です。看護師や医療事務を採用したい場合、一般的な求人サイトでは埋もれてしまうことが多いですが、医療業界に強い媒体やSNSを活用することで、ターゲット層に確実に届く情報発信が可能になります。その結果、応募の母数が増えるだけでなく、クリニックの文化や働き方にフィットする人材に出会える確率が高まります。
採用コストの最適化と投資効果の向上
「採用代行は費用がかかるのでは?」
と懸念する院長もいますが、実際にはコストを最適化する効果があります。例えば、経験の浅い担当者が手探りで求人広告を出稿すると、効果が出ないまま広告費が消えてしまうことも少なくありません。
採用代行を利用すれば、媒体選定や原稿改善を専門家が行うため、無駄な出稿を減らし、費用対効果の高い運用が可能になります。また、採用活動にかかるスタッフの人件費や残業時間を考慮すると、外部に任せたほうがトータルコストが抑えられるケースも多いのです。さらに、採用に成功すれば欠員による機会損失や離職リスクが減少し、経営的にも安定につながります。コスト削減だけでなく「必要な人材を確実に採用できる」という投資効果を得られる点で、採用代行はクリニックにとって合理的な選択肢となります。
定着率の向上につながる採用の質改善
採用代行のもう一つの効果は、採用した人材の定着率向上につながる点です。従来の採用活動では「応募が来た人をとりあえず採用する」という流れになりやすく、結果的にクリニックとの相性が合わず、短期間で退職してしまうケースが多発していました。
採用代行では、応募段階からクリニックの魅力や特徴を求人票やスカウトメールで丁寧に伝え、応募者が職場をイメージしやすいようにサポートします。そのため、入職前後のギャップが小さくなり、早期離職の防止につながります。こうしたフィルタリング機能が働くことで、採用の質そのものが改善され、結果的に「長く働いてもらえる人材」を確保できる可能性が高まるのです。定着率の向上は、採用コスト削減だけでなく、院内の安定した診療体制の維持にも直結します。

クリニック採用代行を活用する際の注意点

任せすぎによるリスク
採用代行を導入する際に最も注意すべき点は、「全てを丸投げしてしまう」ことです。確かに業務負担を減らすために外部に任せるのは有効ですが、完全に任せきりにすると、応募者とのコミュニケーションに温度差が生まれます。
例えば、求人原稿や初期対応を外部が担うこと自体は問題ありませんが、クリニックの雰囲気や現場での具体的な働き方までは外部の担当者が完全に把握しているわけではありません。そのため、応募者にとって知りたい情報が欠けたり、面接時に「思っていたイメージと違う」と感じられたりするリスクが高まります。
採用代行はあくまでサポート役であり、クリニックの「顔」である院長やスタッフが直接発信する情報や姿勢がなければ、信頼性は低下します。丸投げにせず、役割分担を明確にしたうえで適切に活用することが重要です。
情報共有不足が招くミスマッチ
採用代行を利用する際には、クリニックと代行会社の間で十分な情報共有が不可欠です。例えば
「どんな人材を求めているのか」
「クリニックの強みや特徴は何か」
といった情報を伝えきれていないと、求人票の内容が抽象的になり、結局は求める人材が集まらない結果につながります。
さらに、現場の声を代行担当者に共有しないまま進めてしまうと、実際に働くスタッフとのギャップが生まれ、採用後に早期離職が発生するリスクも高まります。具体的には、応募者に対して「残業が少ない」と伝えていたのに、現場では繁忙期に残業が多く発生している場合、ミスマッチが生じるのは必然です。このような事態を防ぐためには、定期的な打ち合わせや進捗報告を通じて、代行担当者に最新の情報を提供することが欠かせません。採用代行は「外部」ですが、パートナーとして密に連携することで、初めて本来の効果を発揮します。
契約内容と料金体系の理解不足
採用代行サービスには、契約形態や料金体系の違いが数多く存在します。月額固定で一定範囲の業務を委託できるプランもあれば、成果報酬型で採用決定時に費用が発生するものもあります。また、対応範囲も「求人票作成のみ」「応募者対応まで含む」「面接同席も可能」など、サービスによって大きく異なります。契約前にこれらを十分に確認せずに依頼すると、期待していたサポートが含まれていなかったり、想定以上の追加費用が発生したりするリスクがあります。
特に小規模クリニックでは予算が限られているため、料金体系を誤解したまま契約するのは大きな負担になりかねません。導入を検討する際は、複数社のサービス内容を比較し、どの範囲まで委託できるのか、追加費用の有無、成果が出なかった場合の対応などを事前に確認することが必要です。
クリニック独自の魅力を伝える工夫不足
採用代行に任せると、求人票の品質や応募者対応のスピードは向上しますが、クリニック独自の魅力を十分に伝えられないままになってしまうリスクがあります。代行担当者は採用のプロですが、日々現場で働いているスタッフの雰囲気や、院長の理念、地域患者との関わり方などの「温度感」までは完全に把握できません。そのため、画一的な求人原稿になってしまい、他の医療機関との差別化が不十分になる可能性があります。求職者にとって
「どんな人と一緒に働けるのか」
「自分の価値観に合う職場かどうか」
は大きな判断基準です。その部分を伝えるには、院長やスタッフの生の声や具体的なエピソードを積極的に提供する必要があります。採用代行はそれを言語化し、発信の形に整える役割を担います。外部任せにせず、クリニックならではの特徴をしっかり共有することが、差別化と定着率向上のカギとなります。
採用代行と院長の役割分担

採用代行に任せられる領域
採用代行に依頼できる領域は幅広く、求人原稿の作成から応募者対応、面接日程の調整まで多岐にわたります。特にクリニックにとって効果的なのは、求人媒体の選定や原稿の最適化です。求職者に響く言葉選びや、応募が集まりやすい媒体の組み合わせは、専門的な知識がなければ的確に行うことは難しいものです。採用代行はその部分を担うことで、応募の母数を増やす効果を発揮します。
また、応募者との初期対応や問い合わせ対応も任せることが可能です。これにより、院長やスタッフは細かな事務作業に追われることなく、本来の業務に集中できます。さらに、選考フローの進捗管理も代行できるため、面接の日程調整や候補者へのリマインドといった細やかな作業をスムーズに進められます。これらの領域を任せることで、採用活動全体の効率が格段に高まります。
院長が関与すべき重要な場面
採用代行が多くの業務を担ってくれるとはいえ、院長が必ず関与すべき場面があります。その代表が「面接」と「最終判断」です。求職者は応募段階から「院長はどんな人なのか」を強く意識しています。院長の人柄やビジョンに共感できるかどうかが、入職を決める大きな要因となるため、この部分を代行に任せることはできません。
特に小規模クリニックでは院長の存在が職場全体の雰囲気を形づくるため、面接で直接顔を合わせることが信頼関係の構築につながります。さらに、採用の最終判断を下すのも院長の責任です。代行業者が候補者の情報を整理し提案することはできますが、最終的にクリニックにふさわしいかどうかを見極めるのは院長の役割です。代行を活用しつつも「ここは自分が関わるべき」という線引きを持つことが、成功する採用の前提条件となります。
採用代行と院長が役割分担を明確にする方法
採用代行と院長の役割を明確にするためには、最初の契約段階で「誰がどこまでを担当するのか」を定義しておくことが重要です。例えば、「求人原稿の作成と応募者対応は代行」「面接と最終判断は院長」といったように、業務範囲を具体的に決めておくことで混乱を防げます。
また、進捗管理をどう行うかも大切なポイントです。月1回の定例ミーティングやチャットツールを活用した共有など、情報を途切れさせない工夫が求められます。役割分担が曖昧なままだと
「代行がやってくれていると思ったら対応されていなかった」
「院長が確認すると思っていた内容が抜けていた」
という事態が発生しかねません。事前に役割を明確にし、定期的に確認する仕組みを作ることで、スムーズな協力関係を築くことができます。
院長が果たすべき「クリニックの顔」としての役割
院長は採用において単なる意思決定者ではなく、「クリニックの顔」として求職者に安心感を与える存在です。特に小規模の医療機関では、院長の理念や人柄が職場の文化を大きく左右します。採用代行が求人原稿を整え、応募者を集めてきても、最終的に「ここで働きたい」と思わせるのは院長の姿勢や言葉です。
例えば面接の場で、診療に対する考え方やスタッフを大切にする想いを語ることで、応募者は「この院長と働きたい」と感じやすくなります。また、入職後の定着にも院長の関与は欠かせません。採用代行は採用段階でのサポートが中心ですが、院長が日常的にスタッフと信頼関係を築いていくことで、働きやすい環境が整い、離職防止につながります。採用代行はあくまで「橋渡し役」であり、その先にある本当の魅力を伝えるのは院長自身です。
クリニック採用代行を選ぶポイント

医療業界での知見があるか
採用代行を選ぶ際、まず確認すべきクリニックで採用代行を活用する院長です。例えば看護師という一つの資格であっても、病院勤務、訪問看護、クリニック勤務では求められる役割や働き方が大きく異なります。さらに、同じ職種でも「子育て中で時短勤務を希望する人」と「キャリアアップを重視する人」では価値観や仕事への姿勢が違います。医療業界特有のこうした多様性を理解していない代行会社では、求人票に現場感を反映できず、応募が集まらなかったり、採用しても早期退職につながったりするリスクがあります。
特に、一般業界にしか経験のない代行担当者は「条件整理」に終始しやすく、求職者の共感を引き出す求人設計には不慣れなケースが目立ちます。医療業界の知見を持つ代行会社であれば、現場で働く人の価値観を理解し、応募者が「自分に合いそう」と感じられる求人を提案できるため、採用の質を大きく高められます。
クリニックでの実績があるか
次に重視すべきは「クリニックでの採用実績があるか」です。病院や介護施設とクリニックでは採用の条件や働き方が異なり、単純に同じ方法が通用するとは限りません。例えば、病院採用に慣れている代行業者は「夜勤あり」「24時間体制」を前提に求人を作成する傾向がありますが、クリニックは日勤中心でワークライフバランスを重視する人材が多く集まります。この違いを理解しないまま求人を出すと、的外れな訴求になり、応募が集まらない結果につながります。
実際にクリニックでの採用支援実績がある代行業者であれば、診療所ならではの特徴や求職者が重視するポイントを踏まえた求人を作成できます。さらに、成功事例や失敗事例をもとに具体的なアドバイスを行えるため、クリニックにとっても導入の安心感が高まります。「過去にどのようなクリニックで、どんな職種を採用したか」を必ず確認し、実績を公開している代行会社を選ぶことが重要です。
レスポンスの速さ
採用代行を選ぶうえで意外に見落とされがちなのが「レスポンスの速さ」です。医療現場は診療が中心で、院長や事務スタッフが採用対応に割ける時間は限られています。多くの場合、応募者とのやり取りは昼休憩や診療後などに行われるため、代行会社からの返答が遅いと、その時間を逃してしまい、仕事が前に進みません。これは単なる効率の問題ではなく、院長自身のストレスにも直結します。
さらに、求職者対応のスピードはクリニックの印象に大きく影響します。応募後すぐに返信が来ると「対応が丁寧な職場だ」と感じてもらえますが、数日放置すれば「ここは人手が足りていないのでは」「働きづらそう」と不安を与えかねません。採用市場ではスピードが命であり、レスポンスの速さはそのまま採用成功率につながります。代行会社を選ぶ際には「問い合わせに対する返答時間」や「進捗報告の頻度」などを確認し、レスポンスの質を重視することが欠かせません。
提案型の採用代行かどうか
最後のポイントは「提案型の採用代行かどうか」です。単に依頼した業務を遂行するだけでは、採用活動の改善や成果の最大化は望めません。クリニックに必要なのは、求人状況や市場の変化を分析し、「今後はこの媒体が効果的です」「求人原稿の表現をこのように変えましょう」といった具体的な提案をしてくれる代行会社です。提案型の代行は、単なる外注先ではなく「パートナー」として伴走してくれる存在です。たとえば、応募数が伸び悩んだ場合に「新しい媒体を試してみましょう」と指摘してくれたり、応募者対応の改善点を具体的に助言してくれたりします。こうした提案を受けることで、院長は「採用がうまくいかない原因」を自ら理解し、改善の方向性を把握できます。逆に、言われたことだけを行う代行に依頼すると、成果が出なかったときに「なぜダメだったのか」が分からず、同じ失敗を繰り返すリスクがあります。提案型の代行を選ぶことは、採用を一時的な活動ではなく、継続的に改善していく仕組みに変える第一歩なのです。
クリニックにとって採用は経営の生命線であり、従来の求人広告だけでは人材確保が難しい時代になっています。採用代行を活用することで、業務負担の軽減、応募数とマッチングの改善、採用コストの最適化といった効果が期待できます。ただし、成功の鍵は「医療業界の知見」「クリニックでの実績」「迅速な対応」「提案型の姿勢」を持つ代行会社を選ぶことです。HOAPは医療・介護業界に特化した採用支援を行っており、院長と並走しながら課題解決を支援します。外部委託にとどまらず、経営に根差した採用の仕組みづくりまで一緒に考えるパートナーとして、安定した人材確保を実現するサポートを提供します。