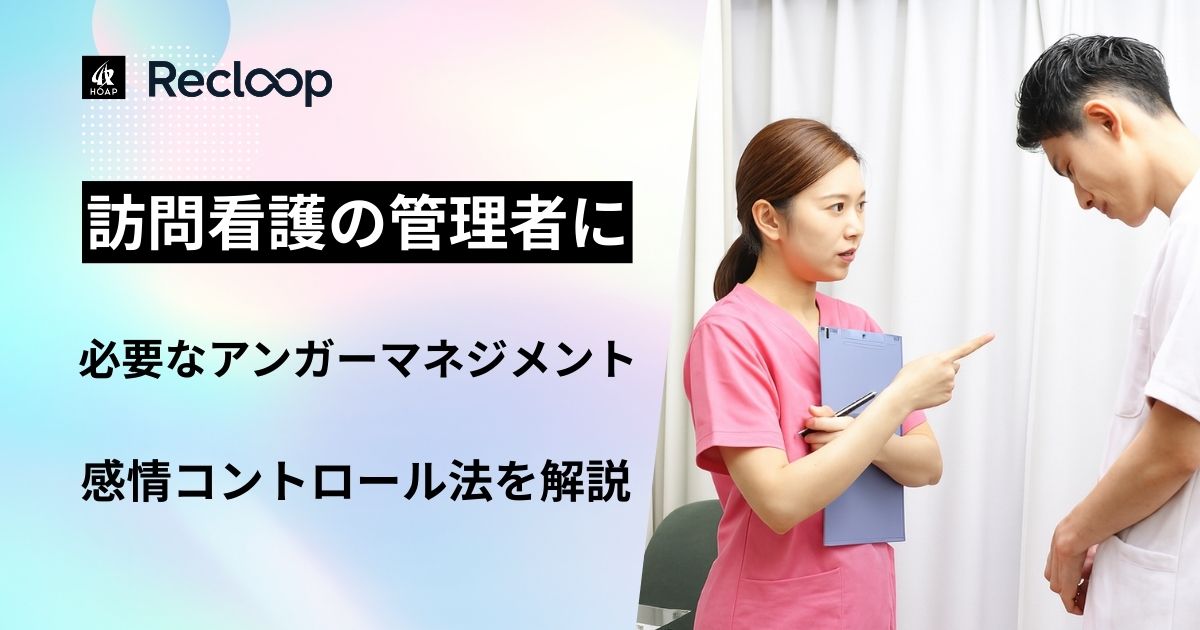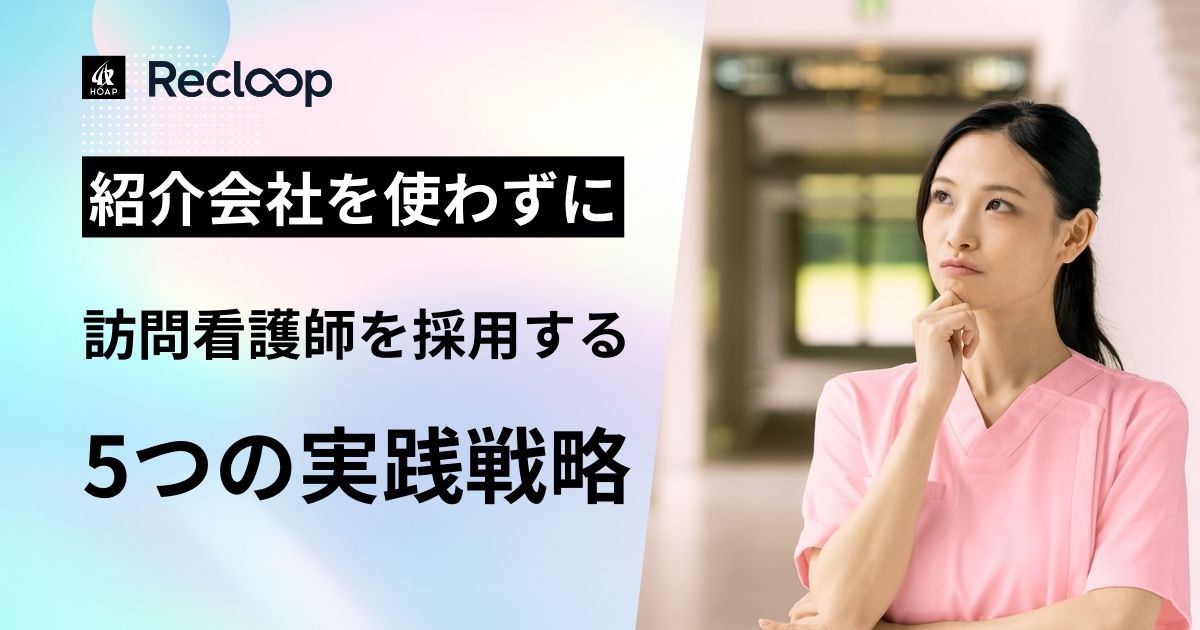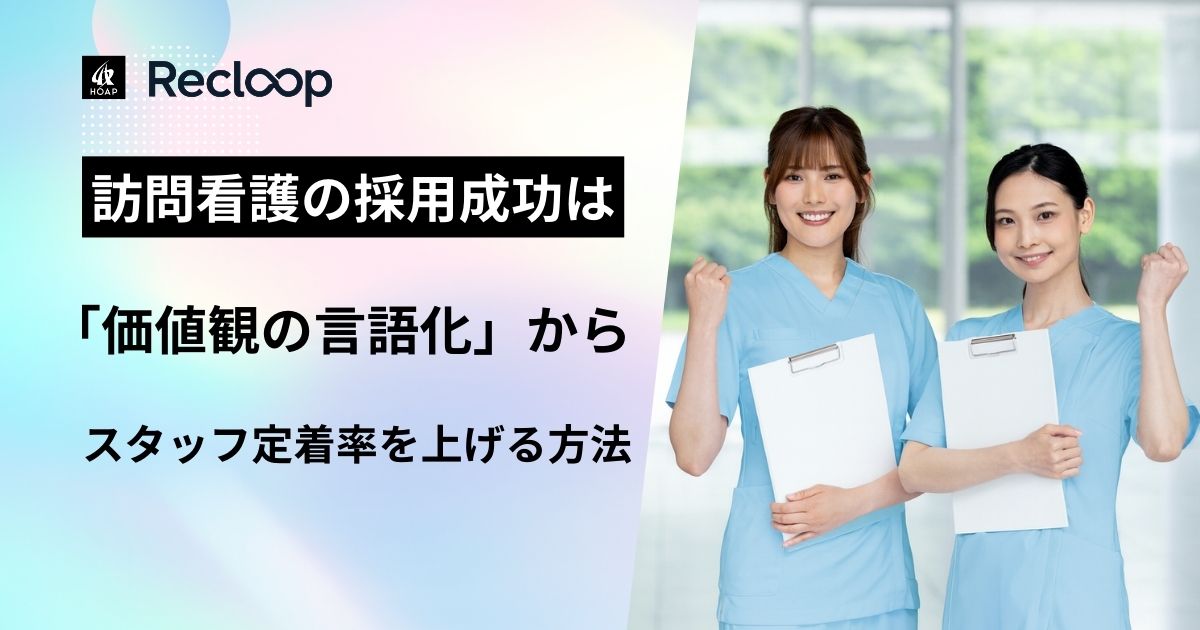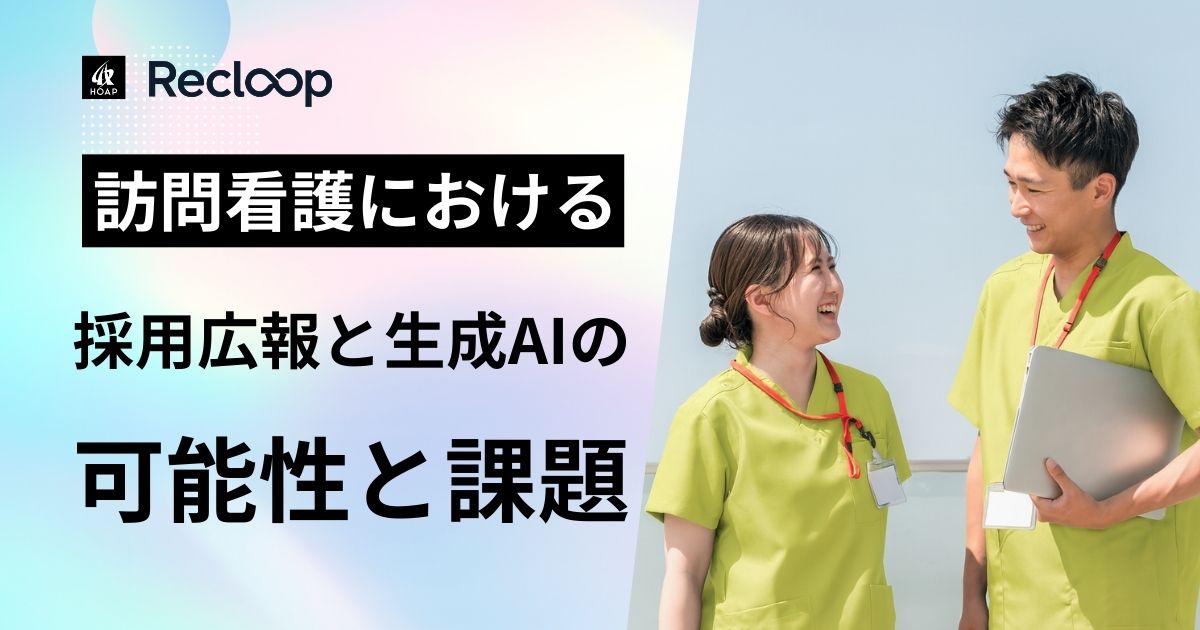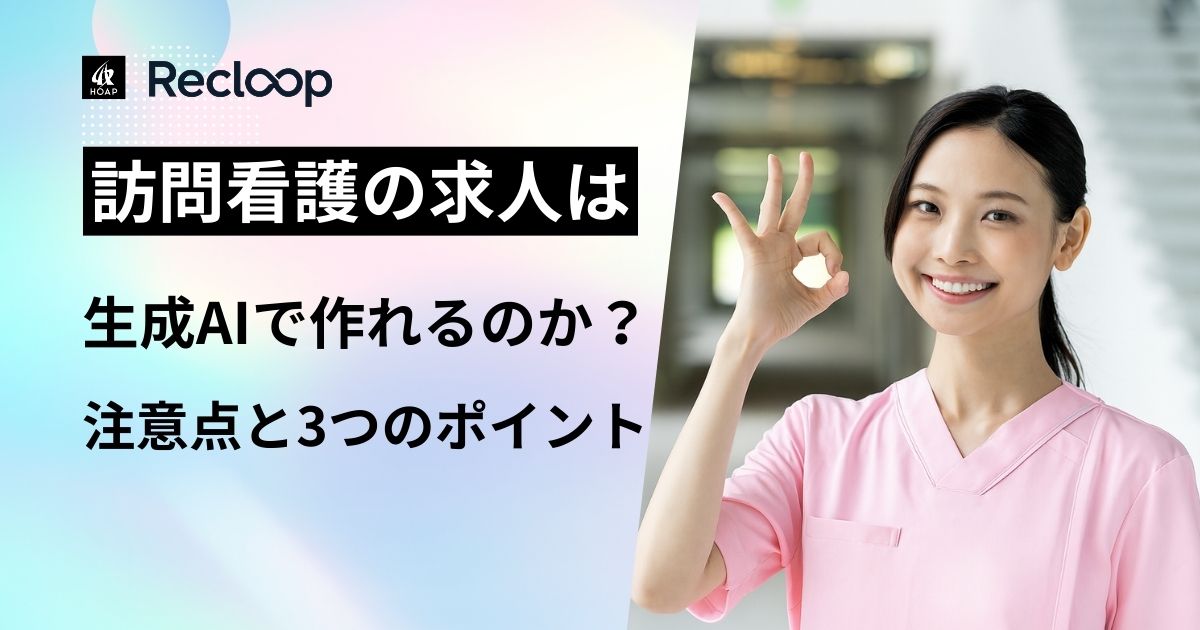訪問看護– category –
-
ハローワークを活用した看護師採用の成功法
 訪問看護の現場では、慢性的な人材不足に悩む事業所が少なくありません。とくに看護師の採用については、「求人を出しても応募が来ない」「問い合わせはあるが面接につながらない」といった声が多く聞かれます。その背景には、医療機関や介護施設との人材獲得競争が激しさを増していること、そして求職者側が「働きやすさ」や「自分に合った職場の雰囲気」を重視するようになったことがあります。 一方で、採用活動の入り口として多くの事業所が利用しているのがハローワークです。国の機関であり、利用が無料とい...
訪問看護の現場では、慢性的な人材不足に悩む事業所が少なくありません。とくに看護師の採用については、「求人を出しても応募が来ない」「問い合わせはあるが面接につながらない」といった声が多く聞かれます。その背景には、医療機関や介護施設との人材獲得競争が激しさを増していること、そして求職者側が「働きやすさ」や「自分に合った職場の雰囲気」を重視するようになったことがあります。 一方で、採用活動の入り口として多くの事業所が利用しているのがハローワークです。国の機関であり、利用が無料とい... -
訪問看護の管理者に必要なアンガーマネジメント【感情コントロール法を解説】
 訪問看護の現場では、管理者が日々さまざまなプレッシャーに直面します。スタッフの急な欠勤対応、利用者や家族からのクレーム処理、限られた時間でのスケジュール調整など、管理者は感情の揺れが避けられない状況に立たされやすい立場です。その中で「怒り」の感情をどのように扱うかは、スタッフとの信頼関係や組織全体の雰囲気にも直結します。 一方で、「怒りを抑えなければ」と無理に感情を押し殺すことが、必ずしも正しいとは限りません。怒りは人間にとって自然な反応であり、その表現の仕方を工夫すること...
訪問看護の現場では、管理者が日々さまざまなプレッシャーに直面します。スタッフの急な欠勤対応、利用者や家族からのクレーム処理、限られた時間でのスケジュール調整など、管理者は感情の揺れが避けられない状況に立たされやすい立場です。その中で「怒り」の感情をどのように扱うかは、スタッフとの信頼関係や組織全体の雰囲気にも直結します。 一方で、「怒りを抑えなければ」と無理に感情を押し殺すことが、必ずしも正しいとは限りません。怒りは人間にとって自然な反応であり、その表現の仕方を工夫すること... -
看護師採用コスト100万円超?費用内訳と削減の具体策
 看護師を採用する際、「1人あたり100万円を超えるコストがかかる」と耳にしたことはないでしょうか。実際、人材紹介会社を利用すると年収の20〜30%が手数料として発生し、1人の採用だけで100万円を超えることも珍しくありません。さらに求人広告の掲載料、面接対応にかかる人件費、入職後の研修コストなどを含めると、採用活動は経営にとって大きな負担となります。 一方で、こうした高額なコストをかけても早期離職が起きてしまえば、再度採用をやり直す必要があり、結果的に費用が積み重なります。「採用しても...
看護師を採用する際、「1人あたり100万円を超えるコストがかかる」と耳にしたことはないでしょうか。実際、人材紹介会社を利用すると年収の20〜30%が手数料として発生し、1人の採用だけで100万円を超えることも珍しくありません。さらに求人広告の掲載料、面接対応にかかる人件費、入職後の研修コストなどを含めると、採用活動は経営にとって大きな負担となります。 一方で、こうした高額なコストをかけても早期離職が起きてしまえば、再度採用をやり直す必要があり、結果的に費用が積み重なります。「採用しても... -
SNSから応募が来ない|訪問看護のSNS採用で避けるべき5つの落とし穴
 訪問看護ステーションの経営者にとって、SNS採用はもはや「やるかどうか」ではなく「どう成果につなげるか」が問われる時代になっています。InstagramやX(旧Twitter)を中心に、SNSは求職者が情報収集の第一歩として触れる場となりました。しかし現実には「毎日投稿しているのに応募が来ない」「フォロワーは増えているが採用には結びつかない」と悩む経営者も少なくありません。 その背景には、SNSを通じて応募につなげるための視点が欠けているケースが多くあります。例えば、発信の対象が曖昧で「誰に伝えたい...
訪問看護ステーションの経営者にとって、SNS採用はもはや「やるかどうか」ではなく「どう成果につなげるか」が問われる時代になっています。InstagramやX(旧Twitter)を中心に、SNSは求職者が情報収集の第一歩として触れる場となりました。しかし現実には「毎日投稿しているのに応募が来ない」「フォロワーは増えているが採用には結びつかない」と悩む経営者も少なくありません。 その背景には、SNSを通じて応募につなげるための視点が欠けているケースが多くあります。例えば、発信の対象が曖昧で「誰に伝えたい... -
地方こそインスタグラム|訪問看護の採用を変えるSNS活用法
 地方の訪問看護ステーションにおいて、人材採用は常に大きな課題です。求人を出しても応募が少なく、ようやく応募があっても「地域に根ざした働き方を望む人材」とは限らない。そのような悩みを抱えている事業所は少なくありません。特に地方では、都市部に比べて母数が限られており、従来の求人媒体だけに頼ると採用競争で後手に回ってしまう現実があります。 一方で、若い世代の看護師は情報収集の場を求人サイトからSNSへと移しつつあります。日常の延長線上で「どんな職場で働くのか」をイメージできるコンテ...
地方の訪問看護ステーションにおいて、人材採用は常に大きな課題です。求人を出しても応募が少なく、ようやく応募があっても「地域に根ざした働き方を望む人材」とは限らない。そのような悩みを抱えている事業所は少なくありません。特に地方では、都市部に比べて母数が限られており、従来の求人媒体だけに頼ると採用競争で後手に回ってしまう現実があります。 一方で、若い世代の看護師は情報収集の場を求人サイトからSNSへと移しつつあります。日常の延長線上で「どんな職場で働くのか」をイメージできるコンテ... -
紹介会社を使わずに訪問看護師を採用する5つの実践戦略
 訪問看護ステーションの経営において、採用活動は常に頭を悩ませる大きなテーマです。「求人広告を出しても応募が来ない」「せっかく採用しても定着せず、すぐに辞めてしまう」「紹介会社への手数料が重くのしかかる」――こうした状況は決して珍しくありません。特に人材紹介会社に頼る場合、採用が決まるたびに高額な費用が発生し、年間を通じてみると数百万円単位の出費になることもあります。加えて、紹介された人材が必ずしも自社の働き方や雰囲気に合うとは限らず、早期離職につながるリスクも存在します。 一...
訪問看護ステーションの経営において、採用活動は常に頭を悩ませる大きなテーマです。「求人広告を出しても応募が来ない」「せっかく採用しても定着せず、すぐに辞めてしまう」「紹介会社への手数料が重くのしかかる」――こうした状況は決して珍しくありません。特に人材紹介会社に頼る場合、採用が決まるたびに高額な費用が発生し、年間を通じてみると数百万円単位の出費になることもあります。加えて、紹介された人材が必ずしも自社の働き方や雰囲気に合うとは限らず、早期離職につながるリスクも存在します。 一... -
訪問看護の採用成功は「価値観の言語化」から|スタッフ定着率を上げる方法
 訪問看護の採用において「応募はあるのに定着しない」「なぜか面接で意欲が伝わらない」といった悩みを抱えるステーションは少なくありません。制度や待遇を整えても、なぜか採用が長続きしない。そんなときに見落とされがちなのが「価値観の共有」です。 訪問看護は、病院や施設勤務とは違い、一人で利用者の自宅を訪問し看護を提供します。そのため、看護師としての技術だけでなく、「利用者や家族とどう関わるか」「チームでどう支え合うか」といった考え方が日常の行動に直結します。つまり、職場ごとの価値観...
訪問看護の採用において「応募はあるのに定着しない」「なぜか面接で意欲が伝わらない」といった悩みを抱えるステーションは少なくありません。制度や待遇を整えても、なぜか採用が長続きしない。そんなときに見落とされがちなのが「価値観の共有」です。 訪問看護は、病院や施設勤務とは違い、一人で利用者の自宅を訪問し看護を提供します。そのため、看護師としての技術だけでなく、「利用者や家族とどう関わるか」「チームでどう支え合うか」といった考え方が日常の行動に直結します。つまり、職場ごとの価値観... -
訪問看護における採用広報と生成AIの可能性と課題
 訪問看護の採用活動において、多くの事業所が共通して抱えている悩みがあります。求人を出しても応募が集まらない、せっかく面接に進んでも定着につながらない、あるいは「仕事内容や魅力をどう伝えればよいのかわからない」という声です。訪問看護は病院勤務と比べて仕事内容のイメージが湧きにくく、働き方ややりがいも伝えづらい領域です。そのため、情報発信の工夫次第で求職者の印象が大きく変わってしまいます。 従来の採用広報は、求人票や説明会資料など、限られたフォーマットの中で表現することが中心で...
訪問看護の採用活動において、多くの事業所が共通して抱えている悩みがあります。求人を出しても応募が集まらない、せっかく面接に進んでも定着につながらない、あるいは「仕事内容や魅力をどう伝えればよいのかわからない」という声です。訪問看護は病院勤務と比べて仕事内容のイメージが湧きにくく、働き方ややりがいも伝えづらい領域です。そのため、情報発信の工夫次第で求職者の印象が大きく変わってしまいます。 従来の採用広報は、求人票や説明会資料など、限られたフォーマットの中で表現することが中心で... -
生成AI求人で失敗する訪問看護ステーションの典型パターン4選
 訪問看護ステーションの経営者や採用担当の中には、「生成AIを使えば求人文も簡単に作れるし、人材不足の悩みも解決できるのではないか」と期待した方も少なくありません。実際、AIは短時間で文章を整え、体裁の整った求人を出力してくれるため、一見すると効率的に見えます。しかし現場からは「応募は来たけれど定着しない」「そもそも応募が増えない」といった声が少なくありません。 なぜこうしたギャップが生じるのでしょうか。その背景には、生成AIが「言葉」を自動で並べることには優れている一方で、訪問看...
訪問看護ステーションの経営者や採用担当の中には、「生成AIを使えば求人文も簡単に作れるし、人材不足の悩みも解決できるのではないか」と期待した方も少なくありません。実際、AIは短時間で文章を整え、体裁の整った求人を出力してくれるため、一見すると効率的に見えます。しかし現場からは「応募は来たけれど定着しない」「そもそも応募が増えない」といった声が少なくありません。 なぜこうしたギャップが生じるのでしょうか。その背景には、生成AIが「言葉」を自動で並べることには優れている一方で、訪問看... -
訪問看護の求人は生成AIで作れるのか?注意点と3つのポイント
 訪問看護の現場では、人材不足が慢性的な課題となっており、求人募集を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。管理者や採用担当者にとって「いかに効率的に、かつ応募者に響く求人を作成できるか」は大きな関心事です。近年、生成AIを活用して求人原稿を作る取り組みが広がりつつありますが、その有効性やリスクについてはまだ判断が分かれる部分も多いといえます。 生成AIを利用すれば、短時間で複数の求人文案を作成でき、採用担当者の業務負担を軽減できます。また、現場の声をもとにした文章や、求職...
訪問看護の現場では、人材不足が慢性的な課題となっており、求人募集を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。管理者や採用担当者にとって「いかに効率的に、かつ応募者に響く求人を作成できるか」は大きな関心事です。近年、生成AIを活用して求人原稿を作る取り組みが広がりつつありますが、その有効性やリスクについてはまだ判断が分かれる部分も多いといえます。 生成AIを利用すれば、短時間で複数の求人文案を作成でき、採用担当者の業務負担を軽減できます。また、現場の声をもとにした文章や、求職...