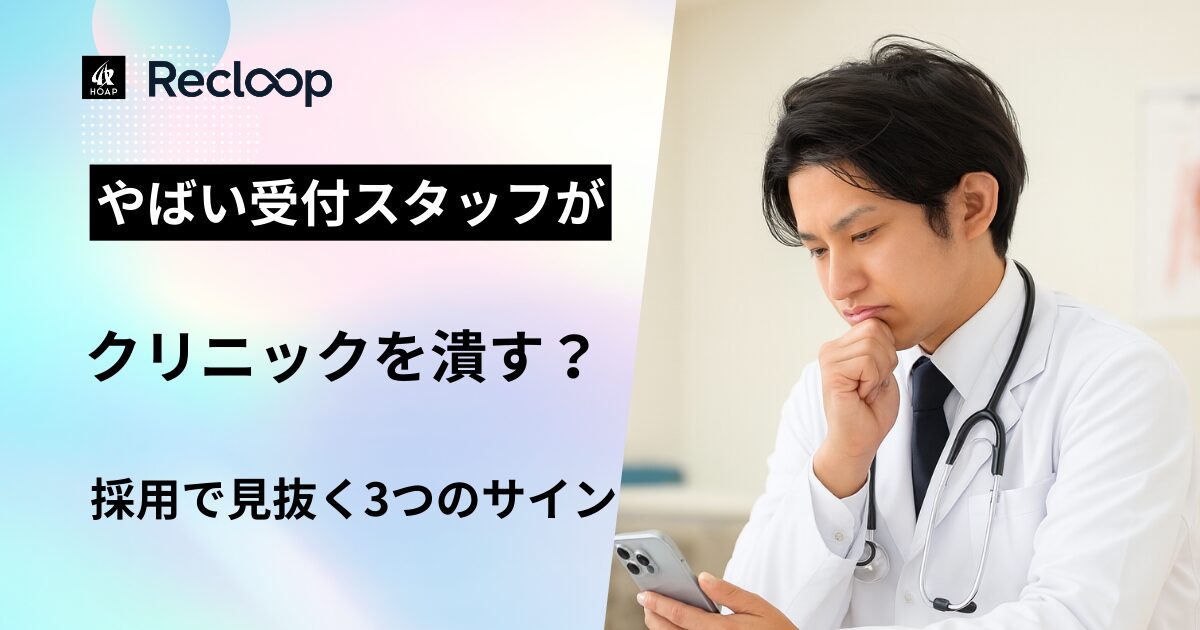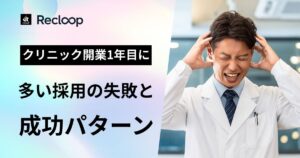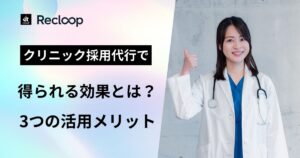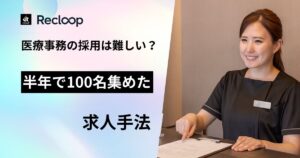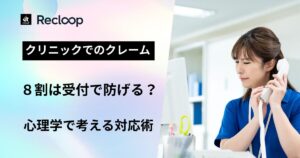患者との最初の接点となる受付は、クリニックの「顔」とも言える存在です。電話対応や来院時のひと声ひと声が、患者に安心感を与えることもあれば、不快感や不信感を植えつけることもあります。院長が診療の質向上に力を注いでいても、受付スタッフの対応ひとつで患者が離れてしまうのは珍しくありません。実際、「受付の人が冷たいから別のクリニックに変えた」という声は、医療現場では少なくないのです。
一方で、受付スタッフは業務範囲が広く、事務処理や会計だけでなく、患者と医師の橋渡し役としての役割も担っています。そのため、適性を誤った人材を採用してしまうと、内部のスタッフ間に摩擦が生じたり、院内全体の雰囲気が悪化したりすることがあります。最悪の場合、スタッフが次々と辞めてしまい、経営自体が不安定になるリスクすらあります。
問題は、採用の段階でそのリスクをどれだけ見抜けるかです。履歴書や資格だけで判断してしまうと、患者対応に向いていない人材を採用してしまう可能性が高まります。では、面接ややりとりの中で何をチェックすれば良いのか。そのヒントになるのが「やばい受付スタッフ」に共通する特徴です。
本記事では、クリニック経営を揺るがしかねないスタッフの特徴を取り上げながら、採用面接で見抜くための具体的なサインを解説します。さらに、採用後に後悔しないための工夫や、すぐに実践できる改善アクションまで順を追って紹介します。
なぜ受付スタッフでクリニックが傾くのか?

患者の第一印象を左右する重大な役割
受付スタッフは、患者がクリニックに足を踏み入れた瞬間に最初に出会う存在です。診療の内容や医師の腕が優れていても、最初に接する受付の対応が冷たいと、それだけで全体の印象は大きく損なわれます。「先生はよかったけれど受付の人が不親切だった」という感想は、口コミやSNSでも頻繁に見られるものです。患者にとって受付は診療の入口であり、心理的な安心感を得られるかどうかを決める大きな要素なのです。
さらに、電話対応においてもその影響は顕著です。初めて受診を検討している患者にとって、問い合わせの電話一本がクリニックの印象を決定づけます。丁寧に応じてもらえれば来院につながりますが、事務的で投げやりな対応をすれば、別のクリニックに流れてしまう可能性が高いのです。つまり、受付スタッフの対応は患者数の増減に直結する経営リスクを常にはらんでいます。
院内の信頼関係を壊す存在にもなり得る
受付スタッフの役割は患者対応だけにとどまりません。診療の進行をスムーズにし、医師や看護師と連携をとる重要なハブでもあります。ところが、情報共有を怠ったり、連絡が不正確だったりすると、診療の流れに支障が出てしまいます。例えば
「次の患者さんを呼び忘れる」
「検査依頼が伝わっていない」
といった小さなミスが積み重なれば、現場は混乱し、他のスタッフからの信頼も失ってしまいます。
また、院内の人間関係に悪影響を及ぼす場合もあります。患者の前では一見普通に振る舞っていても、裏では同僚に不平不満をぶつけ続けるタイプのスタッフは、職場全体の士気を低下させます。結果として離職者が増え、採用や教育にかけるコストが膨らみ、経営に直結するダメージとなるのです。
院長が見落としがちな「小さなズレ」
院長は、どうしても診療の質や集患施策に目を向けがちです。そのため、受付スタッフの採用リスクは軽視されやすい傾向にあります。「資格があるから」「経験年数が長いから」といった表面的な条件で判断してしまうと、実際に働き始めてから深刻な問題が露呈するケースが少なくありません。
例えば、経歴上は十分に即戦力と思われる人材でも、患者対応においては横柄な態度が出てしまう人もいます。あるいは、医療事務の知識は豊富でも、突発的なトラブルに柔軟に対応できない人材は、かえって現場を混乱させることになります。こうした「小さなズレ」を見抜けないまま採用すると、時間が経つほどにダメージが広がっていくのです。
長期的な信頼を失うリスク
受付スタッフの問題は、一度トラブルが起きると修復が難しいという特徴があります。患者が抱いた不信感は簡単には消えず、口コミや紹介といった地域での評判にも影響します。医療機関は一度信頼を失うと取り戻すのに長い時間がかかり、時には回復できない場合すらあります。特にクリニックは地域密着型の性質が強いため、ネガティブな印象が広がるスピードも早いのです。
さらに、内部の人材に与える影響も深刻です。
「あの受付スタッフのせいで雰囲気が悪い」
「自分の仕事がやりにくい」
といった声が広がると、優秀なスタッフほど早く職場を去ってしまいます。結果的に残るのは不満を抱えた人材ばかりとなり、院内の機能不全が進んでしまうのです。
受付スタッフは単なる事務職ではなく、クリニック全体の信頼や安定を支える基盤です。ここを軽視すると、知らぬ間に患者離れやスタッフ離れが進み、経営を大きく揺るがしかねません。次の章では、具体的に「やばい受付スタッフ」に共通する特徴を掘り下げ、採用段階で注意すべきポイントを明らかにしていきます。
「やばい受付スタッフ」に共通する特徴とは?

高圧的または事務的すぎる態度
受付スタッフにとって、最も大切なのは「患者を迎える姿勢」です。ところが、やばい受付スタッフに共通して見られるのは、高圧的な態度や、極端に事務的すぎる接し方です。例えば、患者が質問をした際に「そこに書いてあります」と冷たく突き放す、あるいは「忙しいので後にしてください」といった発言を繰り返すケースです。こうした対応は、患者の不安を増幅させ、クリニックに対する不信感を一瞬で高めます。医療機関は、患者にとって健康や命に関わる場です。その状況で「寄り添ってもらえなかった」という経験は強烈に記憶に残り、再来院を避ける理由につながります。
また、過度に事務的な態度も危険です。効率性を重視するあまり、患者の気持ちや状況に耳を傾けないスタッフは、「人として扱われていない」と感じさせてしまいます。表面的には業務をこなしていても、患者満足度を大きく損なう典型例です。
指示待ち体質で主体性がない
もうひとつの特徴は、主体性の欠如です。やばい受付スタッフは「言われたことしかやらない」という傾向が強く、突発的なトラブルや想定外の出来事に対応できません。たとえば、患者が体調を急に崩した場合、臨機応変に看護師へ連絡したり、他の患者対応をスムーズに調整したりといった判断が求められます。ところが、指示がないと動けないスタッフはその場で固まってしまい、対応が遅れることで院内全体に迷惑をかけます。
このような指示待ち体質は、経歴やスキルだけでは見抜きにくいものです。しかし現場に入るとすぐに露呈し、他のスタッフから「一緒に働きづらい」と感じられる要因になります。結果として、チームワークの低下や職場の雰囲気悪化につながりやすいのです。
情報共有や連携ができない
受付は診療の進行を支える「情報のハブ」でもあります。患者からの要望や問い合わせ、医師からの指示を正確に伝達できなければ、診療は滞り、現場は混乱します。やばいスタッフの特徴として多いのは、報告や連絡を怠ることです。例えば「先生には伝えました」と言いながら実際には伝わっていない、あるいは看護師に共有すべき内容を自分だけで判断して省いてしまうといったケースです。
情報が正しく伝わらないことは、小さな誤解や不便を積み重ね、最終的に大きなトラブルへと発展します。さらに、チームメンバーが不信感を抱き「またあの人が抜けていた」となると、組織全体の信頼関係が崩れてしまいます。こうした隠れたリスクを抱えるスタッフは、長期的に見ると院内の結束を弱める存在になります。
院内の雰囲気を悪化させる言動
患者対応が無難でも、裏側での振る舞いが問題になるスタッフもいます。代表的なのは、同僚に対する不満や愚痴を頻繁にこぼすタイプです。小さな不満を言い続けることで、周囲の士気を下げ、院内にネガティブな空気を広げてしまいます。さらに悪質な場合は、他スタッフの失敗を大げさに言いふらす、陰口を叩くといった行動に及びます。こうした態度は一気に職場環境を悪化させ、優秀な人材ほど早く離職してしまう原因になります。
加えて、患者の前で態度を切り替えるのがうまい人も少なくありません。表向きは愛想よく振る舞っているが、裏では協調性がなく、責任を他人に押しつける。このような二面性を持ったスタッフは、経営者にとって特に見抜きづらく、結果として長期的なリスクになりやすいのです。
「やばい受付スタッフ」の特徴は、患者への態度、仕事への姿勢、院内での振る舞いなど多岐にわたります。表面的には問題がないように見えても、水面下でクリニック全体の信頼を崩していく存在になることもあります。次の章では、こうしたリスクを採用段階でどのように見抜けるのか、具体的な「3つのサイン」を解説していきます。
採用面接で見抜ける「3つのサイン」

志望動機が浅く表面的である
面接で最初に確認すべきなのは志望動機です。やばい受付スタッフに共通するのは、
など、理由が浅く表面的であることです。もちろん勤務条件や通勤距離が重要なのは否定できませんが、それだけでは「この職場で働きたい」という意欲の裏付けになりません。
一方で、優秀な人材は自分の経験や価値観と照らし合わせながら応募理由を語ります。
といった言葉には、業務への理解や前向きな姿勢が表れます。逆に動機が浅い応募者は、入職後に壁にぶつかったときに簡単に辞めてしまう傾向があります。面接時点で「なぜこのクリニックでなければならないのか」を掘り下げて質問することで、表面的な動機に気づけるのです。
質問例としては、
「当院のどんなところに魅力を感じましたか?」
「これまでの経験をどう活かしたいと思っていますか?」
などが有効です。答えが曖昧だったり、求人票の文言をそのまま繰り返すだけであれば、長期的に定着する可能性は低いと考えるべきでしょう。
コミュニケーションの姿勢に違和感がある
採用面接は短時間ですが、その中に応募者のコミュニケーションスタイルが表れます。例えば、
・質問に対して目を合わせず一方的に答える
・こちらの話をさえぎって自分の意見ばかり主張する
といった態度は危険信号です。受付は患者の声に耳を傾け、柔軟に応じることが求められるため、面接のやり取りでその姿勢が欠けていれば、実務ではさらに問題が大きくなると予想されます。
また、表情や声のトーンも重要な観点です。緊張している応募者は多いものの、基本的な礼儀や感じのよさがにじみ出るかどうかは隠せません。例えば「面接を受けられることに感謝しています」と一言添えられるか、「ありがとうございます」と自然に言えるか。こうした小さな言葉の積み重ねは、日常業務で患者に安心感を与えるかどうかに直結します。
チェックの工夫としては、面接官がわざと曖昧な指示や少し意地悪な質問をしてみる方法があります。たとえば「少し聞き取りにくかったので、もう一度説明してもらえますか?」と依頼したとき、苛立ちを見せるのか、それとも丁寧に言い換えるのか。その瞬間の反応に人柄が表れます。
過去職場でのトラブル経験の語り方
経歴に触れる場面では、応募者の本音が見えやすくなります。注意すべきなのは、過去の職場についてネガティブな言葉ばかり使うケースです。「人間関係が最悪だった」「上司が理解してくれなかった」など、一方的な批判が多い場合、その人自身が問題を引き起こしていた可能性を疑うべきです。もちろん、誰しも職場で困難を経験するものですが、それをどう捉え、どう乗り越えたかを語れる人材は、逆境に強く成長も期待できます。したがって、
「前職でうまくいかなかったことは何ですか?」
「そのときどう対応しましたか?」
といった質問を投げかけるのが有効です。健全な応募者は
と前向きに説明します。やばいスタッフは「環境が悪かったから辞めた」と他責的に語る傾向が強く、責任感や改善意欲が欠けていることを見抜けます。
さらに、トラブル経験を聞く際には、その人が「学び」をどう表現するかもポイントです。たとえば「同僚との関係が難しかったけれど、自分の伝え方を工夫したことで改善できた」というような答えは、チームで働く上での柔軟性を示しています。逆に「自分は悪くないのに…」という姿勢を崩さない人材は、入職後も同じ問題を繰り返すリスクが高いといえます。
採用面接で注視すべきサインは、志望動機、コミュニケーションの姿勢、そして過去の経験の語り方に集約されます。これらを丁寧に掘り下げることで、入職後に大きな問題を引き起こす人材を避ける可能性が高まります。次の章では、こうしたサインを踏まえ、採用後に後悔しないための具体的な工夫について解説していきます。
採用後に後悔しないための工夫

複数人での面接評価を取り入れる
採用の失敗は、多くの場合「面接官一人の判断」に依存しているときに起こりやすいものです。応募者が一見感じよく見えると、院長が好意的に評価してしまい、冷静な判断を欠いてしまうことがあります。そこで有効なのが、複数人での面接評価です。院長だけでなく、現場の看護師やベテラン受付スタッフに同席してもらい、それぞれの視点で応募者を評価します。
例えば、院長が「しっかり答えていた」と好意的に感じても、スタッフが「患者対応に必要な柔らかさがない」と違和感を持つこともあります。複数の視点を掛け合わせることで、応募者の強みや弱みをより正確に把握でき、採用のリスクを大幅に減らすことが可能です。
さらに、同席するスタッフに「この人と一緒に働きたいと思うか」という観点でフィードバックを求めるのも有効です。現場で直接関わる人たちの意見は、実際の相性やチームワークに直結するからです。
実技テストやシミュレーションの導入
面接だけでは見えにくい部分を確認する方法として、実技テストやシミュレーションを取り入れる方法があります。受付スタッフの場合、電話応対や来院時の声かけ、会計処理などの基本業務を短時間でも模擬的に体験してもらうと、実際のスキルや対応力が明確に見えてきます。
たとえば、「予約の電話を想定して応対してみてください」と依頼し、声のトーンや言葉遣い、相手への配慮ができているかを観察します。シナリオを少し複雑にして、「患者が不安を抱えて質問をしてきた場合」や「予約が希望通りに取れない場合」などを設定すると、その人の臨機応変さや誠実さが分かりやすくなります。
また、患者対応のシミュレーションに加えて、医師や看護師への報告や連携の流れを試してもらうのも効果的です。「先生にこの内容を伝えてください」と指示したとき、正確かつ簡潔に伝えられるかどうかは、実際の現場で大きな差を生みます。
試用期間の活用
どれだけ慎重に面接や選考をしても、人材の本当の姿は現場で働いてみなければ分からない部分があります。そこで有効なのが試用期間の設定です。一定期間を試用として設け、その間に適性や協調性を確認する仕組みを整えることで、ミスマッチを早期に見抜くことができます。
試用期間中は、単に仕事をこなすだけでなく、スタッフ同士の関わり方や患者に対する態度も細かく観察することが大切です。例えば
といった行動は、書類や面接では判断できない部分です。
また、この期間を「教育の場」と位置づけることも効果的です。最初から厳しく評価するのではなく、業務を通じて適性を見極めながら育成する意識を持つと、ポテンシャルのある人材を伸ばしやすくなります。逆に、期間を通して改善の兆しが見られない場合は、早めに判断を下す勇気も必要です。
現場スタッフを巻き込んだフォロー体制
採用後に後悔しないためには、選考段階だけでなく入職後のフォローも重要です。やばいスタッフが育ってしまう背景には、「教育やフォローが不十分で放置されてしまった」というケースも多くあります。新しいスタッフが孤立せず、早期に職場に馴染めるよう、現場全体でのフォロー体制を整えることが不可欠です。
具体的には、先輩スタッフをメンター役として配置し、業務だけでなく日常の疑問や不安を気軽に相談できるようにします。さらに、定期的に面談の場を設け、成長度合いや課題を確認しながらサポートを続けることが望ましいでしょう。
また、院長も「採用して終わり」ではなく、一定のタイミングで声をかけることが効果的です。「最近どう?困っていることはある?」と一言かけるだけで、スタッフは安心感を得られます。フォロー体制が整っていれば、多少の課題を持つスタッフでも改善や成長が見込め、結果的に「やばい人材」へ転落するリスクを下げることにつながります
採用後に後悔しないためには、複数の視点での評価、実技を通じた確認、試用期間の活用、そしてフォロー体制の充実が鍵となります。これらを取り入れることで、採用リスクを大幅に減らし、長期的に安定した職場づくりが可能になります。次の章では、こうした工夫を踏まえて、明日から実際に取り組める具体的な採用改善アクションを紹介します。
明日からできる採用改善アクション

求人票に「合わない人材」を明示する
採用での失敗は「誰でも歓迎」といった曖昧な求人票から生まれやすいものです。応募の母数を増やすことを優先しすぎると、結果的にミスマッチが増え、採用後の離職リスクも高まります。そこで有効なのが、あえて「当院には向かない人材」を求人票に記載することです。
例えば、「患者さんに寄り添う姿勢を大切にしているため、効率だけを重視する方は合わないかもしれません」といった表現です。この一文で応募者は自分の価値観を照らし合わせることができ、応募の段階でフィルターがかかります。勇気のいる取り組みではありますが、結果的に定着率が高まり、経営の安定につながる確率は格段に上がります。
面接チェックリストの活用
面接時の印象だけに頼ると、相手の雰囲気に流されて冷静な判断ができなくなることがあります。そこで効果的なのが「チェックリスト」の活用です。事前に「患者対応への姿勢」「柔軟なコミュニケーション力」「過去の経験からの学び」など、評価項目を決めておき、面接官全員が同じ基準で観察できるようにします。
チェックリストがあることで、後から振り返ったときに「雰囲気はよかったけど、具体的に何が評価できたのか」を客観的に比較できます。加えて、複数人で採点を行うと、バイアスを避ける効果がさらに高まります。
現場スタッフの声を採用に反映する
採用の最終判断を院長だけが担うのではなく、実際に一緒に働くスタッフの声を反映させることも欠かせません。現場を知る人たちは「この人となら協力できそうか」「日常業務をスムーズに回せそうか」という感覚を持っています。採用の場にスタッフを巻き込むことで、現場とのギャップを減らし、定着につながりやすい人材を見極められます。
具体的には、最終面接の一部をスタッフ同席で行い、終了後に感想をフィードバックしてもらう方法があります。
「患者対応の声かけは良かった」
「質問に対して柔らかさが足りなかった」
など、現場ならではの気づきが得られます。採用は経営上の判断ですが、日々の業務を共にするスタッフの感覚を軽視してはいけません。
応募から採用までのスピードを意識する
良い人材ほど、複数の職場を同時に検討しています。面接や内定の連絡が遅いだけで他院に流れてしまうケースは少なくありません。そのため、応募から採用までのスピード感を持つことは、優秀な人材を確保する上で非常に重要です。
例えば「応募から面接まで最長でも3日以内」「面接から合否連絡まで1週間以内」といった基準を決めておくと、候補者に安心感を与えられます。また、連絡が早ければ早いほど「自分を必要としてくれている」と受け止めてもらえるため、内定承諾率の向上にも直結します。
Next Action(明日から実践できる具体的行動)
最後に、経営者や採用担当者がすぐに取り組める具体的なアクションを整理します。抽象的な改善ではなく、現場で即実践できるステップに落とし込むことで、採用力を確実に高めることができます。
・求人票に「合わない人材」の一文を入れる
・面接チェックリストを作成し、必ず複数人で評価する
・最終面接に現場スタッフを同席させ、感覚を反映する
・応募から面接までの流れを短縮し、スピード採用を徹底する
・試用期間を導入して、適性を早期に判断する
採用改善は大掛かりな制度改革だけでなく、日常の小さな工夫から始められます。こうしたアクションを積み重ねることで、やばいスタッフを避けつつ、定着率の高い安定した組織を築くことが可能になります。
クリニック経営において、受付スタッフの採用は患者満足度と組織の安定を左右する重要な要素です。対応一つで信頼を得ることも失うこともあり、採用の段階から慎重さが求められます。本記事で取り上げた「やばいスタッフ」の特徴や面接でのサイン、採用後の工夫、そして明日からできる具体的アクションを実践することで、採用リスクを大幅に減らすことが可能です。小さな工夫の積み重ねが、患者に選ばれ、スタッフに長く愛されるクリニックづくりにつながります。