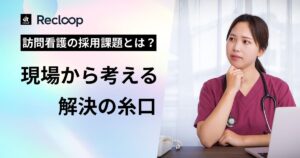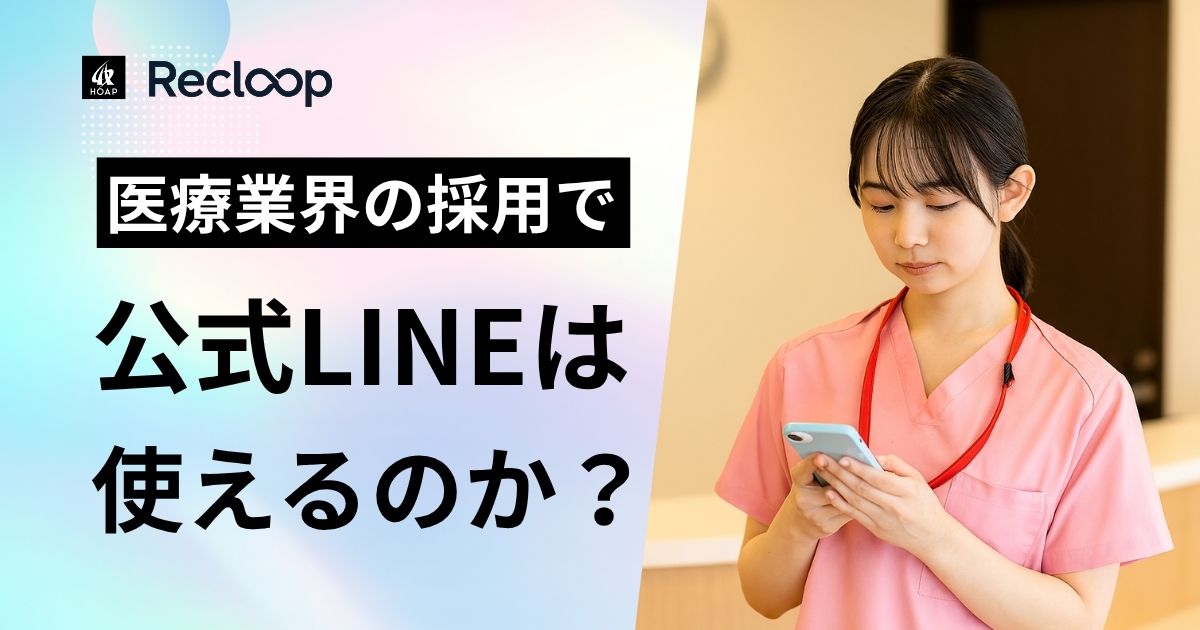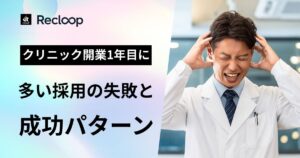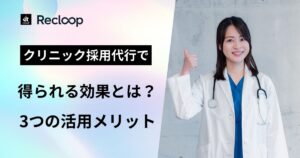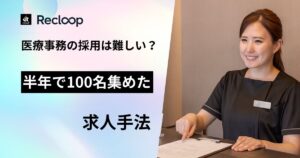「LINEを使えば応募が増えるのでは」と考え、採用活動にLINE公式アカウントを導入する事業者が増えてきました。手軽に登録でき、求職者との距離も縮めやすいという期待感は確かにあります。しかし、実際に活用してみると「登録はあるけど応募に至らない」「そもそも登録者が増えない」といった声が少なくありません。
その背景には、「LINEを開設すれば応募につながる」という短絡的な発想があります。本来、LINEは「応募のきっかけ」ではなく、「興味を持った人がもう一歩踏み出すための橋渡し」です。つまり、LINEは最初の入口ではなく、後半のステップで力を発揮するツールなのです。
にもかかわらず、前段となる認知活動や情報提供が十分でないまま、LINEアカウントだけを立ち上げても、求職者には存在すら気づかれず、結果として機能しないことが多くあります。また、登録後も単に「応募はこちら」と送るだけでは、求職者にとっての意味がなく、そのまま離脱されてしまう可能性も高まります。
LINEの活用は決して間違ってはいません。しかし、大切なのは「LINEを使うこと」そのものではなく、
LINEに至るまでの導き方、登録後に提供する中身、そして継続的な関係づくりです。
本記事では、医療業界の採用におけるLINE活用について、よくある誤解と現実、そして運用を効果的にするために必要な準備や考え方を順に見ていきます。
なぜ「LINEを使っても応募が来ない」のか?

「LINEを導入したのに応募がない」現象の正体
「LINEを導入したのに思ったように応募が来ない」という悩みは、医療業界における採用活動でしばしば聞かれる声です。手軽に登録でき、やり取りもしやすいという点でLINEを導入する事業所は増えていますが、結果が伴わないケースが多く存在します。このギャップの背景には、「LINEを始めた=応募につながる」という短絡的な前提があることが多く見受けられます。
実際には、LINEそのものが悪いわけではありません。問題は、LINEを“入り口”のように捉えてしまっている点にあります。
多くの事業者では、LINEのアカウントを立ち上げ、QRコードやリンクをホームページに設置するだけで運用が始まってしまっている状態です。
つまり、「LINEを設置した」という事実はあっても、「求職者がLINEを登録したくなる導き方」までは考えられていないケースがほとんどです。
本当に求職者に見られているのか?
多くの事業所では、LINEの登録導線が採用サイトに限定されており、認知される機会が非常に限られています。求職者側の視点で見ると、「この職場、ちょっと気になる」と感じた時に、すぐにLINE登録に踏み切るような接点が用意されていないのです。採用サイト内のリンクだけでは、行動に至るほどの動機付けとしては弱いのが実情です。
また、LINE登録を「応募の意思表示」と勘違いしてしまい、その後のコミュニケーションが一方的になることもあります。実際には「なんとなく気になったから」「採用ページの中にあったから」「応募する前に質問してみたかったから」という理由で登録されている場合も多く、温度感はさまざまです。そのため、いきなり「ご応募お待ちしています」と送っても、関心の薄いユーザーには距離を感じさせてしまい、むしろ離脱を促してしまう結果にもつながりかねません。
LINEは「応募の場」ではなく「関係の始まり」
LINEは応募の窓口ではなく、関係を築くための通路のひとつです。たとえば、SNSの投稿や紹介記事などを通して自社の雰囲気に共感してくれた求職者が、さらに詳しく知るためにLINEを登録する。
そういった「興味を持ったあとの行動」に対応するための手段であって、「まず登録してもらう」こと自体が目的になるのは本末転倒です。
この順番が逆になってしまうと、求職者の関心が育たないままLINEに誘導され、結果として何も起こらず、反応も返ってこないという状態になります。採用活動の中でLINEを活用するには、「どうやってLINEまでたどり着いてもらうか」という流れ全体を見直す必要があります。
見直すべきは「導く流れ」のつくり方
LINEが機能しない理由の大半は、LINEに至るまでの流れが構築されていないことにあります。
たとえば、SNSでの情報発信がない、採用ページに日々の様子が書かれていない、スタッフの声が外部に届いていない。
こうした状態では、LINEの存在そのものが知られず、登録の動機も生まれません。つまり、LINEは「入口」ではなく「反応した人をさらに受け止める場所」として位置づけるべきです。
LINEに意味を持たせるためには、「この人たちと話してみたい」と思われる前段階の工夫が欠かせません。LINE単体では成果は生まれにくく、それを使うための事前準備や周囲の発信があって初めて効果を発揮します。
採用LINEアカウントが機能するステップとは?

登録したのに応募が来ない理由は「流れの分断」にある
LINEの公式アカウントを開設してみたものの、「登録されても応募につながらない」「登録数自体が伸びない」といった課題を感じている事業所は少なくありません。
この状況を見て「LINEはうちには合わなかった」と結論づけるのは早計です。問題は、LINEを活かすための全体の流れが構築されていないことにある場合がほとんどです。
たとえば、LINEに登録するきっかけが求職者にとって自然な流れになっていない場合、登録する理由がそもそも見つかりません。採用サイトにLINEのQRコードを置くだけでは、興味関心が薄い人にとっては行動を起こす動機にはなりにくいのです。
つまり、求職者との最初の接点からLINEにたどり着くまでの一連の流れがつながっていないために、LINEが十分に機能しないのです。
採用でLINEを活かすには「順番」がある
採用活動におけるLINEは、関心を持った人にもう一歩踏み込んでもらうためのツールです。つまり、LINEは最初から使うものではなく、
ここを誤解し、「まずLINEから始める」という発想で進めてしまうと、登録はされても動きが出ない、という結果になります。
たとえば、InstagramなどのSNSで日々の様子や現場の雰囲気を発信し、「ちょっと気になる」と思ってくれた人が「もっと詳しく知りたい」と感じたタイミングでLINEの存在に触れる。そうした順番で流れをつくることで、LINEは「情報収集」や「相談の場」として機能しはじめます。
実際に成果が出ている事業所では、LINEを直接的な応募窓口としてではなく、「つながり続ける手段」として位置づけています。
いきなり応募を促すのではなく、「見学会の案内」「Q&Aコンテンツの配信」「現場スタッフの声」などを通じて、関心を持った人が安心して行動できるような接点をつくっているのです。
「関係性を深める場」としてLINEを使う
LINEに登録したからといって、すぐに応募に動く人は少数です。特に未経験分野(例えば病院から在宅分野)に挑戦しようと思っている求職者にとってはハードルの高い選択肢でもあります。そのため、まずは関心を持ってくれた人が「様子を見る」ための場としてLINEを活用することが現実的です。
メッセージの内容も「応募はこちら」ではなく、「うちの働き方って、こんな感じです」「こんな人が活躍しています」といった、関係づくりに重きを置いた発信が効果的です。
その積み重ねのなかで、「この職場なら合うかもしれない」「ちょっと相談してみたい」と思えるようになり、ようやく応募や面談といった行動に移ります。このように、LINEは決断の場ではなく、「迷っている人が安心できる場」として捉える必要があります。
タレントプールとしての機能を前提に考える
すぐに採用につながらないからといってLINE登録者を「動かない人」と判断するのは早すぎます。
LINEは、すぐに動くわけではないが将来的に可能性がある人たちとの接点を維持する「ストック」の役割を果たします。いわば、LINEは「候補者の引き出し」のような存在であり、ここに一定の登録者が蓄積されていれば、必要なタイミングでアプローチできる強力な手段となります。
この考え方を持てるかどうかで、LINE活用の成否は大きく変わります。「今すぐ応募してもらう」ためのツールではなく、「未来の応募者と関係を築く」ための場所として捉えることで、LINEの持つ可能性は広がっていくのです。
LINE登録者が離脱しない情報提供とは?

登録されても反応がない――その原因は「中身」にある
LINE公式アカウントを導入した多くの事業者で、「登録されたのに応募が来ない」「メッセージを送っても反応が薄い」といった課題が生じています。
これは、LINEそのものの機能性ではなく、登録者にどのような情報を届けているか、その内容の工夫が不足していることに起因します。単に「応募はこちら」といった一方的な案内を送るだけでは、求職者にとって魅力あるチャネルとはなりません。
LINE登録はあくまでスタート地点です。登録後に「このLINE、読んでいて参考になる」と思われる内容が届けられていなければ、通知は開かれず、反応も返ってきません。つまり、登録者にとって「読み続ける理由」がなければ、すぐに離脱されてしまいます。
LINEで届けるべき情報とは?
では、求職者が求めているのはどのような内容なのでしょうか。最も重要なのは、「自分に関係のある話だ」と感じられることです。たとえば、以下のような情報は、登録者の興味関心をつなぎとめる効果があります。
・よくある質問に対する回答(応募前に不安に感じる点)
・訪問看護の1日の流れ(時間の使い方や移動の様子など)
・スタッフの声(入職の理由・働いて感じた変化)
・未経験から始めた人の体験談
・福利厚生や制度が実際にどう活用されているか
・見学や面談の様子・気軽な接触の場の紹介
・子育てしながら看護師を続けているスタッフの両立ポイント
こうした情報は、「知らなかったことがわかった」「ちょっと安心できた」と感じられる内容であり、LINEを読み続ける理由になります。「応募の促し」よりも、「知れてよかった」と思える情報を重ねることが、関係を深めるうえでの基本です。
日常に近い話題こそ求職者の関心を引きつける
よりも、
のほうが、読み手の心を動かします。たとえば、スタッフが「子どもの発熱時に直帰できて助かった」と語る実例や、「訪問先で利用者さんと一緒に季節の話をした」などの日常は、求職者にとって「自分の未来を想像する材料」となります。
また、Instagramやブログなどと連動してLINEでも補足情報を送ることで、より自然に継続的な接点をつくることが可能になります。SNSで見かけてLINEを登録した人に対して、あらためて詳しい情報を届けることで、関心が高まりやすくなるのです。
一方通行の発信ではLINEの意味が薄れる
採用活動において、LINEを「通知ツール」のように扱ってしまうケースは少なくありません。「応募受付中」「面談会のお知らせ」などの案内だけを送っていては、登録者にとってメリットを感じにくくなり、結果としてスルーされるようになります。
求職者が知りたいのは「自分にとって意味のある情報かどうか」です。LINEを使うなら、「読み手の関心」を常に起点にしなければなりません。たとえば、「初めて訪問看護を経験する人が感じる不安」や「ブランク明けの再就職で戸惑ったこと」など、リアルなエピソードを通して「共感」と「安心」を届けることが求められます。
一度登録されたLINEを「続けて読まれる存在」にするには、送り手都合の情報から脱却し、「このLINEなら読んでみよう」と思わせる中身に切り替える必要があります。
本当にLINEを使うべきか?判断基準とは

「LINEを使えばうまくいく」は本当か?
医療業界でLINEを採用活動に取り入れる動きが広がっていますが、「うまくいっている」と実感できている事業所は限られています。その一方で、「LINEは効果的だと聞いた」「他の事業所もやっているから」といった理由だけで導入を進めてしまうケースも多く見られます。
LINEは確かに便利なツールであり、適切に活用すれば採用活動を補強する力があります。しかし、すべての事業所・すべての段階で有効とは限りません。むしろ、LINEを導入してもうまく機能しない場合は、「導入すること自体が目的化していた」というパターンが少なくありません。何のために使うのか、どのような段階の人とつながりたいのかを明確にしておかないと、ただ形だけのアカウントが残ることになります。
LINEが有効に働くケースとそうでないケース
LINEが効果を発揮するのは、「ある程度の認知が取れていて、もう少し深く関係を築きたい人がいる」場合です。
たとえば、Instagramで日々情報発信をしており、そこからプロフィール経由でLINE登録につながっている、あるいは見学会やイベントで接触した人に対して、フォローアップ手段として使っているケースです。このように、すでに「関心を持っている人」とのつながりを保つ手段としてLINEは非常に有効です。
反対に、「まず人が集まらない」「自社の存在を知られていない」という段階では、LINEを用意したところで登録すらされません。そもそも入口がない状態では、どれだけLINEの内容を充実させても求職者には届かず、運用が空回りしてしまいます。このような場合、優先すべきはLINEではなく、まず「知ってもらう」ための動きです。
LINEは「母数」のある組織にこそ機能する
LINEの特性は、「つながり続ける」点にあります。したがって、ある程度の登録者数が蓄積されるまでは、大きな反応や成果が見えづらいのが現実です。つまり、LINEは初動で成果が出るツールではなく、母数を活かしてじっくりつながるためのものです。
そのため、導入前に「どのくらいの登録を目指すのか」「その登録はどこから生まれるか」を具体的に考えておく必要があります。SNS運用や現場スタッフとの連携が弱いままでは、LINEに人が流れ込むことはありません。
また、登録者が一定数いたとしても、そこに届ける内容が乏しければ、結局反応は得られません。LINEは単なる窓口ではなく、関係を維持する土台です。その土台が強くなるかどうかは、「どうやって関わるか」にかかっています。
導入の前に注意すべきこと
LINEを導入すべきかどうか判断する際には、次のような視点で自問してみることが有効です。
・今の自社に「つながり続けたい」と思われる情報や接点があるか?
・自社のことをすでに認知してくれている人はどれくらいいるか?
・LINEに登録する理由が、求職者の側にとって明確になっているか?
・登録後に届けられる中身に、自信を持って読んでほしいと思えるか?
・中長期的にコンテンツ配信ができるリソースが確保できているか?
こうした問いを通じて、「LINEを使うかどうか」ではなく、「LINEを使って何を伝えたいか」「どう関係を築いていきたいか」が明らかになっていきます。
医療業界における採用活動でLINEを活用することは、求職者との関係を深める手段として有効です。しかし、LINEそのものが応募を生むわけではありません。鍵となるのは、LINEに至るまでの流れと、登録後に届ける情報の中身です。SNSなどを通じて関心を持った人に対して、LINEで「つながり続ける場」をつくることで、応募や面談といった行動に結びついていきます。大切なのは、導入するかどうかではなく、「誰と、どう関わりたいか」を起点に考えることです。目的に合った活用であれば、LINEは採用活動の有力なサポートになります。