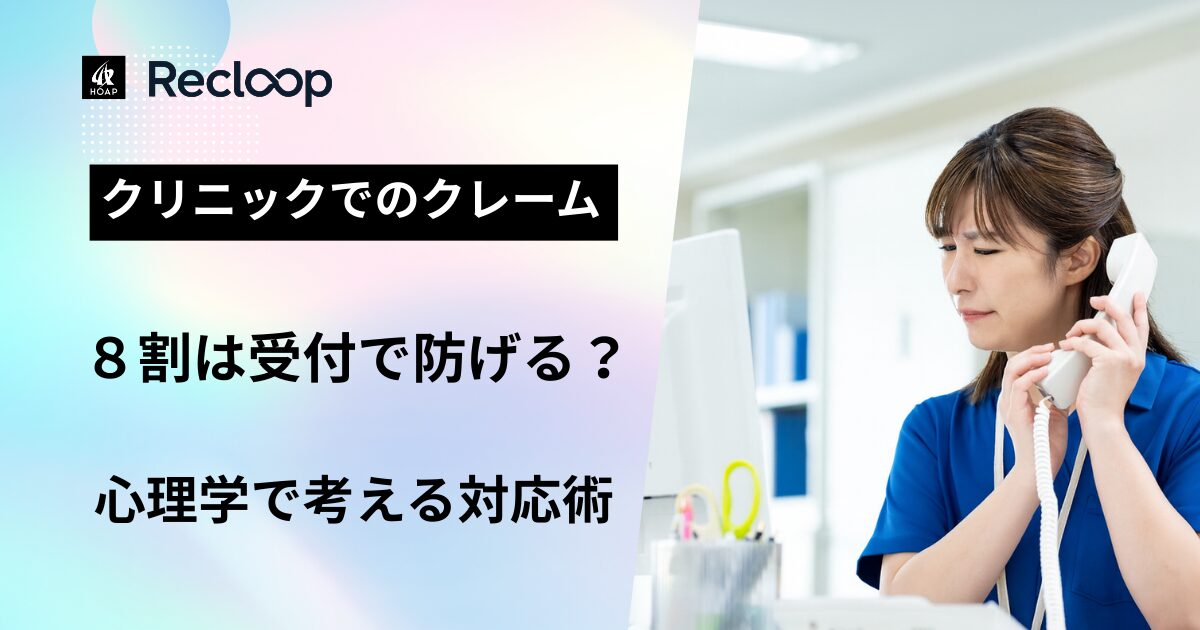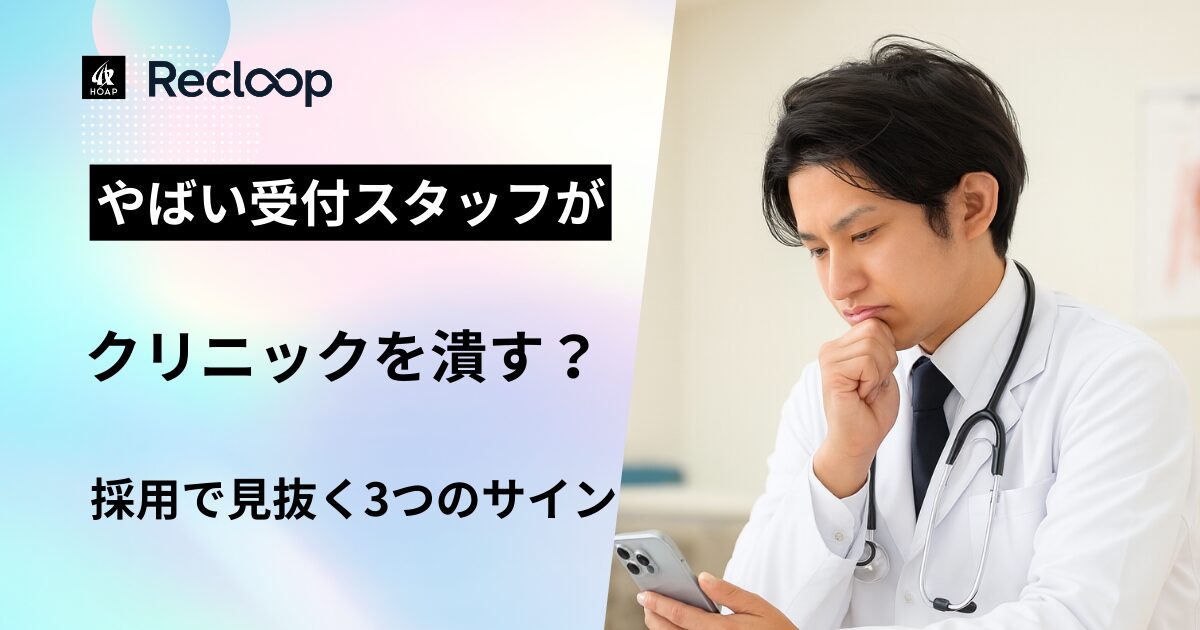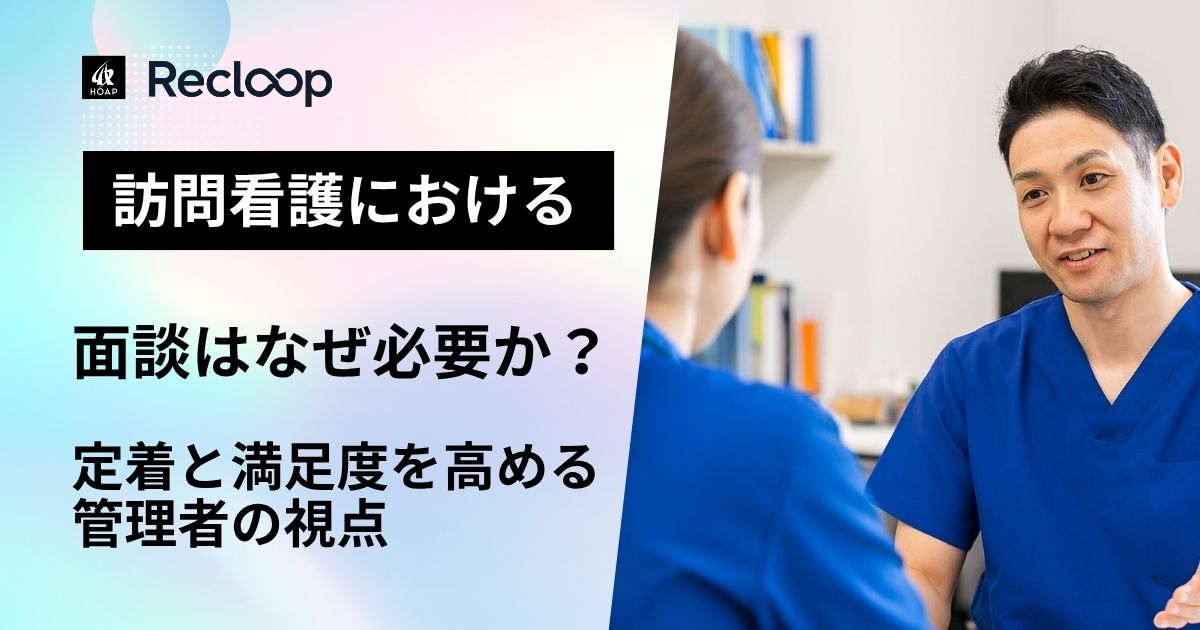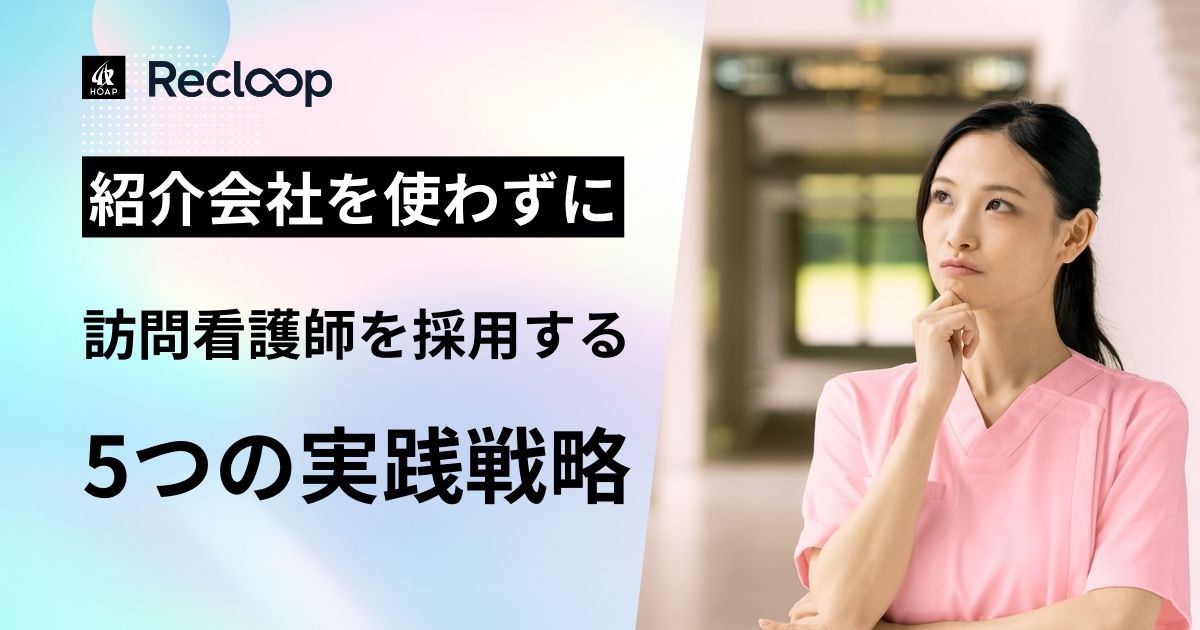-
訪問看護における人事評価を変える自己評価と評価者の開示
 訪問看護の現場では、人事評価に関する不満や戸惑いが少なくありません。「一生懸命やっているのに何を基準に評価されているのか分からない」「本当に自分の努力が伝わっているのか不安」という声は、スタッフのモチベーション低下や離職のきっかけにもなり得ます。日々の業務は利用者宅での個別対応が中心であり、上司や同僚がそばで見ているわけではありません。そのため、細やかな気配りや突発的な判断といった重要な行動が、評価の場面では見落とされやすいのです。 一方で、管理者や評価者も悩みを抱えていま...
訪問看護の現場では、人事評価に関する不満や戸惑いが少なくありません。「一生懸命やっているのに何を基準に評価されているのか分からない」「本当に自分の努力が伝わっているのか不安」という声は、スタッフのモチベーション低下や離職のきっかけにもなり得ます。日々の業務は利用者宅での個別対応が中心であり、上司や同僚がそばで見ているわけではありません。そのため、細やかな気配りや突発的な判断といった重要な行動が、評価の場面では見落とされやすいのです。 一方で、管理者や評価者も悩みを抱えていま... -
医療事務はクリニックの司令塔:採用で重視すべき3つの資質
 クリニックにおける医療事務は、単なる「受付担当」や「会計係」ではありません。患者さんが最初に接する窓口であり、診療報酬請求や予約管理といった事務作業を担いながら、医師や看護師と患者さんの間をつなぐ存在でもあります。つまり、医療事務はクリニックの円滑な運営を支える「司令塔」のような役割を果たしているのです。 しかし、採用にあたっては「経験があるかどうか」「パソコンが使えるかどうか」といった表面的な条件だけに注目されがちです。その結果、業務の正確性には長けていても、患者対応に不...
クリニックにおける医療事務は、単なる「受付担当」や「会計係」ではありません。患者さんが最初に接する窓口であり、診療報酬請求や予約管理といった事務作業を担いながら、医師や看護師と患者さんの間をつなぐ存在でもあります。つまり、医療事務はクリニックの円滑な運営を支える「司令塔」のような役割を果たしているのです。 しかし、採用にあたっては「経験があるかどうか」「パソコンが使えるかどうか」といった表面的な条件だけに注目されがちです。その結果、業務の正確性には長けていても、患者対応に不... -
訪問看護の業務改善を進めるときに知っておきたい5つの視点
 訪問看護の現場では、「スタッフが定着しない」「事務作業に追われて訪問に集中できない」「情報共有の場が形骸化している」といった悩みが少なくありません。利用者が増える一方で人材は不足しており、限られた人数で業務を回す状況が続いています。その結果、負担が積み重なり、離職につながる悪循環に陥るケースも見られます。 背景には、仕事の流れが属人的になっていること、役割分担が明確でないこと、ICT導入が不十分で活用されきれていないことがあります。さらに「改善の必要性は感じているが、どこから...
訪問看護の現場では、「スタッフが定着しない」「事務作業に追われて訪問に集中できない」「情報共有の場が形骸化している」といった悩みが少なくありません。利用者が増える一方で人材は不足しており、限られた人数で業務を回す状況が続いています。その結果、負担が積み重なり、離職につながる悪循環に陥るケースも見られます。 背景には、仕事の流れが属人的になっていること、役割分担が明確でないこと、ICT導入が不十分で活用されきれていないことがあります。さらに「改善の必要性は感じているが、どこから... -
クリニックでのクレーム8割は受付で防げる?心理学で考える対応術
 患者対応において「クレームは避けられないもの」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、発生するクレームの多くは初期段階で予防できるものです。特にクリニックの場合、患者が最初に接するのは受付であり、そこでのやり取りがその後の診療体験全体の印象を大きく左右します。例えば「予約したのに待たされた」「説明が曖昧でわかりにくい」「冷たい態度をとられた」といった声は、医師の診療内容そのものよりも受付の対応に起因していることが少なくありません。 心理学の観点から見ても、人は...
患者対応において「クレームは避けられないもの」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、発生するクレームの多くは初期段階で予防できるものです。特にクリニックの場合、患者が最初に接するのは受付であり、そこでのやり取りがその後の診療体験全体の印象を大きく左右します。例えば「予約したのに待たされた」「説明が曖昧でわかりにくい」「冷たい態度をとられた」といった声は、医師の診療内容そのものよりも受付の対応に起因していることが少なくありません。 心理学の観点から見ても、人は... -
訪問看護における褒め方:具体的な伝え方と人材定着のヒント
 訪問看護の現場では、スタッフが日々一人で利用者や家族と向き合い、多くの判断を重ねながら業務を進めています。病院のように常に同僚と一緒に動ける環境ではないため、行ったケアや工夫が周囲に見えにくく、「本当に自分のやっていることは役に立っているのだろうか」と不安を抱きやすい職種でもあります。こうした背景から、スタッフの努力をどう認め、どのように言葉をかければ良いのかに悩む管理者は少なくありません。「ただ『ありがとう』と言うだけでは足りないのではないか」「褒めたつもりが逆におだて...
訪問看護の現場では、スタッフが日々一人で利用者や家族と向き合い、多くの判断を重ねながら業務を進めています。病院のように常に同僚と一緒に動ける環境ではないため、行ったケアや工夫が周囲に見えにくく、「本当に自分のやっていることは役に立っているのだろうか」と不安を抱きやすい職種でもあります。こうした背景から、スタッフの努力をどう認め、どのように言葉をかければ良いのかに悩む管理者は少なくありません。「ただ『ありがとう』と言うだけでは足りないのではないか」「褒めたつもりが逆におだて... -
やばい受付スタッフがクリニックを潰す?採用で見抜く3つのサイン
 患者との最初の接点となる受付は、クリニックの「顔」とも言える存在です。電話対応や来院時のひと声ひと声が、患者に安心感を与えることもあれば、不快感や不信感を植えつけることもあります。院長が診療の質向上に力を注いでいても、受付スタッフの対応ひとつで患者が離れてしまうのは珍しくありません。実際、「受付の人が冷たいから別のクリニックに変えた」という声は、医療現場では少なくないのです。 一方で、受付スタッフは業務範囲が広く、事務処理や会計だけでなく、患者と医師の橋渡し役としての役割も...
患者との最初の接点となる受付は、クリニックの「顔」とも言える存在です。電話対応や来院時のひと声ひと声が、患者に安心感を与えることもあれば、不快感や不信感を植えつけることもあります。院長が診療の質向上に力を注いでいても、受付スタッフの対応ひとつで患者が離れてしまうのは珍しくありません。実際、「受付の人が冷たいから別のクリニックに変えた」という声は、医療現場では少なくないのです。 一方で、受付スタッフは業務範囲が広く、事務処理や会計だけでなく、患者と医師の橋渡し役としての役割も... -
訪問看護における「面談」はなぜ必要か?定着と満足度を高める管理者の視点
 「最近、なんとなくスタッフの表情が硬い」「面談をしても、毎回『とくに問題ありません』で終わってしまう」 そんな違和感を抱えたまま、なんとなく対話の機会をやり過ごしてはいないでしょうか。訪問看護の現場では、看護師一人ひとりが単独で行動する時間が多く、管理者とスタッフが日常的に会話する場面は限られています。だからこそ「定期的な面談」が重要だとされますが、実際にはその「面談」が形だけの時間になってしまっているケースも少なくありません。「状態の確認」や「報告を受ける場」にとどまり、...
「最近、なんとなくスタッフの表情が硬い」「面談をしても、毎回『とくに問題ありません』で終わってしまう」 そんな違和感を抱えたまま、なんとなく対話の機会をやり過ごしてはいないでしょうか。訪問看護の現場では、看護師一人ひとりが単独で行動する時間が多く、管理者とスタッフが日常的に会話する場面は限られています。だからこそ「定期的な面談」が重要だとされますが、実際にはその「面談」が形だけの時間になってしまっているケースも少なくありません。「状態の確認」や「報告を受ける場」にとどまり、... -
訪問看護の採用は「トップの言葉」で変わる:代表メッセージ活用法
 「代表のメッセージを書いてみたけれど、思ったより反応がない」「ホームページには載せているけれど、読まれているか分からない」 ──こうした声は、訪問看護ステーションの採用現場で少なくありません。トップメッセージの重要性を感じながらも、その手応えが得られないまま時間だけが過ぎていく。このような状況は、経営者にとってもどかしいものです。 しかし、なぜ代表の想いが求職者に届かないのでしょうか。その背景には、発信する言葉と受け取る側との間にある「温度差」や「生活感のズレ」があります。多...
「代表のメッセージを書いてみたけれど、思ったより反応がない」「ホームページには載せているけれど、読まれているか分からない」 ──こうした声は、訪問看護ステーションの採用現場で少なくありません。トップメッセージの重要性を感じながらも、その手応えが得られないまま時間だけが過ぎていく。このような状況は、経営者にとってもどかしいものです。 しかし、なぜ代表の想いが求職者に届かないのでしょうか。その背景には、発信する言葉と受け取る側との間にある「温度差」や「生活感のズレ」があります。多... -
訪問看護の採用課題とは?現場から考える解決の糸口
 訪問看護の現場では、「求人を出しても応募がない」「やっと採用できてもすぐ辞めてしまう」といった声が後を絶ちません。看護師不足は医療業界全体の課題ですが、その中でも訪問看護は特に採用が難しいとされてきました。病院やクリニックと比べて業務内容が想像しづらく、単独で利用者宅を訪問することへの不安が大きいからです。 さらに、応募があっても「思っていた働き方と違った」と感じて退職してしまうケースも少なくありません。たとえば「病棟よりも楽だと思っていたが、実際は一人で判断する場面が多く...
訪問看護の現場では、「求人を出しても応募がない」「やっと採用できてもすぐ辞めてしまう」といった声が後を絶ちません。看護師不足は医療業界全体の課題ですが、その中でも訪問看護は特に採用が難しいとされてきました。病院やクリニックと比べて業務内容が想像しづらく、単独で利用者宅を訪問することへの不安が大きいからです。 さらに、応募があっても「思っていた働き方と違った」と感じて退職してしまうケースも少なくありません。たとえば「病棟よりも楽だと思っていたが、実際は一人で判断する場面が多く... -
AI時代の「求人票」作成術!求職者を惹き付ける3つの鉄則
 「求人を出しても応募が来ない」「条件は悪くないはずなのに反応が薄い」 訪問看護の現場で、こんな悩みを抱えている経営者や採用担当者は少なくありません。実際、基本給や福利厚生を整えても、他社と大きな差が出るわけではなく、「求人票に書いてあることが似たり寄ったり」になっているケースも多く見られます。 一方で、同じような条件でも、なぜか応募が集まる事業所も存在します。両者の違いはどこにあるのでしょうか? それは「求人票の書き方」にあります。単に制度や条件を並べるのではなく、「誰に向け...
「求人を出しても応募が来ない」「条件は悪くないはずなのに反応が薄い」 訪問看護の現場で、こんな悩みを抱えている経営者や採用担当者は少なくありません。実際、基本給や福利厚生を整えても、他社と大きな差が出るわけではなく、「求人票に書いてあることが似たり寄ったり」になっているケースも多く見られます。 一方で、同じような条件でも、なぜか応募が集まる事業所も存在します。両者の違いはどこにあるのでしょうか? それは「求人票の書き方」にあります。単に制度や条件を並べるのではなく、「誰に向け...