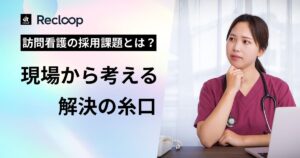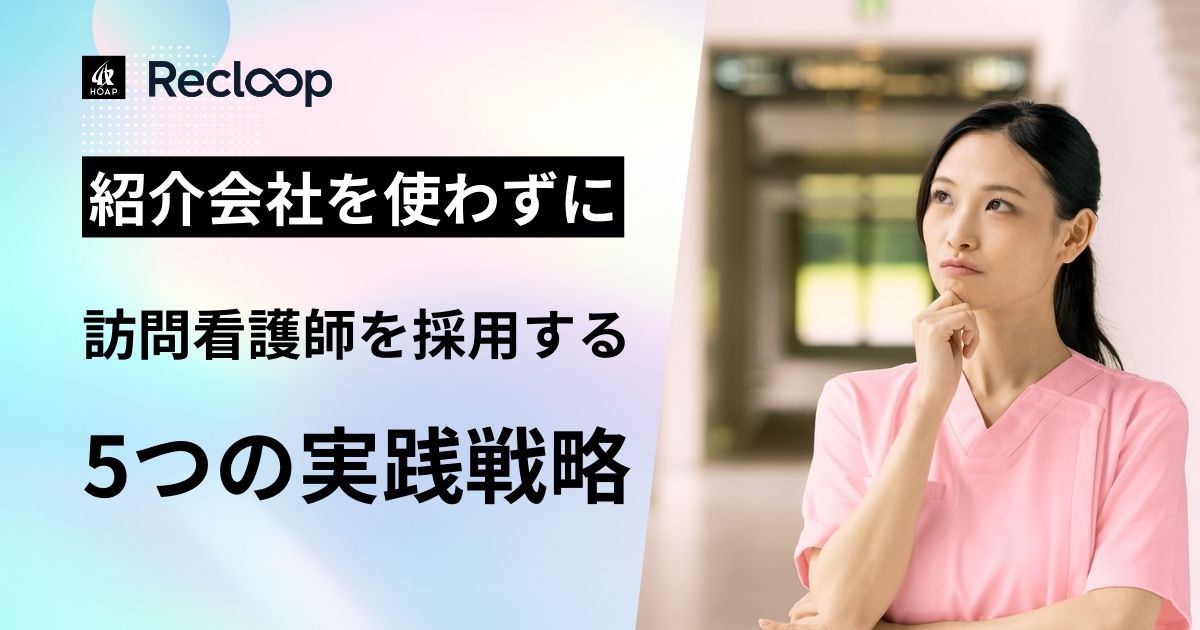訪問看護ステーションの経営において、採用活動は常に頭を悩ませる大きなテーマです。「求人広告を出しても応募が来ない」「せっかく採用しても定着せず、すぐに辞めてしまう」「紹介会社への手数料が重くのしかかる」――こうした状況は決して珍しくありません。特に人材紹介会社に頼る場合、採用が決まるたびに高額な費用が発生し、年間を通じてみると数百万円単位の出費になることもあります。加えて、紹介された人材が必ずしも自社の働き方や雰囲気に合うとは限らず、早期離職につながるリスクも存在します。
一方で、近年は「紹介会社を使わず、自社で採用を完結させる」動きが注目されています。SNSを活用した情報発信や、自社ホームページの採用ページ強化、専門媒体の活用など、取り組み次第で十分に成果を上げられる事例が増えています。もちろん手間はかかりますが、その分「採用コストの削減」「ミスマッチの軽減」「自社の魅力を直接伝えられる」といった利点が得られます。
本記事では、人材紹介会社に依存せず、訪問看護師を採用するための実践的な戦略を5つの視点から解説します。採用力の強化は単なるコスト削減にとどまらず、ステーション全体の成長やブランド力向上にもつながります。経営者や管理者が次の一手を考えるうえで、参考となる視点を整理してお伝えします。
訪問看護師の採用で紹介会社に頼らないメリット

採用コスト削減につながる
訪問看護師を紹介会社経由で採用する場合、一般的には年収の20〜30%程度の紹介料が発生します。仮に年収500万円の看護師を採用すれば、100〜150万円の費用が追加で必要になります。1名の採用であればまだ許容できる範囲かもしれませんが、複数名を同時に採用する場合や離職に伴って再度採用する場合には、この費用が経営を圧迫する大きな要因となります。特に訪問看護では慢性的な人材不足が続いているため、年間で数名規模の採用が必要になるケースも少なくありません。
自社採用に切り替えることで、この高額な紹介料を削減することができます。もちろん、求人媒体の掲載費用や採用サイト運営費、SNS運用のための人件費や運用費は必要ですが、それでも紹介会社に支払う手数料と比べれば格段に抑えられます。また、削減できた費用を新人教育や福利厚生・待遇改善に回すことで、採用後の定着率を高めることも可能です。採用にかけるお金を「単なる人材獲得のコスト」ではなく「人材を育て、長く働いてもらうための投資」に転換できる点は、自社採用の大きな魅力といえるでしょう。
さらに、自社での採用活動は一度仕組みを構築すれば、翌年以降も継続して活用できます。たとえば採用サイトやSNSアカウントは、運用を続けることで情報が資産として蓄積され、時間が経つほどに効果を発揮します。初期的には一定の労力が必要ですが、中長期的には紹介会社依存よりも圧倒的に効率的な方法といえます。
ステーションに合った人材を見極めやすい
紹介会社を通じて採用すると、候補者の経歴やスキルは確認できても、その人の価値観や働き方のスタイルが自社に合っているかどうかは見えにくいのが現実です。その結果「スキルは十分だが、職場文化やチームとの関係性に馴染めず、早期に離職してしまう」というケースが少なくありません。
自社採用であれば、求人票や採用ページで「直行直帰が可能か」「オンコールの頻度」「訪問件数や移動距離」「チーム体制か個別体制か」といった、現場に即した情報を具体的に提示できます。さらに、SNSでスタッフの雰囲気や現場でのリアルな情報を発信すれば、求職者が自ら「自分に合うかどうか」を判断しやすくなります。この情報公開は応募前からの相互理解を促進し、採用後のミスマッチを減らす効果があります。
また、候補者が自社を理解したうえで応募してくるため、面接の場でも「理念やビジョンに共感しているか」「訪問看護に求めるやりがいと、自社が提供できる環境が一致しているか」といった深い部分に焦点を当てて対話できます。結果的に、採用した人材が現場に馴染みやすく、長く働き続けやすい状況を生み出せるのです。
ステーションの魅力やリアルを直接伝えられる
紹介会社に依存する採用では、求職者に伝わる情報は紹介会社がまとめた定型的なプロフィールや求人票に限られます。そのため、事業所の雰囲気や理念、働くスタッフの人柄といった「本当の魅力」が十分に伝わりません。一方で、自社採用ならこれらを直接発信できるため、ブランドを築く大きなチャンスになります。
たとえば、自社ホームページにスタッフインタビューを掲載すれば「この人と一緒に働きたい」といった共感を呼び起こすことができます。InstagramやYoutubeなどのSNSで日常の取り組みを発信すれば、求職者だけでなく地域の人々に対しても「信頼できる訪問看護ステーション」という認知を広げることが可能です。こうした情報発信は、単なる求人活動にとどまらず、地域医療における存在感を高める役割も果たします。
さらに、ブランド力が向上すれば、求人広告を出していないタイミングでも「ここで働きたい」という候補者が自然と現れるようになります。これは、短期的な採用効果だけでなく、長期的に採用活動を安定させるための大きな資産となります。
ステーションの採用力そのものが育つ
自社採用を継続することで、組織全体の「採用力」が向上します。採用力とは、候補者を惹きつけ、選び、定着させる力のことです。紹介会社に頼る採用では、この力はなかなか育ちません。なぜなら、候補者を集める段階や初期接触のプロセスを外部に依存しているためです。
自社で採用を行うと、求人票作成や面接の準備、候補者とのやり取りを通じて「自社の強みと弱みは何か」「どんな人材が合うのか」を自ら分析する機会が増えます。これは経営課題を客観的に見直すきっかけにもなり、組織運営そのものの改善につながります。また、現場スタッフがSNS投稿や採用イベントに関わることで「自分たちの職場をどう見せたいか」を意識し、職場環境の改善意欲が高まる効果も期待できます。
さらに、どの媒体から応募が集まりやすいか、面接でどのような質問をすれば候補者の適性を見抜けるかといったノウハウが蓄積されていきます。これらの知見は次回以降の採用活動を効率化し、組織としての採用力を底上げします。結果として、紹介会社に頼らずとも安定的に人材を確保できる体制が整うのです。
自社採用が向いているステーションの特徴と判断基準

ステーション自体に採用活動を担える体制があるか
自社で採用を進める場合、求人票の作成や応募者対応、面接調整、SNS発信など、紹介会社が担っていた役割を自ら実施しなければなりません。そのため、管理者が日々の業務に追われて余裕がない場合には、十分な対応ができずに応募者とのやり取りが滞ってしまう可能性があります。採用力を高めるには、事務スタッフや人事担当を明確に役割分担することが欠かせません。
また、体制づくりには「スピード感」も重要です。応募者が問い合わせをしたのに数日間返信がない場合、それだけで応募意欲が低下してしまいます。自社採用を成功させているステーションは、多くが「問い合わせ当日か翌日には返信」「面接日程を即時に調整」といった迅速な対応を徹底しています。これは紹介会社が仲介する場合に比べて直接的に評価される部分であり、応募者に「信頼できる職場だ」という印象を与える大きなポイントです。
さらに、体制の有無は単なる人数の問題ではなく「採用を経営課題として位置付けているかどうか」にも直結します。現場に丸投げするのではなく、経営層が主体的に関わり、組織的に取り組む姿勢があって初めて、自社採用は継続可能なものになります。
ステーションに発信できる強みや独自性があるか
自社採用では「うちで働く魅力」を求職者に直接伝える必要があります。そのため、他のステーションと比較したときの独自性や強みがはっきりしているほど効果的です。たとえば「直行直帰が可能で子育て中のスタッフが働きやすい」「がん終末期ケアに特化して専門性を磨ける」「多職種連携を重視しており医師やリハ職との協働がしやすい」といった具体的な特徴です。
このような強みを発信できれば、求人票やSNSを通じて「ここなら自分の希望に合う」と感じた人材が集まりやすくなります。逆に独自性が不明確だと、数ある求人のひとつに埋もれてしまい、応募数を伸ばすのが難しくなります。自社採用が向いているステーションは、自分たちの強みを明確に言語化し、それを積極的に発信できる準備が整っているところです。
さらに、自社の魅力を発信する姿勢そのものが「透明性のある運営」を示し、応募者に安心感を与えます。表面的な条件だけでなく、働く上でのリアルな一面も示すことで、逆に合わない人材を早い段階でふるい分けでき、結果的にミスマッチの少ない採用につながります。
ステーションの中長期的な採用計画があるか
自社採用は、一度求人広告を出して終わりでは成果が見えにくいものです。SNSのフォロワーを増やす、自社サイトの採用ページを育てるといった取り組みは、継続して初めて効果が現れます。そのため、中長期的に採用活動を続ける計画を持つステーションにこそ適しています。
特に訪問看護は、利用者の増加やスタッフのライフステージの変化に伴い、毎年一定数の採用ニーズが発生します。そのため、採用活動を単発で考えるのではなく「毎年の業務の一部」として組み込むことが大切です。採用を継続して発信していると、必要なタイミングで自然に応募が集まる「仕組み化」が実現します。
また、中長期の視点を持つと、採用活動を通じて組織文化を磨く機会にもなります。たとえば、採用コンテンツをつくる過程で「うちの理念を改めて確認しよう」「スタッフが働きやすい仕組みを整えよう」といった見直しが進みます。自社採用は人材獲得だけでなく、組織の成熟度を高めるプロセスでもあるのです。
地域とのつながりを持てるか
訪問看護の採用は、病院勤務の看護師に比べて情報が行き渡りにくい傾向があります。だからこそ、地域との関わりを持てるステーションは自社採用に強みを発揮します。地域包括支援センターや医師会との関係、看護学校へのアプローチ、地域イベントや講習会への参加など、地域に根差したつながりはそのまま採用チャネルになります。
地域での活動実績を発信することで「この地域で信頼されているステーション」という認知が高まり、働く場所として選ばれる可能性が広がります。特に訪問看護は「地域密着型」であることが求められるため、地域に顔が見える存在であること自体が大きな強みです。
さらに、地域とのネットワークは単なる採用チャネルにとどまらず、入職後の新人教育や研修の場としても活用できます。地域の医療・介護関係者と連携しながらスキルアップできる環境を示せれば、求職者にとって魅力的な職場と映りやすくなります。
紹介会社を使わずに訪問看護師を採用する5つの実践戦略

戦略1:専門求人媒体を効果的に活用する
自社採用を進めるうえで、まず検討すべきは医療・介護領域に特化した求人媒体です。一般的な総合求人サイトに比べ、訪問看護の求人を探している人材が集まりやすく、職種や資格で絞り込んで応募してくるため、効率よく候補者に出会えます。特に、看護師専門の転職サイトや地域の医療系求人サイトは、訪問看護に興味を持つ層がアクセスしていることが多く、自社の魅力を的確に届ける場として活用できます。
求人媒体を利用する際に重要なのは「ただ求人票を出す」だけで終わらせないことです。具体的には、写真やスタッフのコメントを掲載して、職場の雰囲気が伝わるようにすることが効果的です。また、掲載する文言も「利用者に寄り添うケアを重視」「直行直帰制度あり」「子育て中のスタッフ活躍中」といった、候補者がイメージしやすい表現に工夫します。こうした情報は、応募者が自分のライフスタイルと照らし合わせながら判断する材料になるため、ミスマッチの少ない採用につながります。
さらに、媒体ごとの反応を分析して改善を重ねることが成果を左右します。応募数や採用数を記録して比較すれば、自社に合った媒体が見えてきます。最初は複数の媒体を試し、効果の高いものに絞り込んでいくと、コスト効率を高めることができます。

戦略2:SNSでステーションのリアルを伝える
求人媒体だけでは伝えきれない魅力を補うのが、SNSを活用した情報発信です。InstagramやYoutubeを中心に、現場スタッフの日常や訪問のエピソードを投稿することで、求職者に「働くイメージ」を直接届けることができます。たとえば、「子どもが急に熱を出したときに直行直帰できた」「利用者さんとの会話が日々のやりがいになっている」といったリアルな声は、求人票よりも強く心に響きます。
SNS発信のポイントは、情報を制度や条件の説明にとどめないことです。制度が「どのように役立ったか」「スタッフの生活にどんな安心感をもたらしたか」といったストーリー形式にすると、読み手の共感を得やすくなります。また、スタッフ紹介やイベント風景など、日常を切り取った投稿も効果的です。
加えて、SNSは双方向のコミュニケーションが可能です。投稿を見た求職者から質問やコメントが寄せられることで、直接の接点が生まれます。そのやり取りが信頼感を育て、応募につながるケースも少なくありません。SNS運用を採用活動の一部と位置付け、定期的に更新する体制を整えることが、紹介会社に頼らない採用を実現する鍵となります。

戦略3:ステーションの採用ページを強化し応募導線を整える
自社のホームページに採用ページを設けることは、紹介会社に依存しない採用の要となります。応募者は求人媒体やSNSを見た後、多くの場合「この会社はどんなところか」と検索してホームページを訪れます。そこで採用情報が見やすく整理されていなければ、せっかくの応募意欲が途切れてしまいます。
採用ページで重要なのは「応募までの導線をいかにシンプルにするか」です。条件や仕事内容をわかりやすく示したうえで、LINEや問い合わせフォーム、電話といった複数の応募方法を用意しておくと、候補者が行動に移しやすくなります。また、スタッフインタビューや1日の流れを掲載すれば、求職者が働く姿を具体的にイメージしやすくなります。
さらに、SEO対策も欠かせません。「訪問看護師 求人 ○○市」など地域名を含む検索ワードで上位表示されるように工夫すれば、地元で働きたい人材に自然にリーチできます。採用ページは単なる求人掲載の場ではなく、ステーションの理念や強みを発信する「顔」となる存在であり、長期的に応募を呼び込む資産になります。

戦略4:定着率を高める仕組みを整える
紹介会社に頼らない採用を続けていくには、「採用して終わり」ではなく「入職後に定着してもらう」ことが最も重要です。定着率が低ければ、いくら自社採用でコストを削減しても再び採用活動が必要になり、結局は負担が大きくなってしまいます。
定着率を高めるには、まず新人教育の仕組みを明確にすることです。入職直後にどのような研修を行い、どのように先輩スタッフが同行するのかを事前に示しておけば、新人は安心して業務を始められます。また、定期的な面談やフォローアップの場を設けることで、不安や不満を早期に解消することができます。
さらに、ワークライフバランスを支える制度も定着に直結します。直行直帰やシフトの柔軟性、子育て中のスタッフを支援する体制など、現場の声を反映した仕組みを整えることが欠かせません。これらは求人票に書くだけでなく、実際に活用されているエピソードを発信することで「本当に働きやすい職場」という信頼につながります。
採用と定着は表裏一体であり、両方を意識した戦略を立てることが、紹介会社に頼らず成果を出し続けるための基盤になります。

戦略5:社員紹介制度や地域ネットワークを活用する
紹介会社に頼らない採用のもう一つの柱が「社内外のネットワークを活かすこと」です。まず取り組みやすいのはリファラル採用、つまり社員紹介制度です。現場で働くスタッフが「知人に勧めたい」と思える職場づくりを前提に、紹介者にインセンティブを設定すれば、自然に候補者の質も高まります。既存スタッフと価値観が近いため、入職後の定着率も高くなる傾向があります。
加えて、地域とのつながりも有効です。訪問看護は地域包括支援センター、医師会、看護学校などと日常的に関わる仕事ですから、そのネットワーク自体が採用チャネルになります。地域イベントや学校説明会に参加し、自社の取り組みを伝えることで「地域に信頼されている事業所」という印象を広げられます。こうした活動はすぐに応募につながらなくても、長期的には「働く場として知っている」という候補者を増やし、安定した採用基盤を築きます。

実践後のフォローと改善のためのチェックポイント
応募経路を数値化して効果を把握する
自社採用を始めると、求人媒体やSNS、自社サイト、紹介や口コミなど複数の応募経路が生まれます。これらを「なんとなく」で評価していると、効果的な方法が見えず、無駄なコストや時間が発生します。導入後は必ず、応募者に「どこでこの求人を知りましたか?」と確認し、経路を記録しておくことが重要です。
たとえば、求人媒体Aからは毎月10件の応募があるが採用に至るのは1名、SNSからの応募は3件だが2名が定着している、といったデータが取れれば、次回以降の投資先を明確にできます。この数値化がなければ「応募数が多いから効果的」と錯覚し、実は定着につながっていない施策に費用を投じ続けてしまうリスクがあります。
応募経路の把握は、単なる集計ではなく「どのチャネルが自社に合う人材を引き寄せやすいか」を見極める手段です。定期的にデータを整理し、半年ごとに媒体の見直しを行えば、採用活動の精度は格段に向上します。
応募者からのフィードバックを集める
採用活動の改善には、応募者自身の声を集めることが欠かせません。応募から面接、内定までの流れで「分かりにくかったこと」「不安を感じたこと」「安心できた点」などを直接聞き取ることで、自社の改善点が明確になります。
たとえば「応募フォームが複雑で入力に時間がかかった」「面接案内のメールがわかりにくかった」といった小さな指摘も、応募者の離脱につながる要因になり得ます。逆に「スタッフ紹介のページが印象的で応募を決めた」「SNS投稿を見て雰囲気が分かった」などのポジティブな声は、今後の採用活動の強みにできます。
フィードバックを得る方法としては、内定者アンケートや面接終了後の簡単なアンケートフォームが有効です。また、辞退者に対しても「どこが気になったのか」を聞ければ、改善のヒントになります。採用のプロセスを応募者目線で見直すことが、次の成果を高める近道となります。
定着率と離職理由を分析する
採用活動の評価は「採用できたかどうか」だけでは十分ではありません。大切なのは、採用した人材が実際に現場に馴染み、長く働いているかどうかです。そのためには、定着率と離職理由を定期的に確認する必要があります。
具体的には、入職から3か月、6か月、1年といったタイミングで定着率を集計します。また、退職者が出た場合には「業務内容が合わなかった」「オンコール対応が負担だった」「人間関係に不安があった」など、理由を必ず記録します。これにより、採用段階で伝えきれていない情報や、職場環境の改善が必要な部分が見えてきます。
もし「オンコール負担」を理由に辞める人が多いと分かれば、求人票であらかじめ頻度を明示したり、負担を軽減する仕組みを整えるといった対策が可能です。定着率と離職理由の分析は、採用活動を単なる人集めではなく「働き続けてもらうための仕組みづくり」へと進化させるための重要な工程です。
職場環境と文化の改善に活かす
採用活動で得られるデータやフィードバックは、単に募集方法を見直すためだけでなく、職場環境の改善に直結します。応募者が「雰囲気が良さそう」と感じたポイントや、逆に「不安を感じた」という意見は、ステーションの文化や日常の働き方に反映させるべき貴重な情報です。
たとえば「面接でスタッフ同士の会話が和やかで印象的だった」という意見は、日常のチームワークの良さを強みにできます。一方「残業時間についての説明が曖昧だった」という声があれば、業務量の調整や情報の透明性を見直す必要があります。
また、定着率や離職理由の分析で見えてきた課題は、そのまま組織文化の改善課題でもあります。「オンコールが負担」という声が多ければ、勤務シフトの工夫や役割分担を見直すことが必要です。採用活動は組織運営と切り離せないものであり、改善のサイクルを回すことが、持続可能な自社採用の実現につながります。
訪問看護師の採用において、人材紹介会社に依存せず自社で採用を進めることは、コスト削減だけでなく、自社に合った人材を確保し、定着率を高め、ブランドを強化するための有効な戦略です。本記事で紹介したメリットや特徴の確認、具体的なアクション、改善のためのチェックポイントを実践すれば、自社採用は決して難しいものではありません。最初は求人票の見直しやSNS発信といった小さな取り組みからで十分です。継続と改善を積み重ねることで、紹介会社に頼らずとも安定した採用が可能になります。人材不足が続く今だからこそ、自社の力で人を集め、育て、活かす仕組みを整えることが、訪問看護ステーションの持続的な成長につながります。